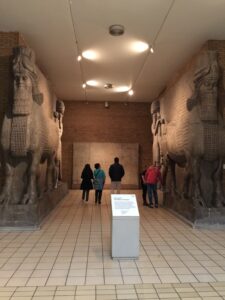はじめに:なぜ今「地域とのつながり」が問われるのか
博物館が地域社会とどのような関係を築いていくかという問いは、決して新しいものではありません。しかし、人口減少や高齢化、地域の空洞化といった課題が深刻化するなかで、「地域との連携」や「地域に開かれた博物館」といったキーワードが、近年改めて注目されるようになってきました。地方創生や文化資源の地域活用に関する政策動向と相まって、博物館が文化的中核施設として担う役割もまた、大きく変化しています。
これまでの博物館は、学術的な知識や文化財を「保存し、展示する」ことを中心的な役割としてきました。そしてその活動は、一定の専門性や権威性によって支えられていました。しかし今日では、そうした専門性を維持しつつも、博物館が地域の人びとと協働し、課題を共有し、共に未来を構想する場として変容しつつあります。展示室の外に広がる地域社会といかに関係を築くのか。その問いは、単なる集客戦略や教育普及の技術にとどまらず、博物館のミッションそのものにかかわる本質的な問題です。
本記事では、博物館が地域と「つながる」とはどういうことかを、コミュニティの多様性と関係性構築の視点から考えていきます。その際、「連携」や「協力」といった表面的な接続ではなく、共創(co-creation)、包摂(inclusion)、信頼(trust)といったキーワードを軸に、持続可能な関係性のあり方を検討します。
今、博物館は「誰のものか」という問いを改めて考える局面にあります。そしてその問いへの一つの答えは、「地域とともにあること」にあるのではないでしょうか。本記事では、博物館が地域社会と持続可能な関係を築くための理論的視点と実践的可能性について、丁寧に考察していきます。
コミュニティとは何か ― 博物館が向き合う多様な「地域」
博物館が地域とつながることの重要性が語られる一方で、「地域」あるいは「コミュニティ」という言葉が、具体的に何を指すのかについては、しばしば曖昧なまま使われています。実際、地域という概念は必ずしも地理的な近接性だけでは定義されず、歴史的な記憶、文化的価値、社会的関係性など、さまざまな要素が交差する複合的なものです。
Sheila Watson 編の『Museums and their Communities』(2007)では、博物館が関係を築く「コミュニティ」のあり方について、Mason による以下のような7つの類型が紹介されています(Watson, 2007)。これは、博物館が接点を持ちうる多様な共同体を理解するうえで、理論的にも実践的にも有効な枠組みです。
- 地理的コミュニティ:博物館の所在地に居住する地域住民や自治体。
- 文化的・宗教的コミュニティ:民族的・宗教的背景を共有する人びと。
- 社会的・経済的属性によるコミュニティ:年齢層、所得層、教育レベルなどで構成される集団。
- 排除された・疎外されたコミュニティ:社会的・歴史的に周縁化されてきた人びと。
- 専門的な知識・関心をもつコミュニティ:学芸員、研究者、愛好家団体など。
- 来館行動によるコミュニティ:学校団体、観光客、リピーターなど博物館を訪れる集団。
- 仮想・ネットワーク型のコミュニティ:SNSなどを通じてつながる非物理的な関係性。
これらの分類は、博物館が向き合う「地域」や「市民」が、単なる一枚岩ではなく、多様な関心や属性、立場をもつ集団であることを前提とするものです。たとえば、高齢者による語りの保存プロジェクトは「地理的コミュニティ」と「排除されたコミュニティ」の両方に関係することがありますし、博物館を何度も訪れるリピーターとの関係構築は「来館行動によるコミュニティ」に属します。
このように考えると、「地域とつながる」という言葉は、単に地域イベントを開催したり、施設を開放したりするだけでは捉えきれません。博物館は、その活動のなかで多様なコミュニティと向き合い、それぞれの背景や価値観、関心に応じて丁寧に関係性を構築していくことが求められます。そしてそのプロセスこそが、信頼や共創といった価値を育む土台になるのではないでしょうか。
博物館と地域のつながり方 ― 実践から見る多様なアプローチ
前節では、博物館が関係を築く「地域」や「コミュニティ」は、地理的な範囲だけでは定義できない複層的な存在であることを確認しました。本記事ではその前提を踏まえ、博物館が多様なコミュニティとどのようにつながっているのか、具体的な実践を通じて考えていきます。ここでは、特に共創・包摂・信頼の3つの観点から事例を紹介し、それぞれが示す可能性と課題を整理します。
共創:地域の人びとと展示や活動をつくる
近年、博物館の活動において「共創(co-creation)」という概念が注目されています。これは、学芸員や専門家が一方的にコンテンツを提供するのではなく、地域の人びとが主体的に関わり、共に学び、表現する過程を重視するものです。
たとえば、Watson 編に収録された Viv Golding(2005)の「Inspiration Africa!」という事例では、英国の博物館が障害のある若者たちと協働して展示をつくり上げるプロジェクトが紹介されています。この取り組みでは、参加者自身がテーマを決め、展示物の選定や解説文の執筆にまで関与することで、「語る権利」を獲得し、博物館が包摂的な場として機能する様子が描かれています(Watson, 2007)。このような共創型のアプローチは、博物館が地域の「語り」を取り込み、記憶やアイデンティティの共有空間として再編される契機となります。
包摂:排除されてきた声をすくいあげる
博物館が地域とつながるもう一つの鍵は、社会的に排除されてきた人びとや集団に向き合い、彼らの存在や語りを展示や活動に組み込んでいくことです。Dillon(2003)は、環境教育において「コミュニティがしばしば“無視されてきた存在”である」ことを批判的に指摘し、学びの場が特定の価値観や制度のなかで排他的に運営されていることへの問題提起を行っています(Dillon, 2003)。
この視点は、博物館における地域連携においても重要です。たとえば、移民コミュニティの語りを展示に取り入れたり、LGBTQ+当事者の記憶をアーカイブ化したりする試みは、従来の「標準的な来館者像」から逸脱する人びとに対して開かれた場を創出する可能性を示します。包摂的な博物館は、地域の中で見過ごされてきた声に光をあて、社会的承認の場を提供することができるのです。
信頼:継続的な関係づくりと対話の積み重ね
地域とのつながりを一過性のイベントに終わらせないためには、信頼にもとづく継続的な関係構築が欠かせません。特定の事業年度に合わせたプロジェクト型の連携は、予算の終了とともに解消されてしまうことが多く、地域の側からは「また別の一過性の企画」として受け止められてしまうこともあります。
Andre, Durksen & Volman(2016)は、博物館が子どもとの学びを実現するためには、継続的な関係性のなかで参加者の関心や習熟度に応じたプログラムを設計しなければならないと述べています(Andre et al., 2016)。この考え方は、地域住民との関係性においても通用します。たとえば、毎年恒例の地域イベントに博物館が継続的に関与したり、地元住民との対話の場を定期的に設けたりすることで、対等で信頼にもとづく関係性が築かれていきます。
地域連携の課題とこれからの展望 ― 信頼と持続性をいかに築くか
地域とのつながりを重視する博物館の取り組みが広がる一方で、それを継続的かつ実質的な関係へと発展させるためには、いくつかの重要な課題があります。本記事では、特に「信頼の構築」「非対称性の認識」「制度との接続」という三つの視点から、その課題と展望を整理します。
信頼は一朝一夕には築けない
地域との連携において、しばしば見落とされがちなのが、信頼関係の形成には時間がかかるという事実です。単発のワークショップや展示企画を通じて一時的に関係が生まれたとしても、それが継続的な連携に結びつくとは限りません。むしろ、年度単位の予算や短期の助成金に依存したプロジェクトは、地域住民から「また終わってしまう取り組み」と見なされ、かえって距離を生むこともあります。
そのため、博物館側には、「関わり続ける覚悟」を示す姿勢が求められます。小さなイベントであっても、毎年継続し、地域住民の声を丁寧に聞き取り、記録を蓄積していくこと。こうした粘り強いプロセスこそが、やがて信頼を生み出し、地域の中で「共にある」存在として認識される土台となるのです。
「誰が語るか」という非対称性
もう一つの重要な課題は、博物館と地域コミュニティの間にある権力関係の非対称性です。展示内容の決定権、資金、人材、専門知識など、あらゆる資源が博物館側に集中している場合、「共創」や「協働」といった言葉が実態を伴わず、形式的に使われてしまうことがあります。
Watson(2007)は、博物館がこうした権力構造を自覚せずに「地域と連携する」と主張することの危うさを指摘しています(Watson, 2007)。とくに、周縁化されてきたコミュニティや社会的に弱い立場にある人びとと関わる際には、「誰が語るのか」「誰が選ばれるのか」という問いに対して誠実に向き合うことが不可欠です。
制度的支援と戦略的な位置づけ
地域との連携を持続的なものにするためには、博物館内部での担当者の熱意だけに頼らず、制度的な支援と経営レベルでの戦略的位置づけが不可欠です。具体的には、地域連携を担当する部署や専門スタッフの配置、評価指標への組み込み、長期的なビジョンの策定などが挙げられます。
英国の「Renaissance in the Regions」プログラムでは、博物館が地域との関係性を戦略的に強化するための制度的枠組みが導入され、多くの地域博物館で実践が積み重ねられました。こうした国レベルの支援がなければ、地域との連携は「各館の自主的努力」にとどまり、成果の蓄積や共有も難しくなります。
以上のように、博物館が地域と持続的な関係を築くためには、信頼・対等性・制度設計という3つの観点から課題に取り組む必要があります。次節では、これまでの議論をまとめ、地域とつながる博物館の経営的意義について改めて考察します。
まとめ ― 地域とともにある博物館経営の可能性
本記事では、博物館が地域とつながるとはどういうことかを、コミュニティの定義、具体的な連携の実践、そしてその課題と展望を踏まえながら考察してきました。そこから見えてきたのは、「地域との連携」とは単にイベントを共催したり、地元の来館者を呼び込んだりする表層的な取り組みではなく、共創・包摂・信頼にもとづく持続可能な関係性の構築であるという点です。
博物館は、単にモノを保存・展示する場ではなく、地域に生きる人びとの記憶や価値観、語りを共有する「文化のハブ」としての役割を担っています。そのためには、どのようなコミュニティと関係を築くのかを丁寧に見極め、その多様性を尊重しながら関係性を編み直していくことが求められます。
また、地域連携を成功させるためには、博物館側の主体的な姿勢だけではなく、制度的な支援や戦略的な経営判断も不可欠です。一時的な熱意ではなく、長期的な信頼を基盤とした関係づくりが、地域とともに歩む博物館の未来を開いていくのです。
地域と向き合うことは、博物館が自らの存在意義を見つめ直すことにもつながります。「博物館は誰のものか」という問いに対して、「地域とともにあるものだ」と答えるためには、今後も多様なコミュニティとの対話と協働の実践を、経営の中核に据えていく必要があるでしょう。
参考文献
Andre, L., Durksen, T., & Volman, M. (2016). Museums as avenues of learning for children: A decade of research. Educational Research Review, 10, 52–67.
Dillon, J. (2003). On learners and learning in environmental education: Missing theories, ignored communities. Environmental Education Research, 9(2), 215–226.
Golding, V. (2007). Learning at the museum frontiers: Identity, race and power. In S. Watson (Ed.), Museums and their communities (pp. 362–385). Routledge.
Mason, R. (2007). Museums, galleries and heritage: Sites of meaning-making and communication. In S. Watson (Ed.), Museums and their communities (pp. 200–217). Routledge.
Watson, S. (2007). Introduction: Museums and their communities. In S. Watson (Ed.), Museums and their communities (pp. 1–24). Routledge.