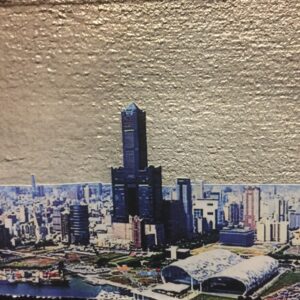はじめに:なぜ今、博物館スタッフの職責と専門性を考えるのか
博物館という組織は、展示や教育活動、収蔵資料の管理、地域との連携など、さまざまな機能を果たしています。これらの活動は、館長や学芸員だけでなく、教育担当者、事務職員、技術スタッフ、さらにはボランティアなど、多様な人びとの協働によって支えられています。博物館が公共性と専門性を両立させながら、その使命を果たしていくためには、誰がどのような責任を担い、どのような知識や経験によってその職務を遂行しているのかを理解することが欠かせません。
組織としての博物館を考えるとき、まず注目されるのは、部門や階層の構造です。館長を頂点とする指揮命令系統や、学芸・教育・管理といった機能別の分担は、組織図として視覚化されることで、全体の枠組みを明らかにしてくれます。しかし、どれほど整った構造であっても、それを日々動かしているのは、そこで働くスタッフ一人ひとりの判断と行動です。組織構造が「静的な設計図」だとすれば、スタッフの役割と専門性は、それを「動かすエンジン」にあたります。
とくに近年では、博物館に求められる機能が拡張し、それに応じて職種の範囲や専門性の定義も広がりを見せています。たとえば、デジタルアーカイブの整備、地域との協働、来館者体験の設計などは、従来の枠を超える新たな職能を必要とします。こうした変化のなかで、博物館における人材配置のあり方を見直すことは、組織の持続可能性や柔軟性を高めるうえでも重要な課題です。
本記事では、博物館で働くさまざまな職種とその職責、求められる専門性について整理し、どのように人材が配置され、連携しているのかを検討します。組織のかたちと人の働きがどのように結びついているのかを捉え直すことで、博物館経営の実態に一歩深く迫る視点を提供したいと考えています。
博物館における主なスタッフとその職責・専門性
博物館には、実にさまざまなスタッフが働いています。展示を企画する人、教育プログラムを設計する人、資料を守る人、組織全体を運営する人――そのすべてが、博物館の活動を支える欠かせない存在です。こうした職種ごとの役割と責任、そして求められる専門性は、制度的な枠組みの中でおおまかに規定されているものの、実際の業務内容は館ごとに大きく異なります。
とくに小規模な博物館では、一人が複数の役割を兼ねることも珍しくありません。一方で大規模館では、職種ごとに明確に業務が分かれ、より専門的な人材が配される傾向にあります。こうした差異を理解する前提として、まずは博物館における主な職種について、その職責と専門性を順を追って確認していきましょう。
館長 ― 組織全体を統括する運営責任者
館長は、博物館の最上位に位置する責任者として、組織全体の運営に関わる重要な意思決定を担います。展示や収蔵の方針を決めるだけでなく、予算の管理、人事の承認、渉外活動、そして行政や市民社会との対話など、対内外にわたる幅広い責務を持ちます。
学芸的な知見に基づく判断だけでなく、経営的なバランス感覚やリーダーシップも必要とされます。とくに大規模館では、複数部門の調整や中長期的な経営戦略の策定も求められます(Holmes & Hatton, 2008)。
学芸員 ― 博物館の専門機能を担う中核職種
学芸員は、博物館法にも位置づけられた専門職であり、主に資料の収集・保存・調査・展示・教育を担います。専門分野に基づく研究活動を土台に、展示の企画構成や資料の保存管理、来館者向けの解説執筆、調査成果の発信など、多様な業務を遂行します。
近年では、従来の学術研究にとどまらず、教育普及や地域連携、SNS運用など、より社会との接点に関わる機会も増えています。博物館の公共性と専門性を支える存在として、柔軟で広範な対応力が求められています(Lord & Lord, 2009)。
教育普及担当 ― 来館者の学びを支えるつなぎ手
教育普及担当は、展示と来館者との間をつなぎ、博物館での体験が学びや気づきへとつながるよう支援する役割を担います。学校向けのプログラム設計、ワークショップの運営、展示解説ツールの開発、ボランティアとの連携など、現場での実践力が問われる仕事です。
この職種には、教育学や発達心理学に関する知識だけでなく、ファシリテーション能力や対話を通じたコミュニケーション力も不可欠です。来館者の多様な背景やニーズを読み取りながら、学びをデザインする専門職といえます(Gainon-Court & Vuillaume, 2016)。
事務職員 ― 組織の屋台骨を担う運営支援者
事務職員は、予算編成、会計処理、契約事務、人事労務管理、広報活動、庶務全般など、組織を内側から支える実務を幅広く担っています。多くの事務業務は表立って見えにくいものの、円滑で安定した博物館運営には欠かせない存在です。
特に公立館では、行政機関との連携や報告業務なども含まれるため、制度理解や法的知識、計画的な実行力が必要とされます。にもかかわらず、その専門性や責任の重さが過小評価される傾向もあり、業務の見える化と職責の再定義が求められています(Holmes & Hatton, 2008)。
技術職員・IT担当 ― 展示・保存・デジタルを支える技術の担い手
技術職員は、展示空間の設営、照明・音響の調整、資料輸送や梱包作業、保存環境の制御など、現場の技術的な運営に特化した職能です。一方、IT担当は、デジタルアーカイブの構築、Webサイトやアプリの管理、館内ネットワークの保守などを専門とします。
デジタル化と脱炭素化の両方が求められる現代において、こうした技術系スタッフはますます不可欠な存在となっています。適切な配置と継続的なスキル育成が、今後の博物館の競争力を左右する鍵になります(Gainon-Court & Vuillaume, 2016)。
レジスター(Registrar) ― 収蔵品の流通と制度を司る管理職
レジスターは、資料の登録・移動・貸出・保険・輸送など、収蔵品のライフサイクル全体にわたって責任を持つ管理職です。館内外の資料の流れを可視化し、記録の正確性と制度的な整合性を確保するのが主な役割です。
欧米では独立した専門職として確立されており、特に大型展覧会の運営には不可欠な存在です。しかし日本では、制度化が進んでおらず、学芸員や事務職員が兼務している例も多く見られます。今後の専門職制度の整備と認知の向上が課題です(Lord & Lord, 2009)。
ボランティア・アルバイト ― 柔軟に組織を支える多様な人材
ボランティアやアルバイトは、展示案内、イベント補助、資料整理、来館者対応など、柔軟な働き方で博物館を支える存在です。正規職員の手が届きにくい領域を補完する形で、実践的な役割を担っています。
一方で、十分な研修がなされないまま現場に立つケースもあり、適切な情報共有や責任範囲の明確化が必要とされます。モチベーションの維持や継続的な学びの機会を提供する制度設計が、彼らの力を最大限に活かすための鍵となります。
組織規模と人の配置 ― 小規模館と大規模館の違い
博物館には、法律や制度によって定められた一定の職種区分がありますが、実際の現場で「誰が」「何を」「どのように」担っているかは、組織の規模や性格によって大きく異なります。同じ「学芸員」や「教育担当」という肩書きであっても、配置のされ方や担う役割には幅があり、働き方の実態も多様です。
なかでも、博物館の「規模」は、人の配置や役割の設計に直接的な影響を与える重要な要因です。小規模館と大規模館とでは、必要な人員構成、求められる柔軟性、職種間の連携のあり方がまったく異なります。本節では、この違いに注目しながら、博物館における「人の配置」がもつ経営的・組織的な意味を詳しく考察していきます。
小規模館:限られた人員で多様な職務をこなす柔軟性
日本の博物館の多くは、数人〜十数人規模の職員で運営される小規模館です。地方自治体が設置する郷土資料館や文学館、歴史民俗資料館などでは、常勤職員が3〜5人程度という体制も珍しくありません。
このような小規模館では、一人の職員が複数の業務を兼務することが当たり前のように求められます。たとえば、学芸員が資料調査・展示企画・ワークショップ運営を行うだけでなく、広報物の作成、受付業務、教育普及活動、時には予算管理や庶務まで担う場合もあります。
役職の垣根を超えた「何でも屋」としての働きが求められる一方で、その都度の対応力や個人の経験値に依存した属人的な運営になりやすいというリスクもあります。
また、小規模館における最大の課題の一つは、「専門性の継続的育成が難しい」という点です。多忙な日常業務の中で、外部研修への参加や研究活動の継続が難しく、最新の知見や技術を取り入れる余地が限られがちです。そのため、館全体の知的蓄積が停滞する傾向も見られます。
とはいえ、柔軟で機動的な対応ができるのは、小規模館の大きな強みでもあります。地域の住民や学校との密な関係性を築いたり、自由な発想で小回りの利く取り組みを展開したりすることで、独自の存在感を発揮している例も少なくありません。
大規模館:明確な分業体制と調整の複雑さ
一方で、国立博物館や大都市の総合博物館など、職員数が数十人〜100人規模に達する大規模館では、組織構造がはるかに複雑になります。
学芸部門、教育部門、総務部門、広報部門、施設管理部門など、部門ごとの機能が明確に分化し、それぞれに専門職が配置されるのが一般的です。さらに、学芸員の中でも分野ごと(考古、美術、自然史など)に専門が細分化され、担当範囲が限定されていることもあります。
こうした体制では、高度な専門性を発揮しやすく、また一定の分業によって業務の効率化も可能となります。しかしその一方で、部門間の調整業務が煩雑になりやすく、「縦割り」や「情報の断絶」が課題になることもあります。
たとえば、展示部門と教育部門の連携が不十分であれば、せっかくの展示内容が教育普及に十分活用されないまま終わる可能性があります。あるいは、広報戦略と研究成果の共有がうまく連動していないために、発信力が分散してしまうといった問題も起こり得ます。
また、大規模館では職員数の多さゆえに、個々のスタッフが組織全体の動きを把握しづらくなることもあります。結果として、自分の担当業務に閉じこもり、組織の一体感が薄れるといった傾向も見られるのです。
中規模館:柔軟性と専門性のバランスを求められる現場
中規模館は、上記2つの極端なモデルの中間に位置します。専任の学芸員や事務職員が配置される一方で、すべての職種に専属の人材を確保できるとは限らず、部分的な兼務や補完関係が必要とされます。
たとえば、教育普及を担当するスタッフが1人だけ配置され、その人物が学校連携からワークショップの運営、広報との調整まで担っているというケースもあります。あるいは、事務職がSNS発信や来館者対応も並行して行っている場合もあります。
中規模館では、一定の専門性を保ちつつ、同時に柔軟な組織運営も求められるため、スタッフの能力や経験値、チームの協働力がそのまま組織の成果に直結する傾向があります。
配置のあり方が経営をかたちづくる
人の配置の仕方は、単に「人を置く」というだけの話ではなく、組織の理念や戦略を体現する具体的な表れです。どの部門にどれだけの人を割くか、どの職種に重点を置くかといった判断には、博物館が「何を大切にしているのか」が如実にあらわれます。
また、配置には「役割を明確に分担する」視点と、「必要に応じて越境して協働する」視点の両方が求められます。とりわけ近年では、正規職員、契約職員、嘱託職員、アルバイト、ボランティアといった多様な働き方が併存する中で、組織全体としての目標共有や情報共有のあり方が問われています。
人材配置は、制度設計だけでなく、現場の創意工夫によってこそ磨かれていくものです。どのような館においても、スタッフ一人ひとりの力を活かす仕組みをつくること。それが博物館の持続可能な運営の鍵となるのです。
専門性の再定義とハイブリッド人材の時代
「博物館には専門性が必要である」――これは疑いようのない前提のように語られてきました。学芸員には専門分野の学識が求められ、技術職には保存環境に関する知識、教育普及担当には来館者理解と教育学の素養、事務職には財務や制度に関する実務的な理解が不可欠です。
しかし、現代の博物館では、その「専門性」とは何か、改めて問い直す必要があります。単一の領域に特化した知識を深めるだけでは、多様化する社会的ニーズや組織の複雑化に対応しきれない場面が増えてきたからです。求められているのは、「複数の領域を横断し、新たな価値を生み出す力」――いわゆるハイブリッドな専門性をもつ人材です。
本節では、従来の専門性の枠組みを一度立ち止まって見直し、これからの博物館において必要とされる人材像を描き出していきます。
学芸員の再定義:研究職から「つなぐ専門職」へ
かつて学芸員は「調査研究を行う人」であり、博物館内における「学術の番人」のような存在でした。しかし近年、その役割は大きく広がりつつあります。資料を収集・保存するだけでなく、展示で伝え、教育普及に関わり、時には地域の住民と対話を重ねながら企画をつくり上げていく――そんな動的な姿が求められています。
この変化は、学芸員がもつべき「専門性」が変化してきたことを意味します。研究成果を蓄積する力はもちろん重要ですが、それだけではなく、それをいかにわかりやすく、魅力的に、他者へ届けるかという「翻訳」の力こそが、現代の学芸員には欠かせないのです。
「非学芸」部門にこそ必要な専門性の理解
一方で、教育普及、広報、事務管理、ITといった「非学芸」部門でも、高度な専門性が必要とされています。たとえば、教育普及においては、子どもの発達段階や学習理論を理解したうえで、適切なプログラムを設計・実施する能力が求められます。対話型の鑑賞、アクセシビリティ対応、多文化対応など、極めて高度なスキルが必要な場面も増えています。
広報・マーケティングでは、SNS運用やWebコンテンツ制作、データ分析に基づくターゲット設定など、ビジネス領域に通じるスキルが欠かせません。IT領域では、デジタルアーカイブの構築、クラウド管理、UXデザイン、データ保全といった知識が問われます。
これらの分野に携わる職員はしばしば「補助的」とみなされがちですが、実際には博物館の公共性や持続可能性を支える不可欠な専門職であることを、私たちはもっと明確に認識する必要があります。
ハイブリッド人材とは何か:越境する専門性のかたち
こうした状況を背景に、いま注目されているのが「ハイブリッド人材」という存在です。これは、単一の職能にとどまらず、複数の専門性を横断的に身につけ、領域と領域をつなぎながら価値を生み出す人材のことを指します。
たとえば、学芸員でありながら教育普及の実践に長けた人物、教育担当として展示企画にも関与するスタッフ、あるいはITの専門知識を持つ広報職員など、実際に博物館の現場には、そうした越境的な実践を行う人々が少なからず存在しています。
こうした人材は、組織内に新たなつながりを生み、複数の部門にまたがる課題を発見し、解決へと導く力を持っています。まさに、変化の時代における博物館にふさわしい「複合的専門職」と言えるでしょう。
組織としての支援体制:育成・評価・環境整備
とはいえ、個々の努力や偶然に頼るだけでは、ハイブリッド人材は生まれません。館として、そうした人材を育成・評価する仕組みを整えることが不可欠です。
たとえば、部門横断的な研修プログラムの導入や、職種間の異動制度、複数職種が協働するプロジェクトチームの編成などが考えられます。また、職員が新しい領域に挑戦できる心理的安全性と制度的な保障も重要です。
さらに、評価制度の見直しも必要です。「展示件数」や「予算執行率」といった従来の定量的指標だけでなく、職員の貢献の質や部門を越えたつながりの創出、来館者との対話の成果など、より多元的な視点をもった評価軸が求められています。
専門性は「固定」ではなく「進化」するもの
最後に確認しておきたいのは、専門性とは決して「静的な資格」ではなく、「環境と経験のなかで育まれる力」だということです。大学での専攻や資格取得にとどまらず、日々の実践を通じて変化し、深化し、場合によっては再構成される――それが現代の専門性のリアルな姿です。
博物館においても、こうした「進化する専門性」を前提とした人材観を共有し、支援する組織文化が求められています。一人の職員が、多様な経験を経て、組織の知的資源として育っていく。そのプロセスこそが、持続可能な博物館経営の鍵なのです。
期待と責任のずれをどう埋めるか ― 組織内コミュニケーションの視点から
博物館の業務は、学芸、教育、広報、事務、技術といった多様な専門職が関わり合いながら進められています。それぞれの職種が持つ専門性は博物館の活動の柱となりますが、一方で、その専門性や業務範囲についての理解や認識がスタッフ間で食い違っていると、誤解や摩擦が生じやすくなります。
たとえば、「この業務は誰の担当なのか」「なぜ私ばかりが負担しているのか」「どうしてあの人はもっと関与しないのか」といった感情が積み重なると、業務効率の低下だけでなく、チーム内の信頼関係にも悪影響を及ぼしかねません。このような状況を招く要因の一つが、「期待と責任のずれ」です。つまり、ある職務に対して誰がどのような働きを期待されているかと、その人自身が抱く認識とが一致していない状態です。
この問題を整理するための枠組みとして参考になるのが、組織内の人間関係を「上下関係」「同僚関係」「外部関係」という三つの軸から分析する考え方です(Emery, 1990)。この「三軸モデル」は、博物館のように多職種協働の場において、期待のズレがどこから生じるのかを理解する上で非常に有効です。
上下関係 ― 指示と裁量のギャップを乗り越える
まず最初の軸は、「上司と部下」の関係です。上司が部下にどのような成果を求め、どこまでの裁量を与えているか。そして部下がその期待をどう理解し、実際の行動に反映しているか。この関係にずれがあると、業務指示がうまく伝わらなかったり、過剰な責任を感じて負担を抱えたりすることになります。
たとえば、展示の準備において上司は「教育的な観点を強めてほしい」と考えていたのに、部下は「研究成果を中心に構成するべき」と判断していたとすれば、出来上がった展示の方向性に食い違いが生じ、最終的にはやり直しや対立が発生することになります。こうした事態は、事前の目的確認や中間報告といったフィードバックの機会が十分にあれば防ぐことができたかもしれません。
上下関係のなかで期待と責任のバランスを保つためには、明確なコミュニケーションと、裁量と責任の範囲についての共通認識が不可欠です(Emery, 1990)。
同僚関係 ― 職種間の“暗黙の期待”に気づく
二つ目の軸は、「同僚関係」、すなわち横の関係性です。これは学芸員と教育担当、広報と事務、あるいはITと現場職員など、異なる職種間で協働する場面において顕著に現れます。
たとえば、教育普及担当が「学芸員がもっと説明資料を用意してくれるはず」と思っていたのに対し、学芸員は「展示だけで十分伝わる内容だから、教育担当が独自に補足すればよい」と考えていたとしたら、相互の期待がすれ違っていることになります。これは事前に明示的な確認をせず、役割を“暗黙の了解”のまま進めていると起こりやすい現象です。
職種ごとに培ってきた価値観や業務観が異なるため、無意識に「これくらいはやってくれるだろう」と思い込んでしまうことがあります。こうした期待の押し付けや誤解が続くと、不満や摩擦が蓄積し、結果的に組織の連携力が低下してしまいます。
こうした横の関係では、「相手の立場に立って期待を言語化する」「すり合わせの時間を意図的につくる」といった努力が求められます(Emery, 1990)。
外部関係 ― 外からの期待と現場の実態のギャップ
三つ目の軸は、「外部との関係」です。これは、行政機関、地域住民、来館者、メディアといった館の外にあるステークホルダーからの期待と、現場の実態との間にあるズレを意味します。
たとえば、行政が「地域イベントとの連携を強化してほしい」と要請している一方で、現場ではすでに展示や教育事業で手一杯であり、十分な人員や予算を確保できないというケースはよくあります。また、来館者からの「もっと子ども向けの企画を増やしてほしい」という声に対し、学芸員が「企画展の質を保つことが先決」と考えている場合も、意図と期待がすれ違うことになります。
こうしたギャップに対応するためには、外部の期待を受け止めつつ、現場のリソースや戦略とどう折り合いをつけるか、館全体としての合意形成が必要です。特定の職員に負担が集中しないよう、役割分担や組織的支援体制の整備も欠かせません(Emery, 1990)。
ズレを前提とした“修正可能な組織”をつくる
これら三つの軸に共通して言えるのは、「期待と責任のズレは避けられない」という現実です。むしろ、それを前提として組織を設計し、修正できる関係性を育むことの方が重要です。
たとえば、各職種の役割を明文化した職務記述書を定期的に更新し、異動や新規事業に応じて内容を見直す。プロジェクト単位で業務の担当者と役割を文書化する。定期的なチームレビューや面談を通じて、認識の差異を共有する。こうした「見える化」と「対話の機会」が、期待と責任のズレを最小限にとどめる鍵となります。
そして何よりも、こうした対話や修正を可能にするには、スタッフ同士の信頼が前提になります。信頼は、完璧なマネジメントや制度ではなく、「違いを理解しようとする姿勢」と「必要なときにすり合わせができる場の存在」から生まれます。
組織の実効性は、対話の文化から生まれる
博物館における人材配置の実効性は、単に職種の制度設計や人数の確保にとどまるものではありません。むしろ、日々の業務の中でどれだけ相互に期待を確認し合い、役割の認識を調整し合う文化が根づいているかが、実質的な力となります。
このような「期待と責任のすり合わせ」を可能にする仕組みや関係性は、最終的には組織全体の信頼文化に支えられるものです。
参考文献
- Emery, F. E. (1990). The management of organizational design: Strategies and implementation. Martinus Nijhoff.
- Gainon-Court, C., & Vuillaume, L. (2016). Who is a museum curator? Definitions and evolutions of the profession in France and Switzerland. Museum International, 68(3–4), 54–67.
- Holmes, K., & Hatton, A. (2008). The differing expectations of staff and volunteers in museums. Museum Management and Curatorship, 23(3), 203–217.
- Lord, G. D., & Lord, B. (2009). The manual of museum management (2nd ed.). AltaMira Press.