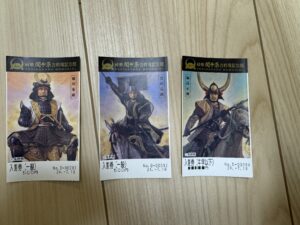はじめに:組織は展示の「裏側」でしょうか?
ミュージアムという言葉から、私たちはまず何を思い浮かべるでしょうか。美しく照明された展示室、歴史的価値のある収蔵品、あるいは印象的な建築デザインや、話題性のある特別展などが思い出されるかもしれません。確かに、ミュージアムの「表側」は、来館者が直接目にする展示や空間、体験といった、視覚的かつ感覚的に訴える要素によって構成されています。
しかし、そのような「表側」が成立するためには、それを支える「裏側」、すなわちミュージアムの内部構造や運営体制、職員の役割分担といった組織的な基盤が不可欠です。展覧会を企画し、資料を調査し、施設を維持し、来館者を迎える──こうした一連のプロセスには、実に多くの職員が関与し、部門を超えた協働が日々行われています。
つまり、ミュージアムとは単なる「展示の場」ではなく、組織としての一面を併せ持つ複雑な社会的装置なのです。そこでは、芸術や学問に関する専門性と同時に、組織運営に関する知見やスキルも求められます。館長や学芸員、広報担当、教育普及スタッフ、経理や人事などの管理部門、さらにはボランティアや外部委託業者に至るまで、多様な人々が関わり合いながら「ひとつのミュージアム」を形作っています。
しかしながら、こうした運営の「裏側」は、外部からはなかなか見えにくく、また研究対象としても十分に注目されてきたとは言いがたい領域です。特に日本においては、展示や収蔵品の質に関する議論は活発であっても、組織構造や職員配置、リーダーシップや意思決定の仕組みといった「管理」の側面については、体系的な議論が行われてこなかった面があります。
ところが、グローバルな視点で見ると、ミュージアムの組織運営は今まさに大きな転換期にあります。社会の多様化、テクノロジーの進展、そしてパンデミックのような突発的な危機を経て、ミュージアムはその在り方を根本から問われるようになっています。そしてその問いの多くは、展示の内容ではなく、むしろ「組織はどうあるべきか」という問題に深く関わっているのです。
本稿では、こうした背景を踏まえながら、現代のミュージアムにおける組織管理のあり方を探っていきます。とくに「人」「構造」「価値観」の3つの観点を軸にしながら、海外の研究や事例も交え、持続可能で柔軟性のある組織づくりのヒントを考察します。展示という「表側」を支える「裏側」の仕組み──それがいかに重要で、かつ変化の渦中にあるのかを、読者の皆様とともに見つめ直していきたいと思います。
組織構造の再考─上下関係からネットワーク型へ
これまで多くのミュージアムは、上下関係を前提とした階層的な組織構造のもとで運営されてきました。これは、官公庁や大学、あるいは企業などにおける伝統的なマネジメントのあり方と通底しており、明確な職務分掌と権限の所在が定められていることによって、秩序と統制が保たれてきたという側面があります。館長のもとに副館長や各部門の責任者が置かれ、学芸、教育、広報、事務といった各部署が縦割りで業務を遂行していく体制は、多くの公立ミュージアムにおいて今なお主流です。
しかし、このようなヒエラルキー型の構造は、変化の激しい現代社会において必ずしも効果的とは言えなくなりつつあります。とくに2020年以降、新型コロナウイルス感染症の世界的流行によって、ミュージアムはかつてないスピードで事業の見直しや対応の即応性を迫られました。加えて、Black Lives Matter運動に代表される社会正義や多様性への要請が高まるなかで、内部構造そのものが硬直化しており、時代の要請に応える柔軟性を持ち得ていないという課題が浮き彫りになったのです。
たとえば、アメリカの主要な美術館では、意思決定が上層部に集中しすぎているために、現場の職員の声が届かず、外部環境の急激な変化に機動的に対応できないという問題が観察されました。このような「静的な権力構造」は、ミュージアムが本来担うべき社会的役割──すなわち、公共性、透明性、参加性といった価値──との間に矛盾を生じさせているのです(Tanga, 2021)1。
このような背景を受けて、近年注目されているのが「ネットワーク型」の組織構造です。これは、従来のように上位者が指示を出し、下位者が実行するという直線的な指揮命令系統ではなく、各部署や職能の間を横断的に結びつけ、情報や意思決定を相互に共有することで、柔軟かつ迅速に動ける体制をつくることを目指すものです。水平的な構造、あるいはホラクラシー(権限の分散)などと呼ばれることもあります。
このようなネットワーク型の構造は、フェミニズム理論や草の根的な組織モデルからも大きな影響を受けています。たとえばフェミニズム組織論では、権力や知識の集中を避け、すべてのメンバーが意見を表明しうる場づくりを重視します。また、草の根型の運動体では、フラットで柔軟な意思決定プロセスが、より創造的かつ包摂的なアクションを生み出すことが示されてきました。これらの思想を取り入れたミュージアムの運営モデルは、職員の自律性や信頼関係を基盤とし、役割や責任を柔軟に再構築していくアプローチとして注目されています。
もちろん、すべてのミュージアムが即座にフラットな構造へと転換できるわけではありません。行政的な制約や財政構造、雇用慣行など、制度的な壁は依然として存在します。しかしながら、少なくとも「階層的な構造こそが当然である」という発想から離れ、多様な組織形態の可能性を模索していく姿勢こそが、変化に適応し、未来を見据えるための第一歩となるのではないでしょうか。
ネットワーク型の組織づくりには、単なる「構造」の変更だけでなく、「関係性」の再構築が求められます。つまり、情報を共有し、信頼を育み、異なる意見を尊重する文化的な基盤を醸成することが必要です。組織改革は技術論ではなく、文化変容であるという認識が求められているのです。
組織文化と価値観の可視化──MVFという視座
ミュージアムという組織は、単に機能的な業務の集合体ではありません。むしろそこには、人々の価値観や信念、行動規範といった「文化的な要素」が深く根付いており、それが日々の意思決定や対外的な姿勢に大きな影響を及ぼしています。展示の内容や教育プログラムの方向性、あるいはスタッフ同士のコミュニケーションの仕方に至るまで、組織文化はあらゆる場面において可視・不可視のかたちで作用しているのです。
このような組織文化の複雑さに光を当て、理論的に整理したものとして注目されているのが、「ミュージアム・バリューズ・フレームワーク(Museum Values Framework, 以下MVF)」です。これはイギリスの研究者であるDaviesらが、ミュージアムにおける価値観の多様性とその共存・葛藤の構造を明らかにするために提案した概念的枠組みです(Davies et al., 2013)2。
MVFでは、ミュージアムの内部に存在する価値観を大きく4つに分類しています。
• クラブ型(Club):伝統と仲間意識を重視する価値観で、組織の歴史や内部の結束に強い関心を持ちます。職員間の信頼関係や、組織としての一体感を大切にし、保守的で安定志向の文化を育みます。
• 寺院型(Temple):学問的・専門的権威を重んじる価値観であり、保存・研究部門などに多く見られます。知識の体系化や遺産の保護を至上命題とし、「正しさ」や「真正性」を重視する傾向があります。
• 来館者志向型(Visitor Attraction):来館者の満足や楽しさを第一に考えるサービス重視の価値観で、展示や広報、マーケティング部門に根付くことが多いです。体験の質、来館者数、イベントの効果などが重視されます。
• フォーラム型(Forum):社会的課題への関与、対話、参加を重視する価値観です。ミュージアムを市民と共に築くプラットフォームと捉え、多様な視点やマイノリティの声を取り入れることを使命としています。
多くのミュージアムでは、これら4つの価値が混在しており、部門ごとに優勢な価値観が異なるのが一般的です。たとえば、保存・学芸の部門では寺院型の価値観が強く現れ、学術的厳密さや資料の保護が最重要事項とされます。一方、マーケティングや広報の担当者は来館者の反応や満足度を重視し、イベントの話題性や集客力を軸に活動を展開する傾向があります。また、地域連携や教育普及の現場では、フォーラム型の視座から、社会包摂や市民参加を促進する取り組みがなされることもあります。
このように価値観が部門間で異なること自体は、決して否定的なものではありません。むしろ、ミュージアムという複合的な組織においては、複数の視座が共存し、それぞれの役割を果たすことによって全体のバランスが保たれているとも言えるでしょう。しかしながら、こうした価値観の違いが明示されず、相互理解が不十分なまま放置されていると、やがて対立や軋轢の原因となってしまいます。
たとえば、来館者サービスを拡充したいと考える広報部門と、収蔵品保護を最優先とする学芸部門との間で、「展示空間の使い方」や「撮影の可否」をめぐって意見が衝突することがあります。このような摩擦は、単なる意見の食い違いではなく、背後にある価値観の違いに根ざしているのです。
こうした状況において、組織のリーダーには重要な役割が課せられます。それは、異なる価値観を一元的に統制することではなく、それぞれの立場や視点に耳を傾け、対話を促し、共通の目標へと調和させていく「価値のファシリテーター」としての働きです。MVFは、そのための思考ツールとしても有効であり、組織内部の価値観を可視化し、課題を言語化する助けとなります。
さらに、MVFは自己診断や職員研修の際にも活用できます。たとえば、各職員に「自分の仕事や部門はどの価値観を最も重視しているか」を考えてもらい、全体としての分布をマッピングすることで、組織の文化的傾向や潜在的な摩擦点を事前に把握することが可能です。
ミュージアムにおける組織運営とは、単に機能や成果を管理するだけでなく、「人と価値の関係性をどう築くか」を問う営みでもあります。MVFのような枠組みを用いて、見えにくい「文化」の層を丁寧に観察することは、変化と調和を可能にする第一歩となるのです。
リーダーシップの再定義──調整と共感の力
ミュージアムの館長や管理者は、かつては学芸分野のエキスパートであり、豊富な専門知識と強い判断力をもって組織を率いる「知的リーダー」であることが求められてきました。とくに公立ミュージアムでは、学芸員としてのキャリアを積み重ねた人物が組織の頂点に立ち、コレクションの選定や展示内容の決定、研究の方向性などを一手に担ってきたという歴史があります。
しかし、現代のミュージアム運営においては、こうした「専門性と統制力」のみを重視するリーダーシップでは、必ずしも組織全体を効果的に導くことができなくなっています。社会環境の変化、来館者の多様化、部門間の利害対立、組織文化の多元性──こうした要素が複雑に絡み合うなかで、いまミュージアムのリーダーに必要とされているのは、異なる価値観を認識し、調整し、関係性を築き直す「共感と対話のリーダーシップ」なのです。
この点を明確に指摘しているのが、GriffinとAbrahamによる研究です。彼らは効果的なミュージアム運営を行っている組織に共通するリーダーシップの特性として、以下のような点を挙げています(Griffin & Abraham, 2000)3。
• ビジョンの共有と浸透:組織の方向性を明確に示し、それを職員全体に浸透させていく能力。リーダーは単に戦略を語るのではなく、それが現場の職員一人ひとりの行動とどのように結びついているのかを具体的に伝える必要があります。
• スタッフ間の信頼と協働の促進:部門間、階層間の壁を越えて、信頼関係を築き、協働を推進する力。これは形式的な会議運営ではなく、非公式な対話や日常的なコミュニケーションの質を高めることによって実現されます。
• 現場対応力と柔軟性の尊重:計画や制度にとらわれすぎず、現場の判断や状況に応じた柔軟な対応を可能にする組織風土の醸成。スタッフの主体性を尊重し、ボトムアップの提案を歓迎する姿勢が求められます。
• 来館者中心の組織設計:組織の目標を「来館者の価値ある体験の創出」に再設定し、それを軸に部門横断的な活動を再編する力。ミッションが内部志向に偏らないよう、常に来館者の視点から組織全体を俯瞰する視座が必要です。
このように、リーダーの役割は「命令を下す者」から、「対話を通じて価値を調整する者」へと大きく変化しているのです。
とりわけ現代のミュージアムは、価値観の異なる多様な関係者に囲まれています。来館者、研究者、地域社会、自治体、支援者、ボランティア、さらにはSNSなどを通じて声を上げる匿名の市民──それぞれが異なる期待や視点を持っており、リーダーはそのすべてと向き合わなければなりません。こうした環境においては、感情的知性(emotional intelligence)、すなわち共感力、聴く力、感情の調整力といった人間的なスキルが、リーダーにとって極めて重要な資質となります。
また、組織の中にも価値観の違いが存在することは前章で述べたとおりです。リーダーは、学芸員と広報担当、教育担当と総務部門、ベテランと若手、正規職員と契約スタッフといった異なる立場の人々の意見に耳を傾け、可能な限りフラットな場を作り出す必要があります。そこでは、完璧な解決策を独断で打ち出すのではなく、「問いを共有すること」「合意を丁寧に育てること」が重視されます。
このようなリーダーシップは一見すると「優柔不断」あるいは「リーダーらしくない」と見なされるかもしれません。しかし、組織における複雑な利害や価値観を可視化し、対話を重ねながら共通の目的に向けて少しずつ進んでいくその姿勢こそが、これからのミュージアムを持続可能なものにするための「構造的共感力(structural empathy)」なのです。
従来の「ヒーロー型」から、「ホスト型」あるいは「触媒型」へ──。それが、これからのミュージアム・リーダーに求められる新しい姿だといえるでしょう。
人材マネジメントの失敗と教訓──イタリアの改革から学ぶ
組織改革の議論において、制度や構造の見直しばかりが注目され、人材マネジメント──つまり「人」に関する要素──が軽視されるケースは少なくありません。特に文化機関においては、法律やガバナンスの設計に多くのリソースが割かれる一方で、そこで働く人々の意識や能力、キャリア開発に関する視点が後回しにされる傾向があります。
この問題を象徴的に示しているのが、近年のイタリアにおける博物館制度改革の事例です。2014年から2016年にかけて、イタリア文化財省は一連の大規模な組織改革を進め、特に30の主要博物館を「自律的機関」として位置づけることで、財務管理や運営における柔軟性を高めることを目指しました。この「フランチェスキーニ改革」と呼ばれる取り組みは、組織の構造や法制度に大きな変更を加えたという点で注目を集めました(Zan et al., 2018)4。
しかし、こうした制度改革が進行する一方で、現場の職員の育成、評価制度、キャリアパスの整備といった「人材マネジメント」の領域には、ほとんどと言ってよいほど手がつけられていませんでした。人員の配置は旧来のままで、職員のスキル開発や役割の明確化はなされず、新体制の理念や目的が十分に共有されることもなく時間が過ぎていきました。
その結果として何が起きたのでしょうか。改革に対する現場の理解と納得は乏しく、意欲的な取り組みを促すためのインセンティブも不在であったため、多くの博物館では新しい制度が形骸化してしまいました。トップレベルでは制度上の自律性が確保されたにもかかわらず、実態としては職員の働き方や意思決定のスタイルは旧来のまま温存され、組織の活性化には結びつかなかったのです。
Zanらはこの状況を、「制度の上塗りによる改革疲労」と表現しています(Zan et al., 2018)5。つまり、制度だけが次々と刷新される一方で、制度を運用する「人」の側が置き去りにされてしまうことで、現場ではむしろ混乱や抵抗が生まれ、組織としての機能は弱体化してしまうというのです。これは、組織改革において人材マネジメントがいかに重要であるかを示す、極めて示唆的な事例であるといえるでしょう。
この教訓は、イタリアに限らず、私たちの身近な文脈──たとえば日本のミュージアム行政や公立館の運営体制──にも深く関係してきます。近年、日本でも「指定管理者制度」や「独立行政法人化」などにより、ミュージアムの運営主体やガバナンスの形が大きく変化してきました。しかし、そこで実際に働く人々、すなわち学芸員、教育担当、管理部門スタッフ、契約職員、ボランティアなどに対して、どのような研修が行われ、どのようなキャリアパスが用意されているかと問われると、依然として多くの課題が残されています。
制度改革を成功させるためには、それを担う人々の理解と納得、そして成長の仕組みが不可欠です。人材マネジメントは、単に評価制度を整えることではありません。それは、職員が自らの役割を理解し、学び、成長し、組織の目標と自身の価値を結びつけられるような環境を整備することに他なりません。
そのためには、継続的な研修プログラムの導入、メンター制度やピアレビューの仕組み、職務記述書の明確化、職員同士のフィードバック文化の醸成など、多角的なアプローチが必要です。制度は、運用する「人」がいてこそ生きるのです。
ミュージアムの未来を支えるのは、建物でも制度でもなく、現場で働く一人ひとりの職員です。組織の改革とは、「人の力を最大限に引き出すための条件を整えること」であり、それなくしてどれほど立派な制度を築いても、持続可能な変化は実現しないということを、イタリアの改革は私たちに教えてくれています。
職員の役割変化とチームワークの重要性
ミュージアムという場は、専門性を有する職員によって支えられています。学芸員、教育普及担当、管理スタッフ、広報担当、受付スタッフ、清掃や保守の業務に従事する外部パートナーに至るまで、それぞれが異なる知識とスキルをもって日々の運営に貢献しています。しかし近年、この「職員の役割」に対する期待と求められる資質は、大きく変化しつつあります。
デンマークで行われた長期にわたる職員採用情報の分析によると、過去50年間で博物館が求める人材像は大きく様変わりしたと報告されています(Jensen, 2019)6。1960年代から1980年代にかけては、学歴や学位、特定分野における研究業績といった「形式的資格」や「専門性の深さ」が採用の基準とされていました。とくに公立ミュージアムにおいては、美術史、考古学、自然科学といった学問領域に精通した人物こそが「理想の職員」と見なされていたのです。
ところが1990年代以降、社会の多様化や来館者ニーズの複雑化、そして組織運営の柔軟化が進むにつれて、ミュージアムにおける人材像もまた変化を余儀なくされてきました。現在では、以下のような「人間的スキル」──いわゆるソフトスキルや越境的能力──が重視される傾向が強まっています。
• チームワーク力:他者と協力しながら業務を遂行し、部門間の橋渡し役となる力。特に複数の部署が連携してプロジェクトを実施する際に不可欠な資質です。
• 創造的思考と課題解決能力:型にはまった手法ではなく、柔軟で革新的なアプローチを取り入れながら、現場で発生するさまざまな問題に対応できる能力。
• 多様性への理解と共感:年齢、文化的背景、障がい、ジェンダーなど、さまざまな属性をもつ来館者や同僚への理解をもち、包摂的な態度で接する姿勢。
• 柔軟なコミュニケーション能力:一方的な情報伝達ではなく、相手の立場や感情に配慮しながら、対話的・状況適応的に関わる力。
これらの能力が重視される背景には、ミュージアムの職場環境が「部門の集合体」から「協働するチーム」へと進化しつつあるという構造的変化があります。もはや、専門性の壁に閉じこもって個別に業務を完結させる時代ではありません。むしろ異なる立場や知識、視点を持ったスタッフ同士が連携し、課題を共有しながら横断的に業務を進めていく「コラボレーティブ・チーム」として機能することが、ミュージアムの成果や社会的意義の発揮に直結するのです。
このような環境下では、職員一人ひとりが「専門家であると同時に、協働者でもある」という二重の役割を担うことが求められます。たとえば、ある学芸員が展覧会を企画する際には、広報チームや教育普及部門と緊密に連携し、来館者の体験設計や地域社会との関係づくりまで視野に入れた設計が必要になります。そのためには、単なる知識の専門性だけではなく、共通言語での対話力や、相手の立場を尊重する態度が重要となるのです。
また、組織全体としても、変化に柔軟に対応しながら自律的に学び続ける「ラーニング・オーガニゼーション」としての性格が強まっています。これは、全職員が「自分は学びの担い手である」と意識し、自己成長と組織の成長をリンクさせながら行動する文化を意味します。こうした文化の形成には、上下の命令系統だけでなく、職員同士が学び合い、知識を共有し合うフラットで開かれた関係性が必要です。
このように、職員の役割はもはや「与えられた職務を遂行する個人」ではなく、「チームの中で役割を創造しながら協働し、組織の学びを牽引する存在」へとシフトしています。つまり、ミュージアムは専門性を束ねる場所であると同時に、人と人との関係性を媒介とした「学びの共同体」でもあるのです。
今後、ミュージアムが社会的包摂や地域連携、デジタル変革などの複雑な課題に取り組んでいくうえで、このような人材像とチーム文化の整備は、ますます重要性を増していくことでしょう。
おわりに:組織もまた「展示」である
ミュージアムと聞いて、多くの人がまず思い浮かべるのは、展示室に並ぶ美術品や資料、あるいは展示そのものの構成でしょう。確かに、展示はミュージアムの「顔」とも呼ぶべき存在であり、来館者にとって最も直接的な体験の場であることは間違いありません。しかし、今日におけるミュージアムは、単に作品や資料を「見せる」場ではなく、その展示の背後にある組織のあり方、運営の哲学、働く人びとの姿勢そのものが、来館者に対して強いメッセージを放つ「社会的装置」としての役割を担いつつあります。
言い換えれば、ミュージアムの「展示」とは、物理的な展示室の中だけにとどまるものではなく、むしろその組織構造、意思決定のプロセス、人材の多様性、チームの関係性、そして価値観の可視化といった「見えにくい部分」こそが、現代のミュージアムにおける新しい展示のひとつなのです。
たとえば、多様な文化的・社会的背景を持つスタッフがチームを組み、対等な立場で意見を出し合いながらプロジェクトを遂行している姿は、それ自体が「包摂性のある社会のモデル」として映ります。あるいは、年齢や雇用形態、専門性の違いを越えて連携し、組織の枠を超えた知の協働が実現されている様子は、「学びの民主化」や「社会的連帯」の実践として機能するのです。こうした組織文化そのものが、来館者や地域社会に対する無言のメッセージとして届いていくことになります。
また、展示や教育普及活動がいかに優れていたとしても、それを支える組織の基盤が不安定であれば、長期的な持続可能性は確保できません。日々の運営を担うスタッフが疲弊し、意思決定が非透明で、組織内部の対話が閉ざされていれば、そのひずみはやがて外部にも現れ、来館者の体験や地域社会との関係性にも悪影響を及ぼすでしょう。
だからこそ、持続可能なミュージアムを築くためには、「制度」や「建物」といった目に見えるインフラの整備だけでなく、「人」と「構造」、そして「文化」という、組織の内側にあるソフトな要素の再設計が不可欠なのです。言い換えれば、ミュージアムの未来は、法律や予算だけでは語り尽くせない、関係性と価値観のデザインのうえに成り立っています。
本稿で見てきたように、現代のミュージアムは、価値観の調整が求められる組織であり、リーダーシップやチームワークのあり方が問われる現場であり、制度改革と人材育成のバランスが求められる運営体であると同時に、そのすべてが来館者や社会に向けた「展示」でもあります。展示ケースの中にあるものだけでなく、その外側──つまり組織そのもの──が発信している無数のメッセージにこそ、ミュージアムの本質が映し出されているのです。
これからの時代において、ミュージアムが信頼され、愛され、そして成長し続けるためには、この「組織の展示性」に対する意識を高め、戦略的かつ人間的に組織を育てていく必要があります。そのプロセスは決して一朝一夕に完了するものではありません。しかし、日々の実践のなかで、「どのように展示をつくるか」ではなく、「どのように組織を育てるか」「誰と価値を共有するか」を問い直すことこそが、未来のミュージアムを支える力となっていくでしょう。
参考文献
- Tanga, Martina. “Let’s Imagine a New Museum Staff Structure.” Journal of Conservation and Museum Studies, vol. 19, no. 1, 2021, pp. 1–16. https://doi.org/10.5334/jcms.197. ↩︎
- Davies, Sue M., Rob Paton, and Terry J. O’Sullivan. “The Museum Values Framework: A Framework for Understanding Organisational Culture in Museums.” Museum Management and Curatorship, vol. 28, no. 4, 2013, pp. 345–361. https://doi.org/10.1080/09647775.2013.831247. ↩︎
- Griffin, Des, and Morris Abraham. “The Effective Management of Museums: Cohesive Leadership and Visitor-Focused Public Programming.” Museum Management and Curatorship, vol. 18, no. 4, 2000, pp. 335–368.https://doi.org/10.1080/09647770000301804. ↩︎
- Zan, Luca, Sara Bonini Baraldi, and Maria Elena Santagati. “Missing HRM: The Original Sin of Museum Reforms in Italy.” Museum Management and Curatorship, vol. 33, no. 6, 2018, pp. 530–545. https://doi.org/10.1080/09647775.2018.1537608. ↩︎
- Zan, Luca, Sara Bonini Baraldi, and Maria Elena Santagati. “Missing HRM: The Original Sin of Museum Reforms in Italy.” Museum Management and Curatorship, vol. 33, no. 6, 2018, pp. 530–545. https://doi.org/10.1080/09647775.2018.1537608. ↩︎
- Jensen, Susanne Krogh. “What a Curator Needs to Know: The Development of Professional Museum Work and the Skills Required in Danish Museums 1964–2018.” Museum Management and Curatorship, vol. 34, no. 3, 2019, pp. 1–20.https://doi.org/10.1080/09647775.2019.1641832. ↩︎