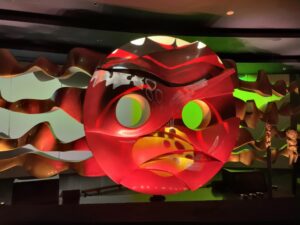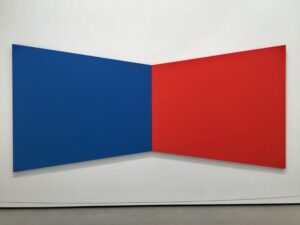はじめに─ミュージアムの予算管理はなぜ語られにくいのか
ミュージアムは、私たちの文化や歴史、美術や科学といった人類の知的・創造的営みを未来へと伝えるための社会的装置です。展示、教育普及、保存、研究、地域との連携といった多様な活動は、その使命を形にする手段であり、ミュージアムの存在意義そのものといえるでしょう。そうした活動を安定して継続するためには、人材、施設、資料、技術、そして何より「お金」が必要です。つまり、持続可能なミュージアムを実現するためには、確かな財務基盤と、それを支える適切な予算管理が不可欠なのです。
ところが、ミュージアムにおける「財務管理」や「予算編成」といったテーマは、専門書でも研究でも、比較的後回しにされてきた傾向があります。その理由の一つは、「お金の話」は公共文化機関にとってタブー視されがちであるという文化的背景にあります。文化や芸術の価値は、しばしば「経済的価値とは異なる」ものとされ、経済性を語ることが本質を損なうかのような抵抗感を伴うことも少なくありません。
また、ミュージアムの運営に携わる専門職員の多くは、学芸、保存、教育、広報といった分野に専門性を持ちながらも、予算や会計、資金調達といった財務管理の専門的な教育を受ける機会が限られてきたという構造的な問題もあります。現場では「なんとか回している」ものの、その基盤がどのように成り立っているのか、持続可能なのかを明確に見通すことができずに、予算不足や事業縮小のリスクに直面するケースも多く見られます。
実際、世界のミュージアム界においても、経済危機や自然災害、パンデミックといった外的要因により、多くの施設が一時的な閉鎖や人員削減を余儀なくされてきました。特に2008年の世界金融危機や2020年以降の新型コロナウイルスの拡大は、ミュージアムの財務の脆弱性をあらわにしました。収入源の多くを観覧料や寄付に依存しているミュージアムでは、来館者数の減少や経済全体の停滞が直撃し、いかに安定した財政基盤を確保しておくかが大きな課題となりました(Skinner et al., 2009)1。
本稿では、こうした現状を踏まえながら、「ミュージアムにおける予算管理とは何か」「なぜそれが難しいのか」「どうすれば持続可能な仕組みを作れるのか」といった問いを軸に、理論と実践の両面から考察を深めていきます。
なぜミュージアムに予算管理が必要なのか
ミュージアムにおける予算管理の重要性は、あらためて強調されるべき論点です。多くの人は、ミュージアムという存在に対して「学術的で高尚な空間」「教育や文化を担う社会的装置」というイメージを抱きますが、実際にはその背後で日々行われている財務管理が、施設の安定性と存続を支えていることは意外と知られていません。予算が適切に組まれ、執行され、見直されることで、ようやく展示活動や保存修復、教育プログラム、調査研究といった中核的な機能が継続可能になるのです。
特に重要なのは、「予算の問題」は突発的な危機によって発生するものではなく、日常的な慢性的課題であるという点です。戦争や自然災害、パンデミックといった外的リスクは確かにミュージアム運営にとって深刻な脅威ではありますが、近年の調査によれば、それ以上に深刻なのが「恒常的な資金不足」と「予算編成・運用の脆弱性」であると指摘されています(Eppich & Grinda, 2019)2。多くのミュージアムが必要最低限の運営資金さえも十分に確保できず、修復やメンテナンスを後回しにせざるを得ない状況に追い込まれているのが現実です。
文化遺産を扱うミュージアムでは、収蔵品や建築物そのものが「保存を必要とする対象」であり、しかもその保存は一過性ではなく、数十年、あるいは百年単位で継続されなければなりません。このような長期的視野に立った運営には、単年度ごとの予算だけではなく、中長期の財務見通しと積極的な財源確保の方針が不可欠となります。
さらに、興味深いのは、不況時におけるミュージアムの来館者数と財務状況の「逆行現象」です。2008年のリーマン・ショック以降の経済後退期や、2020年以降のパンデミック禍においても、一部のミュージアムでは来館者数がむしろ増加したという事例が報告されています。これは、経済的に困難な時期にこそ、安価で質の高い文化的体験を求めて人々がミュージアムを訪れる傾向があることを示しています(Skinner et al., 2009)3。
しかし、このように来館者が増えたとしても、それが直ちに収入の増加につながるとは限りません。実際、多くのミュージアムでは、来館者1人あたりの平均入館料は低く抑えられており、無料公開日などを導入している施設もあります。また、ミュージアムの運営費の多くは、入館料収入ではまかないきれず、寄付や助成金、行政からの補助金によって補完されています。ところが不況時には、こうした外部資金の供給が減少傾向にあり、財源の「入り口」が同時多発的に縮小するという構図が生まれます。
つまり、ミュージアムは「需要が高まる時期に、最も財政的に脆弱になる」という構造的ジレンマを抱えているのです。この矛盾を乗り越えるためには、日頃から柔軟で戦略的な予算管理体制を構築し、突発的な収入減にも対応可能な備えをしておく必要があります。堅牢な予算管理とは、単に「無駄を省く」ことではなく、需要の変動や資金調達の不確実性を想定し、文化的使命を絶やさぬための持続的戦略なのです。
このように見てくると、ミュージアムの財務管理は、単なる会計的操作ではなく、文化政策そのものの実践であることがわかります。予算の設計・執行は、ミュージアムが社会に対してどのような価値を提供し続けるかという問いに対する、非常に実務的な答えの一つです。そしてその答えは、施設ごとに異なる文脈の中で設計されるべきものであり、普遍的な知識とローカルな知恵の両方が求められる分野でもあるのです。
財政的持続可能性の5つの構成要素
ミュージアムの予算管理を考える際、「持続可能性(sustainability)」という概念は欠かせません。特に近年、文化資源の保存と活用を取り巻く国際的な議論では、「文化遺産の持続可能な管理」が重要なテーマとして取り上げられるようになっています。それは、限られた財源の中で、いかにして将来にわたって文化的使命を果たし続けられるかという問いに向き合うことでもあります。
EppichとGrinda(2019)は、ユネスコの世界遺産を含む複数の文化遺産サイトの調査を通じて、ミュージアムを含む文化施設が「財政的持続可能性(financial sustainability)」を確保するために必要な構成要素を5つに分類しました。この枠組みは、営利企業や一般的なNPOとは異なるミュージアム特有の事情──たとえば保存義務、教育的使命、入館料の低価格設定など──をふまえた実践的かつ柔軟な視点を提供してくれます。
以下では、その5つの構成要素について順に見ていきます。
管理計画(Management Planning)
最初の構成要素は、「管理計画の策定」です。ここでいう「管理計画」とは、単なる年間予算書や事業計画書ではなく、ミュージアムが掲げるミッションと長期的な保存・活用戦略を土台にした、戦略的な運営ビジョンのことです。
多くの施設では、保存や展示に関するガイドラインは整備されていても、財務運営と統合された包括的な「中長期計画」が存在しないというケースが少なくありません。Eppichらは、持続可能性の高い施設ほど、財務面と文化的ミッションの両方を視野に入れた計画書を定期的に更新し、関係者と共有している点に着目しています。
特に、建物の老朽化や展示の更新、災害対策など、将来的に多額の支出が見込まれる項目について、あらかじめ予算的見通しを持っているかどうかが、予算の「防御力」を大きく左右します。
収入源の特定と多様化(Revenue Identification and Diversification)
次に重要なのが、「収入源の特定と多様化」です。ミュージアムの収入には、入館料、グッズ販売、寄付、助成金、行政からの補助金、イベント収入、施設貸出など様々な形態がありますが、これらが偏っていると、いずれかの財源が縮小したときに直ちに影響を受けてしまいます。
たとえば、あるミュージアムが運営費の80%以上を行政の補助金に依存していた場合、政権交代や制度改正によって補助金が削減された瞬間に、その運営自体が危うくなる可能性があります。また、寄付金に頼る場合も、寄付の用途が制限されていると(Yermack, 2017)4、自由に使える資金が少なく、結果的に柔軟な運営が困難になるリスクをはらみます。
したがって、持続可能性の高いミュージアムほど、「財源のバスケット」を意識的に組み立て、リスク分散のポートフォリオを築いています。
支出の分析と管理(Expenditure Analysis)
第三の要素は、「支出の分析」です。収入が限られているからこそ、いかに支出をコントロールするかは極めて重要です。ここでいう支出分析とは、単なる経費削減ではなく、各支出がミュージアムのミッションや成果にどのように寄与しているかを定量・定性の両面から見直すことです。
たとえば、管理部門や保守コストの膨張、不要なイベントや広報の投資が予算を圧迫していないか。あるいは、来館者に対する「支出あたりのインパクト」が不均衡になっていないか。これらを把握するためには、財務部門と事業部門が連携して、共通の指標を設定することが求められます。
戦略的な組織運営(Administration and Strategic Planning)
第四の構成要素は、組織全体としての「戦略的な管理体制」です。ここでは特に「予算の意思決定がどこで、誰によってなされているか」がポイントになります。
一部の研究では、分権的で柔軟な管理体制をとっているミュージアムの方が、急激な収入変化への対応力が高いという傾向が指摘されています(Sandalgaard & Bukh, 2021)5。また、外部環境の変化──例えば法改正、パンデミック、資源価格の高騰など──に対して機動的に対応できるかどうかも、組織文化や意思決定プロセスと密接に関係しています。
ミッションとの整合性(Alignment with Cultural, Educational, and Conservation Missions)
最後の構成要素は、「ミッションとの整合性」です。ミュージアムの財務活動は、あくまでも文化的・社会的使命を実現するための手段であり、自己目的化してはなりません。
したがって、予算編成や支出決定のプロセスにおいては、「これは当館のミッションに本当に資する支出か?」「教育や保存の成果と結びついているか?」という問いを繰り返す姿勢が不可欠です。
持続可能性とは、単に赤字を出さないことではなく、文化資源の保全と活用をいかに長期的・自律的に実現していくかという問いに対する、組織の誠実な応答でもあるのです。
このように、財政的持続可能性とは、単なる収支のバランスを取る技術ではなく、「計画」「収入」「支出」「運営」「価値判断」という5つの柱をいかに統合していくかにかかっています。次章では、これらの構成要素がどのように現場で実装され、成功しているミュージアムにはどのような共通点があるのかを、具体的な事例を交えて詳しく見ていきます。
財政的に成功している文化施設の特徴
前節では、ミュージアムの財政的持続可能性を構成する5つの基本要素について詳しく見てきました。それらはすべて、ミュージアムが単年度ごとの収支に一喜一憂するのではなく、文化的使命を長期的に果たしていくための財務体制を築くための「基礎構造」といえるものでした。
では、実際にそれらの構成要素を活用して、財政的に安定し、かつ社会的・文化的成果を上げているミュージアムはどのような特徴を備えているのでしょうか。この節では、国内外の事例研究をもとに、いくつかの共通する「成功の鍵」を明らかにし、次章以降で議論する制度的・文化的課題との対比にもつなげていきます。
開かれた計画環境:内部と外部をつなぐビジョンの共有
財政的に成功しているミュージアムの多くは、まず「計画づくりの段階」から既に組織文化が異なっています。それは、限られた内部メンバーだけで年度予算を決めるのではなく、学芸、教育、保存、広報、財務などの複数部門が横断的に連携し、さらには理事、ボランティア、地域コミュニティや寄付者など外部のステークホルダーとも対話しながら、中長期の運営ビジョンを共有しているという点です。
このような「開かれた計画環境」は、単に民主的であるということだけでなく、財政的リスクの感知や多様な資金源との結びつきを強化するという実利的なメリットをもたらします。財務部門が単なる支出管理の役割にとどまらず、組織全体の「未来を設計するパートナー」として機能しているのが特徴です(Eppich & Grinda, 2019)6。
財務に関する知識の共有と実践
成功している施設では、財務担当者だけが予算を理解しているのではなく、非財務部門の職員──たとえば学芸員、教育普及担当者、施設管理者など──にも基本的な予算構造の理解が浸透しています。これは、管理職のための定期的な財務研修や、誰でも読めるような形で工夫された予算報告書の存在によって実現されています。
特に、アメリカの中小規模のミュージアムでは、職員数が限られるなかで1人が複数業務を兼任している場合も多く、そのような現場では「全員がある程度財務をわかっていること」がむしろ運営の効率性や柔軟性を支えているのです(Christensen & Mohr, 2003)7。
財政に対する肯定的な認識と価値観の共有
ミュージアムというと、「経済性よりも文化性が優先されるべき」という認識が根強い分野でもあります。しかし、財政的に成功している施設の職員は一様に、「予算管理=使命実現の手段である」と明確に捉えています。予算の作成も、支出のコントロールも、すべてはミュージアムの教育・保存・研究という使命を現実化するための「ツール」であり、「敵」ではないという認識が共有されているのです。
このような前向きな財政意識は、財務部門のあり方とも関係しています。財務部が「Noと言う部門」ではなく、「一緒にやる方法を考える部門」として存在している組織では、財政的な議論がプロジェクト推進の出発点になり得ます。これこそが、財政と文化の対立を超える運営モデルです。
分権的で柔軟な運営体制
財政的な健全性を保っているミュージアムでは、現場レベルでの裁量が認められているという点も見逃せません。たとえば、各部門が独自に小規模な予算を管理し、自ら企画を立ち上げ、支出の妥当性を判断することができる仕組みです。
このような分権的な運営は、予算の執行速度や現場の士気を高めると同時に、上位組織が全体戦略をマクロ的に統括することで、柔軟性と方向性の両立が可能になります。また、デンマークの調査によると、実際に収入が予算を下回った年には翌年の予算が大きく削減される一方で、上回った場合の予算増額は限定的であるという「ラチェット効果」が観察されており(Sandalgaard & Bukh, 2021)8、このような制度下では分権的な判断力が危機対応力を左右する可能性があります。
地域や来館者との関係性の強さ
最後に見逃せないのが、地域社会や市民との関係性です。財政的に安定している施設ほど、地元企業や自治体、ボランティア団体、学校などとの連携が密であり、何かあったときには「一緒に支える」力がすでに育っています。
たとえば、寄付キャンペーンの告知やクラウドファンディングの実施時には、既存の来館者ネットワークが呼び水となり、財源確保の実効性が高まります。また、こうした関係性は一朝一夕で築かれるものではなく、日常的な活動において信頼と共感を積み重ねてきた証でもあります。
このように、財政的に成功している文化施設には、構造的な仕組みだけでなく、組織文化や対話の姿勢、マネジメント哲学といった「目に見えにくい資産」が共通して存在しています。次章では、これらの特徴がなぜ一般化しにくいのか、また制度的な障壁や文化的な壁がどのようにそれを阻んでいるのかを考察し、改善への方向性を探っていきます。
よくある課題と改善のヒント
前節では、財政的に成功しているミュージアムの共通点として、「開かれた計画環境」や「財務知識の共有」、「分権的な運営体制」などが鍵であることを見てきました。しかしながら、現実にはそのような理想的な状態に到達できているミュージアムはまだ少数派であり、多くの文化施設では日々、予算編成や財務管理にまつわるさまざまな課題に直面しています。
本節では、ミュージアムが抱えがちな「予算管理に関する壁」について具体的に整理し、それぞれの課題に対してどのような改善策が可能なのかを考察していきます。読者の皆さんが所属する組織でも、すぐに活かせる視点が含まれているかもしれません。
財務情報への忌避感と「お金の話」を避ける文化
ミュージアムの現場で最も根深い課題の一つは、「お金の話はタブー」という空気感がいまだに根強く存在していることです。とくに学芸・教育部門の職員の中には、「予算のことは経理に任せておけばいい」「芸術や文化に金銭を持ち込むのは本質を損なう」といった認識を持つ人も少なくありません。
しかし、そのような姿勢は、結果として財務担当と非財務担当の間に見えない壁を生み、組織内のコミュニケーションや意思決定のスピードを遅らせてしまいます。また、文化の公共性を重視するあまり、収支管理や資金調達に関する議論を避けてしまうことは、かえって持続可能性を脅かす要因にもなり得ます(Eppich & Grinda, 2019)9。
改善に向けた第一歩は、「財務はミッション実現のための言語である」という価値観の共有です。たとえば職員向けの財務勉強会を実施したり、年度末の決算説明を「成果発表会」として可視化することで、財務を「対話のきっかけ」として活用することが可能です。
財務スキルの不足と教育の欠如
多くのミュージアムでは、非財務職のスタッフが予算書の読み方を知らなかったり、「数字に弱いから…」と財務への関心を自ら遠ざけてしまうケースが見られます。とくに中小規模の施設では、財務・経理専門職が不在で、すべての予算処理を館長一人で抱えているような例も少なくありません。
こうした状況は、人材育成の問題でもあります。大学や専門学校でのミュージアム学教育においても、財務や経営に関する科目が十分に位置づけられていないことが多く、学芸員資格や文化財修復士資格の取得に際しても、財務知識が求められることはほとんどありません。
したがって、研修制度の整備や、外部からの専門家招聘、自治体やネットワーク団体による「文化施設の財務講座」の開設など、教育環境の改善が求められます。実際、アメリカの一部の州では、州立ミュージアムネットワークによって定期的なファイナンス研修が提供されており、これにより職員の財務リテラシーが格段に向上している事例もあります(Christensen & Mohr, 2003)10。
使途制限付き寄付の増加と財務の硬直化
寄付や助成金は、ミュージアムにとって重要な収入源ですが、その多くには「使途の指定」があり、特定のプロジェクトや展示、施設整備などにしか使用できないケースが多くあります。Yermack(2017)の研究によれば、アメリカの美術館においては、制限付き寄付の比率が年々高まっており、結果として「自由に使えるお金(unrestricted fund)」が減少する傾向にあると指摘されています11。
このような状況下では、予算の硬直性が増し、突発的な修繕費や緊急対応に使える資金が限られてしまいます。特に、寄付者や助成団体が「目に見える成果」を求めるあまり、長期的な保存や資料整理のような地味だが重要な活動に資金が回らなくなるという逆転現象も起こり得ます。
改善策としては、寄付受入れの段階で「使途の柔軟性」について交渉することが一つです。たとえば「展示関連費」ではなく「文化事業一般」として寄付を受けることで、状況に応じた資金活用が可能になります。また、寄付者に対して「運営の裏側」を可視化し、保存や研究といった分野の重要性を丁寧に伝えることで、共感に基づいた支援を得やすくなります。
財務データの非公開・不透明性
もう一つの大きな課題は、ミュージアムの財務状況が外部に対して十分に開示されていないことです。年次報告書においても、ミッションやイベント報告には力が入っている一方で、収支報告や財務分析に関する情報は簡略的に済まされていることが多く、比較可能性や説明責任の観点からは課題が残ります。
Christensen & Mohr(2003)の調査では、アメリカのミュージアムにおける年次報告書の分析から、財務情報の掲載の有無や内容の詳細さは、規模やジャンルによって大きな差があることが確認されています12。こうした情報格差は、結果として市民の信頼や行政の支援判断にも影響を与えかねません。
改善の方向としては、非営利団体向けの財務報告ガイドラインに基づいた財務開示を進めると同時に、非専門家にも理解しやすい図表・解説付きの報告書を用意することが挙げられます。たとえば「100円の入館料が何に使われているか」といった図解は、来館者や支援者との信頼構築に大きく寄与します。
このように、ミュージアムの予算管理における課題は、制度的・文化的・人的要因が複雑に絡み合っています。しかし、これらは「克服できない壁」ではありません。一つひとつの改善が積み重なることで、ミュージアムの財務体質はより健全で柔軟なものへと変化していきます。
まとめ:予算管理はミッションを支える土台
ミュージアムの予算管理は、単なる帳簿管理ではありません。それは、文化・教育・保存という本来のミッションを支えるための「戦略的行為」なのです。予算管理が適切に行われることで、ミュージアムはその価値を未来にわたって維持・発展させていくことができます。
不況や補助金の削減、寄付の制約など、多くの不確実性が取り巻く中で、柔軟性と透明性を両立した財務運営がこれからのミュージアムに求められる条件といえるでしょう。
参考文献
- Skinner, Sarah J., Robert B. Ekelund Jr., and John D. Jackson. “Art Museum Attendance, Public Funding, and the Business Cycle.” American Journal of Economics and Sociology, vol. 68, no. 2, 2009, pp. 491–516.https://doi.org/10.1111/j.1536-7150.2009.00631.x ↩︎
- Eppich, Rand, and José Luis García Grinda. “Sustainable Financial Management of Tangible Cultural Heritage Sites.” Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, vol. 9, no. 3, 2019, pp. 282–299. https://doi.org/10.1108/JCHMSD-11-2018-0081. ↩︎
- Skinner, Sarah J., Robert B. Ekelund Jr., and John D. Jackson. “Art Museum Attendance, Public Funding, and the Business Cycle.” American Journal of Economics and Sociology, vol. 68, no. 2, 2009, pp. 491–516.https://doi.org/10.1111/j.1536-7150.2009.00631.x ↩︎
- Yermack, David. “Donor Governance and Financial Management in Prominent US Art Museums.” Journal of Cultural Economics, vol. 41, no. 3, 2017, pp. 303–331. https://doi.org/10.1007/s10824-017-9290-4. ↩︎
- Sandalgaard, Niels, and Per Nikolaj Bukh. “Budget Ratcheting in Museums.” Aalborg University Business School, 2021.https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2023-0055 ↩︎
- Eppich, Rand, and José Luis García Grinda. “Sustainable Financial Management of Tangible Cultural Heritage Sites.” Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, vol. 9, no. 3, 2019, pp. 282–299. https://doi.org/10.1108/JCHMSD-11-2018-0081. ↩︎
- Christensen, Anne L., and Rosanne M. Mohr. “Not-for-Profit Annual Reports: What Do Museum Managers Communicate?” Financial Accountability & Management, vol. 19, no. 2, 2003, pp. 139–170.https://doi.org/10.1111/1468-0408.00167 ↩︎
- Sandalgaard, Niels, and Per Nikolaj Bukh. “Budget Ratcheting in Museums.” Aalborg University Business School, 2021.https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2023-0055 ↩︎
- Eppich, Rand, and José Luis García Grinda. “Sustainable Financial Management of Tangible Cultural Heritage Sites.” Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, vol. 9, no. 3, 2019, pp. 282–299. https://doi.org/10.1108/JCHMSD-11-2018-0081. ↩︎
- Christensen, Anne L., and Rosanne M. Mohr. “Not-for-Profit Annual Reports: What Do Museum Managers Communicate?” Financial Accountability & Management, vol. 19, no. 2, 2003, pp. 139–170.https://doi.org/10.1111/1468-0408.00167 ↩︎
- Yermack, David. “Donor Governance and Financial Management in Prominent US Art Museums.” Journal of Cultural Economics, vol. 41, no. 3, 2017, pp. 303–331. https://doi.org/10.1007/s10824-017-9290-4. ↩︎
- Christensen, Anne L., and Rosanne M. Mohr. “Not-for-Profit Annual Reports: What Do Museum Managers Communicate?” Financial Accountability & Management, vol. 19, no. 2, 2003, pp. 139–170.https://doi.org/10.1111/1468-0408.00167 ↩︎