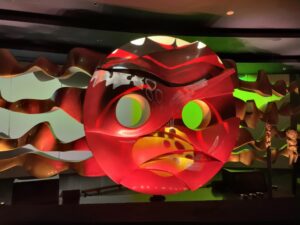はじめに:なぜ今、博物館のデジタル化が重要なのか
21世紀に入り、私たちの社会はあらゆる側面でデジタル技術の影響を受けるようになりました。特にここ十数年で進行したスマートフォンの普及やクラウドサービス、ソーシャルメディアの発展は、人々の情報取得行動、コミュニケーションの形式、そして学習や体験の在り方そのものを大きく変化させています。このような変化は、文化施設である博物館にとっても例外ではなく、これまでのように「展示を整え、来館者を受け入れる」だけの運営では、社会の多様なニーズに応えきれなくなりつつあります。
加えて、COVID-19の世界的な拡大は、博物館経営に対してかつてないほどの転換点をもたらしました。多くの館が長期休館を余儀なくされ、フィジカルな場に依存しない新たな運営形態を模索せざるを得なくなったことで、ソーシャルメディアによる情報発信、オンライン展示やバーチャルイベントの実施、さらにはデジタルアーカイブの公開などが急速に進展しました。Agostinoら(2020)は、このパンデミックによる急激な変化を「外部から強制されたデジタル変革」と位置づけ、従来の延長線上にない戦略的再編が必要であることを強調しています(Agostino et al., 2020)1。
このような社会的背景において、博物館のデジタル化とは、単に新しい技術を導入するというレベルの話ではありません。それはむしろ、博物館が社会においてどのような使命を果たし、どのような価値を提供するのかという「ミッションの再構築」と直結する根本的な課題なのです。来館者との関係性が物理的空間の中だけではなく、デジタル空間にも拡張される現在、展示の設計、学芸活動の可視化、教育コンテンツの配信、さらには運営管理のあり方までもが、再設計を迫られています。
実際、Kamariotouら(2021)は、ICTの活用が博物館の「人的資源」「財務的資源」「技術的資源」という三つの経営資源に大きく関与しており、デジタル戦略はもはやオプションではなく、博物館経営の中核的要素になりつつあると述べています(Kamariotou et al., 2021)2。このように、技術導入という表層の変化の背後には、博物館の価値創造の仕組みそのものが変わるという、より本質的な変化が横たわっているのです。
本稿では、こうした変化を踏まえ、デジタル化が博物館にもたらす影響を「経営資源としてのデジタル技術」「来館者体験の変容」「制度的・政策的枠組みとの関係」という三つの視点から検討していきます。これは単にITを活用するか否かの問題ではなく、博物館が「どのような社会的存在であるべきか」を問い直す営みでもあります。その意味で、デジタル化とは“手段”であると同時に、“価値の再構築”を促す契機なのです。
経営資源としてのデジタル技術
デジタル化の進展は、展示や広報の手法を変えるだけではありません。それは博物館の「経営資源」の再定義を促すものでもあります。これまで博物館の資源といえば、展示資料、建物、人的資源、予算などが中心とされてきましたが、ICT(情報通信技術)はそれ自体が新たな資源であり、また既存資源の価値や活用方法を変質させる力を持っています。
Kamariotouら(2021)は、ICTの導入を博物館の「人的資源」「財務的資源」「技術的資源」の3つに分類し、それぞれが経営戦略に深く関与していると指摘しています(Kamariotou et al., 2021)3。たとえば、人的資源の面では、単にITスキルを持つ人材を確保するだけでなく、学芸員や教育担当者がICTを活用して新たな来館者体験を創出する能力が求められます。財務的資源においては、デジタル設備の導入・更新費用や、システム運用にかかるランニングコストをどのように捻出し、持続可能性を確保するかが問われます。そして技術的資源においては、Wi-Fi環境、データベース構築、CMS(コンテンツ管理システム)などが、日常的な運営の質と効率性を左右します。
こうした経営資源としてのICTの活用をめぐっては、COVID-19の影響も無視できません。Agostinoら(2020)は、パンデミック下で多くの博物館が急速にオンライン化を進めた過程を分析し、「戦略なき導入」のリスクを警鐘しています。イタリアの博物館を対象にした調査では、感染拡大防止のためにSNS配信やオンライン展示を実施したものの、その多くが短期的施策にとどまり、組織的に継続できなかった事例が少なくなかったと報告されています(Agostino et al., 2020)4。
このように、ICT導入の成否は、単なる技術選定やツール導入にあるのではなく、それを「なぜ導入するのか」「どのように戦略化するのか」という問いへの明確な答えにかかっています。デジタル技術を「経営の中核的リソース」として位置づけるには、それが博物館のミッション達成にどう寄与するのかを可視化し、組織内で共有することが求められます。
また、技術を持続可能に活用していくには、部門間の連携も不可欠です。展示部門・教育部門・広報部門・情報システム部門が、それぞれの視点を持ち寄りながら、ICTを共通の「戦略的インフラ」として扱うことができるかどうか。これこそが、これからの博物館経営における競争力を左右する鍵となるでしょう。
来館者体験とデジタル化の接点
博物館の本質的な価値は、単に資料や作品を展示することではなく、それらを通じて来館者が何を感じ、何を学び、どのような意味づけを行うかという体験にあります。そうした観点から、デジタル技術の導入は来館者体験そのものを変革し得る力を持っています。展示空間における解説メディアの進化、AR(拡張現実)やVR(仮想現実)を活用した没入型体験、スマートフォンを通じたセルフガイド、または来館前後のオンライン接点など、体験の接点は時間的にも空間的にも拡張しています。
Heら(2018)は、博物館の展示にAR技術を導入した実験的研究の中で、視覚的情報の拡張によって来館者の理解と興味が高まり、鑑賞体験における“記憶への残りやすさ”が向上することを報告しています(He et al., 2018)5。このような視覚的没入の強化は、知的好奇心の喚起だけでなく、作品や資料との感情的なつながりを育むという点でも有効であると考えられます。
また、Leeら(2021)の研究では、教育プログラムにARを導入することで、児童・生徒がより能動的に展示物と関わるようになり、「知識の受け手」から「発見の主体」へと認知的枠組みが移行するプロセスが描かれています(Lee et al., 2021)6。これは、来館者の学びが「鑑賞」から「参加」へと変容しつつある今日のミュージアムの在り方を象徴するものであり、展示の構成や教育普及活動の設計にも大きな影響を与えます。
さらに、Parsehyan(2020)は、イスタンブールの博物館群を対象とした研究において、デジタル化の成熟度を四つの類型に分類しました。それによれば、「体験志向型」に分類される館では、ARガイドやオンライン展示、インタラクティブな参加型コンテンツが統合されており、来館者は単なる情報受容者ではなく、体験の共創者として位置づけられています(Parsehyan, 2020)7。このタイプの館では、来館前・来館中・来館後においてデジタル技術が一貫して活用されており、総合的な来館者体験の質の向上が確認されています。
このように、デジタル化は来館者体験の各段階において新たな選択肢をもたらしていますが、それは同時に「どの技術をどの目的で使うのか」という選択と設計が不可欠であることも意味します。単なる目新しさに終始するのではなく、来館者にとって意味のある体験をいかに設計するか。そこにこそ、博物館におけるデジタル化の本質的な課題があるのです。
COVID-19と強制的デジタル化の教訓
2020年以降、世界的に広がったCOVID-19のパンデミックは、博物館経営におけるデジタル化の位置づけを劇的に変化させました。物理的な施設の閉鎖、三密回避、観光客の減少などにより、これまで当たり前であった「現地で展示を体験する」というモデルが一時的に成立しなくなったのです。この状況下で、多くの博物館は来館者との接点を維持するため、急速にソーシャルメディア、ライブ配信、オンライン展示などのデジタル手段に移行しました。
Agostinoら(2020)は、イタリアの100の国立博物館に対する調査において、COVID-19を契機に博物館のオンライン活動が急増したこと、そしてその多くが「戦略に基づかない即応的施策」であったことを明らかにしました(Agostino et al., 2020)8。彼らは、こうしたデジタル対応が新たなサービス提供の可能性を拓いた一方で、持続可能な資源投下や組織横断的な連携が欠如していたことを問題点として指摘しています。
この調査では、パンデミック期の博物館が直面した「三つのジレンマ」も示されています。第一に、ユーザー中心と博物館中心の価値提供のバランス。すなわち、来館者のニーズに応じた柔軟な発信と、博物館の学術的・専門的立場との間に生じる摩擦です。第二に、計画性と即応性の間の緊張関係。オンライン施策は迅速な対応を可能にしたものの、戦略性を欠いた場合には継続的成果に結びつかないという課題があります。第三に、無料提供と収益化の問題。多くの館が無償でコンテンツを公開したことでアクセス数は増えましたが、有料化の導入には慎重な検討が必要となり、その線引きは依然として課題です。
こうしたジレンマは、日本を含む多くの国の博物館においても共通する課題といえるでしょう。デジタル化が短期的には危機対応策であったとしても、それを中長期的な経営資源として組み込むには、ミッション、運用体制、資金、そして人材といった多面的な視点からの再設計が必要です。
COVID-19の経験は、単なる非常時対応を超えて、「デジタル技術は博物館の根幹に関わる」と再認識させる契機となりました。この教訓を踏まえ、今後のミュージアム経営には、デジタルを単なる手段ではなく、文化的価値と社会的ミッションを実現するための基盤として戦略的に活用していく姿勢が求められます。
博物館のデジタル成熟度と4つのタイプ
博物館におけるデジタル技術の活用状況は、必ずしも一律ではありません。館の規模、設立形態、地域性、職員のスキル、予算状況などによって、デジタル化の進展には大きなばらつきが見られます。こうした違いを体系的に整理し、段階的に把握するための有効なフレームワークとして注目されているのが、Parsehyan(2020)が提唱した「博物館のデジタル成熟度の4類型」です。
この研究は、イスタンブール市内の私立博物館を対象に、デジタル技術の導入状況を「来館前・来館中・来館後」の3フェーズに分けて分析し、それぞれの館がどの程度ICTを活用しているかをもとに以下のような4つのタイプに分類しました(Parsehyan, 2020)9。
- 睡眠型(Dormant Type) デジタル技術の活用が極めて限定的で、ウェブサイトやSNSすら整備されていない館。来館者との接点が物理的空間のみに限定されており、情報発信や関係性の構築が著しく制限されている。
- 社会志向型(Social-Oriented Type) SNSを通じた情報発信は活発に行っているものの、展示や館内でのICT活用は不十分。主に外部への広報に焦点を当てており、デジタル技術はあくまで宣伝手段として捉えられている。
- 訪問志向型(Visit-Oriented Type) 館内でのAR展示やデジタルガイドなど、来館中の体験強化に一定の投資がなされている。来館前後のフォローやオンライン上での双方向的な関係構築には未着手のことが多い。
- 体験志向型(Experience-Oriented Type) 来館前のウェブ予約・情報発信、館内での没入型展示、来館後のフォローアップコンテンツ提供までを一貫してICTでカバーしている。デジタルが単なる手段ではなく、館全体の運営理念に組み込まれている。
この分類の意義は、単に技術の導入有無を評価するのではなく、博物館がどのような来館者体験を設計しているか、そしてその体験をどう持続可能なかたちで提供しているかを可視化できる点にあります。特に体験志向型に分類される館では、デジタル技術が展示と統合され、来館者が物理的・感覚的・感情的に関与できるよう工夫されているため、満足度の向上や再訪意向の増加が期待されます。
日本国内においても、規模の大きな国立博物館や一部の先進的私立館がこの体験志向型に近づきつつある一方で、多くの地域館や中小規模館はまだ社会志向型または訪問志向型にとどまっているケースが少なくありません。自身の館がどのタイプに該当するかを把握し、そこからどのような改善が可能かを考えることは、今後のデジタル戦略を描くうえで有効な出発点となるでしょう。
公共文化政策と制度整備の視点
博物館におけるデジタル化は、個々の館の努力だけで推進できるものではありません。その基盤には、制度、予算、法的整備、専門人材の育成といったマクロな支援体制が不可欠です。とりわけ公立博物館においては、地方自治体や文化行政の方向性が、デジタル施策の実施可能性に大きく影響を与えています。
Antonova & Hololobov(2023)は、ウクライナの博物館を事例に取り上げ、文化施設におけるデジタル技術導入の障壁として、制度的整備の遅れ、専任スタッフの不足、資金不足の三点を指摘しています(Antonova & Hololobov, 2023)10。この調査は、戦争という極端な文脈下における博物館のデジタル適応を扱っていますが、その課題構造は日本を含む多くの国と共通するものといえるでしょう。
たとえば、日本の地方自治体が設置する小規模な博物館では、デジタル施策に充てられる予算が限定されているケースが少なくありません。ICT機器の導入に加え、その運用や保守にかかる経費、あるいはコンテンツ制作にかかる人的コストを計上できる体制が整っていない場合も多く見られます。また、情報システム担当者の不在や、展示・教育・広報部門との連携不足といった組織内の課題も、デジタル化の定着を妨げる要因となっています。
さらに、文化財保護や教育との整合性を保ちつつ、博物館がデジタル領域でどこまで自由に発信できるかという「ガバナンス」の問題も見逃せません。たとえば、アーカイブ資料のデジタル公開には著作権処理が伴い、館の判断だけでは対応しきれないケースも存在します。こうした複雑な課題に対しては、国や自治体による支援制度の整備と方針の明確化が必要不可欠です。
一方で、文化政策がデジタル技術を経営戦略の中核に据えた成功事例もあります。たとえばイギリスでは、国が主導する「Digital Culture Compass」のような指標を用いて、各文化機関のデジタル成熟度を可視化し、補助金制度や職員研修との連携を図っています。このようなトップダウン型の支援とボトムアップ型の現場実践が連携する構造は、制度としての持続可能性を高めるうえで有効なモデルといえるでしょう。
したがって、今後日本においても、館ごとの自主性や創意工夫を尊重しつつ、国家レベルでの制度設計・人材育成・予算措置の三位一体による支援が求められます。デジタル化が「できるかどうか」ではなく、「どのように社会的価値と結びつけるか」を問う段階へと移行している今、政策の在り方もまた変革を迫られているのです。
おわりに:未来の博物館は「技術の場」か「関係性の場」か
ここまで見てきたように、デジタル化は博物館のあらゆる側面に影響を与えています。経営資源としての再編、来館者体験の変容、公共文化政策との接続といった観点から、ICTはすでに博物館にとって「付加的な道具」ではなく、「中核的な運営基盤」として機能しつつあることが明らかになりました。
とはいえ、こうした技術の進展は、必ずしも自動的に博物館の価値や公共性を高めるものではありません。むしろ今後は、「何を目的にデジタル化を進めるのか」「その技術が誰のために、どのように使われるべきか」といった、より根本的な問いが重要になります。
その際に鍵となるのが、博物館が社会とどのような関係性を築いていくのかという視点です。来館者が「情報を受け取る」だけの存在であった時代から、「体験の共創者」や「意味の担い手」として位置づけられる現在、デジタル技術はその関係性を支えるための媒介装置として機能する可能性を秘めています。
たとえば、ARによって見えなかった文化的背景を可視化したり、SNSによって展示に対する感想や対話を共有したりする場面では、技術が人と人、人と文化遺産、人と組織をつなぐ接点となります。そこでは、「どの技術を使うか」ではなく、「どのような関係性をつくりたいのか」が起点となり、デジタル化はそのビジョンを実現するための手段として位置づけられます。
今後、博物館にとってのデジタル化とは、単に便利な仕組みや見栄えの良い技術を導入することではなく、「自らの存在意義を問い直し、社会とどうつながるかを再設計するプロセス」なのだと言えるでしょう。
すなわち、未来の博物館とは、「技術の場」である前に、「関係性の場」としてのあり方を模索する空間であり、そこにこそ、デジタル時代における公共文化施設の使命が宿るのです。
参考文献一覧
- Agostino, D., Arnaboldi, M., & Lampis, A. (2020). Italian state museums during the COVID-19 crisis: From onsite closure to online openness. Museum Management and Curatorship, 35(4), 362–372.https://doi.org/10.1080/09647775.2020.1790029 ↩︎
- Kamariotou, V., Kamariotou, M., & Kitsios, F. (2021). Strategic planning for virtual exhibitions and visitors’ experience: A multidisciplinary approach for museums in the digital age. Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage, 21, e00183.https://doi.org/10.1016/j.daach.2021.e00183 ↩︎
- Kamariotou, V., Kamariotou, M., & Kitsios, F. (2021). Strategic planning for virtual exhibitions and visitors’ experience: A multidisciplinary approach for museums in the digital age. Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage, 21, e00183.https://doi.org/10.1016/j.daach.2021.e00183 ↩︎
- Agostino, D., Arnaboldi, M., & Lampis, A. (2020). Italian state museums during the COVID-19 crisis: From onsite closure to online openness. Museum Management and Curatorship, 35(4), 362–372.https://doi.org/10.1080/09647775.2020.1790029 ↩︎
- He, Z., Wu, L., & Li, X. R. (2018). When art meets tech: The role of augmented reality in enhancing museum experiences and purchase intentions. Tourism Management, 68, 127–139.https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.03.003 ↩︎
- Lee, J., Lee, H. K., Jeong, D., Lee, J., Kim, T., & Lee, J. (2021). Developing museum education content: AR blended learning. International Journal of Art & Design Education, 40(3), 473-491.https://doi.org/10.1111/jade.12352.
↩︎ - Parsehyan, B. G. (2020). Digital transformation in museum management: The usage of information and communication technologies.DOI:10.47356/TurkishStudies.45995 ↩︎
- Agostino, D., Arnaboldi, M., & Lampis, A. (2020). Italian state museums during the COVID-19 crisis: From onsite closure to online openness. Museum Management and Curatorship, 35(4), 362–372.https://doi.org/10.1080/09647775.2020.1790029 ↩︎
- Parsehyan, B. G. (2020). Digital transformation in museum management: The usage of information and communication technologies.DOI:10.47356/TurkishStudies.45995 ↩︎
- Antonova, L., & Hololobov, S. (2023). Digital transformation of museums: challenges and opportunities for state policy in the field of culture. Public Administration and Regional Development, (20), 303-329.https://doi.org/10.34132/pard2023.20.02 ↩︎