博物館における「経営」とは何を意味するのか
近年、博物館においても「経営」という言葉が頻繁に用いられるようになってきました。かつて博物館は、文化財の保存や学術的研究、教育普及といった公益的な活動を担う非営利の文化施設として、営利を目的とした「経営」からは距離を置いて捉えられていました。しかし、公共施設のあり方が見直される中で、持続可能な運営を実現するために、博物館もまた「経営視点」を必要とする組織として再評価されています。
この背景には、自治体財政の逼迫、来館者数の減少、社会的な多様性への対応といった複雑な課題が重なって存在しています。これらに対応するためには、従来の「文化施設=行政運営主体」という枠組みを超えて、目標設定・資源配分・評価のサイクルを意識した運営が求められています(Lord & Lord, 2009)。そのため「博物館経営」とは、単なる管理・維持運営ではなく、より戦略的・持続的にミッションを実現していくための総合的な営みと位置付けることができます。
ミッション達成を軸とした経営の定義
博物館における経営は、営利企業のように売上や利益を追求することを目的とするものではありません。むしろ、各館が掲げるミッションを出発点とし、その使命を達成するためにどのような資源を、どのように活用するかを設計することが重要です。たとえば、「地域の自然と文化を次世代に継承する」「子どもたちに生きた学びの場を提供する」といったミッションは、来館者対応だけでなく、展示・収蔵・教育・研究といった複数の機能にまたがって体現される必要があります。
Lord & Lord(2009)はこの点を、「博物館経営とは、資源の調整・統合を通じて、ミッションの実現を図る行為である」と定義しており、経営の中核にあるべきは“価値”の創出であるとしています。また、Sandell & Janes(2007)は、経営とは外部環境の変化に柔軟に対応しながら、組織の方向性と優先順位を調整していくプロセスであると述べています。
このように、ミッション達成を出発点に据える経営の定義は、公共文化施設としての責任と戦略性を両立させるための根幹であり、後述する制度や関係性とも密接に結びついています。
公共施設における経営視点の必要性
現代の博物館は、公共施設であると同時に、社会からの信頼を維持し続けるための説明責任を負っています。かつてのように「行政が担保する公益性」だけでは不十分であり、いかにその役割を具体的に可視化し、評価し、持続的に支えていくかという点において、経営視点が欠かせなくなっているのです。
特に日本では、自治体財政の厳しさに伴い、指定管理者制度の導入や、補助金の削減、自主財源の確保といった現実的課題が博物館経営に重くのしかかっています(Greffe et al., 2017)。こうした状況の中で、ミッションと財源、人材と来館者、文化的価値と経済的持続性をどうバランスさせていくかは、まさに経営の課題です。
この点で重要なのは、「経営=収益化」という単純な図式ではなく、「経営=選択と配分の意思決定の質を高めること」と再定義する姿勢です。限られたリソースをいかに戦略的に使うか、社会的インパクトをいかに生み出すかという視点は、あらゆる公共施設の運営に求められている時代的要請であり、博物館も例外ではありません(Hatton, 2012)。
制度と財政が左右する博物館の運営構造
博物館の経営を考える上で、避けて通れないのが「制度」と「財政」の問題です。どれほど理想的なミッションを掲げ、魅力的な展示や教育活動を計画しても、それを実行に移すためには、制度的な枠組みと安定した財源の裏付けが不可欠です。とりわけ日本においては、博物館を取り巻く制度的背景が多様であり、運営主体によってその影響も大きく異なるため、制度と財政は博物館経営に直結する基本構造といえます。
この節では、まず日本の博物館制度の全体像と制度区分について概観し、次に財源構造の現状と課題を整理します。さらに、指定管理者制度の導入による影響や、国際的な制度比較にも触れながら、制度と財政が博物館経営にどのように影響を与えているかを考察していきます。
日本の制度的枠組みと登録博物館制度
日本の博物館は、「博物館法」(1951年)を根拠法とし、その法制度のもとで「登録博物館」としての公的認証を受けることができます。この制度は、社会教育法や文化財保護法と連動しながら、博物館の社会的役割を規定しており、教育機関としての性格を持つ博物館にとって一定の信頼性を担保する仕組みとなっています(文部科学省, 2022)。
しかし一方で、登録制度の要件(専任職員の配置や収蔵資料数など)がハードルとなり、多くの私立博物館や小規模館が未登録のまま運営されている実態もあります。これは、制度が「整備された博物館」に適用されることを前提としている一方で、地域密着型や民間主導の博物館が制度的な保護を受けにくい状況を生んでいるとも言えます。
指定管理者制度と財政的自立の課題
2003年の地方自治法改正により導入された「指定管理者制度」は、公立博物館の運営形態を大きく変える契機となりました。従来は自治体の直営が主流であった博物館も、この制度によりNPO法人や民間企業などが指定を受けて運営を担うことが可能となり、「公設民営」という形が一般化してきました。
この制度のメリットとして、柔軟な経営判断、運営コストの削減、多様なノウハウの導入が挙げられます。一方で、短期的な業績評価に偏りやすく、学芸員の継続雇用が困難になるなど、文化施設としての安定性を損なうケースも報告されています(みずほ総合研究所, 2019)。また、指定期間が数年単位であることが多いため、長期的視点に立った展示計画や人材育成が難しいという課題も指摘されています。
経営の自由度が増した反面、財政的な自立が求められ、補助金に依存せずに収益を確保する必要が高まっています。このような状況では、単なる運営効率化にとどまらず、「何のための経営か」という価値判断がますます重要になっています。
海外の制度に見る比較視点と示唆
国際的に見ると、フランスやイギリスでは、国家や自治体が博物館の公共的役割を法的に明確化しつつも、運営の多様性と自律性を尊重する制度設計が進められています。とくにフランスでは、文化的権利や文化民主主義の観点から、地域と連携した制度モデルが発展してきました(Greffe et al., 2017)。
一方、アメリカでは公的支援が限定的である代わりに、寄付文化やメンバーシップ制度が財政基盤の中核を成しており、民間の参加が制度に組み込まれています。このような事例は、日本の制度改革に対しても多くの示唆を与えています。
制度は単に博物館を管理する枠組みではなく、「どのような価値を社会に提供するか」をめぐる選択の反映でもあります。したがって、経営を考える際には、制度的背景を単なる制約と捉えるのではなく、戦略的に活用すべき構造として再評価することが重要です。
戦略的経営とは何か ― ミッションと資源の再配分
博物館が持続的かつ効果的に社会的役割を果たしていくためには、制度や財政の枠組みを理解するだけでなく、それを踏まえた「戦略的経営」の構築が不可欠です。ここでいう戦略とは、単なる計画や目標の羅列ではなく、ミッションを軸にした資源配分と意思決定の体系を意味します。つまり、博物館が何を優先し、何に制約を受けるかを見極めながら、限られた資源を最大限に活かしていくための方向づけこそが戦略なのです。
この節では、まず博物館における戦略的思考の基本と実務上の適用可能性を整理し、次に「使命志向」と「市場志向」のバランスをとるための視点について考察します。さらに、展示・教育・収蔵といった複数の機能がどう相互補完され、どのように優先順位を設定するべきかについても言及します。
来館者・地域・研究・教育の優先順位をどう決めるか
博物館は展示・収蔵・教育・研究・来館者対応といった複数の使命を持つ複合的な組織です。しかしながら、現実には人材も予算も限られており、すべてを等しく実行することは困難です。こうした状況下で、いかに優先順位を設定し、資源を配分するかが戦略的経営の中核をなします。
たとえば、観光資源としての役割を重視する地方館では、地域振興との接続を強めた来館者サービスが優先される一方、大学附属の博物館では研究と収蔵の充実が重視される場合もあります。このように、同じ「博物館」であっても、その立地・運営母体・ミッションによって戦略の形は大きく異なります(Lord & Lord, 2009)。
重要なのは、単なる部門ごとの最適化ではなく、全体のミッションに照らして「この資源配分が社会にどのような価値をもたらすのか」を判断する視座を持つことです。展示に偏るのではなく、調査研究や教育活動とも連動した戦略設計が求められています。
「使命志向」と「市場志向」のバランスをとる思考法
近年、博物館の経営において注目されているのが、「使命志向(mission-driven)」と「市場志向(market-driven)」の調和という考え方です。Sandell & Janes(2007)は、公共的価値を追求することと、来館者の期待に応えることは、対立概念ではなく相補的に設計可能であると述べています。
たとえば、学術的に価値のある展示であっても、来館者の関心に配慮したナラティブ設計やデジタル体験を導入することで、教育と参加を両立させることができます。こうした視点は、展示企画や広報戦略だけでなく、料金制度やミュージアムショップ、ボランティアマネジメントなどにも応用可能です。
戦略的経営とは、単に「人を集める」ことでも、「文化を守る」ことでもなく、両者のあいだに橋を架ける思考をもつことだと言えるでしょう。そのためには、来館者の属性やニーズを調査・分析し、可視化されたデータに基づいて意思決定を行うことが鍵となります。
関係性のマネジメントが経営を支える
現代の博物館経営において、もはや無視できないのが「関係性」の視点です。かつては、収蔵品を中心に据えた展示や保存が博物館の主たる使命とされていましたが、現在では、来館者・地域社会・支援者・行政など、さまざまなステークホルダーとの関係構築が経営の質を左右する要素として位置づけられています。
こうした関係性を戦略的に設計し、育てていく営みは、「リレーションシップ・マネジメント」とも呼ばれ、来館者満足や地域との連携、ファンドレイジング、そして組織の信頼性強化に直結しています(Macdonald, 2006)。この節では、来館者との信頼形成、地域・行政との協働、支援者との継続的関係といった観点から、博物館の関係性マネジメントの実際と課題を考えていきます。
来館者との信頼構築とデータ活用
来館者との関係性は、単なるサービス提供の枠を超えて、博物館の存在意義そのものを社会に対して可視化する営みでもあります。来館者にとっての「また来たい」と思える体験や、「ここで学び、考えたい」と感じられる場づくりは、経営にとっての長期的なリピート率や支援意欲にも大きく影響します。
特に近年は、来館者調査やデジタル分析ツールを活用することで、来館者の満足度やニーズを可視化し、戦略的な施策に反映させる取り組みが進んでいます。定性的な声と定量的なデータを組み合わせることで、「なぜ来館するのか」「なぜ帰ってこないのか」を分析し、展示や広報の改善、サービス設計に活かすことができます。
また、アクセス解析やアンケート結果を来館者との対話のきっかけとして活用することも重要です。データは分析のためだけでなく、関係性を構築・修復するための資源としても機能するのです。
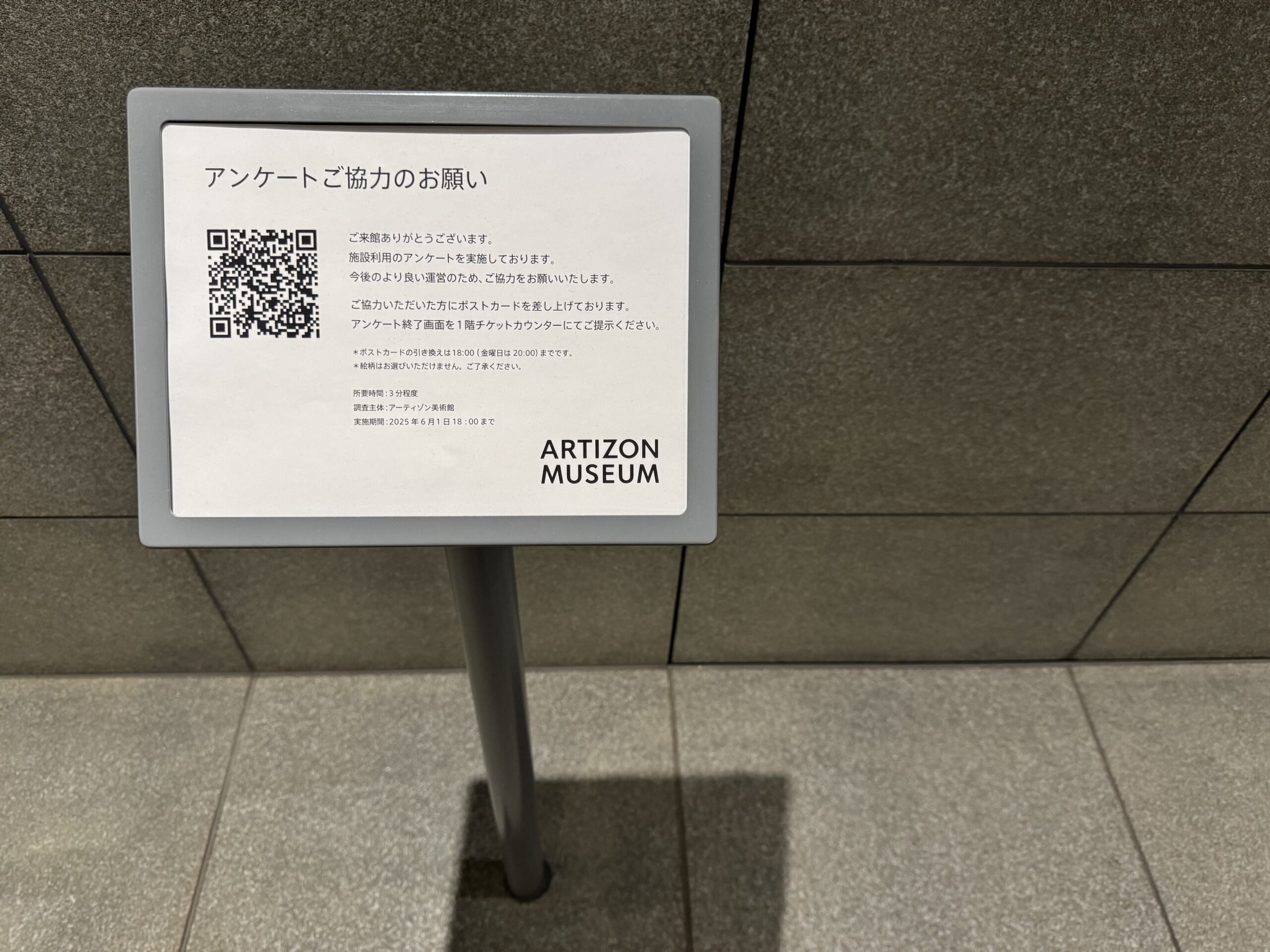
地域・行政・支援者との協働と共創
博物館はその立地する地域に根ざし、社会的文脈の中で存在しています。地域住民や行政、学校、NPO、観光事業者などとの協働は、単なる連携ではなく、地域課題の解決や文化的価値の共創を生み出す基盤となります。とくに近年では、「地域のリビングラボ」としての博物館の役割が注目されており、まちづくりや地域教育に博物館が積極的に参画する動きが広がっています。
行政との関係については、予算措置や制度設計を含む「外部環境」としての理解に加え、「共創パートナー」としての位置づけも重要です。たとえば博物館が地域文化振興や観光政策において提案型の役割を果たすことで、単なる補助金受給主体から、地域政策の担い手へと進化する可能性が生まれます。
また、個人・法人の支援者との関係性も無視できません。クラウドファンディング、寄付、メンバー制度といった多様なファンドレイジング手法は、資金調達の手段であると同時に、支援者との継続的な対話と信頼構築のプロセスでもあります(D’Angelo, 2020)。こうした関係性の質が、博物館のレジリエンスを支えるのです。
公共性と収益性の両立は可能なのか
「公共性」と「収益性」という一見対立する二つの価値のあいだで、博物館はどのような経営判断を下すべきなのでしょうか。博物館は本来、非営利で文化的・教育的な使命を担う公共施設です。しかし、財政支援の減少や経営の多様化を背景に、自主財源の確保が不可欠となっており、「収益を生み出す力」が経営の持続可能性に直結する時代に突入しています。
こうした状況において問われるのは、営利化の是非ではなく、「どのような収益活動であれば、ミッションと整合的であり、むしろ公共性を高めることにつながるか」という視点です。つまり、収益性と公共性は必ずしも対立するものではなく、設計次第で相互補完的に働くことが可能なのです。
クラウドファンディングや寄付事業の可能性
公共的価値の高い活動を市民と共有し、参加を募る手段として、クラウドファンディングや寄付事業は近年大きな注目を集めています。たとえば特別展の実施資金、文化財修復プロジェクト、ユニバーサル対応の整備など、具体的な目的を示すことで、多くの支援を集める事例が増えています。
こうしたファンドレイジング活動は、単に財源確保の手段にとどまらず、「支援者との関係性を育てる機会」として機能します。支援者は、博物館の活動に共感し、自らの意思で支える存在です。彼らとの継続的な関係構築こそが、経営の公共性を内側から強化する力となるのです(D’Angelo, 2020)。
また、税制上の寄附控除制度や、法人協賛をめぐる仕組みを理解し、戦略的に活用することも、現代の博物館に求められる経営スキルのひとつといえるでしょう。
成功事例に見るバランス戦略の実践知
収益性と公共性の両立に成功している博物館の事例を見ると、共通しているのは「来館者体験を軸としたサービス設計」に基づく戦略性です。たとえば、ミュージアムショップで販売される商品が、展示と連動した知識の補完や文化的ストーリーの延長として機能するように設計されている場合、それは単なる物販ではなく、公共性の一部とみなすことができます。
また、カフェやイベントスペースなどの活用も、地域住民が集うサードプレイスとしての役割を果たしている場合、商業的要素がむしろ地域における文化基盤の一端を担うことになります。こうした事例からは、「収益は目的ではなく、手段である」という視座を持つことの重要性が浮かび上がります。
重要なのは、収益活動を単独で行うのではなく、常にミッションや社会的文脈との関係の中で設計することです。その意味で、公共性と収益性の両立とは、経営の巧拙ではなく、「価値の翻訳と連携」によって実現されるものなのです。
まとめ ― なぜ今「博物館経営」を学ぶのか
本記事では、「博物館経営とは何か」という問いに対して、制度・財政・戦略・関係性・収益性といった複数の視点からアプローチしてきました。かつては行政主導で運営されていた博物館も、今では多様な制度的枠組みと厳しい財政環境の中で、自律的かつ戦略的な経営判断を求められる存在へと変化しています。
とりわけ、博物館に期待される役割が多様化し、社会的な課題解決や市民の学び・交流の拠点としての価値が問われる中で、「ミッションをどう実現するか」「限られた資源をどう配分するか」「誰とどのような関係性を築くか」という問いに向き合う力が、経営の核心をなしています。
重要なのは、収益化や制度対応といった個別の課題に対して近視眼的に対処するのではなく、それらを包括的に捉える視座を持つことです。公共性と収益性は両立可能であり、それを実現する鍵は、経営を通して「価値の意味」を翻訳し、社会と共有する力にあるのです。
「経営」という言葉に抵抗を覚える方もいるかもしれません。しかし、本来の博物館経営とは、文化的価値を社会に根付かせ、持続可能に発信し続けるための知的営みであり、文化施設における公共性を未来へとつなぐ戦略そのものです。今こそ、博物館にふさわしい経営とは何かを、私たち自身が考え、実践していくことが求められています。
参考文献
D’Angelo, A. (2020). The value of management in the digitalisation era. International Journal of Digital Culture and Electronic Tourism, 3(2), 151–162.
Greffe, X., Krebs, A., Pflieger, S., & Vivien, B. (2017). The future of the museum in the twenty-first century: Recent clues from France. Museum Management and Curatorship, 32(4), 345–363.
Hatton, A. (2012). The conceptual roots of modern museum management dilemmas. Museum Management and Curatorship, 27(2), 129–147.
Lord, G. D., & Lord, B. (2009). The manual of museum management (2nd ed.). AltaMira Press.
Macdonald, S. (Ed.). (2006). A companion to museum studies. Wiley-Blackwell.
Sandell, R., & Janes, R. R. (Eds.). (2007). Museum management and marketing. Routledge.
文部科学省(2022).令和4年度 博物館に関する基礎資料.国立教育政策研究所.https://www.nier.go.jp/jissen/book/r04/index.html#museum
みずほ総合研究所(2019).持続的な博物館経営に関する調査 ― 博物館が抱える課題の整理と解決に向けた取組事例 ―.文化庁(委託事業).














