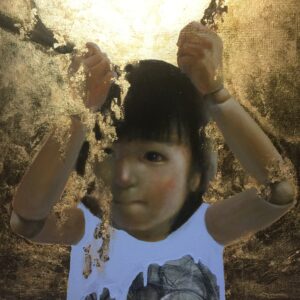はじめに
「博物館の価値とは何か?」――この問いは、一見すると自明のように思えるかもしれません。博物館は文化財を保存し、人々に知識や感動を届ける場であり、その存在自体が“価値あるもの”と考えられがちです。しかし、現代社会において、博物館が社会から期待される役割は多様化し、その“価値”もまた複雑に変化しています。
かつて、博物館の価値は主に「収集」「保存」「研究」「展示」といった専門的な活動を通じて語られてきました。これらは現在でも博物館の基盤を支える重要な機能であることに変わりはありません。しかし近年では、教育的な役割に加え、社会包摂や地域振興、経済効果、さらには環境意識の醸成といった、より広範な社会的ミッションが求められるようになっています。その結果、博物館は単なる「知の保管庫」ではなく、「公共性を担う文化的実践の場」として再定義されつつあるのです。
このような流れのなかで、「博物館の価値」を明確に言語化し、社会に向けて発信することは、もはや選択ではなく、経営上の必須課題となっています。特に、政策評価や助成金の審査、来館者の獲得、地域連携の推進など、あらゆる局面において、博物館は自らの存在意義を“証明”することが求められているのです(Scott, 2006)。
本記事では、こうした背景をふまえ、近年の理論的・実践的な議論をもとに、博物館の価値をどのように捉え直すべきかを考察します。文化的・教育的・社会的という多層的な側面から、価値の再定義を試みることで、博物館が持つ可能性と、その活かし方についての理解を深めていきます。
博物館の価値をめぐる近年の議論
「価値」という概念は、博物館においては極めて多義的な意味を持つ。伝統的には、美術品や歴史資料のような文化的資産に内在する「芸術的価値」や「歴史的価値」が重視されてきた。これらは専門家の審美的・学術的評価によって定められ、多くの場合は一般市民にとって「権威あるもの」として理解されてきた。しかし1990年代以降、とりわけ2000年代に入ってからは、こうした「内在的価値(intrinsic value)」にとどまらず、「公共的価値(public value)」や「社会的インパクト(social impact)」といった外在的な観点から、博物館の価値を再定義しようとする動きが顕著となっている。
この背景には、公共政策領域における成果主義の浸透がある。各国政府は、限られた予算の中で文化機関の資金支出を正当化する必要性に迫られ、博物館に対しても明確なアウトカム(成果)を提示することを求めるようになった。その結果、博物館の価値は、「どれほどの来館者数を記録したか」「どのような教育効果や地域波及効果を生み出したか」「どの層にリーチしているか」といった数値化可能な評価軸によって語られるようになった。
こうした文脈の中で注目されるのが、「パブリック・バリュー(公共的価値)」という考え方である。これはハーバード大学のMark H. Mooreによって提唱されたもので、公共部門における価値創造を三つの要素――「政治的正当性(authorising environment)」「運営能力(operational capacity)」「公共的価値(public value)」――の相互関係として捉える枠組みである(Scott, 2010)。この戦略三角形において、博物館は自らの使命を達成するために、政治的支援を得て(例:予算措置)、運営能力を最大限に活用し(例:専門人材、施設、ネットワーク)、結果として社会にとって有益な価値を生み出すことが求められている。
特に注目すべき点は、「価値を創出する主体」が多様化していることである。かつては、博物館の価値は専門家によって“定義”されるものであり、来館者や市民はそれを“受容”する存在に過ぎなかった。しかし現在では、来館者自身が価値の“共同創出者(co-creators)”とみなされ、展示や教育プログラム、参加型イベントなどを通じて、能動的に価値を構築していくという視点が主流となりつつある。この変化は、民主主義的文化政策の深化と呼応している。
加えて、米国におけるInstitute of Museum and Library Services(IMLS)のような支援機関は、博物館が社会的価値をどのように「可視化」し、「証明」するかに注目している。IMLSの助成プログラムでは、教育格差の是正、高齢者支援、地域連携、アクセシビリティ向上といった社会的課題への貢献を重視しており、これは単なる来館者数の増加ではなく、より深いインパクト(影響力)を追求する価値観の表れである(Semmel & Bittner, 2009)。
このように、近年の博物館は、「何を展示しているか」だけではなく、「その展示や活動がどのように人々の生活や社会に影響を与えているか」という観点から価値を問われるようになっている。言い換えれば、博物館の価値とは、単に“もの”に宿る静的なものではなく、社会との関係性のなかで“動的に生まれる”ものとして捉え直されているのである。
文化的・教育的価値の再定義
文化的価値と教育的価値は、博物館における基幹的な存在意義として、制度の成立当初から強調されてきた。文化的価値とは、歴史資料、美術品、自然標本などを収集・保存・研究・展示することによって、人類の文化的遺産を未来に継承するという役割を指す。教育的価値は、こうした資料群をもとに、来館者に対して学びの機会を提供する社会的機能を意味している。これら二つの価値は互いに密接に結びつきながら、博物館を公共的な知の拠点として支えてきた(Hooper-Greenhill, 2000)。
19世紀に設立された多くの国立・公立博物館は、国家の威信を象徴する文化機関として位置づけられ、そのコレクションには帝国主義的拡張の文脈が色濃く反映されていた。これにより形成された文化的価値は、しばしば「高尚な芸術」や「普遍的な歴史」といった枠組みで語られ、社会の特定層によって定義される傾向が強かった。そのため、文化的価値の定義には、階級、民族、ジェンダーといった社会的文脈が埋め込まれており、近年ではこうした背景を批判的に再検討する動きが活発化している(Scott, 2006)。
現代の博物館では、「誰にとっての文化か」「どのような声が展示に反映されているか」といった問いを通じて、文化的価値の再定義が進められている。とりわけ、先住民コミュニティとの共同展示、多文化社会における包括的ナラティブの提示、移民や難民の歴史を取り上げた展示企画などは、文化的価値の多様化を象徴する実践である。文化的価値は固定されたものではなく、歴史的・政治的コンテクストの中で動的に生成され、展示を通じて社会と交渉されるべきものである(Scott, 2010)。
一方、教育的価値についても大きな転換が見られる。従来の博物館教育は、展示物に関する情報を一方向的に来館者へ伝達するモデルが中心であり、来館者は「知識を受け取る者」として位置づけられていた。しかし現在では、学習理論の進展と来館者の多様化を背景に、教育的価値は対話的・協働的なものとして捉え直されている(Hooper-Greenhill, 2000)。
この転換は、展示のあり方にも顕著に表れている。来館者が自らの関心に応じて展示との関係を構築し、能動的に意味を見出すことができるよう、ストーリーテリング、インタラクティブ・ディスプレイ、体験型プログラムの導入が進められている。これにより、教育的価値は「何を学ばせるか」ではなく、「学びをどう共創するか」という視点へと移行している(Thyne, 2001)。
また、教育的価値は単に認知的学習にとどまらず、感情的・社会的・倫理的な側面も含む複層的な概念となっている。たとえば、差別や災害の歴史を扱う展示では、知識だけでなく共感や市民的関与を喚起することが重視される。さらに、博物館が学校教育と連携し、探究学習やプロジェクト型学習の場として機能する事例も増えており、学習の個別化と社会化の両立を支える存在として、教育的価値は拡張されている(Semmel & Bittner, 2009)。
文化的価値と教育的価値はいずれも、固定された静的な理念ではなく、時代とともに意味を変えながら、博物館の実践の中で再構築されていくものである。文化的価値は「文化を保存すること」から「多様な文化をめぐる対話の場を開くこと」へ、教育的価値は「知識を教えること」から「社会とともに学ぶ場を育てること」へと転換している。この再定義のプロセスを通じて、博物館は公共的存在としての意義を問い直し、より開かれた文化施設へと変容していくことが求められている(Scott, 2010)。
社会的価値とインパクトの指標化
近年、博物館が社会に対して果たす「社会的価値(social value)」が、ますます重視されるようになっています。社会的価値とは、博物館が提供する展示や教育プログラムを通じて、人々の暮らしや地域社会に与える良い影響のことです。たとえば、ある展示を見たことがきっかけで人権について考えるようになった、家族で来館することで世代を超えた会話が生まれた、地域の歴史を学んで地元への誇りが高まった――こうした変化は、博物館が社会にもたらす価値の一つです(Scott, 2006)。
このような「社会的価値」は、しばしば「インパクト(impact)」という言葉で表現されます。インパクトとは、活動そのものではなく、その活動が社会にどのような変化をもたらしたかという視点に立った評価です。たとえば、「年間100回のワークショップを実施した」というのは活動の成果(アウトプット)ですが、それによって「地域の子どもたちが博物館に親しみを感じるようになった」「家庭で博物館の話題が増えた」といった変化が生まれた場合、それがアウトカム(行動・意識の変化)であり、長期的にはインパクト(社会的影響)といえます(Scott, 2010)。
現代の博物館は、このようなインパクトを可視化し、社会に説明する責任を持つようになっています。なぜなら、多くの博物館が公的資金によって運営されている以上、その資金がどのような成果を生んでいるのかを、社会に対して明確に示すことが求められているからです。単に「活動をたくさん行った」という量的な情報だけでなく、「その活動がどんな意味を持ち、どんな効果を生んだのか」といった質的な情報も含めて評価する必要があります。
こうしたインパクトを整理し、わかりやすく伝えるための手法として、「ロジックモデル(Logic Model)」が注目されています。ロジックモデルとは、以下の5つの要素から構成される枠組みです。
- インプット(Input):人材、予算、施設、時間など、活動に投入される資源
- アクティビティ(Activity):ワークショップや展示、講演会などの具体的な活動内容
- アウトプット(Output):実施件数、参加者数、配布資料など、数値化された成果
- アウトカム(Outcome):来館者の意識や行動の変化、学習効果などの実質的な成果
- インパクト(Impact):地域社会の変化、持続可能性の向上、文化理解の深化など、長期的な影響
このように段階的に整理することで、博物館の活動がどのような目的を持ち、どんな価値を生んでいるのかを、より具体的に説明できるようになります。たとえば、平和をテーマにした展示を開催した場合、「展示を見て何人が平和の大切さを再認識したか」「その後、地域でどのような対話が生まれたか」といった変化を指標化することが可能になります。
こうした社会的インパクトの指標化は、すでに海外の政策現場でも実践されています。アメリカのIMLS(Institute of Museum and Library Services)では、助成金の交付に際して、博物館がどのように地域社会に貢献し、どのような変化を生んだかを報告することが求められています(Semmel & Bittner, 2009)。これは、博物館の社会的意義を証明するだけでなく、支援者や行政との信頼関係を築くための重要な手段でもあります。
社会的価値は、目に見えにくく、数値化が難しい側面もあります。しかし、博物館が生み出す価値は、展示や教育を通じて、来館者の心に残る経験や、社会にとって前向きな変化をもたらす力を秘めています。その力を丁寧に捉え、他者と共有し、評価できるようにすることは、博物館の公共的な責任であると同時に、未来に向けた持続可能な経営の基盤にもなります。
博物館の価値は誰が決めるのか?
博物館がもつ価値は、多くの人がなんとなく理解しているように見えます。たとえば「文化財を守っているから価値がある」「教育に役立つから意味がある」といったイメージです。しかし、少し立ち止まって考えてみると、この「価値」は一体誰が決めているのでしょうか。学芸員や研究者でしょうか。それとも、来館者や地域の人びとでしょうか。あるいは、資金を提供する行政や企業でしょうか。
かつて博物館は、専門家が「価値あるもの」を選び、展示を通して人々に伝える場所と考えられていました。このとき、価値は専門知によって定義され、来館者はそれを「学ぶ側」「受け取る側」として位置づけられていました。しかし現代では、こうした一方向の構図に対する見直しが進んでいます。博物館の価値は、専門家だけでなく、社会のさまざまな人びととの関わりのなかで、動的に生まれてくるものだと考えられるようになってきたのです(Scott, 2010)。
この変化は、「来館者中心(visitor-centered)」の考え方として現れています。来館者はもはや情報を受け取るだけの存在ではありません。展示を見ることで自分の経験や感情と結びつけ、新しい意味を見出したり、他者と共有したりする存在だと捉えられています。たとえば、ある戦争展示を見た来館者が、自分の家族の歴史と重ね合わせて語りはじめるとき、展示の価値はその人の中で再解釈され、新たに生まれ変わっているのです。
さらに、博物館の価値は来館者だけでなく、地域の住民、学校関係者、ボランティア、NPO、行政職員、出展作家、そして将来世代など、さまざまな「関係者(ステークホルダー)」によって構成されています。たとえば、地域の子どもたちと一緒にまち歩きをして地域の歴史を展示するプロジェクトでは、その展示の価値は「学芸員が作ったもの」ではなく、「子どもたち、住民、学芸員が一緒に作ったもの」として評価されるべきです。
このような価値の多元性は、博物館の評価や戦略にも深く関係します。行政にとっての博物館の価値は、観光や地域活性化への貢献かもしれません。学校にとっては、探究学習や表現活動の場であることが重視されます。高齢者や子育て世代にとっては、安心して過ごせる居場所や世代間交流の機会としての価値もあるでしょう。どの視点も一面的ではなく、それぞれに意味があります。
したがって、博物館にとって重要なのは、「一つの正解」を示すことではなく、「複数の価値が共存する場」をどうつくるかということです。これには、展示やプログラムの設計において、参加型のアプローチや協働的な関係構築が不可欠です。対話を重ね、異なる立場の人びとの声を丁寧に聞き取りながら、共に価値を育てていくことが、現代の博物館経営における大きな課題であり、可能性でもあります。
このように、「博物館の価値は誰が決めるのか?」という問いには、単一の答えはありません。むしろ、それぞれの立場や経験を持つ人びとが、博物館との関わりのなかで自分なりの価値を見出していく、その過程こそが大切なのです。博物館は、そうした価値の“出会いの場”であり、“対話の場”であり続けることで、社会からの信頼を築いていくことが求められています。
まとめ
博物館の価値とは何かという問いに対して、単純な答えを示すことはできません。なぜなら、その価値は時代とともに変化し、多様な社会的背景のなかで異なる意味を帯びるからです。かつては、文化財や美術品を保存・展示すること自体に価値があるとされてきました。しかし現代においては、博物館が果たす社会的な役割や、来館者との関係性のなかで生まれる経験、さらには地域や世界とのつながりのなかで発揮される影響力こそが、重要な価値として再認識されています。
文化的・教育的な価値は、もはや固定されたものではなく、社会の多様性を反映するかたちで更新され続けています。展示やプログラムは、来館者一人ひとりが自身の経験と重ね合わせながら意味をつくり出す場であり、そこでは知識の伝達だけでなく、共感や対話、社会的気づきといった広がりが生まれます。
また、博物館の活動が地域社会にもたらす影響、すなわち社会的インパクトについても、重視されるようになりました。人々の行動や意識を変え、包摂的で持続可能な社会の実現に寄与するという観点は、博物館の公共的意義を支える根拠となります。そして、その価値はインパクト評価の手法を用いて丁寧に可視化し、社会と共有していくことが求められます。
さらに、博物館の価値は決して一方向的に与えられるものではありません。学芸員や専門家だけでなく、来館者、地域住民、行政、学校、ボランティアなど、多様な関係者との関係の中で生まれ、育まれていくものです。博物館は、異なる視点が交わり、複数の価値が共存できる「対話の場」であり続けることによって、その公共性と信頼性を確保していく必要があります。
このように、博物館の価値は単なる文化財の管理や教育活動にとどまらず、人々との関係性や社会への貢献のなかで、多層的に構成されているのです。そしてその価値は、常に再定義され続けるべきものであり、時代に応じた問い直しと実践を通じて更新されていく必要があります。
参考文献
- Hooper-Greenhill, E. (2000). Museums and the interpretation of visual culture. Routledge.
- Scott, C. (2006). Measuring social value. In S. J. Knell, S. MacLeod, & S. Watson (Eds.), Museum revolutions: How museums change and are changed (pp. 307–321). Routledge.
- Scott, C. (2010). Museums: Impact and value. Cultural Trends, 19(1–2), 45–56.
- Semmel, M., & Bittner, S. (2009). The public value of museums. In American Association of Museums (Ed.), Mastering civic engagement: A challenge to museums (2nd ed., pp. 27–35). American Association of Museums.
- Thyne, M. (2001). The importance of values research for nonprofit organizations: The motivation-based values of museum visitors. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 6(2), 116–130.