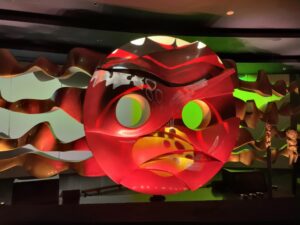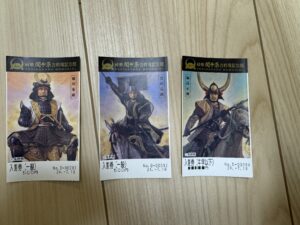はじめに
現代の博物館は、単なる文化財の保存・展示の場を超え、地域社会に対して新たな価値を創出する拠点となることが求められています。とりわけ小規模な博物館にとっては、限られた資源のなかでいかに社会的役割を拡大し、持続可能な発展を実現するかが重要な課題となっています。
こうした背景のなか、近年注目されているのが「イノベーション」の概念です。しかし、博物館におけるイノベーションとは、単に最新技術を導入することや内部改革を進めることだけを指すものではありません。地域の大学や企業、他の博物館、さらには市民社会との連携を通じて、多様なステークホルダーと共に価値を共創するプロセスこそが、博物館にとっての本質的なイノベーションだと考えられます。
本記事では、博物館におけるイノベーションの理論的な枠組みを整理したうえで、近年の実証研究を紹介しながら、連携と共創によってどのような新たな価値が生み出されているのかを探ります。そして最後に、日本の博物館が今後持続的な発展を遂げるために、どのようなイノベーション戦略を描くべきかを考察します。
博物館におけるイノベーションの理論的整理
博物館におけるイノベーションは、単なる新しい技術の導入や展示の刷新にとどまりません。近年では、イノベーションとは「来館者や地域社会、外部パートナーとともに新たな価値を共創するプロセス」であると考えられるようになっています(Massari & Netti, 2024)。つまり、イノベーションとは博物館が単独で成し遂げるものではなく、多様な関係者との対話や協働を通じて生み出されるものだという認識が広がっているのです。
このような視点から見ると、博物館のイノベーションにはいくつかの異なるタイプが存在することがわかります。LiとColl-Serrano(2019)は、博物館におけるイノベーションを次の4つに分類しています(Li & Coll-Serrano, 2019)。
- 技術革新(Technological Innovation)
デジタルアーカイブの構築、バーチャル展示の開発、インタラクティブな展示システムの導入など、ICT技術を活用して来館者体験や業務効率を向上させる取り組みです。これらは博物館の「見せ方」を根本から変える力を持っています。 - 文化的革新(Cultural Innovation)
伝統的な展示解釈にとらわれず、現代的なテーマや社会的課題を取り入れることで、新たな視点や物語を提示する取り組みです。多様な文化やコミュニティの声を反映させることによって、来館者との対話を深めます。 - 組織革新(Organizational Innovation)
博物館内部の働き方や組織運営を見直し、より柔軟で協働的な組織文化を築く取り組みです。例えば、専門分野を超えたチーム編成や、職員の自主性を尊重するマネジメント改革などが含まれます。 - 内容革新(Content Innovation)
従来の収蔵品や展示テーマにとらわれず、地域の歴史や現代社会の課題を取り入れた新たなプログラムや展示を開発する取り組みです。ワークショップや共同制作プロジェクトなど、市民参加型の活動もこの領域に含まれます。
これら4つのタイプのイノベーションは、個別に進められるものではありません。むしろ、それぞれが相互に関係し合いながら、博物館全体の価値を高める総合的な変革を促すものと考えられています(Li & Coll-Serrano, 2019)。
特に近年では、こうしたイノベーションが「トップダウン型」で推進されるのではなく、「ボトムアップ型」、すなわち来館者や地域社会とともに生み出される双方向的なプロセスである点が重視されています(Massari & Netti, 2024)。博物館はもはや一方的に情報を提供する場ではなく、人々との対話と協働を通じて、共に未来を描く場へと変わりつつあるのです。
次節では、このような共創型イノベーションをさらに具体的に支える仕組みとして、博物館がどのように外部パートナーとの連携を活用しているのかを、実際の研究成果に基づきながら詳しく見ていきます。
イノベーションとコラボレーションの関係性
博物館におけるイノベーションを推進するためには、外部とのコラボレーションが欠かせません。特に小規模な博物館では、限られた予算や人員体制のなかで、新たな展示手法や運営モデルを独自に開発することは容易ではありません。そのため、大学、企業、他の博物館、業界団体など、さまざまな外部パートナーと連携し、それぞれの知識・技術・ネットワークを活用しながら、イノベーションを実現していくアプローチが重視されています(Li & Ghirardi, 2018)。
実際の調査では、コラボレーションの「相手」によって、促進されるイノベーションの種類が異なることが明らかになっています。たとえば、地域の大学との連携により、最新のICT技術を活用したインタラクティブな展示を開発した博物館があります。ここでは、学生や研究者と共同でデジタルアーカイブを構築し、来館者がタッチパネル操作で展示物の裏側にあるストーリーを探ることができるように設計されました。このような大学との協働は、主に技術革新を促す役割を果たしています。
また、ITベンチャー企業との連携によって、AR(拡張現実)を活用した館内ガイドシステムを導入した事例もあります。来館者はスマートフォンをかざすことで、展示物に関連する映像やナレーションをその場で体験できるようになり、博物館の滞在価値が大きく向上しました。このように、ハイテク企業との協働も技術革新に直結する成果を生み出しています。
一方、同じ地域内の他館とのネットワーク連携により、ICTシステムの共同開発や情報資源の共有を進めたケースも報告されています。たとえば、複数館で共通仕様のデジタル展示ガイドを共同開発し、それぞれの特色を活かしたコンテンツ配信を可能にする仕組みを構築しました。このような他館との連携は、コスト削減とともに技術革新のスピードを高める効果があります。
さらに、専門団体や業界ネットワークとの連携は、技術面だけでなく、展示やプログラムの内容革新・文化的革新を促進する傾向が強いことがわかっています。たとえば、学芸員ネットワークを通じた共同企画により、ジェンダー平等や環境問題といった社会的テーマを盛り込んだ特別展を実現した博物館もあります。このような連携によって、従来型の展示枠組みを超え、社会に問いかけるような革新的な展示を生み出すことが可能になります。
コラボレーションが単に「誰と組むか」だけでなく、「どう組むか」もまた重要です。博物館と外部パートナーとの連携形態は、次の4つに整理することができます(Li & Coll-Serrano, 2019)。
- チームワーク(Teamwork)
博物館職員と外部パートナーが同じプロジェクトチームを編成し、共同で展示企画やプログラム設計に取り組む形態です。たとえば、大学の研究室と博物館スタッフが一体となって、新しいインタラクティブ展示の試作からテスト運用までを共に行うケースがこれにあたります。 - 外部委託(Outsourcing)
専門技術やサービスの提供を外部に依頼する形態です。たとえば、3Dスキャン技術を活用して文化財のデジタル保存を行うプロジェクトを、外部のテクノロジー企業に委託する場合などが該当します。 - コンソーシアム(Consortium)
複数の博物館や文化機関が資源を持ち寄り、共同で大規模プロジェクトを実施する連携モデルです。ヨーロッパ各国の博物館が連携して実施する国際巡回展や、EUの文化支援プログラムに基づく共同研究プロジェクトなどが典型例です。 - 対話型協働(Conversation)
正式な契約やプロジェクト化を伴わない、緩やかな情報交換やアイデア共有のネットワーク型連携です。たとえば、月例の館長会議やテーマ別ワークショップなどを通じて、博物館同士が互いの知見を共有し合う形態がこれにあたります。
これらのコラボレーション形態は、それぞれ異なるリソースや成果をもたらし、博物館のイノベーション活動を支える重要な基盤となっています。
今日、イノベーションはもはや内部努力だけで達成できるものではなく、外部との知識交換、リソース連携、文化的対話を通じて共に築き上げていくものとなりつつあります。これからの博物館には、こうしたネットワーク型のイノベーション推進モデルを柔軟かつ戦略的に取り入れる姿勢がますます求められていくでしょう。
まとめと考察
本記事では、博物館におけるイノベーションの理論的枠組みを整理し、さらに実証研究をもとにコラボレーションの重要性を考察してきました。
イノベーションはもはや単なる技術導入や内部改革にとどまるものではありません。大学や企業、他の博物館、専門団体など、外部パートナーとの連携を通じて、多様な知識・技術・文化を取り込みながら、新たな価値を共創していくプロセスそのものが、現代の博物館における本質的なイノベーションであることが明らかになりました(Li & Ghirardi, 2018; Li & Coll-Serrano, 2019; Massari & Netti, 2024)。
特に、どの相手とどのような連携を築くかによって、技術革新、文化的革新、組織改革、内容革新といったイノベーションの方向性が大きく異なることは、今後の博物館経営にとって極めて重要な示唆を与えています。連携先の選定と連携形態の設計を、単なるリソース補完の手段ではなく、戦略的なイノベーション推進の基盤として位置づける発想が求められます。
こうした視点は、日本の博物館においてもますます重要性を増していくでしょう。特に地方の小規模館では、人口減少や財政制約といった厳しい環境下において、地域大学、地元企業、他文化施設、地域コミュニティといった多様なアクターと柔軟に連携し、自らの存在意義を再定義していくことが不可欠となります。単なる展示施設としての役割にとどまらず、地域社会との共創拠点、学びと対話のハブとして進化する道を探ることが、持続可能な経営モデルの確立につながるはずです。
今後、博物館は内部完結型の経営から脱却し、開かれたネットワーク型のイノベーション推進拠点へと変革を遂げていくことが期待されています。そのためには、日々の運営のなかで小さな対話を重ね、外部パートナーとの信頼関係を丁寧に育みながら、共に未来をつくり上げていく姿勢が何よりも大切になるでしょう。
参考文献
- Li, Y., & Coll-Serrano, V. (2019). Assessing the role of collaboration in the process of museum innovation. Museum Management and Curatorship, 34(5), 508–525.
- Li, Y., & Ghirardi, M. C. (2018). The role of collaboration in innovation at cultural and creative organisations. The case of the museum. International Journal of Cultural Policy, 24(6), 739–757.
- Massari, S., & Netti, A. (2024). The digitalized ‘innovation lab’: Valorizing the museum outside the museum. Museum Management and Curatorship, 39(1), 40–59.