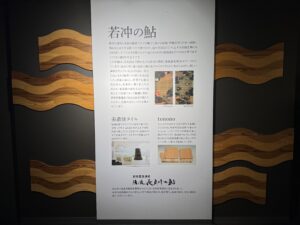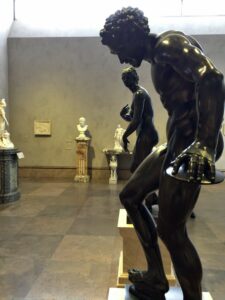はじめに:展示体験はどう変わるのか?
かつて、博物館の展示は「見ること」を前提とした静的なものでした。展示ケースの中に収められた資料と、その横に添えられた説明文。来館者は、ある程度の知識や文脈理解を前提に、それらを読み取り、自分なりに意味づけながら鑑賞することが求められていました。しかし近年、来館者の展示に対する期待や関心は大きく変化しつつあります。ただ情報を受け取るのではなく、展示そのものに関与し、体験を通じて学ぶことを求める声が高まっているのです。
こうした変化の背景には、社会と技術の両面における大きな変動があります。私たちの生活は、スマートフォンやインターネットの普及により、かつてないほど情報にアクセスしやすい環境へと移行しました。知識は“探しに行くもの”から“瞬時に得られるもの”へと変わり、単なる情報の量よりも、驚きや感動といった「体験の質」が重視されるようになっています。このような情報社会における価値観の変化は、博物館にとっても無関係ではありません。来館者は、単に知識を得るだけではなく、感情的に動かされるような体験を求めて展示室を訪れるようになっています。
そうした中で注目されているのが、ICT(情報通信技術)を活用した展示のあり方です。AR(拡張現実)やVR(仮想現実)、AI(人工知能)などの技術は、展示空間に新たな視覚的・体験的次元をもたらしつつあります。たとえば、恐竜の化石にARを用いて肉付けし、まるで生きているかのように動かして見せる。あるいは、AIを活用して来館者ごとに異なる解説を提示する。こうした展示は、「モノを見る」ことを起点としながらも、「情報を感じ、参加し、意味をつくる」プロセスへと来館者を導きます。ICTは単なる視覚的演出にとどまらず、展示と来館者の関係性そのものを再構築する力を持っているのです。
本記事では、このようなICTを活用した展示の意義と実践について考えていきます。まずは、ICTを用いた展示とは具体的にどのようなものかを整理し、その特性や背景を丁寧に解説します。次に、近年注目されている博物館での実践事例や研究成果を参照しながら、ICTが来館者の体験にどのような影響を与えているのかを検討していきます。そして最後に、これからの展示においてICTが果たすべき役割や、その可能性と課題について考察を深めていきます。
ICTによって展示のあり方は大きく変わりつつありますが、それは単に“技術を取り入れる”ということではありません。展示を通じて、誰に、どのように、何を伝えるのか。その問いに対する新たな解答のひとつとして、ICTは重要な手段となり得るのです。この記事を通じて、展示の未来を形づくる手がかりを、皆さんとともに探っていければと思います。
ICTを活用した展示とは何か?
ICTという言葉は、「Information and Communication Technology」の略で、日本語では「情報通信技術」と訳されます。もともとは、コンピュータやインターネット、ネットワークといった情報処理や通信に関わる技術の総称として用いられてきました。しかし、近年ではその範囲が大きく広がり、私たちの生活の中にも身近な形で入り込んでいます。たとえば、スマートフォンやタブレット端末、デジタルサイネージ、さらには人工知能(AI)、拡張現実(AR)、仮想現実(VR)といった技術も、ICTの一部として位置づけられています。
こうしたICTは、教育、医療、観光などさまざまな分野で活用されていますが、博物館においてもその可能性が大いに注目されています。とくに近年は、展示にICTを取り入れることで、来館者の体験をより深く、豊かにする取り組みが各地で進められています。単に情報を見せるだけでなく、来館者が参加し、感じ、考えることのできるインタラクティブな展示を実現する技術として、ICTは新しい価値を提供しています。
では、展示におけるICTとは、具体的にどのようなものを指すのでしょうか。たとえば、ARを用いて、展示資料の周囲に関連する情報や映像を重ねて表示したり、VRゴーグルを通じて過去の風景や文化空間を仮想的に体験したりする事例があります。また、AIが来館者の興味や年齢に応じて展示解説を調整したり、スマートフォンのアプリを使って、個々の来館者が自分のペースで展示を楽しんだりする仕組みも整備されつつあります。これらはすべて、ICTを活用した展示の一例です(Mason, 2020)。
このような展示に共通しているのは、従来の「見る展示」から、「参加し、体験する展示」へと視点が変わっている点です。来館者は、ただ立ち止まって解説を読むだけでなく、自ら操作し、感じ、考えながら展示と関わることができるようになっています。その意味で、ICTは情報の付加的な手段ではなく、展示そのものの在り方を問い直す技術でもあります。
ICTが展示にもたらす特徴をまとめると、大きく三つのポイントが挙げられます。第一に、ARや3Dモデルなどを用いた「視覚化」の力です。これにより、展示資料の構造や背景、使用されていた当時の状況などを、視覚的にわかりやすく提示することができます。第二に、VRや触覚型インターフェースなどによる「体験化」です。来館者は、まるでその時代や場所に自分がいるかのような臨場感を得ながら、より深く展示に没入することができます。第三に、AIや個別対応型アプリを用いた「個別化」です。来館者の年齢、言語、興味・関心に応じて内容を調整することで、誰もが自分に合ったペースと方法で展示を楽しめるようになります(Xu & Pan, 2024)。
こうした視覚化・体験化・個別化によって、来館者の展示体験は大きく変わっていきます。従来は一方向的だった情報の受け取り方が、双方向的で探索的なものへと変化し、展示との関係がより能動的なものになります。来館者は自らの手で知識を発見し、感情を動かし、記憶に残る体験として展示をとらえるようになります。
実際に、ICT展示が来館者にもたらす効果については、多くの研究がその有効性を指摘しています。たとえば、展示の内容が来館者の記憶に残りやすくなったり、展示に対する満足度が向上したり、再訪意欲が高まったりすることが報告されています。これらは、「体験価値(Visitor Experience:VEX)」と呼ばれる概念のもとで整理されており、ICTの導入が単なる演出ではなく、展示の本質的な価値を高める手段であることが明らかになりつつあります(Elgammal et al., 2020)。
このように、ICTを活用した展示とは、単に「技術を取り入れる」ことではありません。むしろ、それは博物館が「どのように伝えるか」を根本から見直し、来館者との新しい関係性を築いていくための試みであると言えるでしょう。次の節では、こうしたICTを活用した展示が実際にどのように展開されているのかを、国内外の具体的な事例をもとに詳しく見ていきます。
実例で見るICT展示の展開 ― 国内外の注目事例
ICTを活用した展示とは、実際の博物館においてどのように実現されているのでしょうか。技術の名称だけを並べても、それがどのように展示空間に取り込まれ、来館者の体験にどのような影響を与えているのかを理解するのは難しいものです。そこで本節では、国内外の具体的な事例を取り上げながら、ICT展示の特性や成果、導入に際しての工夫や課題について見ていきます。
注目すべき点は、これらの事例がいずれも単なる技術導入にとどまらず、「来館者の体験をどう設計するか」という視点に立ってICTを活用していることです。展示を見る人が、どのように感じ、考え、行動するか。それを丁寧に構想しながら設計された展示には、来館者の学びや感情に深く働きかける力があります。
バーチャル展示と伝統的展示の比較 ― MAVとAl Tayebat Museum
イタリアのMAV(Museo Archeologico Virtuale)は、バーチャル技術を活用した先進的な考古学博物館です。ここでは、ARやVRを用いて古代都市ポンペイの街並みを再現し、来館者がその中に“入り込む”ような体験ができるよう設計されています。過去の出来事や文化的背景を、視覚的かつ没入的に学べるこの手法は、知的理解と感情的共鳴を同時に促す仕組みとなっています。
一方、サウジアラビアのAl Tayebat Museumは、伝統的な展示手法を用いた施設です。ここでは実物資料と説明パネルによって構成された静的な展示が中心であり、来館者は観察と読解を通じて理解を深めていくスタイルが基本となっています。
両館を比較した研究によれば、ICTを活用したMAVを訪れた来館者は、「展示が記憶に残る」「内容に満足した」「他者にシェアしたいと感じた」と回答する割合が高く、来館者体験(Visitor Experience:VEX)の向上が明確に示されました(Elgammal et al., 2020)。この事例は、バーチャル技術によって感情的・記憶的な側面を強化することが可能であることを裏付けるものです。
地方博物館の挑戦 ― AR展示室の再構築
イタリアのある地方都市に位置する中小規模の博物館では、AR技術を活用した展示室の再構築が行われました。この取り組みは、限られた予算や人材の中でICT導入を実現しようとする地方館にとって、現実的かつ示唆に富む事例となっています。
この博物館では、常設展示にARを導入し、展示資料の上にスマートデバイスをかざすと、過去の建造物や人物の姿が出現するという体験型の展示を設計しました。たとえば、現在は一部しか残っていない歴史的建築物の前に立つと、ARを通じて往時の全体像が再現され、来館者はその場に立ちながら「かつてそこにあったもの」を視覚的に体験できるようになっています。
このプロジェクトでは、経営陣のリーダーシップが大きな役割を果たしました。また、地域住民や教育機関との協働を通じて、展示の内容や構成を柔軟に調整し、地域社会に根ざしたICT展示の形を模索していった点も特徴的です。来館者へのヒアリングや試験運用を重ねながら、理解しやすく、かつ印象に残る展示体験を目指したその過程は、単なる技術導入にとどまらない学びを含んでいます(D’Angelo, 2020)。
この事例は、ICTが都市部の大型館だけでなく、地方の中小規模館でも有効に活用できることを示すとともに、「技術を導入すること」よりも「どう使うか」が重要であるという教訓を与えてくれます。
展示の未来像 ― AI・AR・バーチャルテキストの融合
ICT展示の可能性をさらに広げるものとして注目されているのが、AI・AR・バーチャルテキストの統合的な活用です。ある研究では、これらの技術を組み合わせた未来型展示の設計が提案されており、来館者の体験を三層的に構成することが目指されています。
第一に、AIが来館者の属性(年齢、関心、言語など)に応じて案内情報を最適化します。第二に、ARが展示物の背後にある文化的背景や動きを視覚化し、資料を“動的に見る”体験を可能にします。第三に、バーチャルテキストが、単なる説明を超えて、来館者の感情に訴える物語として提示されることで、共感や内省を促す仕組みが加わります。
こうした展示モデルにおいては、来館者は知識を得るだけでなく、感情的なつながりや社会的な対話を通じて、展示とより深く関わることができます。展示の目的が「知識の伝達」から「意味の共創」へと広がっている点が特徴です(Xu & Pan, 2024)。
ただし、こうした高度な展示には課題も伴います。AIによる個人データの収集や活用、ARによる演出の正確性、ナラティブによる感情操作のリスクなど、倫理的・社会的な側面にも注意が必要です。ICT展示が社会に広く受け入れられるためには、技術的魅力だけでなく、公共性や信頼性にも配慮した設計が求められます。
実例から見えてくる展示設計の視点
紹介した三つの事例から明らかになるのは、ICTが単なる視覚的演出のための技術ではなく、展示の根本的な設計思想と深く結びついているということです。成功している展示には共通して、来館者の感情や記憶に残る体験を丁寧に設計しようとする姿勢が見られます。
また、いずれの事例も、ICTを導入することで展示と来館者との関係性が大きく変化していることが確認されます。来館者は、受動的に「見る」のではなく、能動的に「感じ、考え、共有する」存在として展示と関わるようになっているのです。
次節では、こうした来館者の体験がどのように変化しているのかを、「体験価値(Visitor Experience)」の視点からより詳しく考察していきます。
来館者にとってのICT展示 ― 体験価値(VEX)の視点から
ICTを活用した展示は、来館者にとっての「鑑賞体験」を大きく変えつつあります。単に展示資料を見るだけの受動的な体験から、参加し、選び、感じながら学ぶ能動的な体験へと移行しつつある今、重要となるのが「Visitor Experience(VEX)」という考え方です。本節では、ICT展示が来館者にもたらす体験の特性や価値について、このVEXの視点から詳しく考えていきます。
Visitor Experience(VEX)とは何か?
VEXとは、来館者が展示を通じて得る体験の全体像を指す概念で、単なる満足度や滞在時間といった定量的な指標にとどまらず、「記憶に残る体験」や「その後の行動に影響を与える体験」までを含んでいます。来館者が展示から何を感じ、どのように意味を見出し、それが個人や社会にとってどのような変化をもたらすのか。この一連のプロセスを重視する点に、VEXの特長があります。
VEXの構成要素は、主に四つに分類されます。第一に「認知的価値」、つまり知識や理解を深める知的な満足感。第二に「感情的価値」、展示を見て感動したり、驚いたりするような情動の動き。第三に「社会的価値」、他者と共有したり会話を生み出したりするような交流の要素。そして第四に「行動的価値」、展示をきっかけに別の行動につながるような影響です。ICT展示は、これらの価値を複合的に引き出す可能性を持っているとされています。
ICT展示が引き出す「体験の深まり」
ICT展示は、視覚的な情報量を増やすだけでなく、来館者の体験そのものを「深く、豊かに」するための仕組みを提供しています。たとえば、ARやVRといった技術を用いることで、来館者は展示資料の背景にある世界を視覚的・空間的に体感できるようになります。これは、感覚を通じて情報を理解するというプロセスを可能にし、学習への動機づけにもつながります(Kamariotou, 2021)。
また、AIやインタラクティブアプリケーションの導入により、来館者が自分の関心に応じて情報を選択したり、表示内容を調整したりすることも可能となっています。この「選べる」体験は、来館者に自律的な鑑賞の感覚を与え、より深い没入や納得をもたらします。さらに、ストーリーテリングや映像表現を通じて、展示資料が「物語」として語られるようになると、来館者はそこに感情的な共鳴を覚え、自身の記憶に長く残る体験へとつながっていきます(Xu & Pan, 2024)。
このように、ICTは知識の提示にとどまらず、「感じる」「考える」「関わる」といった複合的な体験をデザインするための有効な手段となっています。
実証研究に見る来館者の変化
ICT展示が来館者に与える影響については、さまざまな実証研究がその効果を裏づけています。たとえば、VRやARを活用した展示に触れた来館者は、展示内容を「より記憶に残りやすい」と感じたり、「展示に満足した」と答えたりする傾向が高いことが明らかになっています(Elgammal et al., 2020)。また、「他者と共有したい」「また来たい」といった再訪意図も高まることが報告されており、ICTが体験の質そのものを高めていることが示唆されています。
さらに、ICT展示は特定の来館者層にとって、博物館へのアクセスを促進する手段にもなり得ます。たとえば、若年層や外国人観光客、初めて博物館を訪れる人々にとって、インタラクティブで直感的に理解できる展示は大きな魅力となります(Komarac & Ozretić Došen, 2021)。また、共同的な鑑賞体験を重視した設計、たとえば来館者同士が感想を共有したり、SNSで発信したりできるような仕組みは、社会的価値を高める要因となります(Burke et al., 2020)。
誰にとっても「楽しい展示」か? ― 格差と排除の視点
一方で、ICT展示がすべての人にとって平等に効果的であるとは限りません。たとえば、高齢者や障害のある来館者にとって、デバイス操作が難しかったり、AR映像が見づらかったりするなどの障壁が生じる可能性があります。展示が高度になればなるほど、そのインターフェースの複雑さや操作の煩雑さが、来館者にとって負担となることもあるのです。
また、技術的なリテラシーやデジタル環境への慣れの違いによって、「誰がどれだけ展示を楽しめるか」に格差が生まれるリスクもあります。ICT展示を設計する際には、「すべての来館者にとって利用しやすい設計」がなされているか、つまりアクセシビリティとユーザビリティの観点から十分に検討されているかが問われます。
このような観点から、ICT展示には「誰もが意味ある体験を得られる」ように、柔軟に調整可能なデザインが求められています。
来館者の体験を中心に据えた展示とは
ICTを活用した展示が示しているのは、単なる情報の拡張ではなく、「体験の設計」という視点の重要性です。来館者が展示を通じて何を感じ、何を学び、どのような意味を受け取るのか。そうしたプロセス全体を丁寧に捉えることが、これからの展示づくりにおいて欠かせない視点となっています。
ICTは、来館者にとっての意味ある体験を形づくるための有力なツールです。しかし、それは決して「技術を導入すること」自体が目的なのではありません。むしろ、来館者一人ひとりの多様なニーズや関心に応じて、柔軟に対応できる体験をどう設計するか。そのためにICTがどのように役立つのかを考えることが、本質的な問いなのです。
Visitor Experience(VEX)という視点に立つことで、展示はより来館者中心のものへと再構成されていきます。そしてそこには、誰もがアクセスしやすく、自分らしく関われる展示の可能性が広がっています。来館者との関係性を重視することは、ICTの導入を超えて、博物館のあり方そのものを問い直す営みとも言えるでしょう。
ICT活用の可能性と限界 ― 導入にともなう課題を見つめる
ICTを活用した展示は、来館者の体験を豊かにする手段として注目されていますが、導入すれば必ずしも成功につながるとは限りません。多様な来館者を迎える博物館にとって、技術の可能性とともに、その導入がもたらす現実的な課題にも目を向けることが重要です。本節では、ICT活用の限界や留意点を整理し、持続可能な活用のために必要な視点を考えていきます。
「導入すればよい」という単純な話ではない
近年、ICT機器の高度化や低価格化が進んだこともあり、多くの博物館がARやVR、AIガイド、マルチメディア展示などの技術導入を検討するようになっています。しかしながら、展示に技術を取り入れれば自動的に来館者満足が向上するというような「魔法の道具」としてICTを捉えることは適切ではありません。
技術の導入はあくまで手段であり、その効果は「どのような目的で、どのような体験を来館者に届けたいのか」といった設計思想に基づいているかどうかに左右されます。展示体験を設計するうえで、ICTは重要なパートナーですが、決して展示の主役になるものではないのです。
また、ICT展示は来館者だけでなく、職員や組織全体、場合によっては地域社会にも影響を及ぼします。そのため、導入には多方面の調整と合意形成が求められます。単に新しい機器を入れることだけでは、持続的な運用や来館者への影響を担保することはできません。
技術導入に伴う現場の課題
ICT展示を導入する際には、さまざまな現場課題が立ちはだかります。最も分かりやすいのは費用の問題です。機器の導入には初期費用がかかるだけでなく、その後の維持管理にも多くのコストが発生します。ソフトウェアのアップデート、ハードの故障対応、ライセンス更新など、予算化と管理が求められる項目は多岐にわたります。
また、現場の職員にとっては、新しい技術への対応が負担になることもあります。特に、ICTに不慣れなスタッフにとっては、展示機器の操作方法やトラブル対応が大きな負荷となる可能性があります。さらに、来館者からの質問や不具合への対応に追われる場面も少なくありません。こうした運用面での人材育成やサポート体制の整備は、導入と同じくらい重要な課題です。
中小規模の博物館では、技術導入のハードルはさらに高まります。限られた財源や人員体制の中で、ICTを維持・更新していくことは容易ではなく、現実的な活用可能性を慎重に見極める必要があります。
来館者体験とのギャップとその要因
ICT展示がうまくいかなかったという事例には、「技術はすごいが展示としては楽しくなかった」という評価が少なからず存在します。その背景には、展示と技術との連携不足や、鑑賞体験を支える文脈の弱さがあります。たとえば、演出が過剰で展示資料の意味が見えにくくなっていたり、操作が複雑で来館者が戸惑ってしまったりすると、体験そのものが損なわれてしまいます。
来館者にとってICT展示が魅力的に映るためには、技術が展示の主旨ときちんと結びつき、体験に自然な形で組み込まれている必要があります。つまり、「何のために使うのか」「来館者にどんな感覚を届けたいのか」という目的を明確に持ち、それを実現する手段として技術を活用することが求められます。
社会的・倫理的な視点からの懸念
ICT展示には、社会的・倫理的な観点からの注意も欠かせません。たとえば、来館者の行動履歴や属性データを収集・活用するAIガイドやナビゲーションシステムでは、プライバシーへの配慮が不可欠です。どのような情報が取得され、どのように管理されているのかを明示し、来館者の安心を確保する責任があります。
また、ARやVRによって歴史的な出来事や文化的文脈を再現する際には、「真実らしさ」が過剰になり、誤解やステレオタイプの再生産を引き起こす可能性もあります。とくに異文化理解や歴史的事象を扱う展示では、表象の在り方に慎重な姿勢が求められます(vom Lehn, 2014)。
さらに、技術の面白さにばかり焦点が当たると、「誰のための展示なのか」という本質的な問いが置き去りにされてしまう危険もあります。展示の社会的使命や公共性が、技術の利便性や話題性に埋もれてしまうことのないよう、博物館としての価値基準を常に意識する必要があります。
来館者の体験を支えるために必要なこと
ICT展示の可能性を真に活かすためには、いくつかの条件が整っている必要があります。まず大切なのは、導入の目的を明確にし、「技術を入れること」ではなく「来館者にどんな体験を提供するか」という観点から展示を設計することです。
また、ICTを展示に組み込む際には、学芸員・教育普及担当・技術者といった異なる専門性を持つ人々が連携し、「共に使えるチーム」を形成することが求められます。技術だけではなく、内容や教育的意図を共有しながら展示設計を進めることが、体験の質を高める鍵になります。
加えて、初めから完璧な展示を目指すのではなく、スモールスタートで始めて段階的に改善していく柔軟な姿勢も重要です。来館者の反応を丁寧に観察しながら、継続的に評価と見直しを行う体制を整えることが、ICT展示の持続的な運用につながります。
そして何より、「誰にとってもアクセスしやすく、意味のある展示」であることを重視し、ICTの設計そのものに包摂性の視点を組み込んでいくことが、これからの博物館に求められる姿勢といえるでしょう。
ICT展示のこれから ― 博物館における創造的活用に向けて
ICTを活用した展示は、博物館に新しい可能性をもたらしています。技術は単なる視覚的な演出を超え、来館者の記憶や感情、他者との関係性にまで働きかける体験の設計ツールとして機能しつつあります。一方で、その導入や運用には、技術的・組織的・倫理的な課題も伴います。本節では、これまでの議論をふまえ、ICT展示の創造的な活用に向けて、今後博物館に求められる視点について考察します。
これまでの議論の振り返り
本記事ではまず、ICT展示の具体的な展開事例を紹介し、それらが来館者の体験にどのような変化をもたらしているかを考察しました。ARやVR、AIなどの技術は、展示空間に没入感や対話性を加えるとともに、来館者の記憶に残る体験を生み出す力を持っていることが示されました(Elgammal et al., 2020; Xu & Pan, 2024)。
次に、Visitor Experience(VEX)の視点から、ICT展示がもたらす認知的・感情的・社会的価値について整理し、来館者中心の展示設計の重要性を明らかにしました。そして、ICT導入に伴う課題として、現場の運用負担や技術への過度な依存、来館者の多様性への配慮の欠如といった論点を確認し、持続可能で包摂的な運用のための条件を検討しました(vom Lehn, 2014)。
ICTはあくまで「手段」であるという原点
展示にICTを導入する目的は、決して「最新技術を使うこと」そのものではありません。博物館が大切にすべきは、常に「来館者に何を届けたいのか」という視点です。技術はあくまで手段であり、その選択や活用は、展示の目標や理念と整合している必要があります。
技術が展示体験を豊かにするのは、それが展示の文脈と噛み合い、来館者の理解や感情に寄り添っているときです。逆に、技術に振り回された展示は、来館者にとって「情報量が多いだけ」「操作が複雑で疲れる」ものになりかねません。展示の設計においては、技術ありきではなく、「体験の意味」から発想する姿勢が求められます。
未来の展示をつくるために必要な視点
ICTを取り入れた展示づくりには、「すべてを一度に完成させようとしない柔軟さ」も重要です。スモールスタートで実験的に取り組み、来館者の反応を見ながら改善していくプロセスが、より良い展示につながります。こうしたアプローチは、来館者とともに展示を育てる「共創」のあり方を体現しています。
また、ICTの活用はアナログ展示との対立ではなく、相補的な関係にあるべきです。映像やインタラクティブ機能が来館者の関心を引きつけた後に、実物資料の細部をじっくりと鑑賞するといった「融合的な体験」は、博物館ならではの強みでもあります。
さらに、ICT展示の設計にあたっては、社会的包摂性や環境負荷、公共性といった博物館の基本理念とも整合性をとることが必要です。来館者の多様性を尊重し、誰もが安心して参加できる展示空間を目指すことが、ICTを活用するうえでの前提条件となります。
ICT展示の可能性を最大限に活かすために
ICT展示の意義は、来館者との新しい関係を築く手段である点にあります。情報を届けるだけでなく、来館者の感性や経験を引き出し、他者との対話や社会との接続を生み出す場としての可能性があるのです。ICTは、その場を設計するための「道具箱」として、多様な可能性を秘めています。
しかし、どんなに高度な技術があっても、それを活かすのは博物館のビジョンと創造力です。展示が来館者の心に届くかどうかは、どれだけ優れたテクノロジーを使ったかではなく、どれだけ深く「来館者の視点」で考えられているかにかかっています。
これからの博物館にとってICTは、単なる機能の追加ではなく、来館者とともに価値を共創するための手段であるべきです。展示を通して人々がつながり、問いを持ち帰り、再び足を運びたくなるような場をつくる。そのためにこそ、ICTの創造的な活用が求められているのです。
参考文献
- Burke, P. F., Mussolum, S., & Schuck, S. (2020). Museums at home: Digital initiatives in response to COVID-19. Curator: The Museum Journal, 63(3), 417–425.
- D’Angelo, M. (2020). Technologies of knowledge representation and museums: Between immersive narratives and augmented reality. International Journal of Digital Culture and Electronic Tourism, 3(1), 22–38.
- Elgammal, A., Mahrous, A. A., & Mostafa, R. B. (2020). Does digital technology improve the visitor experience? A comparative study in the museum context. International Journal of Tourism Policy, 10(1), 41–59.
- Kamariotou, M. (2021). The impact of interactive technologies on visitor experience in museums: An empirical study. Applied Sciences, 11(2), 1–16.
- Komarac, T., & Ozretić Došen, Đ. (2021). Museums in the digital age: Visitors’ perspective on value creation. Museum Management and Curatorship, 36(2), 123–140.
- vom Lehn, D. (2014). Accounting for new technology in museum exhibitions. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 8(2), 123–133.
- Xu, W., & Pan, L. (2024). Enhancing visitor engagement through AI-powered storytelling in immersive museum environments. I3: Innovation, Integration and Impact, 4(1), 12–27.