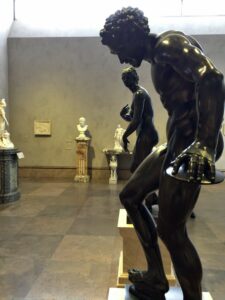はじめに:展示は「ひとりではつくれない」
博物館の展示は、長らく学芸員の専門的知見に基づいて構成されるものであり、その制作の主導権は館内に完結していることが一般的でした。しかし近年では、この前提そのものが大きく揺らぎつつあります。展示の現場では、所蔵者や他館との連携、専門業者との共同作業、さらには地域住民や来館者自身の関与が当たり前のように行われるようになってきました。展示とは「誰かがつくるもの」ではなく、「複数の人々によってつくられるもの」へと変わりつつあるのです。
こうした変化の背景には、博物館の公共性をめぐる認識の広がりがあります。博物館は単に資料を保管・展示するだけでなく、社会や地域と関係を結ぶ場として、その役割が拡張されてきました。展示は知識を伝える手段であると同時に、多様な声や視点を反映するメディアでもあります。展示の制作においても、特定の専門家の視点だけで完結するのではなく、複数のステークホルダーと協働し、対話を重ねながら「共につくる」姿勢が求められるようになっているのです(Davies, 2010)。
また、展示への参加を通じて、来館者が自らの経験や記憶を語る機会が生まれたり、地域に根ざしたストーリーが展示に組み込まれたりすることで、博物館はより開かれた学びの空間としての役割を強化しています。展示に関わる人々は、単なる協力者ではなく、展示の意味や価値を共に生み出す「共創者」として位置づけられるようになっています(Barnes & McPherson, 2019)。
一方で、こうした共創や協働の取り組みには、実務上の課題や、理論的な再考を要する場面も少なくありません。役割分担の曖昧さ、専門性と多様性のバランス、参加者のモチベーション管理など、実際の展示制作における協力関係には複雑な側面が存在します。展示の価値を最大化するためには、関係者との関係づくりを単なる「手段」ではなく、展示そのものの「意義」として捉える視点が求められます(Mygind, Hällman, & Bentsen, 2015)。
本記事では、こうした「展示における協力と共創」のあり方について、実例や研究を参照しながら整理していきます。他館や所蔵者との連携、専門業者との協働、そして来館者や地域との関係性づくりに焦点を当て、展示の現場で起こっている変化とその意味を明らかにすることを目指します。展示制作に関わるあらゆる立場の人々にとって、協力関係を再考し、展示を「ともにつくる」営みとして捉え直すための手がかりとなれば幸いです。
他館・所蔵者・専門業者との協力 ― 展示づくりの基盤としてのパートナーシップ
博物館における展示づくりは、もはや館内の人員だけで完結するものではありません。他館の学芸員、資料の所蔵者、展示設計や照明、グラフィック、映像などを担う専門業者といった、さまざまな関係者の協力を得ながら構築される「関係性のプロジェクト」として捉える必要があります。展示とは、単なる物理的な構成物ではなく、関係性のマネジメントそのものでもあるのです。
とくに他館との連携は、展示協力のなかでももっとも制度化が進んでいる分野のひとつです。巡回展や合同企画展では、貸出交渉、輸送・保険、設営、スケジュール調整など、多岐にわたる業務が発生します。こうした連携を円滑に進めるためには、契約書や標準化されたプロトコルの整備が不可欠とされています(Matassa, 2011)。展示制作の過程では、企画立案、予算管理、空間設計、来館者対応、学習プログラムの設計といった各段階において、他館の職員が積極的に関わるケースも珍しくありません(Davies, 2010)。単に資料を貸し借りするだけでなく、相互に企画意図や運営上の制約を理解し合いながら協働を進めていく姿勢が求められています。
個人や団体の所蔵者との関係構築も、展示の質を左右する重要な要素です。展示に貸し出される資料の背景やストーリーは、所蔵者の語りや意図と深く関係しており、それらを丁寧に受け止めながら展示内容に反映させることが、展示全体の信頼性や説得力を高めます。ある地域博物館では、資料の不足を補うために他館や住民からの貸与を受けつつ、地域に根ざした語りや記憶を展示に取り入れ、多声的な構成を実現していました(Guy, Williams, & Wintle, 2024)。このように、所蔵者は資料の提供者であると同時に、展示の共同制作者ともなり得る存在です。
展示設営にかかわる専門業者との協働も、近年ますます重要性を増しています。照明、空間設計、映像、グラフィックなど、専門的な技術と創造性を要する分野は高度化が進み、展示の印象や体験の質を大きく左右します。ある民族学博物館における事例では、地方の織物協同組合と都市部のデザイン会社が連携して展示を制作し、そのプロセス自体が展示の一部となっていました(Guy, Williams, & Wintle, 2024)。このような取り組みでは、専門業者を単なる請負先とせず、展示の理念を共有する創造的パートナーとして迎え入れる姿勢が求められます。
こうした協力関係を持続的に機能させるためには、個別の信頼に加えて、制度的な基盤の整備が不可欠です。輸送や保険、設営などの業務が不明確なまま進行すると、関係者間の誤解や摩擦の原因になりかねません。展示協力を安定的に支えるためには、役割分担の明確化、リスク管理の仕組み、合意形成のためのルールづくりが欠かせません(Matassa, 2011)。
展示は「ともにつくる」営みであり、その実現には関係者との信頼、継続的な対話、そしてそれを支える制度的な土台が必要です。次節では、来館者や地域住民との協働に目を向け、彼らがどのようにして展示の共創者となっていくのかを考えていきます。
来館者や地域との共創 ― 展示は誰のものかを問い直す
博物館の展示を来館者にとってより意味のあるものにするために、近年では参加型のアプローチが注目されています。かつては来館者の声を集めるといえばアンケートや評価が中心でしたが、現在では展示の企画や構成そのものに、地域住民や市民グループが関わる機会が増えています。展示はもはや一方向的な情報の伝達ではなく、対話や協働を通じて形づくられる「共創のプロセス」として捉えられるようになっています(Mygind, Hällman, & Bentsen, 2015)。
このような共創を実現するためには、適切な仕組みと運営上の工夫が求められます。単に意見を募るだけでは、協働とは言えません。展示の構想段階から関係者を招き入れ、発想や語りの共有を重ねながら構成をつくり上げていく必要があります。参加型展示開発に関する研究では、関与のあり方が「助言的」「代表的」「合意形成的」といった複数のレベルに分類されており、またその動機も「実用的」「理論的」「政治的」と異なる性質を持つことが指摘されています(Mygind, Hällman, & Bentsen, 2015)。これらの視点を踏まえた参加設計がなされなければ、共創は形骸化し、単なる演出にとどまるおそれがあります。
地域との協働もまた、展示に多層的な意味をもたらします。地域の歴史や記憶、生活文化を反映した展示は、来館者にとって身近で親しみやすく、また地域社会にとっては自己表現の機会ともなります。ある展示では、地域の織物生産者とデザイン会社が共同で展示構成に関わり、その制作過程自体が展示内容と密接に結びついていました(Guy, Williams, & Wintle, 2024)。こうした事例に見られるように、地域の人々とともに展示をつくることは、博物館の社会的役割を再定義する行為でもあるのです。
とはいえ、共創には常に課題がつきまといます。時間や人的コストの増加はもちろんのこと、関係者の意見や価値観の違いによって対立が生じることもあります。専門性をどう担保しつつ、開かれた参加を促すかというバランスも簡単ではありません。また、参加型のアプローチが過剰に演出されることで、本来の展示体験―静かに鑑賞し、深く思索するという時間―が損なわれる可能性も指摘されています(Høffding, Rung, & Roald, 2020)。展示の開放性と没入感の両立は、今後の実践において避けて通れないテーマです。
展示は、モノを並べて説明するだけの場ではなく、人と人が出会い、関係性を築く場です。来館者や地域と「ともにつくる」という姿勢は、博物館が社会とどう関わっていくのかを具体的に示すものでもあります。展示を通じて誰と語り、何を共有するのかを問い直すことは、博物館の公共性を再構築する営みにほかなりません。
展示における協働を支える仕組み ― 信頼・制度・評価の視点から考える
博物館における展示づくりは、さまざまな関係者の協働によって支えられています。しかし、協働がうまく機能するかどうかは、関係者の熱意や理念だけに依存するものではありません。展示の共創を現実のものとするためには、それを支える制度的な基盤や運営の仕組みが不可欠です。関係者間の信頼を育み、役割分担を明確にし、協働の成果を継続的に活かすための仕組みを整えることが、展示づくりの質を左右するといえるでしょう。
展示協力における実務的な調整事項は多岐にわたります。資料の貸出条件、輸送と保険の手配、展示中の安全管理、著作権や撮影可否の確認など、ひとつの展示を成立させるには細やかな手続きと合意形成が必要です。とくに巡回展や共同展示では、複数の機関が関与することで条件が複雑化しやすくなります。こうした事態を防ぐためには、あらかじめ共通の手続きや責任分担を明確にしておく必要があります。展示の協働を円滑に進めるには、標準化された契約書やプロトコルの整備が欠かせないとされています(Matassa, 2011)。
一方で、協働の成否を分けるのは、単なる契約や手続きだけではありません。展示制作の現場では、人と人との関係性が大きな影響を及ぼします。関係者の間に信頼が育まれていなければ、たとえ制度が整っていても協働は形だけのものになってしまいます。企画段階からの継続的な対話、意見交換の場の確保、相手の専門性や立場に対する理解と尊重といった日々の積み重ねこそが、良好なパートナーシップの基盤を築いていきます。展示の成功事例においては、こうした信頼関係が前提となっていたことが多く報告されています(Davies, 2010)。
さらに、展示協働の成果を次につなげるためには、評価とフィードバックの仕組みも重要です。展示が終わった後、そのプロセスや結果を関係者間で振り返る機会を設けることで、成功した点や改善すべき点を共有し、次回の展示に活かすことができます。協働の成果を測る評価指標を共有し、記録として残すことで、経験が属人的なノウハウにとどまらず、組織的な学びとして蓄積されます。特に博物館のように異なる専門分野が協働する現場では、こうした学びの共有が持続可能な連携の礎となります。
制度、信頼、評価という3つの視点を通して展示の協働を支える仕組みを整えることは、展示の質を高めるだけでなく、博物館という組織の柔軟性と持続性を高めることにもつながります。協働のあり方を「属人性」から「制度化」へと昇華させることで、より多くの関係者が安心して関わることができ、展示は真に「ともにつくる」営みとして社会に根づいていくでしょう。
展示の共創がひらく未来 ― 協働する博物館の姿とは
展示づくりは、もはや完成された成果物を一方的に提示する営みではなくなりつつあります。企画から構成、設営、発信に至るまで、展示は多様な関係者の協働によってつくり上げられるプロセスであり、そこに参加すること自体が意味を持つようになっています。他館、所蔵者、専門業者、地域住民、来館者といった多様な主体と関係を結びながらつくる展示は、単なる知識の集積や表現にとどまらず、公共性・多声性・包摂性といった社会的な価値を体現する場へと進化しています(Barnes & McPherson, 2019)。
こうした展示の共創は、単なる手法上の変化ではなく、博物館経営そのものに対する新たな視点をもたらしています。誰と展示をつくるか、どのような関係性を育むかといった問いは、ミッションやビジョンの実践そのものと深く関わってきます。専門性に裏打ちされた展示を担保しながらも、同時に社会に対して開かれた対話の場を提供することが、これからの博物館に求められる役割となっています。協働のプロセスを組織的に支え、柔軟で持続可能な経営を実現していくためには、制度と文化の両面から支える視点が必要です。
展示の協働は、制度が整っていれば自動的に成立するものではありません。各国・地域の制度や予算体制だけでなく、博物館職員の意識、組織文化、そして来館者との関係性のあり方といった文化的側面が大きく影響します。協働の場を機械的に設定するのではなく、関係性を丁寧に築き、相互の尊重と信頼に基づいて共創を進めていくことが不可欠です。展示を社会との接点と捉え、そのなかで生まれる対話や摩擦を受け入れる姿勢が、博物館の社会的変化への適応力を高めていくのです(Guy, Williams, & Wintle, 2024)。
展示を「ともにつくる」ことは、博物館の未来を「ともに描く」ことでもあります。関係者一人ひとりの視点や声を反映させながら、展示を共に構築していく営みは、博物館が社会に根ざし、市民とともに育つ存在であることを示す実践です。そのためには、協働を支える制度設計とともに、参加するすべての人が安心して関われる環境づくりが求められます。展示の共創は、博物館が誰のものなのかを問い直すだけでなく、博物館がいかに社会とともにあるべきかを考える起点となるのです。
参考文献
Barnes, P., & McPherson, G. (2019). Co-creating, co-producing and connecting: Museum practice today. Curator: The Museum Journal, 62(2), 257–273.
Davies, S. M. (2010). The co-production of temporary museum exhibitions. Museum Management and Curatorship, 25(3), 305–321.
Guy, K., Williams, H., & Wintle, C. (2024). Histories of exhibition design in the museum. Routledge.
Høffding, S., Rung, M., & Roald, T. (2020). Participation and receptivity in the art museum – A phenomenological exposition. Curator: The Museum Journal, 63(1), 69–88.
Matassa, F. (2011). Museum collections management: A handbook. Facet Publishing.
Mygind, L., Hällman, A. K., & Bentsen, P. (2015). Bridging gaps between intentions and realities: A review of participatory exhibition development in museums. Museum Management and Curatorship, 30(2), 117–137.