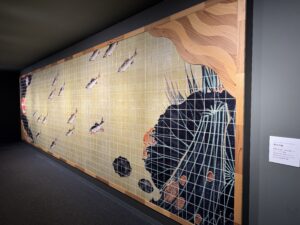導入:なぜ「デジタル時代のキュレーション」が重要なのか
博物館キュレーションを取り巻く環境変化
近年、デジタル技術の進展や社会構造の変化により、博物館のあり方そのものが大きく変化しています。従来、博物館は「保存と展示」を主な役割としてきましたが、グローバル化や多様性の拡大にともなって、来館者や地域社会との「対話」や「共創」が強く求められるようになっています。これにより、キュレーションの実践も大きく変わりつつあり、単なる情報の伝達者から、多様な価値観や体験をつなぐ「媒介者」への役割変化が進んでいます(Lopes, 2020)。
デジタル時代のキュレーション再考
なぜ今、キュレーションの本質を問い直す必要があるのでしょうか。最大の要因は、テクノロジーの進展によって来館者の体験が根本的に変化していることにあります。オンライン展示やバーチャル参加、SNSを活用した双方向型のコミュニケーションなど、博物館の外部・内部での体験の多様化が急速に進んでいます。こうした環境下では、従来の「一方的に作品や情報を見せる」展示だけでなく、来館者自身が参加し、意味を生成するプロセスが重視されるようになっています(An, 2024)。
また、グローバルな視点からは、地理的・社会的な制約を超えて、誰もが博物館の知と文化資源にアクセスできるようになったことも重要な変化です。デジタル化は、博物館の包摂性やアクセシビリティを大きく拡張しました。結果として、博物館のキュレーションは「社会とともに成長する動的な営み」として、より柔軟かつ開かれたものへと進化しています(Liao, 2025)。
本記事の目的と問い
本記事では、デジタル時代における博物館キュレーションの本質的変化と、その可能性について整理します。特に、「多様性」「共創」「パーソナライズ」という現代的なキーワードを軸に、最新研究と事例を参照しながら、これからのキュレーションの枠組みを考察します。主な参考文献としては、デジタル技術がもたらすキュレーター像の変化(Lopes, 2020)、バーチャル空間の特性や体験設計(An, 2024)、そしてロングテール理論が示す多様な展示・参加の可能性(Liao, 2025)を取り上げます。
このように、現代社会においてなぜキュレーションの再定義が求められるのか、その背景と問題意識を明らかにし、読者の皆さまとともに「これからの博物館キュレーション」のあるべき姿を探っていきたいと考えています。
博物館キュレーションの本質的変化 ― デジタル化がもたらしたもの
「選定者」から「媒介者」へ ― キュレーターの新しい役割
デジタル化の進展は、博物館におけるキュレーター像を根本から変えつつあります。かつての博物館キュレーションは、限られた専門家がコレクションを選定し、その価値や意義を「解説する」「伝える」という一方向的な構造に基づいていました。キュレーターは、展示品の管理・解釈・意味づけの権威として、館内外で大きな責任と権限を持っていたのです。しかし、近年のデジタル技術の普及、特にオンライン展示やSNSを活用した情報発信、インタラクティブなデジタル体験の拡大により、キュレーターは「選定者」から「媒介者」へと大きく役割を変えています(Lopes, 2020)。
このような変化は、博物館と来館者の関係性を抜本的に変えるものであり、従来の「展示を見る側」と「展示を作る側」という壁を低くしています。デジタルキュレーションにおいては、来館者自身が展示体験の中で自由に知識を獲得したり、作品への新しい解釈を生み出したりするプロセスが重視されるようになりました。キュレーターは「情報を与える人」から、「来館者とともに意味や価値を探究し、対話を促進する存在」へと進化しているのです。
さらに、デジタル時代のキュレーターは、作品の選定・解説のみならず、教育プログラムの設計やデジタルコンテンツの開発、外部クリエイターとのコラボレーションなど、多岐にわたる役割を担っています。こうした変化によって、キュレーションの現場はより開かれ、柔軟で、社会や観客との「共創」を志向するものへと進化し続けています(Lopes, 2020)。
多様性・包摂性の広がりとキュレーションの再編
デジタル技術の進化により、博物館キュレーションはこれまでにない多様性と包摂性を獲得しました。オンライン展示やバーチャルミュージアムの登場は、地理的・身体的な制約を大きく超えて、多様な背景を持つ人々に博物館体験の機会を開放しています。たとえば、自宅からでも高精細な画像や3Dモデルを使ったバーチャルツアーを体験できるようになったことで、子どもや高齢者、障害のある人など、従来は来館が難しかった層にもアプローチできるようになりました(An, 2024)。
さらに、デジタル空間では、世界中のユーザーが同時に展示にアクセスでき、SNSを通じて意見を発信し合うなど、これまで以上に多彩な視点・価値観がキュレーションに反映されるようになりました。これは博物館にとって、単なる来館者の増加にとどまらず、多文化・多世代・多層的な交流の場としての価値を大きく高めるものです。
組織面でも、従来の「学芸員主導型」から「多職種協働型」へのシフトが顕著です。教育普及、デジタル、マーケティングなど多様なバックグラウンドを持つ専門職が協働し、より包括的で参加型のキュレーションを実現しています。このような体制は、デジタルキュレーションの推進に不可欠であり、今後の博物館経営の重要なポイントになるでしょう(Lopes, 2020)。
展示・体験の質的変化と来館者参加型キュレーション
デジタル化は、博物館展示のあり方そのものにも質的な変革をもたらしています。従来の「一方的に展示物を鑑賞する」スタイルから、来館者が展示体験の中で「能動的に参加する」「自身の視点や感性を反映する」ことができるようになりました。たとえば、インタラクティブなデジタル展示や、VR/AR技術を活用した体験型コンテンツでは、来館者の操作や選択に応じて情報が変化するため、誰もが自分だけの展示ストーリーを作り出すことが可能です(An, 2024)。
また、近年は「観客参加型キュレーション」や「クラウドキュレーション」といった新しいアプローチも注目されています。これは、来館者や一般ユーザーがオンラインで展示の構成や解説作成、関連情報の付与に関わり、プロのキュレーターとともに新たな価値を生み出す仕組みです。こうした動きは、専門家だけでなく多様なユーザーの視点を博物館運営や展示づくりに反映し、より開かれた「共創」の場としての博物館を実現します(Lopes, 2020)。
このような変化は、博物館の社会的役割を拡大させるだけでなく、「来館者との双方向性」「多様な価値観の共存」「個別最適化された体験」といったデジタルキュレーション時代ならではの新たな価値を生み出しています。今後は、デジタル技術の進化に合わせて、より多様で創造的な展示体験がますます広がることが期待されています(An, 2024)。
観客参加・共創型キュレーションとバーチャル時代の新展開
観客参加・クラウドキュレーションの拡大
近年、博物館のデジタルキュレーションは「観客参加」や「クラウドキュレーション」の進化によって、かつてない広がりを見せています。デジタル技術が発展する以前、展示や解説の主導権は学芸員やキュレーターなど限られた専門家にありました。しかし、オンライン展示やSNS、ウェブアプリの普及によって、来館者や一般ユーザーが積極的に展示企画・解説・情報編集に関わる時代となりました(An, 2024)。
たとえば、展示内容のオンライン投票やSNSを通じたテーマ募集、ユーザー生成コンテンツ(UGC)の展示活用、さらには来館者の体験談や写真・イラストなどを展示の一部として取り入れる取り組みが広がっています。Google Arts & CultureやRijksstudioのようなグローバルなデジタルプラットフォームでは、利用者が自分だけのバーチャルコレクションをつくり、オリジナルの解説や展示ストーリーを世界に発信できるようになっています。こうしたクラウドキュレーションは、博物館を「知識の発信源」から「知の共創空間」へと進化させる重要な役割を担っています。
このような観客参加型のデジタルキュレーションが進むことで、博物館は社会や来館者との「対話」や「協働」を一層強化できます。展示づくりのプロセス自体に多様な視点が加わることで、従来の「専門家主導」だけでは生み出せなかった新たな価値やストーリーが次々に誕生します。これはまさに、デジタルキュレーションが「共創」の時代を迎えた証といえるでしょう(An, 2024)。
バーチャルキュレーションの体験設計とアクセシビリティ
デジタル時代の博物館キュレーションで大きな注目を集めているのが、オンライン展示やバーチャル体験の進化による「アクセシビリティの拡張」です。従来の博物館体験は、どうしても地理的・身体的な制約を受けていました。しかし、バーチャルキュレーションの登場により、自宅や学校、さらには海外からも簡単に世界中の博物館展示にアクセスできる時代となっています(An, 2024)。
バーチャル空間では、年齢・文化・性別・障害の有無を問わず、さまざまな来館者が自分に合った情報や体験を選択できます。ユーザーインターフェースやナビゲーションの工夫、選択式の解説、多言語対応、アクセシビリティガイドラインの導入などにより、個々のニーズや興味に応じたパーソナライズド体験が実現しています。たとえば、展示作品ごとに多様な視点からの解説やストーリーが用意されており、ユーザーは自分が関心を持った切り口で深掘りできるのが特徴です。
また、オンライン展示の普及は、来館が難しかった遠隔地の住民や高齢者、障害のある方、子育て世代にも博物館体験の扉を開きました。バーチャルガイドツアーや3Dモデルの展示、AR/VR技術を活用した没入型体験など、誰もが参加できる「開かれた博物館」が実現しています。こうしたバーチャルキュレーションの発展は、博物館の社会的包摂性とアクセシビリティ向上に直結する大きな変革といえるでしょう(An, 2024)。
ロングテール理論によるマイナー展示の価値創出
デジタル時代の博物館キュレーションにおいて、特に注目されているのが「ロングテール理論」の応用です。ロングテール理論とは、メインストリームや著名な作品だけでなく、これまで脚光を浴びてこなかった無名な作品やニッチなテーマの展示も幅広く取り上げることで、博物館全体としてより豊かな価値を生み出すという考え方です(Liao, 2025)。
従来のリアルな博物館では、スペースや運営資源に限りがあったため、注目度の高い作品や話題のテーマに焦点が集まりがちでした。しかし、デジタルキュレーションの進展により、オンライン上で膨大な数の作品や資料を公開できるようになったことで、無名な作品や地域独自の展示、個人的なストーリーも「主役」として輝く機会が増えています。来館者は自分の興味や関心を出発点に、今まで出会うことのなかった展示や情報を自由に発見できるため、体験の多様性と個別最適化が一層進みます。
ロングテール理論を活用したキュレーションによって、来館者やオンラインユーザーが新しい知識や価値観、多様なストーリーと出会う「発見」の機会が格段に広がります。たとえば、マイナーな展示やニッチなテーマのコンテンツにも簡単にアクセスできるようになったことで、従来は注目されなかった作品や資料にも光が当たり、博物館全体として提供できる体験や知的資源の幅が大きく広がっています(Liao, 2025)。
こうした取り組みは、デジタルキュレーションと観客参加型の共創と組み合わさることで、「多様性」「共創」「パーソナライズド体験」を軸とした現代的な博物館の新たな姿を実現しています(Liao, 2025)。
デジタル時代のキュレーションの課題と未来展望
デジタル化がもたらす課題とリスク
デジタルキュレーションの普及は、博物館の新たな可能性を広げる一方で、さまざまな課題やリスクも生み出しています。まず大きな問題となるのが、オンライン上で提供される情報の信頼性や真偽の担保です。膨大なデジタルコンテンツが流通する現代では、誤った情報や意図しない誤解が拡散されるリスクが常に存在しています。加えて、著作権やプライバシー、データ管理に関するトラブルも増加傾向にあり、デジタル展示やバーチャル体験を提供する際には法的・倫理的な配慮が不可欠です(Lopes, 2020)。
また、デジタル化によって誰もが均質な展示体験を得やすくなる一方、逆に体験の没個性化や画一化が進みやすいという課題も指摘されています。テクノロジーの恩恵を最大限に活かすためには、来館者一人ひとりの多様な関心や価値観に対応できる柔軟なコンテンツ設計が必要です。さらに、インターネット環境やデジタルデバイスへのアクセスに格差があることも無視できません。デジタルキュレーションはアクセシビリティの向上に貢献しますが、すべての人に等しく開かれているわけではないという現実的な限界も認識しておく必要があります(Liao, 2025)。
「共創・参加・対話」が拓くキュレーションの未来
こうした課題を乗り越えるためには、「共創」「参加」「対話」というデジタル時代のキーワードがいっそう重要になります。観客参加型や共創型のキュレーションは、従来の博物館のあり方を大きく変えるだけでなく、バーチャル空間とリアル空間を組み合わせたハイブリッド展示の発展にもつながります。たとえば、オンラインで集めた来館者の意見やアイデアをリアルな展示に反映したり、バーチャル体験の中で生まれたストーリーを地域社会と共有する取り組みが進んでいます(An, 2024)。
また、最新のテクノロジーを活用することで、来館者自身が自分に合った展示や体験を選び、積極的に参加・発信できる環境が整いつつあります。これは、博物館の社会的包摂性や教育的価値を一段と高めるだけでなく、持続可能な運営や多様なコミュニティとの協働を促進する新たなガイドラインの構築にもつながります。今後は、テクノロジーと人間の創造力を掛け合わせた「未来志向の博物館運営」がますます求められるようになるでしょう(Lopes, 2020)。
キュレーター・ミュージアムの新たな役割と社会的意義
デジタル時代の進展によって、キュレーターや博物館そのものの役割も大きく変化しています。従来のキュレーターは主に専門知識に基づいて展示を企画・運営してきましたが、現在では多様なコミュニティや来館者と直接つながり、対話や共創の場を生み出す「ファシリテーター」としての役割がより重視されるようになっています(Lopes, 2020)。
また、博物館は単なる展示や教育の場を超えて、文化発信拠点・社会包摂の場としての機能も拡大しています。地域社会や国際的なネットワークとの連携、教育・研究・実践・倫理をめぐる新たな潮流を受けて、今後ますます多様な主体が関わるダイナミックなプラットフォームとして進化していくことが期待されます。こうした変化は、デジタルキュレーションと現代的な社会的課題への応答力を兼ね備えた、新しい博物館像の形成につながっています(An, 2024; Lopes, 2020)。
まとめ
デジタル時代の到来は、博物館キュレーションの在り方に根本的な変化をもたらしています。キュレーターはこれまでの「選定者」から「媒介者」「共創のファシリテーター」へと役割を広げ、来館者や地域社会、オンラインユーザーとともに展示の価値や意味を新たに生み出す時代となりました。観客参加型キュレーションやクラウドキュレーションの進展は、来館者自身が展示企画や解説に参加する機会を増やし、博物館が「知の共創空間」として社会に開かれていくことを可能にしています(An, 2024)。
また、バーチャル展示やデジタルコンテンツの普及によって、博物館は従来以上に多様な層の利用者にアクセシビリティを提供し、年齢や国籍、障害の有無を問わず誰もが知的体験や文化交流を楽しめる環境を実現しつつあります。ロングテール理論を取り入れたキュレーションの考え方は、有名な作品だけでなく、無名な作品やニッチなテーマにも光を当てることで、知的資源や文化的価値の幅を大きく広げています(Liao, 2025)。
一方で、情報の信頼性や著作権・プライバシーといった課題、また体験の画一化やデジタル格差といったリスクも顕在化しています。これらの課題に対しては、法的・倫理的配慮を徹底し、多様なニーズに応える柔軟な運営体制やテクノロジーの活用が求められます(Lopes, 2020)。来館者やコミュニティの多様性を尊重し、共創・参加・対話を軸とした運営に取り組むことが、今後の博物館キュレーションの持続的発展に不可欠です。
現場で働く担当者やキュレーター、これから博物館経営を学ぶ学生にとって、デジタルキュレーションの知見と実践は、現代社会における博物館の新しい役割を考えるうえで極めて重要な指針となるはずです。今後も社会や技術の変化を柔軟に取り込みながら、博物館が多様な人々とともに価値を創造し続ける場となることが期待されます。
参考文献
- An, R. (2024). Art curation in virtual spaces: The influence of digital technology in redefining the aesthetics and interpretation of art. Humanities, Arts and Social Sciences Studies, 24(2), 503–518.
- Liao, L. (2025). Application of the Long Tail theory in modern museum virtual curation: A study of curatorial directions in the digital age. Museum Management and Curatorship.
- Lopes, R. O. (2020). Museum curation in the digital age. In The Future of Creative Work (pp. 124–132). Edward Elgar Publishing.