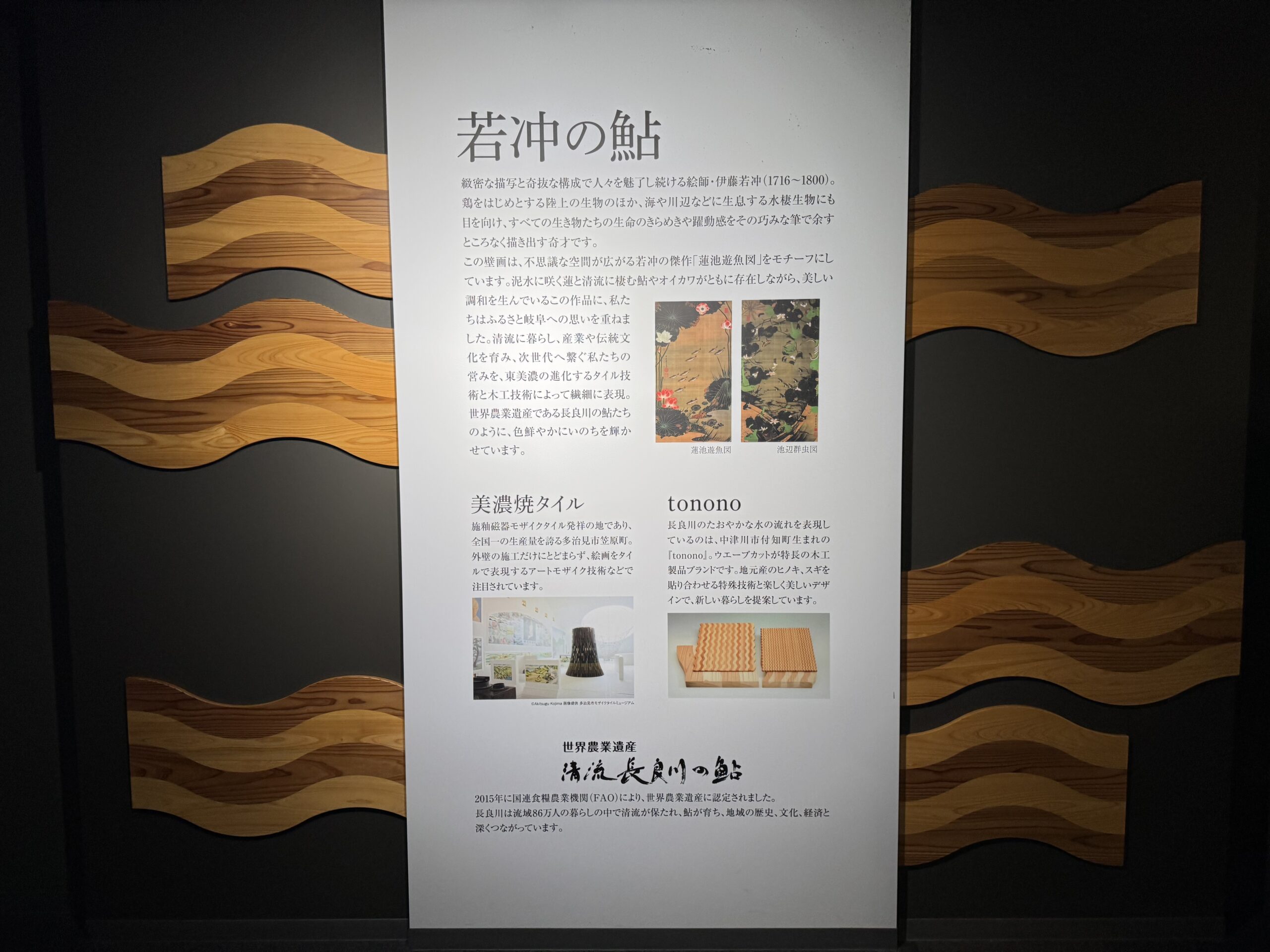読まれるパネル・素通りされるパネル――展示解説の現場で見える来館者の多様な行動
博物館や美術館の展示解説パネルの前では、パネルを素通りする人や、立ち止まってじっくり読み込む人など、来館者の反応はさまざまです。こうした光景から、どんなパネルが読まれやすいのか、または素通りされてしまうのか、その違いに関心を持つことが多くなっています。
解説パネルがどれほど来館者にとって役立っているのか、その意義や効果については、展示をつくる側でもしばしば議論になります。情報量の多さや専門用語の使い方、配置や視認性など、さまざまな要因が「読まれる・読まれない」に影響しているのではないかと考えられています。
近年は、視線追跡や会話分析といった実証的な研究が進み、来館者が展示ラベルをどのように活用しているのか、具体的なデータが得られるようになりました。たとえば、視線追跡調査では、多くの来館者が何らかの形でパネルを読んでいることが確認されています(Reitstätter et al., 2022)。ただし、その「読み方」や「活用のされ方」には大きな個人差があり、また展示の種類やパネルの設計によっても大きく変わることが明らかになっています。
この記事では、「読む」「語る」「記憶する」という3つの観点から、解説パネルが来館者の行動や学びにどのような影響を与えているのかを整理します。実際の現場事例も交えながら、効果的な展示ラベル設計のポイントをわかりやすく解説していきます。
読まれる解説パネルの特徴と来館者の“読み方”の実態
来館者の「読む」行動を可視化する:視線追跡調査の知見
博物館や美術館の展示室では、来館者がどのように展示解説パネル(展示ラベル)を利用しているのか、長年にわたり関心が寄せられてきました。しかし、従来は「読まれているかどうか」を観察者の主観や来館者のアンケート回答などで判断することが多く、実際の“読む行動”の細部までは明らかになっていませんでした。
近年は、視線追跡(アイトラッキング)技術が急速に発達し、来館者が作品と解説パネルの間でどのように視線を動かしているか、リアルタイムかつ客観的に分析できるようになっています。たとえば最新の調査では、多くの来館者が「まず作品をじっくり眺め、その後パネルに目を移し、再び作品に戻る」という“art-label-art”型の視線パターンを繰り返していることが示されています(Reitstätter et al., 2022)。このような動きは、作品理解を深めるうえで解説パネルが重要な役割を担っていることを示唆しています。
さらに、パネルに記載されている情報量が多い場合や、部屋の混雑度が高い場合には、パネル閲覧の回数や視線の移動パターンが複雑化し、「パネルを何度も見返す」「複数のラベルを読み比べる」などの行動も多く観察されています。
また、調査によれば、展示ラベルに記載された情報が“単なる知識の補足”にとどまらず、「鑑賞体験そのものの印象や記憶」にも大きく影響していることが分かっています。パネルの内容が来館者の記憶の“手がかり”となり、帰宅後の振り返りや他者との会話の中で、ラベルの文言やストーリーが“エコー”として引用されるケースも報告されています(Reitstätter et al., 2022)。
読まれる人・読まれない人:読み方の多様性と分類
展示解説パネルの「読み方」や「活用のされ方」には、来館者ごとに大きな個人差があります。最新の研究では、来館者を「高頻度読者」「中頻度読者」「低頻度読者」に分類し、それぞれの行動特性が分析されています。中でも最も多いのは“中頻度読者”で、来館者全体の約4割を占めるとされています(Reitstätter et al., 2022)。
特徴的なのは、美術や博物館に精通していない、いわゆる“初心者”ほどラベルを丁寧に読み、知識の補完や鑑賞の手がかりとして活用する傾向が強いことです。一方、専門的な知識や関心を持つ来館者やリピーターは、作品そのものの鑑賞に重きを置き、パネルの内容には最低限目を通す程度にとどまる場合が多いです。
また、年齢層や来館目的、同伴者(家族連れ・個人・グループなど)によっても「ラベルの読む度合い」は変化します。たとえば子ども連れの家族では、大人が子どもに説明しながらラベルを一緒に読むシーンも多く観察され、世代間での学びの橋渡し役としてパネルが活用されていることがわかります。
こうした多様性を踏まえ、博物館のパネル設計では「どの層の来館者に向けて、どんな情報をどう伝えるか」という観点がますます重要になっています。
読まれるパネルに共通するデザイン・表現の工夫
読まれるパネルにはいくつかの共通する特徴が見られます。まず第一に、フォントの種類や文字サイズが来館者にとって読みやすく設計されていることが大切です。遠くからでも視認しやすい配置や適切な行間、余白の確保など、物理的なレイアウトの工夫は必須です。
また、情報の整理にも配慮が必要です。1つのパネルに盛り込む情報は必要最低限に抑え、箇条書きや短文を中心とした簡潔な構成にすることで、読み手の負担を軽減します。
さらに、来館者の知識や関心を引き出すため、「なぜ」「どうして」などの問いかけ要素をパネルに盛り込む方法も効果的です。問いかけがあることで、来館者は単なる情報受容者ではなく、展示内容について自ら考えたり、他者と対話したりするきっかけを得ることができます。
物理的な要素では、パネルの高さや設置場所、照明による明るさ、他の展示物との距離感も重要です。混雑時にも無理なく閲覧できる配置や、導線上で自然に目に入るレイアウトは、「読まれるパネル」をつくるうえで欠かせません(Reitstätter et al., 2022)。
このような配慮が、来館者の関心を引きつけ、実際の「読む」行動へとつなげていきます。
「読まれない」要因は何か?
一方で、どれほど手間をかけても「読まれないパネル」が生じてしまう場合もあります。その主な要因として、まず挙げられるのは情報量の過多です。解説内容を詰め込みすぎて文字ばかりが並ぶパネルは、来館者に「読むのが大変そう」という印象を与えてしまい、結果的に素通りされることが多くなります。
また、専門用語や難解な表現の多用も、一般の来館者にはハードルとなります。内容が難しすぎると「自分には関係がない」「理解できない」と感じられ、パネルへの関心が薄れてしまいます。
さらに、パネルの設置位置が高すぎたり低すぎたり、照明が当たっていない、展示ケースの奥まった場所にあるなど、物理的な視認性の問題も「読まれない」要因として見逃せません。混雑していて近づけない、動線が悪くパネルが見落とされやすいといった空間的な課題も影響します。
実際の研究でも、こうした要素が来館者の「ラベルを読む機会」を大きく左右することが明らかになっています(Reitstätter et al., 2022)。このように、「読まれる・読まれない」を分ける要因は多岐にわたっており、パネル設計の際には一つひとつ丁寧に検討することが求められます。
語られる・共有される解説パネル――会話を生み出すデザインとその効果
来館者同士の対話が生まれるパネルの条件
展示解説パネルは、来館者に知識を伝えるためだけのものではありません。実際には、パネルの内容や表現次第で、来館者同士の会話や発見、さらにその場での新たな学びが自然に生まれる仕組みとしても機能しています。「問いかけ(オープンクエスチョン)」やストーリー性を持たせた展示ラベルの効果が大きく取り上げられています。
たとえば、「なぜこの作品がここに展示されているのでしょうか?」「あなたならどう感じますか?」といった問いかけがラベルに記載されていると、来館者は展示を受け身で見るだけでなく、自分自身で考えたり、同行者と意見を交わしたりするようになります。実証研究では、こうした質問型ラベルを導入した展示空間で、来館者同士が作品の意味や背景について語り合う頻度が明らかに増加したことが示されています(Hohenstein & Tran, 2007)。
また、ストーリー性のある解説文や、作家の人生、時代背景、作品に込められた思いなどを盛り込むことで、来館者は作品とより強く感情的につながることができ、展示体験そのものが豊かになります。実際に「この作品はどんな思いで描かれたのだろう」と自分なりに想像したり、来館者同士で感想や発見を語り合ったりする姿が多く見られるようになります。
このような“語られるパネル”は、単なる情報伝達の枠を超え、来館者に能動的な参加や思考を促す「対話の仕掛け」としての役割を持っています。パネルの文章構成や問いかけの工夫が、展示全体のコミュニケーションや来館者のエンゲージメントを大きく左右するのです。
コラボレーションを促す指示・仕掛け
展示ラベルに「コラボレーションを促す明確な指示」や「仕掛け」を取り入れることで、来館者が自然に展示内容について意見を交わすようになります。たとえば、「隣の人と話し合ってみましょう」「家族で考えてみてください」「グループで答えを出しましょう」といったフレーズが挙げられます。
グループで協力して問題解決を促すようなパネルがある場合、個人で黙々と鑑賞するよりも深い学びや発見が生まれやすくなります(Wang & Yoon, 2013)。また、親子連れや学校団体など、もともとグループで来館している来館者が多い現場では、こうした協働型のラベルが会話や気づきを生み出す効果が特に高いとされています(Wang & Yoon, 2013)。
こうしたコラボレーションの促進は、展示体験の満足度向上だけでなく、展示をきっかけとした家庭内や学校内での継続的な対話や学びにもつながります。「みんなで考える」「意見をシェアする」ことが展示室の中だけで完結せず、日常生活の中にも広がっていく――こうした波及効果も、コラボレーション型パネルの大きな魅力です。
さらに、グループで問いに答えるワークシートや投票型のパネル、意見を書き込めるボードなども来館者の能動的参加を後押しします。展示設計にこうした“参加の余白”を組み込むことで、博物館や美術館が一方通行の情報発信の場から、来館者同士が相互作用しながら学び合う体験の場へと進化します。
来館者参加型ラベル・多声的解説の意義とインパクト
来館者参加型ラベル(visitor-written label)は、世界の美術館や博物館で導入が広がっている手法です。来館者が作品や展示について自分の言葉で自由に解説や感想を書き、それを他の来館者と共有できる仕組みを指します。たとえば、展示室内に「あなたの感想をシェアしてください」といった書き込みスペースを設けたり、QRコード経由でスマートフォンから意見を投稿したりする方法もあります。
このような参加型の仕掛けを導入すると、来館者が単なる「情報の受け手」から「発信者」へと役割を広げることができ、展示への主体的な関与や思考の深まりが促されます。来館者の平均滞在時間が延びるだけでなく、他者の解釈や感想を読むことがきっかけとなり、新たな発見や共感、さらには来館者同士の対話が広がったという報告があります(Nashashibi, 2003)。
また、多様な価値観や文化的背景を持つ人々の声が展示空間に集まることで、博物館や美術館が「唯一の正解を伝える場」ではなく、「多様な見方・感じ方を認め合う場」として進化することができます。こうした多声的な解説は、専門家による説明だけでは届かない視点や体験を来館者同士が共有し合う知の循環を生み出し、学びや感動を一層豊かなものにします。
この実践は、参加型ミュージアムやコミュニティ連携型展示の流れとも親和性が高く、来館者自身が展示づくりに参加している実感を持てるという点でも大きな意味があります。
会話・エンゲージメントを妨げる要因とその対策
会話やエンゲージメントを促進するには、パネルや展示空間の設計上、阻害要因を避けることも重要です。たとえば、解説文が抽象的すぎたり、専門用語ばかりで読みにくい内容だった場合、来館者はパネルから距離を置きやすくなります。また、「これはこう見るべき」といった一方的で断定的な説明が続くと、来館者の自由な対話や発見の意欲を削いでしまいます。
物理的な要因も見逃せません。ラベルの配置が高すぎたり低すぎたり、照明が暗くて読みにくい、混雑時に立ち止まりにくい動線になっていると、そもそもパネルの前で立ち話や意見交換をする機会自体が減ってしまいます。
これらの課題への対策としては、簡潔で平易な日本語を使うこと、専門用語には注釈や補足説明をつけること、一文一意を心がけることが挙げられます。また、物理的な配置や動線を工夫し、来館者が自然に集まり、立ち止まれる場所を確保することも有効です。さらに、意見を書き込めるスペースやSNS連動の仕掛けを設けることで、デジタル・リアル両方の対話の機会を広げることも現代的な展示には有効な手法となります。
このように、展示解説パネルは工夫次第で来館者の語り合いや気づきのきっかけをつくることができるのです。
記憶に残る解説パネルの条件――印象・学び・来館後の“エコー効果”
なぜ記憶に残るパネルが重要なのか?
博物館や美術館の展示解説パネルは、単にその場で情報を伝えるためだけのものではありません。むしろ、来館者が展示空間を離れた後も内容を思い出したり、誰かに語ったりする「記憶のきっかけ」となることが重要です。印象に残るパネルは、来館者が展示体験を自分の学びや日常生活につなげる架け橋となり、再来館の意欲や博物館への親しみの気持ちにもつながります。
また、パネルの内容が強く記憶に残ることで、教育普及活動や学校連携プログラムでも学びの深化が期待できます。パネルを通じて得られた知識やストーリーが、子どもたちの自由研究や家庭内での会話、SNSでの情報発信など、来館後のさまざまな行動に発展するケースも多いです。
記憶に残りやすいパネルの特徴とデザイン
記憶に残る解説パネルには、いくつかの共通する特徴があります。まず、ストーリー性や具体的なエピソードが盛り込まれているパネルは、読み手の感情に訴えかけ、内容が印象に残りやすくなります。「この作品は誰のために作られたのか」「当時の人々はどう感じていたのか」といった、人や時代の物語を絡めることで、単なる事実説明以上の記憶効果が生まれます。
また、パネルのテキスト量は多すぎず、読みやすいキーワードやフレーズを効果的に配置することが大切です。視線追跡研究によれば、来館者はパネル内の特定の言葉や短い文に目を留めやすく、そうした部分が後の記憶に強く残る傾向があります(Reitstätter et al., 2022)。
さらに、ビジュアル要素や図版、イラストなどもパネルの記憶定着に効果的です。写真やイメージを補助的に使うことで、展示物とパネルの内容が結びつきやすくなり、来館後の印象にも強く残ります。パネルの配置やデザインも重要で、自然な動線上に設置されている場合や、適切な照明が当てられている場合、より記憶に残りやすいとされています。
来館者の記憶に“エコー”するパネルとは
展示解説パネルの内容が来館者の記憶に残ると、その後の生活や会話の中で「エコー現象」と呼ばれる再言及が生まれることがあります。たとえば、友人や家族に展示内容を説明する際、パネルに書かれていたエピソードやキーワードを引用したり、SNS投稿やアンケートでパネルの文章を再利用したりするケースがこれにあたります。
参加型ラベルや来館者自身が書き込む展示パネルは、記憶への残りやすさをさらに高めます。自分の意見や感想をその場で残す体験が、より深い印象となって定着し、後日振り返る際にも鮮明に思い出されることが多いです(Nashashibi, 2003)。
こうした「記憶にエコーするパネル」は、単なる知識の伝達を超えて、来館者一人ひとりの学びや人生経験に根ざした記憶を生み出します。
現場で活かせる「記憶されるパネル設計」のポイント
記憶に残る解説パネルを設計するためには、まず来館者が共感しやすいストーリーや問いかけを意識して盛り込むことが有効です。文章は一文一意を心がけ、キーワードや印象的なフレーズを冒頭や太字で目立たせることで、視線が止まりやすくなります。
また、ビジュアルを活用し、展示物との結びつきが明確になるような写真やイラストを添えると記憶定着率が高まります。レイアウトは見やすさ・読みやすさを重視し、物理的にもパネルの高さや照明、導線上の配置を工夫することが重要です。
さらに、来館者が自分の言葉や体験を残せる参加型スペースやアンケートの導入も、記憶へのエコー効果を高めます。こうした工夫を積み重ねることで、展示パネルは一過性の情報から、来館者の心に残る「記憶のきっかけ」へと進化していきます。
解説パネル設計で避けたい落とし穴――現場でよくある課題と回避のポイント
情報過多・専門用語の乱用が招く“読まれないパネル”
解説パネルで最も多い失敗例のひとつは、伝えたい情報を詰め込みすぎてしまうことです。来館者にたくさんの知識や背景を届けたいという思いが強すぎると、結果的にテキスト量が増え、難解な専門用語や複雑な文章が多くなってしまいます。その結果、「読むのが大変そう」と敬遠され、せっかくの情報が来館者に届かなくなるという本末転倒な状況が生まれます。
特に、展示の専門性や歴史的背景などを詳細に解説したい場合は、「どの層に向けて」「どこまで説明するか」をあらかじめ整理し、情報量を適切に絞り込むことが重要です。やむを得ず専門用語を使う場合は、できるだけ簡単な補足やイラスト、注釈を加えるなどの配慮が求められます。
配置や視認性のミスが引き起こす問題
パネルの物理的な設計ミスも、読まれない原因になりやすいポイントです。たとえば、解説パネルが高すぎる位置に設置されていたり、逆に床近くにあって読みにくい場合、子どもや高齢者にとっては大きな負担となります。また、照明が不十分で暗くなっている、混雑時に立ち止まるスペースがない、動線の途中で見落とされやすい位置にパネルがあるといった配置上の問題も多くの館で見られます。
特に、多世代の来館者や車椅子利用者など、幅広い来館者に配慮したパネルの配置ができているかを現場で定期的に確認することが大切です。簡単なチェックリストや、実際に複数の立場で読みやすさをテストする仕組みも効果的です。
一方的・断定的な説明が対話・エンゲージメントを妨げる理由
「こう見るべき」「これが正しい」といった断定的な解説は、来館者の対話や発見を妨げる大きな要因となります。せっかくのパネルが一方通行の“答え合わせ”になってしまうと、来館者は自分なりに考えたり、他の人と意見を交わしたりする余地を失いがちです。
むしろ、問いかけや複数の解釈を提示することで、来館者が自由に展示内容を受け止めたり、他者と語り合ったりするきっかけを作ることができます。パネルの文章や構成には「発見」「気づき」「対話」の余白を意識することが大切です。
現場でできるシンプルな回避策
こうした失敗や落とし穴を避けるためには、まず情報を「誰に」「何のために」伝えたいのかを明確にし、文章を短く、構成をシンプルに保つことが基本です。さらに、配置や高さ、明るさ、混雑時の動線など物理的な条件も定期的に見直します。
現場では、来館者の声をもとに修正を重ねたり、簡単なフィードバックシートやアンケートで「読みにくい」「難しい」と感じるポイントを拾うことも有効です。また、複数の職員やボランティアによるチェック体制をつくることで、多様な視点からパネルの設計を検証することができます。
小さな改善を積み重ねることで、解説パネルは“読まれない壁”から“伝わる入り口”へと生まれ変わります。
まとめ――来館者の心に響く解説パネル設計のために
本記事では、博物館や美術館の解説パネルが「読む・語る・記憶する」という三つの視点から来館者の体験をどのように形づくるのかを整理してきました。パネルは単なる情報伝達のツールにとどまらず、来館者が展示と向き合い、他者と語り合い、鑑賞体験を深めるための大切なきっかけとなります。
読まれるパネルを設計するためには、内容の分かりやすさや見やすい配置だけでなく、問いかけやストーリーを盛り込むことで来館者の関心や対話を引き出す工夫が求められます。また、記憶に残るパネルは来館後の学びや再来館の動機づけにもつながります。反対に、情報過多や専門用語の乱用、断定的な解説や視認性の悪さは、来館者の関心を遠ざける原因となります。
解説パネルの設計で最も大切なのは、「誰のために、どんな体験や学びを生み出したいのか」という視点を持ち続けることです。実証研究や現場での工夫、多様な来館者の声を参考に、小さな改善を積み重ねていくことが、より良い展示体験につながります。
来館者にとって記憶に残る、語りたくなる、また足を運びたくなるような解説パネルを目指して、日々の展示づくりに活かしていきたいものです。
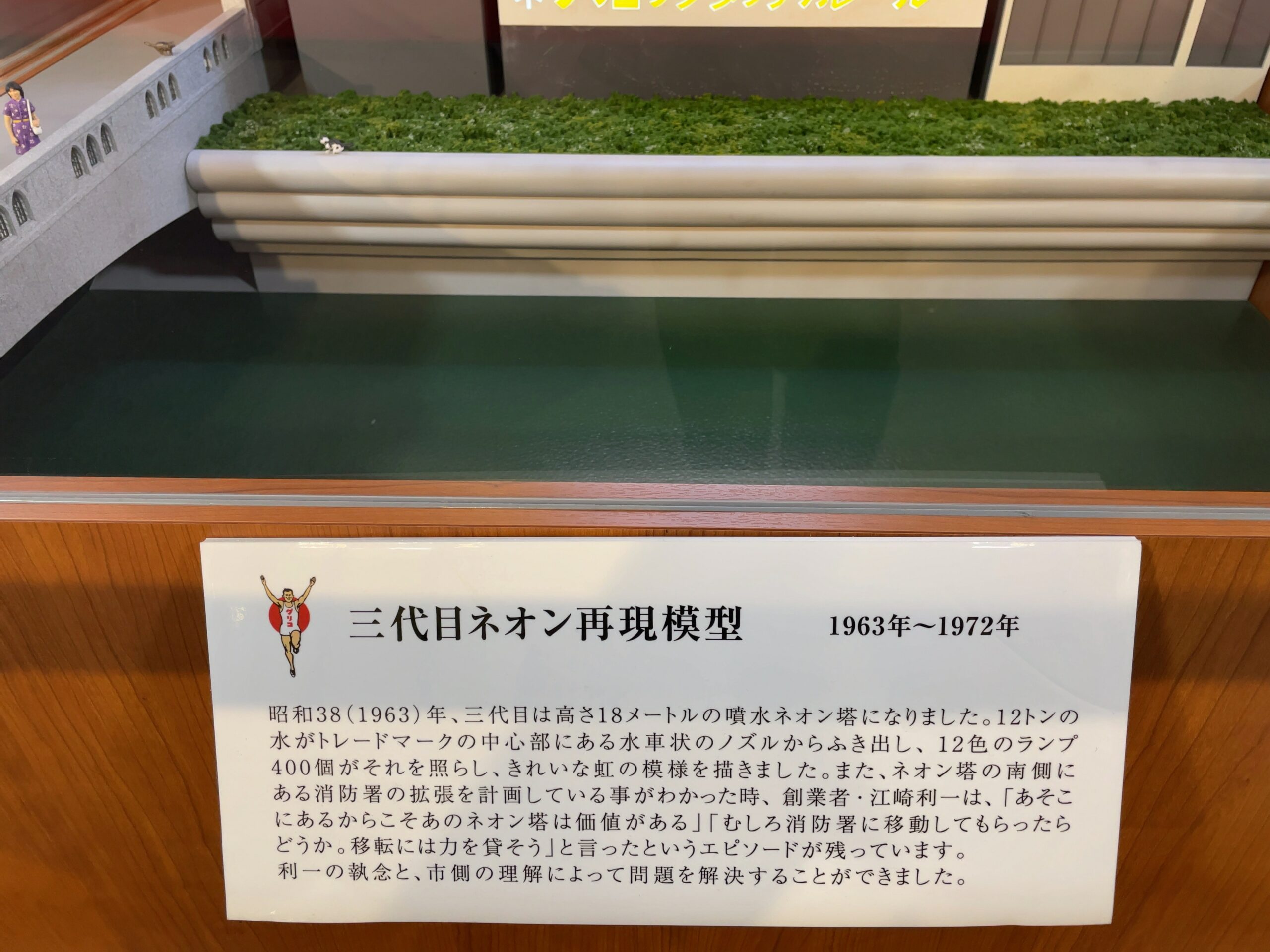
参考文献
- Hohenstein, J., & Tran, L. U. (2007). The Role of Question Prompts in Family Learning at a Natural History Museum. Science Education, 91(2), 191–212.
- Nashashibi, D. (2003). The Visitor-Written Label: A New Way to Open Up the Museum. Curator: The Museum Journal, 46(2), 145–156.
- Reitstätter, L., Nelles, J., & Rumpold, L. (2022). Looking to Read: How Visitors Use Exhibit Labels in the Art Museum. Curator: The Museum Journal, 65(1), 69–85.
- Wang, L., & Yoon, S. A. (2013). Collaborative Group Work in Museum Exhibit Design: Effects on Students’ Attitudes and Learning. Journal of Museum Education, 38(2), 172–182.