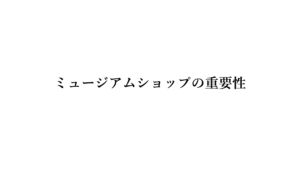デザイン・ミュージアムと「Transformation 2029」計画の背景
ロンドンのデザイン・ミュージアム(Design Museum)は、1989年に創設された比較的新しい博物館であり、2016年にはケンジントンへと移転しました。建築やファッション、工業デザインからデジタルテクノロジーに至るまで幅広い分野を対象とし、デザインを専門的に扱う国際的な拠点として知られています。近年は、世界中から多様な観客を引きつけ、年間数十万人規模の来館者を集めるなど、ロンドンを代表する文化施設の一つに成長しています。こうした背景から、同館は単なる展示施設にとどまらず、社会の中でデザインが果たす役割を発信する重要なハブとして位置づけられています。
そのデザイン・ミュージアムが2025年に打ち出したのが「Transformation 2029」と呼ばれる大規模な刷新計画です。これは2029年に迎える創立40周年を節目として策定されたもので、特に常設展示「Designer, Maker, User」の全面的な改修を中心に据えています。この常設展示は、デザインの歴史や製作の過程、利用者の視点を立体的に提示する革新的な展示として知られていますが、一般的に5〜7年で寿命を迎えるとされる常設展示を10年近く維持してきたことから、来館者ニーズや時代の変化に対応しきれなくなっている点が課題とされてきました(IanVisits, 2025)。
計画の予算規模は約£2.7百万に上ると見込まれ、資金調達には英国のナショナル・ロッタリー・ヘリテージ・ファンドによる二段階の助成制度が活用されます。まずは約£267,000の「開発フェーズ」助成を得て2年間にわたり展示計画や来館者調査、人材採用などの準備を進め、その後に本格的な資金申請を行う仕組みです。こうした段階的な資金戦略は、中規模館がリスクを分散しつつ大規模な展示刷新に挑戦する際の有効なモデルといえます(The Times, 2025)。
本記事では、この「Transformation 2029」を単なる施設改修の枠を超えた経営戦略として位置づけ、博物館経営論の観点からその意義を考察します。特に、①資金調達とリスクマネジメント、②来館者戦略と常設展示の柔軟化、③ブランド戦略と二軸アプローチ、④サステナビリティと社会的責任という4つの視点から整理することで、現代の博物館が直面する課題と可能性を明らかにしていきたいと思います。
「Transformation 2029」とは何か
ロンドンのデザイン・ミュージアムが進める「Transformation 2029」は、同館の常設展示「Designer, Maker, User」を全面的に刷新する大規模プロジェクトです。この常設展示は2016年のケンジントン移転時に新設され、デザインの歴史や製作プロセス、利用者の体験を多角的に紹介してきました。しかし、一般的に5〜7年が寿命とされる常設展示を10年近く維持してきたため、展示手法や内容が来館者の期待や時代の変化に十分に対応できなくなりつつあります。こうした状況を踏まえ、2029年の創立40周年を節目として、展示空間のあり方そのものを再定義する計画が打ち出されました(IanVisits, 2025)。
計画の規模は約£2.7百万に達すると見込まれ、資金調達には英国のナショナル・ロッタリー・ヘリテージ・ファンドの二段階助成制度が活用されます。まずは約£267,000の開発フェーズ助成を受け、来館者調査や関係者との協議、保存修復計画、展示解説の再設計、人材採用といった準備が進められます。その成果を踏まえた上で、実施フェーズに移行し、大規模な資金を申請して改修工事を行う流れです(The Sun, 2025)。この二段階方式は、中規模館にとって大規模プロジェクトに伴うリスクを分散させ、資金獲得の確実性を高める有効な手法といえます。
さらに、この計画は単なる展示更新にとどまらず、明確な数値目標を掲げている点に特徴があります。デザイン・ミュージアムは2029年までに年間80万人の来館者を達成し、オンラインを含めて1000万人の観客にリーチすることを目指しています。特に無料で公開される常設展示の刷新によって、多様な層の来館を促し、社会に対してより広い公共的役割を果たそうとしています(Timeout, 2025)。
展示内容の方向性としては、従来の静的な展示を補完する形で、インタラクティブな技術やデジタル要素を積極的に取り入れる予定です。来館者がデザインを「見る」だけでなく「体験し、参加できる」空間を構築することで、従来の博物館体験を拡張します。また、省エネルギー設計やコレクションの保存修復を進めるとともに、アクセシビリティに配慮したインクルーシブな展示空間を目指している点も注目されます(Luxurious Magazine, 2025)。
資金調達とリスクマネジメント
「Transformation 2029」における最大の特徴の一つは、資金調達の仕組みそのものにあります。ロンドンのデザイン・ミュージアムは、英国のナショナル・ロッタリー・ヘリテージ・ファンドによる二段階助成制度を活用し、段階的にプロジェクトを進めています。まず「開発フェーズ」と呼ばれる準備段階で約£267,000の助成を受け、展示計画や来館者調査、関係者協議、人材採用、保存修復などを進めます。その成果をもとに「実施フェーズ」へと進み、約£2.7mの本格的な助成を申請し、大規模な改修に着手するという流れです(The Sun, 2025)。
この二段階方式は、単に資金を得る手段であるだけでなく、リスクを分散する重要な仕組みとして機能しています。いきなり巨額の助成を申請するのではなく、小規模な支援を得て企画内容を検証・改善した上で次のステップに進むことで、失敗による損失を最小限に抑えることができます。また、この方式は館内外のステークホルダーにとっても安心材料となり、資金提供者との信頼関係を強化する契機にもなります(IanVisits, 2025)。
さらに、中規模館であるデザイン・ミュージアムにとって、財源の多角化は不可欠です。公的助成だけではなく、寄付やスポンサーシップといった民間資金の導入を組み合わせることで、持続可能性を高めることが求められています。特にデザイン分野は企業との親和性が高く、ブランドとの協働は資金調達と広報効果を両立する手段となり得ます。こうした取り組みは、博物館の経営基盤を安定させるうえで、ますます重要になっていくでしょう(The Times, 2025)。
また、資金調達の戦略はリスクマネジメントと直結しています。長期にわたる改修プロジェクトは、経済環境の変動や来館者数の不確実性など多様なリスクを伴います。二段階助成制度を活用することで、もし計画が想定通りに進まない場合でも、初期投資の規模を抑えているため、損害を限定的にすることができます。これは特に財政基盤の脆弱な中規模館にとって現実的で合理的な手法といえます。
このように、資金調達は単なるお金の確保ではなく、経営の持続可能性を確保し、プロジェクトリスクを制御するための戦略的要素です。デザイン・ミュージアムの事例は、中規模館が大規模改修に挑む際に参考となる「リスク分散型資金調達モデル」を提示しており、博物館経営論的に非常に重要な示唆を含んでいるといえるでしょう。
来館者戦略と常設展示の柔軟化
「Transformation 2029」におけるもう一つの大きな柱は、来館者戦略と常設展示の柔軟化です。従来、博物館の常設展示は数年から十数年単位で内容が固定されることが一般的でした。しかしデザインの世界は変化のスピードが極めて速く、来館者が新鮮さを感じられる期間は短縮しつつあります。デザイン・ミュージアムはこの点に着目し、常設を「固定された展示空間」から「頻繁に更新可能な柔軟展示空間」へと再定義しようとしています。つまり「柔軟性」そのものを経営資源と位置づけ、持続的な来館者誘致につなげる戦略です(IanVisits, 2025)。
来館者体験の刷新も重視されています。これまでの展示は主に「見る」ことが中心でしたが、今後はデジタル技術やインタラクティブ要素を積極的に導入し、「体験する」「参加する」方向へとシフトしていきます。例えば、タッチスクリーンを使ったデザインの操作体験や、拡張現実を用いた展示品の利用シーンの再現、触覚模型や音声解説を通じたインクルーシブな展示手法などが想定されます。こうした仕組みによって、若年層や国際観光客、家族連れといった多様な層が博物館を自分ごととして捉えやすくなり、結果として来館者層の拡大につながるのです(The Times, 2025)。
さらに、この計画は具体的な数値目標を掲げています。2029年までに年間来館者80万人、オンラインを含む総リーチ1000万人を目指すとされており、これは単なる展示改修にとどまらない広報・教育戦略の一環です。特に無料で公開される常設展示の刷新は「誰もがアクセスできる博物館」という社会的使命を強調するものであり、教育や社会的包摂の観点からも大きな意味を持ちます(Timeout, 2025)。
このような柔軟展示モデルは、ヨーロッパの他館にも見られる潮流です。たとえばアムステルダムのNEMO科学館やコペンハーゲンのデザインミュージアムでは、テーマや展示物を定期的に更新し、常に新しい知識や体験を提供する試みが行われています。デザイン・ミュージアムの取り組みはこれらと共通する要素を持ちながらも、規模や来館者目標を明示する点で、より戦略的かつ経営論的な性格を強めているといえるでしょう。
つまり「Transformation 2029」における来館者戦略とは、展示更新の柔軟性を経営の根幹に据え、体験型の参加を促進し、社会的使命を拡張する総合的な試みです。これによりデザイン・ミュージアムは、単なる展示刷新を超えて「来館者とともに成長する博物館」という新しいモデルを提示しているのです。
ブランド戦略と展示の二軸アプローチ
デザイン・ミュージアムが「Transformation 2029」を通じて打ち出そうとしているもう一つの重要な側面は、ブランド戦略としての展示方針です。同館の館長ティム・モーロウ氏は、就任以来「専門性を重視したハードコアなデザイン展示」と「大衆文化を切り口とする親しみやすい展示」という二軸を並行させる方針を明確にしています(The Times, 2025)。この二軸戦略は、単に展示の幅を広げるだけでなく、博物館のブランド価値を強化するための経営的判断といえます。
まず、デザイン・ミュージアムの強みである「ハードコア・デザイン」展示は、学術性と専門性の高さによって支えられています。デザインの歴史的資料や先端的なプロジェクトを扱う展示は、研究者やデザイン業界関係者にとって重要なリソースとなり、同館の権威性を確立する基盤です。この専門性こそが、デザイン・ミュージアムが国際的な文化機関として信頼される理由の一つです(IanVisits, 2025)。
一方で、来館者層の裾野を広げるためには、一般の人々にとって親しみやすい展示も欠かせません。実際に同館は「バービー展」や「ティム・バートン展」、「フットボールとデザイン」に関する企画など、ポピュラーカルチャーを切り口にした展示を数多く実施してきました。これらは話題性が高く、SNSなどを通じて若者や観光客を惹きつける効果を発揮しています(Timeout, 2025)。こうした大衆性のある企画は、初めてデザイン・ミュージアムを訪れる人々にとっての入口となり、来館のハードルを下げる役割を果たしています。
重要なのは、この二軸が単に並立しているのではなく、来館者導線を設計する中で統合されている点です。大衆文化を題材にした特別展で来館者を引き込み、その後に常設展示や専門的な企画へと誘導することで、「楽しく親しみやすい体験」と「深く学べる体験」の双方を提供できる仕組みが整えられています。この流れによって、一度限りの来館ではなく、学びや発見を伴う継続的な関係構築が可能になります(The Sun, 2025)。
こうした二軸戦略は、他の欧州の博物館との差別化にもつながります。多くの館が専門性か大衆性のいずれかに偏りがちな中で、デザイン・ミュージアムは両者を同時に追求することで、独自のブランドアイデンティティを築き上げています。その結果、同館は「専門的でありながら親しみやすい」という独特の立ち位置を確立し、国際的にも注目される存在となっているのです。
このように、デザイン・ミュージアムのブランド戦略は、展示方針そのものと密接に結びついています。「ハードコア・デザイン」と「大衆文化展示」という二軸を両立させることで、同館は専門性と公共性を同時に維持し、博物館経営におけるブランド価値の最大化を実現しているのです。
サステナビリティと社会的責任
「Transformation 2029」において、デザイン・ミュージアムが重視しているもう一つの側面は、サステナビリティと社会的責任です。単なる展示の刷新ではなく、環境配慮や社会的包摂を経営戦略に組み込むことで、博物館が持つ公共的使命を強化しようとしています。これは現代の博物館が直面する課題に対して明確な方向性を示すものでもあります。
第一に、計画の中心には「グリーン・トランジション」が据えられています。展示空間の刷新と同時に、省エネルギー型の照明や空調システムの導入、環境負荷を抑えた展示設備の採用が検討されています。これにより、博物館運営に伴う環境コストを削減し、国際的に求められる持続可能性の基準に適合することを目指しています(IanVisits, 2025)。文化施設が自らの運営を通じて環境問題に貢献する姿勢は、来館者に対しても強いメッセージを発することになります。
第二に、コレクションの保存修復と持続可能な活用が重要な課題として組み込まれています。デザイン・ミュージアムは展示刷新の機会を活かし、長期的な保存と公開を両立させる方針を打ち出しています。これは単なる「展示替え」にとどまらず、収蔵品を次世代に引き継ぐための投資でもあります。保存修復に資金と人材を充てることは、短期的にはコストですが、長期的には博物館の信頼性を担保する経営上の基盤となるのです(The Sun, 2025)。
第三に、アクセシビリティとインクルーシブ・デザインの強化も計画に盛り込まれています。触覚資料や音声ガイド、バリアフリー設計など、多様な来館者が展示を等しく享受できる環境を整備することが重視されています。これは障害の有無や文化的背景にかかわらず誰もが利用できる博物館を目指すものであり、社会的包摂を推進する姿勢の表れです(Timeout, 2025)。
最後に、社会的責任を果たす博物館経営という観点から、無料の常設展示を継続する点も注目されます。無料公開は公共性を確保するための重要な方策であり、公的助成を受ける機関としての説明責任や透明性とも結びついています。デザイン・ミュージアムは、資金提供者や来館者に対して開かれた存在であり続けることで、信頼を経営基盤として強化しようとしているのです(The Times, 2025)。
このように「Transformation 2029」は、環境・保存・アクセシビリティ・公共性という複数の要素を経営戦略に組み込み、サステナビリティと社会的責任を体現するプロジェクトとなっています。それは単なる展示刷新ではなく、博物館経営の新たなモデルを示す取り組みだといえるでしょう。
博物館経営論的に見た意義
「Transformation 2029」を博物館経営論の観点から捉えると、いくつかの重要な示唆が浮かび上がります。第一に注目すべきは、段階的資金調達によるリスク回避のモデルです。デザイン・ミュージアムはナショナル・ロッタリー・ヘリテージ・ファンドの二段階助成制度を活用し、まずは小規模な開発フェーズで計画を練り、その成果をもって大規模な実施フェーズに挑む手法を採用しました。この方式は、大規模改修に挑む中規模館にとって現実的かつ持続可能性の高い経営戦略といえます。巨額投資を一度に背負うリスクを避け、柔軟に計画を調整できる仕組みは、他館にとっても参考となるでしょう(The Sun, 2025)。
第二に、柔軟性を持つ常設展示という新しいモデルを提示している点が挙げられます。従来の常設展示は長期間にわたって固定されるのが一般的でしたが、デザイン・ミュージアムは短いサイクルで更新可能な展示空間を構築することで、来館者に常に新鮮な体験を提供しようとしています。この発想は、リピート来館を促す仕組みとして経営的に有効であり、急速に変化するデザイン分野において適応力を高める戦略でもあります(IanVisits, 2025)。
第三に、ブランド戦略と公共性を両立させる取り組みが注目されます。同館は「ハードコア・デザイン」展示によって専門性を維持しつつ、「バービー展」や「ティム・バートン展」といった大衆文化展示を取り入れる二軸戦略を展開してきました。この両立は専門性・公共性・話題性を統合した独自のブランド構築を可能にし、他の文化施設との差別化を実現しています。特に、特別展で新規来館者を引き込み、その後常設展示へと誘導する導線設計は、集客と学習体験を効果的に結びつける仕組みといえるでしょう(The Times, 2025)。
第四に、サステナビリティと社会的責任を経営に統合している点です。省エネルギー設計や保存修復、アクセシビリティ強化などを同時に進めることによって、博物館運営の持続可能性と公共的正当性を担保しています。特に無料常設展示を継続することは、社会的信頼を基盤とした経営を体現しており、公的支援を受ける機関としての説明責任を果たす姿勢を示しています(Timeout, 2025)。
総合的にみると、「Transformation 2029」は単なる展示改修ではなく、経営戦略の総合的な実践例として位置づけられます。資金調達、柔軟性、ブランド、サステナビリティという複数の要素を三位一体で追求することにより、デザイン・ミュージアムは中規模館における新たな経営モデルを提示しています。その意義は同館にとどまらず、国際的な博物館経営の実践においても広く応用可能な普遍性を備えているのです。
まとめ
本記事では、ロンドンのデザイン・ミュージアムが進める「Transformation 2029」計画について、博物館経営論の視点からその意義を検討してきました。このプロジェクトは、単なる常設展示の更新にとどまらず、資金調達、来館者戦略、ブランド構築、サステナビリティという複数の要素を一体化した経営戦略の総合的実践例として位置づけられます。
まず資金調達においては、ナショナル・ロッタリー・ヘリテージ・ファンドの二段階助成制度を活用し、開発フェーズと実施フェーズを分けることでリスクを分散させています。この方式は、中規模館が大規模改修に挑む際に有効なモデルとなり、財政的持続可能性を高める工夫として評価できます(The Sun, 2025)。
次に、来館者戦略と常設展示の柔軟化は、従来の「固定展示」から「更新可能な展示」へと常設の概念を転換する試みです。インタラクティブな技術や体験型要素を導入することで、若者や国際観光客を含む多様な来館者層を惹きつけ、リピート来館を促す仕組みを構築しています(IanVisits, 2025)。こうした柔軟性は、変化の激しいデザイン分野において館の存在意義を維持するために不可欠です。
さらに、ブランド戦略においては「ハードコア・デザイン展示」と「大衆文化展示」を二軸として展開することで、専門性と公共性を両立させています。大衆性の高い特別展から常設展示へと来館者を誘導する流れは、話題性と学術性を橋渡しする経営的仕組みといえます(The Times, 2025)。
加えて、サステナビリティと社会的責任を組み込む姿勢も重要です。省エネルギー設計や保存修復、アクセシビリティの確保といった取り組みは、博物館の公共性を高めるとともに、社会的信頼を基盤とした経営のあり方を体現しています(Timeout, 2025)。無料常設展示を維持する方針も、公共文化機関としての責務を明確に示しています。
総じて、「Transformation 2029」は、デザイン・ミュージアムが直面する課題に応えるだけでなく、国際的な博物館経営に普遍的な示唆を与える事例です。資金調達の工夫、柔軟な展示運営、二軸的なブランド戦略、そしてサステナビリティの統合によって、中規模館でも持続可能で公共的な経営モデルを構築できることを示しています。それは、現代の博物館が社会の中でどのように存在価値を高めていくかを具体的に示す先進的な実践例であるといえるでしょう。
参考文献
- IanVisits. (2025). Design Museum to overhaul its galleries ahead of its 40th anniversary. IanVisits. https://www.ianvisits.co.uk/articles/design-museum-to-overhaul-its-galleries-ahead-of-its-40th-anniversary-83747/
- Luxurious Magazine. (2025). Design Museum announces plans to overhaul its permanent galleries. Luxurious Magazine. https://www.luxuriousmagazine.com/design-museum-permanent-gallery-overhaul/
- The Sun. (2025). Major UK museum named one of the best in Europe to get huge £2.7million expansion. The Sun. https://www.thesun.co.uk/travel/36580903/museum-best-europe-2-m-expansion/
- The Times. (2025). Design Museum chief: ‘Some people call me the Barbie guy’. The Times. https://www.thetimes.co.uk/article/design-museum-chief-tim-marlow-interview-7d8dl7lp3
- Time Out. (2025). The Design Museum is getting a multimillion-pound makeover of its permanent galleries. Time Out London. https://www.timeout.com/london/news/the-design-museum-is-getting-a-massive-multimillion-pound-makeover-of-its-permanent-galleries-090325