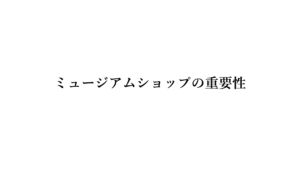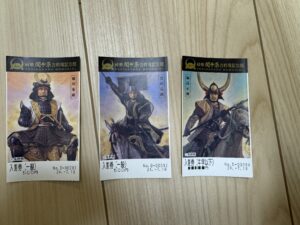博物館ミッションを学ぶ意義 ― 記事の導入
博物館の運営を考えるとき、最も基本的でありながら見過ごされがちな概念が「ミッション」です。一般的に「ミッション」という言葉は、企業の経営理念や大学の建学精神、あるいは学校の教育目標などでも使われ、組織の方向性を示す大切なものとして理解されています。博物館においても同様に、ミッションは単なるスローガンや装飾的な言葉ではなく、館の存在意義を定義し、あらゆる活動を方向づける基盤となります。
博物館のミッションが重要である理由は大きく二つに分けて説明できます。第一に、館の内部において活動の指針や組織の結束をもたらす「内側の役割」です。展示や教育普及活動、研究の企画などを決める際に「この館の存在理由に合致しているか」という問いを投げかける基準となります。職員やボランティアにとっては、自分たちの働きがどのように組織全体に貢献しているのかを理解する拠り所となり、モチベーションや誇りを支える要素にもなります(Lord & Lord, 2009)。
第二に、館の外部に向けた「外側の役割」があります。博物館は公的資金や寄付に支えられる公共的な存在であるため、社会に対してどのような価値を提供するのかを明確に示すことが不可欠です。来館者に対して「この博物館に来ればどのような体験や学びが得られるのか」を約束し、さらに地域社会や国際的なネットワークにおいて「私たちは何を担うのか」を表明することが求められます。これによって博物館は社会的な正当性を獲得し、信頼と支援を得ることができます(Půček, Ochrana, & Plaček, 2021)。
このように、博物館のミッションは内部と外部の双方に機能し、館の存続と発展にとって欠かせない存在です。単に「理念を掲げる」ことにとどまらず、日々の意思決定から長期的な経営戦略に至るまで、あらゆる段階でミッションが具体的に活用されます。本記事では、まずミッションの意味と役割を内側と外側の視点から整理し、続いてニューヨーク近代美術館(MoMA)とアムステルダムのファン・ゴッホ美術館という二つの事例を取り上げ、実際にミッションがどのように体現されているのかを考えていきます。
博物館のミッションとは
博物館のミッションとは、組織が「なぜ存在するのか」を明示し、そのすべての活動を統合・方向づける中心的な理念です。言い換えれば「この博物館はなぜ存在するのか」「社会に対してどのような価値を提供するのか」という根源的な問いに答えるものであり、経営戦略や日々の活動を支える憲法のような役割を果たします(Lord & Lord, 2009)。
ミッションはしばしば「ビジョン」や「スローガン」と混同されますが、これらは性格が異なります。スローガンは外部へのアピールに用いられる簡潔な標語であり、必ずしも活動の指針にはなりません。ビジョンは「将来どのような姿を目指すか」という未来志向を示すものです。これに対してミッションは「現在、この博物館が存在する理由」に焦点を当てており、抽象的でありながら活動全般を具体的に方向づける力を持ちます。
文献においても、ミッションは異なる観点から捉えられています。ある文献では、ミッションはすべての意思決定を方向づけ、組織に一貫性を与える存在とされており、展示、教育、研究、収蔵といった活動が最終的にミッションに沿っているかどうかで評価されるべきだと述べられています(Lord & Lord, 2009)。一方で別の文献では、ミッションを「社会的使命」として理解し、博物館が公共的責任を担う存在であることを強調しています。この立場では、ミッションは館内の指針にとどまらず、社会に対してどのような文化的・教育的価値を提供するかを明示する役割を持ちます(Půček, Ochrana, & Plaček, 2021)。
さらに、国際的な定義においてもミッション的要素は強調されています。ICOM(国際博物館会議)は 2022 年に新しい定義を採択し、博物館を「非営利で恒久的な機関」であると同時に、社会のために奉仕し、有形・無形の遺産を研究・収集・保存・解釈・展示する存在と規定しました。そのうえで、「公開性」「アクセス可能性」「包摂性」「多様性」「持続可能性」を重視し、地域社会の参加と協働、倫理的かつ専門的な運営を通じて、教育、楽しみ、省察、知識共有のための多様な体験を提供することが求められています(ICOM, 2022)。
この定義の更新により、博物館のミッションは従来の「収集・保存・研究・展示・教育」という基本的役割にとどまらず、より広い社会的責任へと拡張されました。包摂性や持続可能性、地域社会との協働といった要素は、博物館が単に文化財を扱う機関ではなく、現代社会の課題に積極的に応答する文化的インフラであることを示しています。
このように、博物館のミッションには「内側」と「外側」の両方の意味があります。内側では組織の存在理由を確認し、職員やボランティアをまとめ、一貫性を持った活動を支える基盤となります。外側では、社会に対して博物館の価値や責任を宣言し、公共的資源としての正当性や信頼を獲得する役割を果たします。現代においては、ミッションの定義そのものが進化し、社会的文脈と不可分に語られるようになっているのです。
この議論については、本ブログの別記事「博物館の使命とは何か ― 社会的責任と未来への貢献を考える」でも紹介しています。現代的な観点から博物館の使命を再検討する議論については、そちらも併せて参照すると理解が深まるでしょう。

以上のように、博物館のミッションは、内部と外部の両面に働きかける多層的な概念であり、今日の博物館経営において欠かせない存在です。次節では、この「内側」と「外側」の役割をそれぞれ整理し、具体的にどのように実務と結びつくのかを見ていきます。
ミッションの内側の役割 ― 組織の基盤としての意味
博物館のミッションは、外部に向けて社会的責任を表明するだけでなく、内部における組織運営の基盤としても重要な役割を果たします。ここでは「方針決定の基盤」「職員・ボランティアの結束」「継続性と一貫性の担保」という三つの観点から整理します。
方針決定の基盤
ミッションは、博物館の日々の意思決定において拠り所となる存在です。展示のテーマや収蔵方針、教育普及活動の方向性を決定する際に「この企画は館の存在理由に合致しているか」という問いを投げかける基準となります。例えば、ある歴史博物館が「地域の歴史を未来に伝える」ことをミッションに掲げている場合、現代芸術の展示企画を採用するかどうかは、その内容が地域史との関連を持つかによって判断されます。このように、ミッションは活動全体の方向性を規定する指針として位置づけられています(Lord & Lord, 2009)。
職員・ボランティアの結束
博物館は学芸員や教育普及担当、管理部門の職員、さらにはボランティアなど、多様な人々によって運営されています。こうした立場の異なる人々を共通の目的で結びつけるのがミッションです。館で働く人々にとって「自分たちはなぜここで活動しているのか」を理解することは、モチベーションや誇りを支える源となります。採用面接や研修において「館のミッションに共感できるかどうか」が重視されるのもこのためです。文献でも、ミッションは組織文化を形成し、一体性を生み出す重要な要素であると指摘されています(Půček, Ochrana, & Plaček, 2021)。
継続性と一貫性の担保
博物館は長期的な視点で活動を続ける機関であるため、館長の交代や予算環境の変化などがあっても、活動の軸が大きく揺らいではなりません。そのために機能するのがミッションです。収蔵計画や教育プログラムが長期にわたって継続できるのは、個々の担当者や時代の変化を超えて「この館はなぜ存在するのか」という根本的な理由が一貫しているからです。ミッションは組織に持続性を与え、代替わりや環境変化を超えて館を安定的に導く役割を果たします(Lord & Lord, 2009)。
まとめ
このように、博物館の内側におけるミッションは「方針決定の基盤」「職員・ボランティアの結束」「継続性と一貫性の担保」という三つの観点から組織を支えています。内部において強固な基盤を築くことによって、博物館は日常的な活動を安定的に進めることができるのです。次節では、この内側の役割と対をなす「外側」、すなわち社会に向けた役割について見ていきます。
ミッションの外側の役割 ― 社会的責任としての意味
博物館のミッションは館内をまとめる基盤であると同時に、社会に対してその存在理由を伝える「約束」としての意味を持っています。ここでは「社会的正当性の獲得」「来館者への信頼の提示」「公共性と協働の強化」という三つの観点から整理します。
社会的正当性の獲得
博物館は多くの場合、公的資金や寄付金によって運営されています。そのため「なぜこの館が存在し、社会にどのような価値をもたらしているのか」を明確に説明できることが不可欠です。ミッションは、資金提供者や行政機関に対して活動の正当性を示す根拠となり、持続的な支援を受けるための土台となります。特に今日では、包摂性や持続可能性など社会的課題に応答することが求められており、ミッションを通じて社会への責任を明示することが重要になっています(ICOM, 2022)。
来館者への信頼の提示
来館者にとっても、ミッションは「この博物館でどのような学びや体験が得られるのか」を理解する手がかりになります。例えば「地域文化の継承」を掲げる博物館であれば、訪れる人々は地域史や生活文化を学べることを期待できます。このようにミッションは、来館者が館の活動に安心して参加し、信頼関係を築くための指針として機能します。さらにミッションが一貫して示されていれば、展示や教育活動に対する評価や満足度も高まります(Půček, Ochrana, & Plaček, 2021)。
公共性と協働の強化
博物館は公共的な資源として地域社会や国際社会に貢献する存在です。ミッションはその公共性を表明する手段であり、地域の学校や市民団体、企業などと協働する際にも活動の共通基盤となります。たとえば「環境教育の推進」を掲げる博物館は、地域の環境団体や学校と協働し、展示やワークショップを展開することで社会的役割を果たすことができます。こうした外部連携においても、ミッションが共有されているからこそ協働が円滑に進むのです(Lord & Lord, 2009)。
まとめ
このように、博物館の外側におけるミッションは「社会的正当性の獲得」「来館者への信頼の提示」「公共性と協働の強化」という三つの側面で大きな役割を担っています。館内に向けた基盤としての意味と並んで、社会に対して存在理由を示し、公共性を高める力を持つことが、ミッションの外側の意義なのです。次節では、これらの理論的整理を踏まえ、MoMA と Van Gogh Museum の事例を通じて、実際にミッションがどのように具体化されているのかを検討します。
事例1:MoMA(ニューヨーク近代美術館)のミッションと実験性
MoMA の公式ミッションは以下のように明記されています。
“The Museum of Modern Art connects people from around the world to the art of our time. We aspire to be a catalyst for experimentation, learning, and creativity, a gathering place for all, and a home for artists and their ideas.” (MoMA, n.d.)
この文章に込められた理念は、「つなぐ」「触媒となる」「開かれた場」「芸術家の拠点」という四つの要素に整理できます。以下では、それぞれがどのように MoMA の活動に具体化されているかを見ていきます。
人々を現代芸術とつなぐ
最初のフレーズ “connects people from around the world to the art of our time” は、MoMA が「現代芸術と人々を橋渡しする機関」であることを強調しています。実際、MoMA の展示はモネやピカソといった巨匠の作品を収蔵しながら、同時に現代アーティストの新作を積極的に取り上げています。その結果、来館者は「過去と現在」を同時に体験でき、現代芸術を歴史的な文脈の中で理解する機会を得られるのです。さらに、オンラインプラットフォームを通じて世界中の人々がアーカイブや解説を閲覧できる環境を整備しており、物理的な制約を超えて「つながる」試みが行われています。
実験・学び・創造の触媒となる
続く “a catalyst for experimentation, learning, and creativity” という表現は、MoMA が持つ革新的な企画の根幹を示しています。その象徴が 1971 年から続く Projects シリーズです。これは新進アーティストの作品や前衛的な表現を紹介するための展示枠であり、伝統的な展示方法では扱いにくい挑戦的な試みを受け止める実験場として機能しています(MoMA, n.d.)。
さらに、教育部門とアーティストが協働する Artists Experiment プログラムでは、来館者が受動的に鑑賞するのではなく、主体的に関与できる仕組みを設計しています(MoMA, n.d.)。例えば、展示を見た後に自らの解釈を共有するワークショップや、作品からインスピレーションを得て創作する活動が行われており、「学び」と「創造」の両方を刺激する体験が提供されています。
すべての人に開かれた集いの場
“a gathering place for all” という理念は、包摂性やアクセス性に直結します。MoMA は、入館料割引制度やオンライン無料公開日を設け、幅広い層が芸術にアクセスできる仕組みを導入しています。また、展示や教育プログラムには多文化的な視点を積極的に取り入れており、多様な背景を持つ来館者にとって「ここは私を歓迎している場だ」と感じられる環境を整えています。これは ICOM が 2022 年に採択した「包摂性・多様性・持続可能性」を重視する新定義とも共鳴しています(ICOM, 2022)。
芸術家とそのアイデアの拠点
最後の “a home for artists and their ideas” は、MoMA が単なる展示機関ではなく、芸術家の活動を支える場であることを示しています。保存修復部門では、ジャクソン・ポロックの大作やナム・ジュン・パイクのメディアアートの保存において科学的分析やデジタル技術を駆使し、作品とアイデアを未来へつなぐ試みを続けています(MoMA, n.d.)。また、デザイン展では iPod や Post-it といった日常品を取り上げ、芸術家やデザイナーのアイデアが社会に浸透する過程を示しています(MoMA, 2025)。
まとめ
MoMA のミッション全文は、抽象的な理念の羅列ではなく、展示・教育・保存・社会的活動のすべてに反映されています。Projects シリーズや Artists Experiment による実験的取り組み、保存修復の先端的挑戦、デザイン展を通じた生活との接続など、いずれも「つなぐ」「触媒となる」「開かれた場」「拠点」といった言葉が具体化されたものです。MoMA の事例は、ミッションを掲げること自体が目的ではなく、その理念を実際の活動に落とし込むことの重要性を示しています。
事例2:Van Gogh Museum(ゴッホ美術館)のミッションとインスピレーション
アムステルダムに所在する Van Gogh Museum は、フィンセント・ファン・ゴッホの作品とその時代を専門的に扱う世界的拠点です。その公式ミッションは次のように明記されています。
“The Van Gogh Museum inspires a diverse audience with the life and work of Vincent van Gogh and his time.” (Van Gogh Museum, n.d.)
このシンプルな宣言には、「多様な観客」「インスピレーション」「人生と作品」「同時代」という四つの核心要素が込められています。以下では、それぞれの要素が館の取り組みにどう反映されているのかを整理します。
多様な観客
“a diverse audience” という言葉は、Van Gogh Museum の運営姿勢の根幹を示しています。年間 200 万人を超える来館者の約 85% が海外からの観光客であることからも分かるように、同館は極めて国際的な観客層を対象としています。そのため展示解説はオランダ語や英語だけでなく複数言語に対応し、オンラインでも多言語コンテンツを充実させています。さらに、子ども向けワークショップやアクセシビリティ対応プログラムを導入し、視覚障害や聴覚障害を持つ人々を含めた「多様な観客」を迎え入れる努力が続けられています。
インスピレーションを与える
次のキーワード “inspires” は、Van Gogh Museum が来館者に単なる知識伝達を超えた体験を提供することを示しています。特別展や常設展示では、ゴッホの絵画の技巧や色彩を紹介するだけでなく、彼の芸術が持つ感情的・精神的な力を体験できるよう工夫されています。
たとえば、ゴッホの手紙を展示に組み込み、彼の芸術への情熱や人生の苦悩を来館者に直接伝える演出は、その人物像をより生き生きと感じさせるものです。また、近年ではデジタル技術を用いた没入型展示を取り入れ、来館者がゴッホの世界に「入り込む」体験を通じてインスピレーションを得られる仕掛けを行っています(Van Gogh Museum, n.d.)。
人生と作品
ミッションに明記されている “the life and work of Vincent van Gogh” は、単にゴッホの作品を展示すること以上の意味を持ちます。館では、油彩画や素描に加え、ゴッホの手紙や関連資料を通じて、芸術家の人間的側面や生活環境に焦点を当てています。これにより来館者は「作品」だけでなく「人生」を通してゴッホを理解できるのです。
また、研究部門はゴッホ作品の真正性の検証や制作技法の科学的分析に取り組み、成果を展覧会や出版物で発信しています。こうした学術的研究は「作品の深い理解」を可能にすると同時に、教育的資源として来館者の学びを支えています。
同時代
最後の “and his time” という言葉は、ゴッホの同時代の芸術家や社会状況に光を当てる姿勢を示しています。美術館はゴッホを孤立した天才としてではなく、19世紀末の芸術的潮流の中で位置づけることを重視しています。特別展では、ゴッホとゴーギャン、印象派やポスト印象派との関わりが繰り返し取り上げられ、ゴッホの作品を広い歴史的文脈に結びつけています。
こうした展示は、来館者に「ゴッホの芸術はどのように形成され、どのように次世代に影響を与えたのか」という問いを考えさせ、彼の芸術をより深く理解する契機を提供しています。
まとめ
Van Gogh Museum のミッション全文は、その運営方針を簡潔に表現しながら、活動全体に一貫性を与えています。
- 「多様な観客」:多言語対応やアクセシビリティを通じて、誰もが楽しめる環境を整備
- 「インスピレーション」:感情的・没入的な体験を提供し、来館者に創造的刺激を与える
- 「人生と作品」:作品だけでなく芸術家の生涯を含めた総合的理解を推進
- 「同時代」:歴史的・社会的文脈を重視し、芸術史全体の中での位置づけを強調
このように、Van Gogh Museum はシンプルな言葉で定義されたミッションを、教育普及、研究、展示、国際的発信といった多面的活動に具体化しています。結果として、ミッションは来館者にとっての「インスピレーションの源泉」となり、館の社会的役割を強固にする基盤となっています。
MoMA と Van Gogh Museum に見るミッションの実践 ― 比較と考察
これまで取り上げてきた MoMA(ニューヨーク近代美術館)と Van Gogh Museum(ゴッホ美術館)の事例は、それぞれの歴史や立地、対象とするコレクションの性格の違いを反映しながら、ミッションを具体的な活動に結びつけている点で共通しています。本節では、両者を比較することで、ミッションの多様性と共通性を考察していきます。
ミッションの方向性の違い
MoMA のミッションは「実験・学び・創造」を触媒とし、「世界中の人々を現代芸術とつなぐ」という未来志向のビジョンを掲げています。これは、常に新しい芸術表現を紹介し、来館者が未知の体験を通じて思考や感覚を広げることを目指すものです。一方、Van Gogh Museum のミッションは「フィンセント・ファン・ゴッホの人生と作品、そして彼の時代を通して多様な観客にインスピレーションを与える」とされています。こちらは、特定の芸術家を深く掘り下げ、その生涯と作品に普遍的な人間経験を見出すアプローチです。方向性は異なりますが、どちらも「芸術を通じて人々に新しい価値を提供する」という根幹では一致しています。
内側への反映の仕方
ミッションが館の内部にどのように作用しているかを見ると、MoMA では「実験性」が組織文化に強く根づいています。キュレーターは新しい表現や挑戦的な展示を企画することを奨励され、Projects シリーズや Artists Experiment に見られるように、職員自身がリスクを取りながら創造に挑む風土が醸成されています。
これに対して Van Gogh Museum では、研究部門がミッションを支える中心的役割を果たしています。作品の真正性検証や制作技法の科学的分析など、ゴッホの生涯と作品を多角的に探究する活動は、学芸員の専門性を発揮する場であると同時に、館全体が「インスピレーションを与える」という使命を担保するための基盤となっています。両者は異なる方法をとりながらも、ミッションを館内運営の柱に据えている点で共通しています。
外側への発信の仕方
外側に向けた発信では、両館の違いがより鮮明に表れます。MoMA は現代芸術を国際的に紹介する場として、包摂性や多様性を重視したプログラムを展開しています。来館者参加型の教育活動やデザイン展は、芸術を社会にひらく取り組みであり、世界規模の「集いの場」としての役割を果たしています。
一方、Van Gogh Museum は「ゴッホ」という固有の人物を切り口に普遍的なテーマを伝えています。ゴッホの手紙や同時代の作品を通して「芸術家の人生」と「人間としての苦悩や喜び」を浮かび上がらせ、多言語解説や没入型展示によって世界中の観光客や家族層を惹きつけています。両館ともにミッションを外向きに表現していますが、MoMA が「新しい芸術体験を提供する」ことを重視するのに対し、Van Gogh Museum は「芸術を通じて心を動かす」ことに焦点を置いている点が対照的です。
共通する本質
両館の比較から浮かび上がるのは、ミッションが単なる理念ではなく「実際の活動に具体化されている」という事実です。MoMA は挑戦的な展示や教育プログラムを通じて、Van Gogh Museum は芸術家の人生を深く掘り下げた展示や研究を通じて、それぞれのミッションを体現しています。
共通しているのは、ミッションが「内側」と「外側」をつなぐ架け橋であるという点です。内側では職員や研究者が行動の指針として参照し、外側では来館者や社会に対する約束として作用します。ミッションが言葉として存在するだけでなく、実務や体験の中で息づいているからこそ、両館は国際的な信頼と影響力を維持できているのです。
まとめ
MoMA と Van Gogh Museum の比較は、博物館のミッションが多様な形で表現され得る一方、その本質は共通していることを示しています。それは「社会に価値を提供する存在理由を明確にし、活動に一貫性を与える」ということです。経営環境や対象とするコレクションが異なっても、ミッションを実際の活動に落とし込むことで、博物館は公共性を強化し、社会からの信頼を得ることができます。
まとめ ― 博物館経営におけるミッションの意義
ここまで、博物館のミッションの定義、内側と外側の役割、さらに MoMA と Van Gogh Museum の事例を見てきました。最後に、それらを統合し、博物館経営においてミッションがどのような意義を持つのかを整理します。
内側の意義 ― 組織を支える基盤
博物館のミッションは、館の内側において組織の安定を支える役割を果たします。方針決定の基盤となり、展示や収蔵、教育普及の方向性を定めるだけでなく、職員やボランティアの結束を促す力を持ちます。さらに、館長交代や社会状況の変化があっても、ミッションがあれば活動の一貫性と継続性を確保できます。つまり、ミッションは「館内の憲法」として機能し、長期的な視点で組織を支える基盤となるのです(Lord & Lord, 2009)。
外側の意義 ― 社会に開かれた約束
一方で、ミッションは館外に対して「社会に開かれた約束」として作用します。公的資金や寄付を受ける際の正当性を裏づけ、来館者に対しては「ここでどのような体験が得られるか」を示す信頼の基盤となります。また、持続可能性や多様性への対応をミッションに盛り込むことで、現代社会の課題に応答する姿勢を明確にすることができます(ICOM, 2022)。外側におけるミッションは、社会との契約であり、公共的資源としての博物館の正当性を担保するものだといえます。
事例からの学び ― 実践の多様性
MoMA の事例では「実験・学び・創造」という理念が、Projects シリーズや Artists Experiment によって具体化されていました。ここには未来志向と挑戦性が強く表れています。一方、Van Gogh Museum では「インスピレーションを与える」というシンプルな言葉が、作品展示、没入型プログラム、多言語対応といった活動に翻訳されていました。どちらの事例も示しているのは、ミッションは抽象的理念にとどまらず、具体的な活動や体験へと変換されることで初めて意味を持つという点です。方法は異なっても、両館はともにミッションを行動原理として位置づけているのです(Půček, Ochrana, & Plaček, 2021)。
博物館経営における普遍的意義
これらを踏まえると、博物館経営におけるミッションの意義は極めて大きいといえます。ミッションは経営戦略、展示企画、教育、研究、保存といったあらゆる活動の出発点となり、組織の内外をつなぐ役割を果たします。また、社会課題が変化する中でも、ミッションは館に一貫性を与え、変化を乗り越える道しるべとなります。長期的に見れば、ミッションは館の存続や公共的信頼の維持に不可欠な概念であると位置づけられるでしょう。
以上のように、博物館のミッションは単なる理念ではなく、組織を内部から支え、社会に対して存在意義を表明する基盤です。経営論の視点から見ても、公共性・継続性・信頼性を担保する中心概念として位置づけられます。そして学芸員を志す学生にとっては、博物館の実務や経営を理解するうえで不可欠な鍵であり、将来の現場で活動する際に自らの判断を導く指針となるのです。
参考文献
- International Council of Museums (ICOM). (2022). Museum definition. Retrieved from https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition/
- Lord, G. D., & Lord, B. (2009). The manual of museum management. AltaMira Press.
- Museum of Modern Art (MoMA). (n.d.). Mission statement. Retrieved from https://www.moma.org/about/mission-statement/
- Museum of Modern Art (MoMA). (n.d.). Projects archive. Retrieved from https://www.moma.org/interactives/exhibitions/projects_archive/
- Museum of Modern Art (MoMA). (n.d.). Artists Experiment. Retrieved from https://www.moma.org/calendar/programs/57
- Museum of Modern Art (MoMA). (2013). MoMA’s Pollock Conservation Project: Update on One: Number 31, 1950. Inside/Out blog. Retrieved from https://www.moma.org/explore/inside_out/2013/05/01/momas-pollock-conservation-project-video-update-on-one-number-31-1950/
- Museum of Modern Art (MoMA). (2025). Pirouette: Turning points in design. Retrieved from https://www.moma.org/calendar/exhibitions/5756
- Půček, M. J., Ochrana, F., & Plaček, M. (2021). Museum management: Opportunities and threats for successful museums. Springer.
- Van Gogh Museum. (n.d.). Mission and strategy. Retrieved from https://www.vangoghmuseum.nl/en/about/organisation/mission-and-strategy