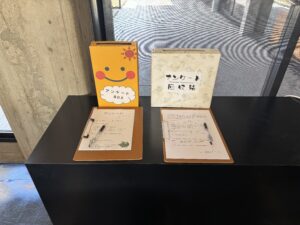博物館の成果の社会還元がなぜ求められるのか
近年、博物館は単に展示や資料保存を行う場ではなく、社会の変化に能動的に関わる公共機関として位置づけられるようになっています。かつては来館者数や展示件数といった数値的な成果が重視されてきましたが、現在は「その活動によって人や社会がどう変わったのか」という質的な成果、すなわちアウトカムを問う流れが強まっています。こうした背景のもとで注目されているのが、博物館の成果を社会に循環させるという考え方――「社会還元」です。
博物館は多くの場合、税金や寄付といった公的資源によって支えられています。そのため、社会からの信頼を維持するためには、活動の成果を明確に示し、どのように公共の利益へと還元しているかを説明する責任があります。いわば社会還元は、説明責任(アカウンタビリティ)を超えて、公共性を再生産するための仕組みと言えます。成果を社会へ返すことによって、博物館は支援と信頼の循環を生み出していくのです。
公共文化施設としての使命と説明責任
博物館は公共財として設立されており、公共資金や寄付によって支えられています。そのため、「どんな社会的価値を生んでいるか」を市民に説明するアカウンタビリティ(説明責任)が不可欠です。公共投資への成果説明が信頼や継続的支援を生み、社会還元は説明責任の延長線上にある行為として、成果を社会に返すことで信頼を再生産する役割を担います。
「来館者数」から「社会的インパクト」へ ― 評価軸の転換
従来の評価は「入館者数」「イベント回数」といったアウトプット中心でした。しかし、それらは“活動の量”を示すにすぎず、「人や社会がどう変化したか」というアウトカム(成果)を捉えることはできません。2000年代以降のイギリスでは、文化政策の中に「社会的インパクト」という考え方が導入され、博物館や芸術機関が社会にどのような影響を与えたかを可視化する仕組みが整えられてきました。日本でも文化庁による文化芸術推進基本計画などを通じて、文化活動が社会にもたらす効果が重視されるようになっています。こうした潮流は、文化施設の存在意義を「活動の量」ではなく「社会への貢献度」で捉え直す動きを後押ししています。
文化政策と助成制度における社会還元の流れ
イギリスのArts Council Englandなどでは、助成金の申請や報告の際に「どのような社会的成果を生んだか」を示すことが求められています。これは、文化事業を単なる支出ではなく、社会的投資(social investment)とみなす発想に基づいています。つまり、文化活動に投入された資金が、教育、福祉、地域づくりといった社会的領域にどのように還元されているかを評価する仕組みが整っているのです。社会還元は、助成金獲得のための手段ではなく、公共文化機関としての存在理由そのものといえるでしょう。
社会とともに成果を生み出す「共創型博物館」への転換
近年の博物館は、社会の課題をともに考え、共に解決を目指す「共創型」へと転換しつつあります。来館者に知識を提供するだけでなく、地域住民、教育機関、福祉団体などと連携しながら、社会のなかで成果を共有し再投資していく姿勢が求められています。社会還元とは、展示の成果を外へ発信することにとどまらず、学びや文化資源を社会全体の利益に還元し、持続的な文化の循環を生み出すことなのです。
このように、博物館の成果の社会還元は、単なる「説明義務」を超えて、社会の信頼を再生産する文化的な行為です。次節では、そもそも博物館における「成果」とは何か、その概念と構成を整理しながら、社会還元の基盤となる考え方を見ていきます。
博物館の成果とは何か
博物館の成果を社会に還元するためには、そもそも「成果」とは何を指すのかを明確に理解する必要があります。博物館の成果とは、単に展示を実施したり、来館者を増やしたりすることではありません。社会との関係性の中で生じる、人々の学びや態度、地域社会の変化など、より質的な「影響」や「価値の創出」を意味します。本節では、博物館の成果をアウトプットとアウトカムという二つの観点から整理し、教育的・文化的・社会的・経済的な側面を体系的に捉えていきます。
アウトプットとアウトカム ― 「活動」と「成果」の違い
アウトプット(output)は展示件数やイベント回数、来館者数など、活動の量を示す数値的な結果です。一方で、アウトカム(outcome)は、その活動によって人や社会にどのような変化が生まれたかを示す成果です。たとえば、「特別展を開催した」というのはアウトプットであり、それによって「来館者が新しい知識を得た」「地域への誇りが高まった」というのがアウトカムです。現代の博物館評価では、後者のアウトカム、つまり質的な変化を重視する傾向が強まっています。この区別を理解することが、社会還元を考える際の出発点になります。
博物館の成果は、一般的に次のような四つの領域で捉えることができます。教育的成果、文化的成果、社会的成果、経済的成果です。これらは互いに重なり合いながら、最終的に「社会的インパクト」と呼ばれる統合的な効果を生み出します。 博物館における主要な成果の分類と具体例
| 成果の区分 | 内容の概要 | 具体的な成果例 | 社会還元との関係 |
|---|---|---|---|
| 教育的成果 | 学びや理解、技能・態度の変化を通じて来館者に内的変化をもたらす成果。 | 展示から新しい知識を得た/学習意欲が高まった/他者理解が進んだ。 | 学校教育・地域学習への還元。教育資源として社会に循環。 |
| 文化的成果 | 文化資源の共有・創造・継承を通じて文化的価値を拡張する成果。 | 伝統文化への関心拡大/新たな創作活動/地域文化資源の再評価。 | 文化継承や地域文化振興への貢献。文化の持続可能性を支える。 |
| 社会的成果 | 包摂・共創・対話を通じて社会的つながりを生み出す成果。 | 障害者・外国人との協働展示/地域住民の参加/対話型鑑賞の実践。 | コミュニティの再生・共生社会の形成など社会包摂へ還元。 |
| 経済的成果 | 地域経済や雇用、観光などに波及する実質的な成果。 | 来館者による地域消費/イベント雇用/都市ブランド価値の向上。 | 地域経済活性化への貢献。文化活動の再投資を促進。 |
| 社会的インパクト | 教育・文化・社会・経済の成果を統合した総合的な社会変化。 | 来館者・地域・行政の連携強化/文化を通じた社会変革。 | 成果を社会全体に循環させる最終的な還元の形態。 |
教育的成果は、博物館の最も基本的な機能である教育普及活動と密接に関わっています。展示やワークショップを通じて新しい知識を得たり、価値観が広がったりすることで、個人の学びが社会へ波及していきます。これは、学校教育や地域学習の現場において博物館が「学びの資源」として機能することを意味します。
文化的成果は、博物館が文化資源を保存・展示するだけでなく、それを共有し、新しい文化的価値を生み出すことによって実現されます。地域文化の再評価や新しい創作活動の誘発は、文化の持続可能性を支える重要な要素です。
社会的成果は、博物館が人々のつながりを育み、包摂的な社会を実現する力に関わります。多様な立場の人々が対話を通じて関係を築き、共に展示をつくることで、博物館は「共生社会」の実践の場となります。
経済的成果は、博物館活動が地域経済や観光に与える波及効果です。来館者の地域消費や文化関連イベントによる雇用創出は、社会的投資収益率(SROI)の観点からも重要な指標となります。こうした成果は、行政や企業に対して博物館の社会的価値を説明する根拠ともなります。
そしてこれらの成果が総合的に重なり合ったものが「社会的インパクト」です。教育、文化、社会、経済の領域を横断しながら、博物館が地域や社会全体に及ぼす変化を示すものであり、社会還元の最終的な形とも言えます。社会的インパクトの理解は、次節で扱う「成果の社会還元」の仕組みを考える上で欠かせない視点となります。
博物館の成果の社会還元とは
博物館の成果は、展示や教育活動といった館内の取り組みの中で生まれるだけではありません。それらの成果が社会とどのように結びつき、再び新しい価値を生み出すかという「循環」の仕組みが重要です。社会還元とは、博物館の活動を通じて得られた知識・経験・感動・信頼といった成果を社会に返し、それをもとに再び文化的価値を創出していくプロセスを指します。単に活動結果を報告する行為ではなく、文化の共有と再生を支える根本的な仕組みなのです。
社会還元の基本構造 ― 「成果→共有→循環」
博物館における社会還元は、「成果(outcome)」を社会と「共有(communication)」し、それを「循環(return)」させるという三層構造で理解できます。展示や教育活動によって生まれた成果は、報告書や展示解説、ウェブサイト、メディアなどを通じて社会と共有されます。その共有の過程で、市民・教育機関・地域団体などが博物館の成果を自らの活動に生かすことで、社会の側に新たな学びや文化的変化が生じます。そして、その変化が再び博物館への支援や協働として戻ってくることで、成果の循環が成立します。つまり社会還元は、博物館と社会を双方向に結びつける「文化的循環」の仕組みであり、持続可能な文化経営を支える中核的な概念です。
社会還元の意義 ― 公共性の再生産と信頼形成
社会還元の本質は、公共性の再生産にあります。博物館は公共資金や寄付によって運営される公共機関であり、社会に対してその成果を明確に示す責任を負っています。成果を社会へ還元することは、説明責任を果たすだけでなく、信頼を再構築する行為でもあります。博物館が成果を社会に返し、その成果が市民の生活や地域の発展に役立つことで、「博物館は社会に必要な存在である」という認識が生まれます。これが支援や寄付の拡大につながり、再び博物館の活動を支える好循環を形成します。社会還元は、単なる結果の発表ではなく、信頼と支援を循環させる「社会的対話の仕組み」なのです。
社会還元の手法 ― 結果を伝え、共に生かす
- 成果の可視化:展示報告や年次報告書、SNSやウェブサイトを通じて成果を社会に分かりやすく伝える。博物館の存在意義を広く理解してもらう第一歩。
- 成果の共有:学校教育、地域学習、福祉、観光など多分野と連携し、博物館が生んだ成果を社会の他領域に活用してもらう。例:展示を教材として活用する授業、地域住民との共同展示、ボランティアとの協働。
- 成果の再投資:寄付や助成金によって得られた成果を次の活動へ循環させる仕組みを整える。自立的に文化価値を再生産していく基盤となる。
これら三つの手法を組み合わせることで、社会還元は単なる報告ではなく、社会全体を巻き込んだ学びと共創のプロセスになります。
社会還元と評価の関係 ― 「伝える」から「測る」へ
社会還元を持続的に実践するには、成果を適切に評価し、それを社会に伝えることが不可欠です。評価は単なる数値報告ではなく、社会との対話を通じて「どのような変化が起きたか」を共有する行為です。英国では、博物館や文化機関の成果を測定する枠組みとして、Generic Learning Outcomes(GLOs) と Generic Social Outcomes(GSOs) が整備され、学習・社会・文化の成果を体系的に評価する試みが進められています。これらの仕組みは、社会還元の過程を客観的に可視化し、政策や助成制度とも連動させる役割を果たします。「伝える」だけでなく「測る」段階への進化は、社会的インパクト評価の基礎をなします。
まとめ ― 社会還元が生み出す文化の循環
博物館の成果を社会へ還元することは、単に情報を発信することではありません。それは、文化的成果を社会と共有し、再び新たな成果として循環させる「文化の再生プロセス」です。成果を社会に返すことで信頼が生まれ、信頼が支援を生み、支援が次の成果を生む。この循環こそが、公共文化機関としての博物館を支える基盤です。次節では、この社会還元の考え方を制度的に支える英国の評価枠組み「GLOs」と「GSOs」について詳しく見ていきます。
英国の評価枠組み ― GLOsとGSOsから学ぶ博物館の成果評価
博物館の成果を社会に還元するためには、その成果を的確に「測り」「伝える」仕組みが欠かせません。活動の価値を可視化し、社会に対して説明可能な形で示すことは、公共文化機関としての信頼を築く上で不可欠です。イギリスでは、こうした目的のもとに整備された代表的な評価枠組みとして、Generic Learning Outcomes(GLOs) と Generic Social Outcomes(GSOs) が広く活用されています。これらは、博物館がもたらす学習的・社会的成果を体系的に評価するための指標群であり、成果の社会還元を支える制度的基盤として機能します。
背景 ― 英国の文化政策と評価への転換
1990年代後半以降、イギリスの文化政策は「アクセスの拡大(access)」から「インパクトの創出(impact)」へと転換しました。文化活動を社会的・経済的価値を生む公共投資として捉え直す流れの中で、博物館・図書館・アーカイブを統括していた Museum, Libraries and Archives Council(MLA) が中心となり、2001年にGLOを策定。その後、社会的効果を評価するGSOが加わり、成果の定量・定性的把握が進みました。
GLOs ― 学習成果を可視化する評価枠組み
GLOは、来館者が展示や活動を通じて得る変化を次の5領域で整理します:①知識と理解、②スキル、③態度と価値観、④楽しみ・インスピレーション・創造性、⑤行動変化・進展。アンケートや観察、インタビュー等により、質的な学習成果を可視化し、教育普及の効果を社会に説明します。
GSOs ― 社会的成果を測定する枠組み
GSOは、個人と地域社会に生じる社会的インパクトを測る枠組みです。主な領域は、①個人の自信・能力・幸福感の向上、②包摂的でつながりのある地域社会の形成、③学びと参加の拡大。文化政策の文脈で、博物館の社会的貢献を説明するために用いられます。
GLOとGSOの比較 ― 教育的成果と社会的成果の接続
GLOとGSOの比較表(評価対象・目的・主要領域・社会還元との関係)
| 区分 | 評価対象 | 主な目的 | 主要領域 | 社会還元との関係 |
|---|---|---|---|---|
| GLO(Generic Learning Outcomes) | 個人の学習・内的変化 | 学びの成果を可視化し、教育効果を説明 | 知識・技能・態度・創造性・行動変化 | 教育的成果を社会へ共有し、学びを循環させる |
| GSO(Generic Social Outcomes) | 社会・地域全体の変化 | 包摂や幸福感など社会的価値を可視化 | 自信・包摂・参加拡大 | 社会的成果を地域に還元し、信頼と連携を強化 |
GLO/GSOの運用 ― 評価を通じた社会的対話
GLO・GSOは、職員・行政・来館者が共通言語で成果を共有する「対話の枠組み」です。Arts Council Englandの助成審査や年次評価でも用いられ、各館が自館の成果を体系的に提示することで、政策的支援や資金配分の根拠が明確になります。評価は内部報告にとどまらず、社会的信頼を築くコミュニケーションツールとして機能します。
社会還元との関連 ― 成果の循環を支える評価
前節の「成果→共有→循環」モデルに照らすと、GLOは学習段階の成果を、GSOは社会への波及効果を可視化します。両者を接続することで、成果がどのように社会に還元されるかを説明可能になり、さらにSROI等の経済分析とも接続して、教育・社会・経済を横断する価値の連続性を示せます。
まとめ ― 評価を通じた社会との関係構築
GLOとGSOは、博物館が社会的存在として信頼を獲得するための実践的評価枠組みです。成果を可視化・共有することで社会との対話が深まり、支援と共創の循環が生まれます。次節では、この評価枠組みを具体的に活用した事例として、Derby Museums – Museum of Making のSROI(社会的投資収益率)分析を取り上げます。
Derby Museums – Museum of Making にみるSROI(社会的投資収益率)分析
これまで見てきたGLOやGSOは、博物館の成果を「学び」や「社会的変化」として定性的に評価する枠組みでした。しかし、文化活動の成果を政策的・財政的に説明するには、より客観的で数値化された根拠が必要とされます。こうした要請に応える形で注目されたのが、SROI(Social Return on Investment:社会的投資収益率)という評価手法です。SROIは、文化機関の活動が社会にもたらす便益を金額として可視化し、博物館の存在意義を「社会的投資効果」という形で示すものです。本節では、イギリスのDerby Museumsによる「Museum of Making」の事例を通じて、博物館の社会的価値を定量的に評価する方法とその意義を考察します。
SROIとは何か ― 社会的価値を数値化する仕組み
SROI(社会的投資収益率)は、社会的成果を貨幣価値に換算して投資効果として示す評価手法です。もともとは非営利組織や公的機関の社会的インパクトを測定するために開発されたもので、「1ポンドの投資がどれだけの社会的価値を生むか」を算出することを目的としています。基本的な計算式は次の通りです。
SROI = 社会的便益(社会的成果の金額換算) ÷ 投入資源(コスト)
たとえば、教育活動による学習効果、地域イベントによる交流促進、ボランティアによる社会参加など、博物館が生み出す幅広い成果を金額に置き換え、総合的な社会的価値として算定します。これにより、文化事業の「費用対効果」を示すと同時に、公共投資としての妥当性を政策的に裏づけることが可能になります。
Derby MuseumsとMuseum of Making
Derby Museumsは、イギリス・ダービー市が運営する公共博物館群で、地域の産業史や科学技術、デザイン文化を伝えることを目的としています。その中核施設であるMuseum of Makingは、産業革命期の工場跡地を再生して2021年に開館しました。「つくること(making)」を通じて地域の創造性を育むことを使命とし、展示だけでなく市民参加型のワークショップや実習工房などを中心に活動しています。この館は、文化的成果だけでなく、地域経済・雇用・教育・幸福感の向上といった多面的な成果を生み出したことから、開館後にSROI分析の対象となりました。
SROI分析の方法と算出結果
- ステークホルダーの特定:来館者、ボランティア、地域企業、行政など。
- 成果の把握:教育的効果、雇用促進、地域ネットワーク形成、幸福感の向上など。
- 成果の金額換算:統計データやアンケートに基づき、既存研究の数値モデルで換算。
- コスト比較によるSROI比率の算出:投入資源に対して便益総額を割り、比率化。
その結果、「Museum of Making」は投資1ポンドあたり約4.9ポンドの社会的価値を創出したと報告されています。つまり、投入された資金の約5倍に相当する価値が社会に還元されたことになります。これには、来館者の学習機会や地域雇用の創出だけでなく、幸福感や地域コミュニティの結束といった無形の社会的便益も含まれています。この分析は、文化投資がもたらす社会的効果を実証的に示した先進事例といえます。
社会的価値の内訳と波及効果
- 教育的価値:技能の習得、生涯学習の促進、STEM教育への貢献。
- 社会的価値:地域住民の幸福感、参加意識の向上、包摂的コミュニティの形成。
- 経済的価値:地域雇用の創出、観光収入の増加、地域ブランド価値の向上。
特に注目すべきは、「幸福感の向上」や「アイデンティティの再構築」など、従来の経済分析では捉えにくかった価値が貨幣換算によって明示化された点です。これにより、博物館は文化施設としてだけでなく、社会的インフラとしての役割を持つことが具体的なデータとして証明されました。
日本の博物館への示唆
日本においては、展示評価や教育普及の効果を報告する事例は多いものの、社会的便益を経済的指標で示す試みはまだ限られています。Derby Museumsの事例は、博物館が生み出す成果を「信頼」「投資」「再循環」という形で社会に還元していく視点を提供しています。特に地方自治体の文化施設において、来館者調査、ボランティア活動、地域連携の成果を統合し、社会的価値として定量的に示すことは、今後の政策評価や資金調達に大きな意味を持ちます。SROI的な発想は、文化政策や寄付促進、企業との協働など、文化経営の新しい基盤として応用可能です。
まとめ ― 成果を価値として還元する時代へ
Derby MuseumsのSROI分析は、博物館が創出する社会的価値を数値的に可視化した革新的な事例です。投資に対する社会的リターンを明示することで、文化活動を「支出」ではなく「価値創造」として社会に提示しました。博物館経営の目的は、単に展示や教育を行うことではなく、それらの成果を社会的価値として還元し、次の支援と共創を生み出すことにあります。今後の博物館経営は、このような「成果を測り、還元する」循環的な仕組みをどれだけ確立できるかが問われているといえるでしょう。
博物館評価と社会的インパクトの未来 ― 持続可能な文化経営に向けて
博物館の活動成果は、単に展示や教育普及といった事業実施にとどまりません。そこから生まれる「社会的変化」こそが、真の成果といえます。これまで見てきたように、イギリスではGLO(Generic Learning Outcomes)やGSO(Generic Social Outcomes)を通じて学習的・社会的な成果を整理し、さらにSROI(社会的投資収益率)によってそれらを数値化する仕組みが整備されてきました。こうした評価手法は、博物館が社会にどのような価値をもたらしているのかを明示し、文化経営の持続可能性を高める基盤となっています。本節では、これらの枠組みを総合し、博物館評価の新しい方向性を展望します。
評価の役割の転換 ― 「測る」から「変化を生む」へ
かつての博物館評価は、来館者数や展示件数といった数量的指標を中心に構成されてきました。これらのデータは重要であるものの、社会的・教育的な影響を十分に反映しているとはいえません。近年は、社会にどのような「変化(outcome)」をもたらしたのかを重視する、質的な評価への転換が進んでいます。評価はもはや単なる監査や報告の手段ではなく、組織の学びと変化を促すプロセスへと変化しています。つまり、博物館は「評価される存在」から「評価を通じて社会変化を生み出す存在」へと進化しつつあるのです。
社会的インパクト評価の展開
イギリスでは、Arts Council Englandなどの機関が中心となり、博物館・美術館の社会的影響を測定する仕組みを発展させてきました。GLO・GSO・SROIを基盤に、教育、地域社会、環境、経済など多様な領域における成果を包括的に把握するモデルが整備されています。特に注目されるのは「Theory of Change(変化の理論)」の導入です。これは、組織の活動がどのようなプロセスを経て社会的変化を生むのかを因果的に可視化する手法であり、成果の背後にある「価値創造のメカニズム」を明確にします。評価を通して、博物館は自らのミッションを社会的影響と接続することができるのです。
持続可能な文化経営と評価の統合
社会的インパクト評価は、もはや補助的な分析ではなく、博物館経営の中核機能の一つとなりつつあります。評価の導入によって、組織の方向性が明確化され、ステークホルダーと共有される「透明性」が生まれます。さらに、ガバナンスや財務、人材育成、社会関係資本(social capital)といった要素を統合的に捉えることで、文化経営の持続可能性が強化されます。日本では、独立行政法人や地方自治体の博物館がすでに年次評価を実施していますが、それを「経営戦略の一部」として位置づけ、定常的な改善サイクルを形成することが求められています。評価を単なる行政的義務ではなく、価値創造のための戦略ツールとみなす転換が必要です。
共創型評価への移行 ― 対話を軸にした新しい形
今後の評価は、博物館職員や専門家だけでなく、来館者、地域住民、行政、支援者などが共に関わる「共創型評価(co-evaluation)」へと移行していくと考えられます。成果を一方的に報告するのではなく、評価の過程を共有しながら新たな課題や改善策を共に見出していく。このプロセスは「評価=対話」という考え方に基づいており、博物館の公共性を支える新しい実践モデルです。共創型評価は、社会の多様な声を反映し、文化的包摂の実現にも寄与します。
日本の制度的課題と今後の展望
日本の博物館では、評価が「事後報告」や「成果指標の確認」にとどまる傾向が見られます。しかし、近年の文化庁による制度改革や指定管理制度の進展により、評価を経営に統合する流れが徐々に広がっています。今後は、評価を通じて社会との信頼関係を再構築し、「説明責任」から「共創責任」へと意識を転換する必要があります。また、学芸員や教育担当者が評価データをもとに改善策を策定する「エビデンス・ベースト経営(EBM:Evidence-Based Management)」の考え方も重要です。評価文化の成熟は、博物館が自律的に学び続ける組織へと進化することを意味します。
まとめ ― 「評価」を通じて文化を再生する
博物館における評価とは、単に成果を数値で示すことではなく、社会との関係を再構築するための手段です。評価を通じて博物館は社会的インパクトを明らかにし、その成果を社会へと還元していきます。これは、文化を“循環する資源”として再生するプロセスでもあります。数値では測れない人々の学びや感動、共感を含めた「文化の力」をどのように可視化していくか――そこに、これからの博物館評価の未来があるのです。
参考文献一覧
- Arts Council England. (n.d.). Generic social outcomes – Indicator bank. Arts Council England. Retrieved from https://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/S3D29_GSO_Indicator_Bank.pdf
- Derby Museums Trust. (2023). The impact of the Museum of Making: Social return on investment. Derby Museums Trust. Retrieved from https://derbymuseums.org/static/e5fa49422ad3734c1d632df8cd0e222a/DM_MoM_SocialReturnOnInvestment_report2023.pdf
- Derby Museums Trust. (n.d.). Social return on investment – Executive summary. Derby Museums Trust. Retrieved from https://derbymuseums.org/static/c4bb04b162a6e28e0d8e719889514319/DM_MoM_SocialReturnOnInvestment_ExecutiveSummary_.pdf