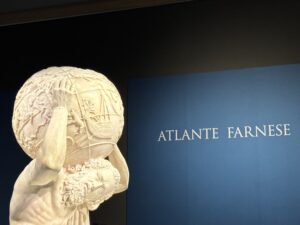なぜ博物館経営を学ぶのか
現代の博物館は、教育・文化・観光・地域振興の拠点として社会の中に確固たる地位を築いています。展示や収蔵資料を通じて人々の知識と感性を育み、地域文化の継承や国際的な文化交流にも貢献しています。しかしその一方で、博物館を取り巻く環境は大きく変化しています。行政の財政制約が進み、公的支援だけに頼れない状況が生まれ、民間助成や寄附、企業連携など新しい資金調達の形が求められるようになりました。また、来館者の多様化やデジタル技術の発展により、展示や教育の方法にも柔軟な発想と経営的判断が必要とされています。こうした社会・経済・技術の変化は、博物館のあり方そのものに問いを突きつけています(Macdonald, 2006)。
かつて博物館の運営は、収蔵品の保管や展示、研究といった専門的業務の延長として捉えられてきました。けれども、社会的使命を持つ文化機関としての博物館が持続的に活動を続けるためには、専門性の枠を超えた総合的な経営の視点が欠かせません。博物館経営とは、単に予算を管理し職員を統率することではなく、限られた資源をいかに活用して使命を果たすかを考える意思決定の体系です。言い換えれば、それは博物館の存在意義を社会の中でどのように実現し、どのように共有していくかを設計する営みだと言えるでしょう(Sandell & Janes, 2007)。
博物館経営は、効率性や収益性を追求する営利経営とは異なり、公共的価値を最大化するための仕組みとして理解されます。Lord & Lord(2009)は、博物館経営を「職員が自らの職務を遂行しやすくするための意思決定を支援する行為」と説明しています。経営の本質は命令や統制ではなく、職員やボランティア、地域社会など多様な関係者が協働し、館の使命を実現するプロセスにあります。その中心にあるのは、博物館の使命(mission)への共感と理解であり、使命が共有されることで組織は一体性をもって動くことができます。この意味で、経営とは内部統制のための技術ではなく、社会と博物館をつなぐ知的実践であると言えます(Lord & Lord, 2009)。
博物館経営を学ぶ意義は、単に効率的な運営方法を身につけることにとどまりません。それは、博物館という公共的存在が、変化する社会の中でどのように信頼を維持し、価値を創造していくかを考えるための基盤を築くことにあります。文化政策や教育、観光、地域開発といった他分野と連携しながら、社会における博物館の役割を再定義する視点が求められています。したがって、博物館経営の理解は、専門的知識の管理から社会的価値の創出へと博物館を発展させるための第一歩なのです(Půček, Ochrana, & Plaček, 2021)。
本稿では、まず博物館経営の定義と発展を確認し、次にその構成要素と実践領域を整理します。さらに、博物館経営の意義を公共性・多様性・持続可能性の観点から考察し、現代における課題と展望を示します。これらを通じて、博物館を「知識と文化の公共基盤」として維持・発展させるための視点を体系的に整理していきます。本稿の目的は、経営を「文化を動かす知的実践」として再考することにあります(Lord & Lord, 2009)。
博物館経営の定義と発展
博物館経営という言葉は、今日では学芸員課程や文化経営の領域で広く使われていますが、その概念が確立したのは比較的近年のことです。1970年代から1980年代にかけて、欧米の博物館を中心に「マネジメント(management)」という発想が導入されるようになりました。その背景には、公共部門全体で進められた行政改革と、文化機関における効率性や説明責任を重視する潮流があります。特に1980年代のイギリスでは、新公共経営(New Public Management)の考え方が文化行政にも浸透し、博物館は「文化資源を社会のために活用する組織」としての側面を強く意識するようになりました(Sandell & Janes, 2007)。
それ以前の博物館は、学術的研究や文化財の保存を主な使命とする「学者の領域」であり、経営という言葉とは距離がありました。しかし、社会の変化とともに、来館者の多様化、財政支出の抑制、地域連携の必要性などが顕在化し、学芸活動だけでは博物館を維持できなくなりました。このとき「マネジメント」という言葉が示したのは、単なる管理ではなく、社会的使命を持つ組織としての博物館が、自らの方向性を明確に定め、持続可能に運営していくための方法論だったのです。すなわち博物館経営は、学問的機関としての専門性を維持しながら、同時に社会的組織としての責任を果たすための新しい枠組みとして導入されました(Macdonald, 2006)。
このような流れの中で、1990年代以降の国際的な議論では、博物館を「社会に開かれた文化機関」として再定義する動きが強まりました。ICOM(国際博物館会議)は2007年の定義において、博物館を「社会およびその発展のために奉仕する非営利の恒久的機関」と位置づけました。この文言は、経営の目的が単なる組織維持や収益確保ではなく、「社会の発展への貢献」であることを明確に示しています。博物館はもはや「モノのための場所」ではなく、「人と社会のための学びと対話の空間」へと変化したのです(ICOM, 2007)。
経営の多様な定義と視点
こうした変化のなかで、博物館経営に関する理論的な定義も多様化していきました。経営は「職員が自らの職務を遂行し、博物館の使命を実現できるよう支援するための体系的行為」とされ、命令や統制の仕組みではなく、組織の構成員が協働して使命を果たすための支援的機能として位置づけられています(Lord & Lord, 2009)。組織の目標を達成するための「指導」ではなく、「整備」や「支援」の行為であり、館の使命を中心に据えた一体的な活動のデザインだといえます。
経営は「市場の論理と博物館の公共的使命との間に生じる緊張関係を調整する知的実践」とも捉えられています。博物館は文化的価値の担い手であると同時に、来館者という「市場」と接する社会的存在でもあります。したがって、経営者は効率性や収益性を高めるだけでなく、博物館の正統性や公共性を維持する責任を負うことになります。経営とは、こうした二つの価値体系の間でバランスをとりながら、社会的信頼を形成していくプロセスでもあるのです(Sandell & Janes, 2007)。
また、現代の博物館経営は「社会・経済・制度環境に適応しながら使命を達成するための戦略的意思決定プロセス」として再定義されています。博物館は固定的な組織ではなく、環境の変化に応じて構造や行動を調整する「学習するシステム」とみなされます。経営は内部の管理や財務統制にとどまらず、外部環境との対話を通じて博物館の存在意義を再構築する動的な行為なのです(Půček, Ochrana, & Plaček, 2021)。
これらの研究に共通して見られるのは、博物館経営を「使命(mission)」「環境(context)」「持続性(sustainability)」の三つの要素から構成される総合的なシステムとして捉える視点です。すなわち、経営とは博物館の理念を社会の中で実現し続けるための知的枠組みであり、その実践が社会的信頼の源泉となるのです。
研究領域としての展開
博物館経営の学問的研究は、1980年代以降、文化経営学(cultural management)、公共経営(public management)、教育マネジメントなどとの関連の中で急速に発展しました。経済学的アプローチでは、非営利組織としての博物館がどのように資源を配分し、効率的に運営できるかが分析されました。社会学的アプローチでは、博物館の組織文化、専門職間の関係、意思決定の構造などが焦点となりました(Macdonald, 2006)。教育学的アプローチは、博物館を学習の場と位置づけ、観客開発(audience development)や参加型プログラムを通じた学びの支援を探求してきました。さらに、政策学的アプローチでは、博物館が文化政策や地域振興の枠組みの中でどのような役割を果たすかが議論されています。これらの学際的研究は、博物館を単なる制度ではなく、「社会的意味(social meaning)」を生み出す文化的主体として理解する視点を提供しています(Sandell & Janes, 2007)。
このように、博物館経営は単一の理論ではなく、経済・社会・文化・教育の各要素が交差する複合的な研究領域として確立してきました。その中心にあるのは、文化的価値を社会的価値へと転換し、その循環を持続させるという理念です。博物館経営の究極の目的は「文化的価値を社会的価値に翻訳し、その成果を再び文化として還元すること」とされます。すなわち、経営の目的は財務的安定ではなく、文化の持続可能な再生産にあります(Půček, Ochrana, & Plaček, 2021)。
目的と価値創造の枠組み
この意味で、博物館経営は効率化や収益化を目的とする技術ではなく、「公共性」「包摂性」「説明責任」を基盤とした文化的実践です。収蔵品・人材・資金・情報というリソースを統合し、社会との関係の中で博物館の使命を具現化することが、経営の本質的な役割なのです。こうした理解は、次節で扱う「博物館経営の構成要素と実践領域」へとつながります。そこでは、理念をいかに組織や制度、日々の活動に落とし込むかという具体的課題が展開されていきます。
博物館経営の構成要素と実践領域
博物館経営を理解するうえで重要なのは、理念や理論を具体的な組織運営の実践へとつなぐ視点です。経営とは単に「管理」や「運用」を意味するものではなく、博物館という複合的な文化機関が、限られた資源を用いながら使命を実現していくための総合的な意思決定の体系です。第1節で確認したように、博物館経営の目的は効率化や収益性の追求ではなく、社会的使命の実現にあります。そのためには、理念を支える具体的構成要素を整理し、それらがどのように連動して経営全体を形づくっているのかを把握する必要があります(Lord & Lord, 2009)。
理念・使命(Mission)と戦略(Strategy)
博物館経営の基礎には「理念(philosophy)」と「使命(mission)」があります。使命とは、博物館が社会の中で果たすべき存在意義を示すものであり、その内容は設立目的や歴史的背景、地域社会との関係などに基づいて形成されます。理念はこの使命を支える価値観であり、博物館が何を守り、何を伝えるべきかという方向性を示します(Lord & Lord, 2009)。
使命を具体化するためには「戦略(strategy)」が不可欠です。戦略とは、限られた資源をどのように配分し、どのような活動を優先させるかという意思決定の枠組みを意味します。戦略は理念と活動の橋渡しを行う「実践的ロードマップ」として、収集・保存・研究・教育・公開といった機能全体を統合します(Sandell & Janes, 2007)。使命と戦略の明確化は、職員の意識統一や外部への説明責任を果たすうえでも不可欠です。
組織構造と人材(Organization & Human Resources)
博物館経営の中核をなすのは人です。学芸員、教育普及担当、管理・事務職、ボランティアなど、多様な人材が連携して初めて博物館は機能します。博物館は「専門知と組織知が交錯する社会的構造」として捉えられ、組織文化や職員間の協働が経営の成否を左右します(Macdonald, 2006)。
組織運営では、部門間の連携と意思決定の透明性が重視されます。近年は、フラットな組織構造やプロジェクト型チームを採用し、展示・教育・広報・財務が横断的に連携する動きが見られます。さらに現代の博物館経営では、人材開発(human capital development)が最重要課題の一つとされ、専門知の深化に加えてリーダーシップ、コミュニケーション、多様性(diversity)への理解を備えた人材育成が求められます(Půček, Ochrana, & Plaček, 2021)。
財務・資源管理(Finance & Resource Management)
経営の持続性を確保するうえで不可欠なのが、財務と資源の管理です。予算配分や収益活動に留まらず、資金・人材・施設・収蔵品といったあらゆる資源をどのように統合的に運用するかが問われます。財務管理は単なる会計処理ではなく、使命を支えるための資源活用の計画的プロセスとして位置づけられます(Lord & Lord, 2009)。
伝統的に博物館は公的資金に依存してきましたが、財政的制約の高まりにより、寄附・助成金・企業連携・自主事業などの多様な資金源を組み合わせる「多元的財源構造」への転換が進んでいます。これは市場的価値と公共的価値の調整を伴い、経営者は両者のバランスを取りながら意思決定を行う必要があります(Sandell & Janes, 2007)。収蔵品や建物などの固定資産も「文化資本(cultural capital)」として捉え、その社会的価値を最大化する視点が求められます(Půček, Ochrana, & Plaček, 2021)。
ガバナンスとリーダーシップ(Governance & Leadership)
ガバナンスは透明性・説明責任・倫理性を確保する枠組みを意味します。とくに公立館では、理事会や行政機関との関係性が経営方針に大きく影響します。ガバナンスは「組織と社会をつなぐ倫理的契約」として、公共的使命の実現に資する信頼形成の役割を担います(Sandell & Janes, 2007)。
ガバナンスの実効性を高めるうえで欠かせないのがリーダーシップです。館長や理事長のみならず、学芸員や教育担当者もそれぞれの立場でリーダーシップを発揮することが求められます。リーダーシップは「理念を組織文化に変換し、構成員を動かす力」として、使命の共有者としての行動を導きます(Lord & Lord, 2009)。今日では、意思決定を分担する共有型リーダーシップ(shared leadership)も注目されています。
社会的関係とステークホルダー(Social Relations & Stakeholders)
博物館経営は、社会との関係性の中で成立します。来館者、地域住民、行政、企業、ボランティア、教育機関など多様な関係者との協働は、経営の持続性を支える基盤です。博物館は「社会的相互作用の場」であり、経営は「関係構築のデザイン」として理解されます(Macdonald, 2006)。
近年は、社会的包摂(inclusion)、地域共創(co-creation)、文化的民主主義(cultural democracy)といった理念が重視され、社会的課題の解決や地域再生に関与するケースが増えています。地域住民と協働した展示や教育機関との連携プログラムは、単なる集客施策ではなく、社会的信頼を高める経営行為の一部として位置づけられます(Sandell & Janes, 2007)。
博物館経営の意義 ― なぜ経営が必要なのか
博物館における「経営」は、単に組織を維持するための管理行為ではありません。経営とは、博物館の使命や理念を現実の活動に落とし込み、社会とともに文化的価値を創り出すための知的営みです。すなわち、経営の意義は「文化を社会に生かすための仕組み」にあります。保存・展示・教育といった伝統的機能を超えて、社会との関係を再構築し、未来に文化を継承する戦略的な視点が求められます(Lord & Lord, 2009)。
経営は使命を実現する仕組み
博物館には、それぞれの存在意義を示す使命(mission)があります。経営は、この使命を実際の活動に翻訳し、組織全体として一貫した方向性を持たせる役割を果たします。教育を重視する館であれば、展示設計・教育プログラム・広報・評価が使命と整合するよう計画されます。経営はこの整合性を保つ「接着剤」として機能し、理念を現実へと変えるプロセスです(Lord & Lord, 2009)。
また、博物館は学芸・教育・管理など多様な専門職で構成され、価値観や優先順位が異なります。経営はそれらを調整し、共通の目的に向けて意思決定を統合する「翻訳装置」として機能します。この仕組みがなければ、個別の専門性が独立し、博物館としての統一的な成果が得られなくなります(Sandell & Janes, 2007)。
経営は社会とつながる仕組み
博物館は公共的組織として社会の中で機能します。経営は、行政、地域住民、学校、企業など多様な関係者と対話・協働関係を築くための「関係のデザイン」です(Macdonald, 2006)。たとえば学校との共同プログラムや地域連携の展示では、目的や役割の調整、資源配分、評価指標の合意が欠かせません。これらの調整を支えるのが経営です。
さらに、経営は透明性と説明責任(accountability)を確保し、社会的信頼を維持する基盤でもあります。収支の公開、意思決定過程の明示、寄附金の使途報告など、経営の透明性が信頼を支えます。信頼は博物館の最大の資産であり、経営という制度的・倫理的枠組みによって保持されます(Lord & Lord, 2009)。
経営は人と文化を循環させる仕組み
博物館の活動は、過去から受け継いだ文化資源を未来へとつなぐ「文化の循環」に位置づきます。経営はこの循環を、社会的・教育的・経済的に持続させる仕組みです。展示やコレクション管理だけでなく、文化を社会に還元し、再び人々の関心や参加を通じて再生産するプロセスが経営によって支えられます(Macdonald, 2006)。
収蔵品や知識は、教育プログラムや参加型展示、デジタル公開などによって社会の「共有財」として活用されます。こうした活用と還元が進むとき、博物館は「知識の倉庫」から「社会の知的基盤」へと発展します。経営はこの文化資源の活用・還元を支える知的枠組みであり、文化の再生産を促進する役割を担います(Půček, Ochrana, & Plaček, 2021)。
経営は未来へ文化をつなぐ仕組み
経営の根本的意義は、文化の持続可能性を実現することにあります。財務の健全性、人材育成、環境配慮、情報基盤の整備など、あらゆる要素は次世代に文化を手渡す準備であり、経営はそのための「橋渡しの知恵」です(Půček, Ochrana, & Plaček, 2021)。
また、技術や社会環境の変化に適応する「未来志向のマネジメント」も重要です。デジタルアーカイブの整備やオンライン教育の展開は、効率化にとどまらず、未来への文化継承の手段です。変化を学びとして取り入れる柔軟性を組織文化として根づかせることによって、博物館は「進化する公共機関」へと発展します(Lord & Lord, 2009)。
まとめ ― 経営は文化を社会に生かす知的実践
博物館経営の意義は、理念を現実に変え、社会と結びつき、文化を循環させ、未来に継承するための知的実践にあります。経営の本質は、組織を動かすことそのものではなく、「社会の中で文化を生かすための知恵」を共有し続けることにあります。すなわち、博物館経営とは文化を未来へ橋渡しする“人と社会をつなぐ文化的マネジメント”なのです(Sandell & Janes, 2007; Lord & Lord, 2009; Macdonald, 2006; Půček, Ochrana, & Plaček, 2021)。
まとめ ― 博物館経営の本質と未来への展望
現代の博物館は、文化を保存するだけでなく、社会とともにその価値を再構築し、未来へとつなぐ使命を担っています。そのため、博物館の経営は単なる管理や運営の技術ではなく、「文化を動かす知的実践」として位置づけられます。これまで見てきたように、博物館経営は制度・人・社会・未来という複数の要素によって構成され、それぞれが密接に結びつきながら博物館の存在を支えています。ここでは、これまでの議論を整理しつつ、博物館経営の全体像と今後の展望を明らかにします。
博物館経営の全体像 ― 四つの柱から見る整理
制度的基盤 ― 公共性と自律性の両立
博物館経営の第一の柱は、制度的な基盤にあります。博物館法や文化政策、補助金制度など、法制度は博物館の活動を支える重要な枠組みです。こうした制度は博物館の公共性を保証し、社会からの信頼を得るための土台となっています。しかし、制度は目的そのものではなく、社会の多様な期待に応えるための手段にすぎません(Lord & Lord, 2009)。したがって、現代の博物館には、制度に守られる存在から、制度を活用して自律的に運営する存在への転換が求められています。公共性を維持しながらも独自の判断で社会に貢献できる経営が、成熟した博物館の姿だといえるでしょう。
人的基盤 ― 専門知と協働知の融合
博物館を動かしているのは「人」です。学芸員、教育担当者、事務職員、ボランティア、そして地域のパートナーなど、異なる立場の人々がそれぞれの知識と経験を持ち寄ることで、博物館の活動は成り立っています。経営の役割は、こうした多様な知をつなぎ合わせ、協働を通して新しい価値を創出することにあります。多様な専門性を束ねる力――すなわち「協働知(collaborative intelligence)」こそ、現代の博物館経営における最大の資源です(Sandell & Janes, 2007)。また、個々の専門職が孤立するのではなく、相互に学び合う組織文化を醸成することが、持続可能な経営の条件となります。
社会的基盤 ― 信頼と共創を軸にした経営
博物館の価値は、展示品の希少性や建物の規模にあるのではなく、社会からどれだけ信頼されているかにかかっています。信頼は、地域社会、来館者、行政、支援団体など、あらゆる関係者との継続的な対話の中で築かれるものです。博物館はもはや「文化財を保管する場所」ではなく、「文化を共に創り出す場」としての性格を強めています(Macdonald, 2006)。このような社会的共創を実現するためには、開かれた意思決定、説明責任の徹底、そして包摂的な運営が不可欠です。経営は、そのプロセスを設計し、実行するための枠組みとして機能します。社会との信頼を再生産し続けることこそ、経営の核心的な役割といえるでしょう。
未来的基盤 ― 持続可能性と文化の継承
博物館経営の最終目的は、文化を未来へ手渡すことにあります。これは単に遺産を保存することではなく、その価値を次の世代に生かすことを意味します。財政的な安定、人材の育成、環境負荷の低減、教育プログラムの継続など、あらゆる側面から持続可能性を確保することが求められています(Půček, Ochrana, & Plaček, 2021)。経営とは、現在の成果を誇ることではなく、未来に対して責任を果たす行為です。短期的な成功ではなく、長期的な社会的価値の創出を重視する視点が必要です。文化を継承するとは、過去を守るだけでなく、新たな意味を創造し続けることでもあります。
博物館経営を学ぶ意義 ― 文化を「守る」から「動かす」へ
博物館経営の理解は、文化と社会の関係を新たに捉え直すための基盤となります。経営を学ぶことは、単に効率的な運営を目指すことではなく、文化を社会にどう生かし、共有し、継承するかを考えることです(Lord & Lord, 2009)。経営は、文化の価値を翻訳し、社会の中でその意味を再構築する知的実践といえます。
また、理論と実践の往還によって理解が深まります。理論は現場を分析するための枠組みを与え、実践は理論を検証し、豊かにします。経営の思考を持つことは、日々の実務を構造的に理解し、より意図的に文化を運営する視点を持つことでもあります。博物館経営を学ぶことは、文化を動かすための「社会的リテラシー」を身につけることにほかなりません。
これからの博物館経営 ― 信頼・共創・希望をつなぐ
博物館を取り巻く社会環境は急速に変化しています。人口減少、デジタル化、地域格差、災害、感染症――こうした課題に直面するなかで、経営の柔軟性と創造性がこれまで以上に問われています。変化に適応するだけでなく、その変化を学びの契機として活かすことが、現代の博物館経営の重要な使命です(Půček, Ochrana, & Plaček, 2021)。
変化に学び続ける経営は、単なる危機管理ではありません。それは、社会の動きを文化的視点から捉え直し、新しい公共性を築く営みです。博物館が社会の信頼を得続けるためには、開かれた組織として自己変革を恐れない姿勢が必要です。文化を静的なものとして扱うのではなく、絶えず変化し続ける「生きた知」としてマネジメントしていくことが求められています。
そして、博物館経営の究極の目的は「希望の創出」です。文化は人々に生きる意味と誇りを与え、社会に希望をもたらす力を持っています。経営はその文化的希望を支える仕組みを築くことです。財政的・制度的課題を乗り越えながら、信頼と共感に基づく社会関係を構築することが、これからの博物館経営の方向性といえるでしょう(Macdonald, 2006)。
博物館経営の核心にあるもの
博物館経営は、制度・人・社会・未来をつなぐ総合的な知の実践です。その目的は収益化や効率化ではなく、文化を通じて社会に信頼と共感を生み出すことにあります。経営とは、文化を守ることではなく、文化を動かし続けることです。変化する社会の中で、博物館が希望と対話の場であり続けるためには、経営の思考が欠かせません。
博物館経営を理解することは、単に文化施設の管理を学ぶことではなく、「人と社会の関係を再構築する知」を身につけることです。それは、文化を未来へつなぐ責任を自覚し、希望を育てるための行為でもあります。博物館の経営は、文化を動かし、社会を照らす知的営みであり、その根底にあるのは人と文化への信頼です。これこそが、博物館経営の本質であり、未来への展望を支える確かな出発点となるのです(Lord & Lord, 2009; Sandell & Janes, 2007; Macdonald, 2006; Půček, Ochrana, & Plaček, 2021)。
参考文献
- Lord, G. D., & Lord, B. (2009). The manual of museum management. AltaMira Press.
- Macdonald, S. (2006). A companion to museum studies. Wiley-Blackwell.
- Půček, M. J., Ochrana, F., & Plaček, M. (2021). Museum management: Opportunities and threats for successful museums. Springer.
- Sandell, R., & Janes, R. R. (Eds.). (2007). Museum management and marketing. Routledge.