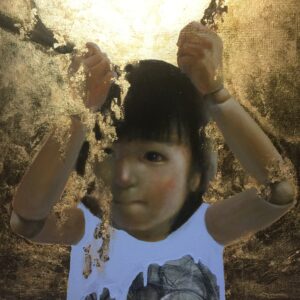はじめに
水族館は広義の意味において、博物館に含まれる施設と位置づけられます。日本の博物館法では、博物館を「歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集・保管・展示し、調査研究および教育普及活動を行う施設」と定義しています。この定義に照らせば、生きた水生生物を収集・飼育・展示し、さらに教育や研究、保全活動にも取り組む水族館は、博物館の機能と理念を広く備えた施設であるといえます。事実、動物園や植物園とともに、水族館も博物館類似施設として博物館法の対象に含まれています。
しかし、現代の水族館は単なる生物展示施設にとどまらず、社会に対して多様な役割を担う存在へと進化してきました。19世紀、最初に誕生した水族館は、来館者に珍しい生き物を見せることを主たる目的とする娯楽施設でした。直線的に並んだ小型の水槽に、分類学的な基準で生物を収容する「タクソノミック・コンセプト(分類学にもとづいて種類ごとに整理・展示する考え方)」が支配的だった時代です(Karydis, 2011)。しかし、20世紀末から21世紀にかけて、展示の方法や施設の理念は大きく変わり始めます。自然環境を模した大型水槽による生態系展示(エコロジカル・コンセプト)の普及に加え、教育活動、研究機関としての機能強化、さらに絶滅危惧種の保全を担う社会的使命が強調されるようになりました(Hutchins & Smith, 2003;Minteer & Collins, 2013)。
とりわけ地球温暖化や生物多様性の危機が深刻化する現代において、水族館には、種の保存や生態系の理解促進、さらには市民への環境教育を推進する「公共的拠点」としての役割が期待されています。淡水魚の保全活動をはじめとする、国際的な自然保護ネットワークへの積極的な参加も進んでいます(Arthington et al., 2016)。
この記事では、このような背景を踏まえ、水族館経営の「特殊性」と「博物館経営論に通じる共通性」の両面に目を向けていきます。水族館に特有の課題(生体管理、倫理問題、運営コスト)と、博物館に共通する使命(保存、教育、研究、公共性)とを比較しながら、両者をつなぐ視点を探っていきます。そして最後に、水族館経営を広義の博物館経営論の中でどう位置づけるべきかを考えます。
水族館の特徴と進化
水族館の起源:娯楽施設としての誕生
水族館の歴史は19世紀半ばに始まります。1853年、ロンドン動物園内に世界初の公立水族館「フィッシュハウス」が開設され、一般市民に向けた水生生物の展示がスタートしました(Karydis, 2011)。この時代の水族館は、来館者にとって珍しい生き物を間近で観察できる娯楽施設として位置づけられていました。
展示の考え方も現在とは大きく異なっており、「タクソノミック・コンセプト(taxonomic concept)」に基づいて構成されていました。これは、生物を分類学上のカテゴリー(例:魚類、甲殻類、軟体動物など)ごとに整理し、それぞれの種を個別に紹介する方法です。生態系の中での役割や相互作用を見せるのではなく、種類ごとの違いを強調することが目的でした。
例えば、「サメのコーナー」「クラゲのコーナー」のように、分類された生物群が単独で展示され、観覧者は種類ごとに「珍しさ」や「奇妙さ」を楽しむ形になっていました。このような展示スタイルは、科学教育の普及という側面を持ちつつも、基本的には人々の好奇心を満たすエンターテインメント性が中心に据えられていたのです。
展示コンセプトの変化:分類から生態系へ
20世紀後半に入ると、水族館の展示理念には大きな変革が訪れます。従来の分類別展示に代わって、生態系全体を再現する展示が導入されるようになりました。これを「エコロジカル・コンセプト(ecological concept)」と呼びます(Karydis, 2011)。
エコロジカル・コンセプトとは、自然界に存在する生物たちの相互関係を重視し、「生きた生態系の縮図」を水槽内に再現する発想です。例えば、サンゴ礁の水槽では、多種多様な魚や無脊椎動物、植物が共存し、自然界で見られる捕食や共生の関係までも表現されます。
この転換により、水族館は単に「珍しい動物を見せる場所」から、「自然環境のしくみや生物多様性の大切さを体験的に学ぶ場所」へと役割を変えていきました。生物の名前だけでなく、「なぜその生物がそこにいるのか」「どんなつながりがあるのか」を伝えることが重視されるようになったのです。
また、この変化は来館者の環境意識の高まりにも大きく貢献しました。自然を単なる鑑賞対象としてではなく、守るべき存在として意識させる仕掛けが水族館展示に組み込まれるようになったのです。
教育・研究・保全機能の拡張
展示手法の変化とともに、水族館の持つ社会的機能も大きく広がりました。特に「教育」「研究」「保全」という3つの領域での進展は注目に値します(Hutchins & Smith, 2003;Karydis, 2011)。
教育面では、一般来館者へのガイドツアーだけでなく、学校教育との連携プログラムやワークショップが盛んに実施されるようになりました。環境教育を重視した特別展や、児童・生徒向けの体験学習プログラムなど、水族館は生きた教材の場として教育機関と密接に連携するようになっています。
研究面では、水族館が生態学、生理学、繁殖技術、疾病対策など、さまざまな分野の科学研究の拠点となりつつあります。特に、絶滅危惧種の繁殖や個体群管理(Population Management)に関する研究は、野生生物の保護に直結する重要な取り組みとなっています(Arthington et al., 2016)。
さらに、保全面では、水族館や動物園といった施設で生物を保護・繁殖する「施設内保全(ex situ保全)」と、自然環境下で生物を守る「現地保全(in situ保全)」とを結びつける新たな取り組みが進められています(Minteer & Collins, 2013)。このように、水族館がフィールドワークにも積極的に関わるようになったことで、研究・教育・保全が相互に連動する複合型拠点へと変貌を遂げているのです。
現代水族館の社会的使命
このように、現代の水族館は、単なるレジャー施設ではありません。
公共性、教育、研究、保全という4つの柱を持つ、社会的意義の高い複合施設となっています。
水族館は来館者に楽しい体験を提供しながら、
- 環境保全の大切さを伝え
- 生物多様性の危機に対する意識を高め
- 科学的知見を社会に還元する役割
を果たしています。
また、地域振興や観光資源としての側面も大きく、経済波及効果を持ちながら地域社会との連携も強化されています。
一方で、水生生物の飼育・展示には莫大なコストがかかり、動物福祉や飼育環境に対する倫理的配慮も強く求められます。さらに、気候変動による海水温の上昇など、自然環境の変化も水族館経営に新たな課題を突きつけています。
こうした多様な期待と課題を抱えながら、持続可能で社会に信頼される施設運営を実現していくこと――それが、現代水族館経営の最大の使命であるといえるでしょう。
水族館経営の特殊性
生きた動植物を扱う施設ならではの経営課題
水族館経営の最大の特徴は、他の博物館と異なり、「収集・展示対象が生きた生物である」という点にあります。美術品や歴史資料のような非生物を収蔵・管理する施設とは異なり、水族館では日々呼吸し、成長し、変化する水生生物を相手にしています。
このため、適切な飼育環境を維持しなければ、展示対象そのものが死に至るという、極めてシビアな管理責任を負っています。具体的には、水槽の水温や塩分濃度、酸素濃度などを常に最適な状態に保つ水質管理、栄養バランスを考慮した給餌、疾病の予防・治療、繁殖管理など、きわめて幅広い専門的な飼育業務が日常的に行われています。
特に海水生物を飼育する施設では、人工海水の生成と安定供給が不可欠となり、これに必要な設備投資や維持管理コストは膨大なものとなります。さらに、こうした高度な飼育管理を担うためには、水族飼育員だけでなく、獣医師、環境工学の専門家、電気技師など多様なプロフェッショナルの存在が欠かせません(Karydis, 2011)。
つまり、水族館は単なる展示施設ではなく、「生体維持施設」かつ「教育・研究拠点」という複合的な性格を持つため、その運営はきわめて高度で、かつ繊細なバランス感覚を要求されるのです。
維持運営コストと収益構造の特徴
このような生体管理の特殊性は、水族館の運営コスト構造にも直結しています。水族館は、施設規模や展示内容にかかわらず、常に高額な固定費を抱えています。
たとえば、24時間稼働する水槽のろ過・加温・冷却システム、バックヤードの生体管理設備、照明・空調機器、さらには給餌・清掃・医療行為に伴う消耗品や薬剤費用などが、年間を通じて必要となります。これらは、来館者数の変動に関係なく一定の支出が発生するため、財政的な安定性を確保する上で大きな負担となります。
このため、多くの水族館では、入館料収入への依存度が非常に高くなっています(Hutchins & Smith, 2003)。さらに、グッズ販売、飲食事業、特別展の開催、ナイトアクアリウムなどの体験型イベントを通じて、自主財源の拡大に取り組んでいます。
しかし、これらの収益活動も、社会的使命である教育・研究活動とのバランスを取りながら行う必要があり、単なる「商業施設」としての運営には限界がある点が、水族館経営をより複雑なものにしています。
動物福祉と倫理的責任
現代の水族館経営では、「生き物を適切に飼育しているかどうか」が強く問われる時代に入っています。単に生存させるだけではなく、展示されている生物たちが心身ともに健康で、自然な行動ができる環境にあるかどうかが重要視されるようになりました(Minteer & Collins, 2013)。
この考え方は「動物福祉(アニマルウェルフェア)」と呼ばれ、国際的にも倫理的基準が整備されています。たとえば国際水族館連盟(WAZA)は、加盟施設に対して動物福祉の確保を求めるガイドラインを定めています。
具体的な取り組み例としては、「エンリッチメント(環境充実化)」があります。これは、水槽や飼育空間の中に、探索活動を促すオブジェクトを配置したり、自然に近い採餌行動を促す仕組みを導入することで、生物のストレス軽減や行動多様性を支援する方法です。
水族館はこのような福祉向上に努めつつ、来館者の興味を引く展示も維持しなければならないという、倫理と経営のはざまで非常に繊細な舵取りを求められています。
レジャー施設と教育施設の二重性
水族館は、多くの人にとって「楽しいお出かけ先」というイメージが根付いています。しかしその一方で、環境教育、科学普及、生物保全といった公共的使命も担っています。
この二重性は、施設経営における永遠のテーマといえるでしょう。単なるレジャーとしての娯楽性を追求すれば教育的意義が薄れ、一方で教育・研究に偏重しすぎると来館者数の減少を招くリスクがあります。
たとえば、ショー形式のイルカ展示は高い集客効果を持つ一方で、動物福祉の観点から批判も受けやすくなっています。このような事例は、水族館が持つ社会的期待と経営現実の間での綱渡りを象徴しています(Hutchins & Smith, 2003)。
このジレンマを乗り越えるためには、娯楽と学びを効果的に融合させた展示設計やプログラム開発が不可欠であり、水族館経営には高いクリエイティビティが求められているのです。
危機管理とレジリエンス
水族館経営において、見過ごせないもう一つの特殊性が危機管理とレジリエンス(回復力)の重要性です。
生きた動物を扱う施設である以上、停電、地震、津波、機械トラブル、感染症拡大といったリスクが、直ちに生体の生死に直結します。このため、水族館では災害対応マニュアルの整備、非常用電源設備の設置、災害時対応訓練の実施など、きわめて高いレベルのリスクマネジメントが求められています。
また、2020年以降のコロナ禍は、来館者収入に依存するビジネスモデルの脆弱性を露呈させました。これにより、経済的レジリエンス――たとえばオンラインコンテンツ販売や寄付型ファンディングなど、多様な収益源の確保――が水族館の持続可能性にとって不可欠であることも明らかになりました(Minteer & Collins, 2013)。
水族館は今後、物理的な危機にも、経済的なショックにも耐えられる柔軟な運営体制を構築していくことが求められています。
水族館と博物館経営論の共通性
博物館法における位置づけ
水族館は、その運営理念や社会的役割において、博物館と本質的に多くの共通点を持っています。まず法的側面から見ると、日本の博物館法においても、水族館は「博物館類似施設」として位置づけられています。
博物館法第2条では、博物館の役割について「歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集・保管・展示し、調査研究及び教育普及活動を行う施設」と定義しています。この定義は、単に物を集めて展示するだけでなく、収集・保存・研究・教育普及という一連の機能を総合的に担う施設であることを求めています。
水族館は、展示の対象が生きた水生生物であるという点で特徴的ですが、生体を「資料」とみなして収集・保管し、調査研究を行い、その成果を来館者に伝えるという意味では、博物館法が規定する施設の要件を満たしています。したがって、水族館は単なるレジャー施設ではなく、社会教育機関として法的にも認められた存在であり、博物館経営論の視点から捉えるべき対象であるといえるでしょう。
教育・普及活動の意義
水族館と博物館には、社会に対する教育・普及活動という重要な共通使命があります。いずれの施設も、単なる知識伝達にとどまらず、来館者が自ら発見し、考え、学び取るための場を提供することを目指しています。
たとえば、博物館では常設展や企画展を通じて、歴史や文化、自然科学に関する知見を多角的に紹介しています。同様に水族館でも、海洋環境問題をテーマにした特別展や、学校向けの学習プログラム、参加型ワークショップなどが展開されています。
これらの取り組みの根底にあるのは、「知識を提供する」だけではなく、「気づきのきっかけを与える」という教育哲学です。来館者が水槽越しに魚たちの生態を観察することで、自然環境への興味や問題意識を育む。こうした体験型の学びの提供こそが、博物館と水族館に共通する教育普及活動の核心であるといえます。
また、特に近年では、気候変動や生物多様性の危機といったグローバルな課題をテーマにした展示・プログラムが両者で増加しており、社会的意義のある学びの場としての役割がいっそう重視されています。
研究機関としての役割
水族館と博物館は、教育施設であると同時に、知識の創造拠点でもあります。単に既存の知識を伝達するだけでなく、独自に新たな知見を生み出し、社会に還元する役割を担っています。
水族館では、水生生物の繁殖・生態・疾病に関する研究が広く行われています。特に、絶滅危惧種の人工繁殖技術の開発や、生息地復元プロジェクトへの科学的支援などは、水族館だからこそ可能な実践的な研究領域です。
同様に、博物館も収蔵資料の起源や文化的背景、保存技術に関する研究を進めています。地域史の発掘や考古学的調査、自然史標本の科学分析など、博物館の研究活動は社会の知的基盤を支える役割を果たしています。
このように、「研究成果を社会に還元する」という知的責務において、水族館と博物館は非常に近い存在です。どちらも、教育と研究の両輪を回しながら、公共に対して新たな価値を提供する場であるといえるでしょう。
公共性と社会的使命
水族館と博物館には、公共性という重要な共通理念があります。公共性とは、特定の個人や企業の利益ではなく、広く社会全体の利益のために活動するという姿勢を指します。
博物館が文化遺産や自然史資料を保存し、次世代へ継承する責務を負うように、水族館もまた、貴重な水生生物を保護し、環境保全意識を社会に広めるという使命を持っています。
特に現代では、持続可能な社会形成に向けて、文化・環境・教育の各分野で博物館・水族館の果たす役割がますます重要視されています。単に来館者数を追い求めるのではなく、社会にとって必要な存在であり続けることが、両者に共通する最大の目標です。
また、公共性を維持するためには、収益至上主義に陥ることなく、教育・研究・社会貢献のバランスを適切に保つことが求められます。この点でも、水族館と博物館は極めて近い経営哲学を共有しているといえるでしょう。
経営戦略上の共通課題
最後に、経営の観点からも、水族館と博物館は多くの共通課題に直面しています。
まず、来館者数の確保と社会的使命の両立です。施設の維持・発展には一定の収益が不可欠ですが、収益追求に偏りすぎれば公共性や教育的価値が損なわれるリスクがあります。娯楽性と学術性、楽しさと学びのバランスを取ることは、両者に共通する永続的なテーマです。
また、自主財源確保と公共的価値維持の両立も大きな課題です。財政的自立を目指しつつ、営利活動が教育・研究活動の質を損なわないよう、慎重な戦略設計が必要とされます。
さらに、組織ガバナンスの確立、すなわち透明性・説明責任・倫理性を重視した運営体制の整備も、水族館・博物館双方にとって不可欠です。社会からの信頼を得るためには、経営情報の開示や、倫理的な判断基準に基づく意思決定が求められます。
このように、水族館と博物館は、それぞれ独自の対象と手法を持ちながらも、社会的使命を果たしながら持続可能な運営を追求するという共通の挑戦を抱えているのです。
まとめ:水族館と博物館経営論をつなぐ視点
水族館は、法制度上も博物館類似施設として位置づけられ、単なる娯楽施設ではなく、社会教育機関としての役割を求められています。この点において、歴史・文化・自然科学に関する資料を扱う博物館と、水生生物を対象とする水族館は、本質的に共通する使命を担っているといえます。
特に、教育普及活動や調査研究活動を通じて、来館者の学びを支援し、社会に知見を還元するという営みは、博物館と水族館に共通する根幹的な機能です。さらに、公共性を重視し、営利を目的としない社会貢献型の運営を志向する点においても、両者は同じ理念を共有しています。
経営戦略の面でも、来館者数の確保と社会的使命の両立、自主財源の確保と公共的価値の維持、組織ガバナンスの強化といった課題は、博物館と水族館に共通して存在しています。これらの課題に対して、いかにバランスの取れた対応を図るかは、いずれの施設においても経営の質を左右する重要なポイントとなっています。
もちろん、水族館には「生きた生物を扱う」という特殊性があり、動物福祉や飼育管理といった独自の課題を抱えています。しかし、それらの特殊性を踏まえつつも、博物館経営論が培ってきた知見や理論は、水族館経営の高度化に大いに活用できるものです。
したがって、今後水族館経営を考える際には、博物館経営論の基本理念と経営課題を十分に参照しながら、水族館固有の特性を生かすバランス感覚が不可欠です。博物館と水族館、それぞれの強みと共通性を理解することで、より社会的価値の高い施設運営を目指す道が開かれるでしょう。
参考文献
- Hutchins, M., & Smith, B. (2003). Characteristics of a world-class zoo or aquarium in the 21st century. International Zoo Yearbook, 38(1), 130–141.
- Karydis, M. (2011). Global challenges in freshwater-fish conservation related to public aquariums. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 21, 65–77.
- Minteer, B. A., & Collins, J. P. (2013). Ecological ethics in captivity: Balancing values and responsibilities in zoo and aquarium research under rapid global change. ILAR Journal, 54(1), 41–51.