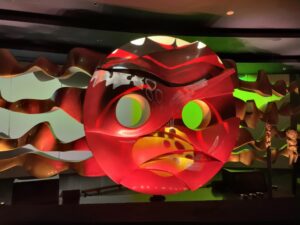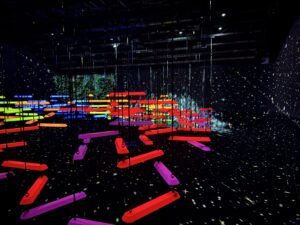導入:ミッションからヴィジョンへ ― 未来を描くということ
博物館は何のために存在しているのでしょうか。この問いに対して、多くの博物館は、自らの「ミッション(使命)」を定めることで、その存在意義を社会に示しています。たとえば、「文化遺産の保存と継承」「地域の歴史と自然を次世代に伝える」「市民の学びや対話の場となる」といった言葉に、博物館が果たすべき役割や理念が込められています。こうしたミッションは、展示や教育、調査研究といった具体的な活動の出発点であり、組織としての価値の根幹をなすものです(Fleming, 2015)。
しかしながら、現代社会において博物館を取り巻く環境は、大きくかつ急速に変化しています。気候変動や人口構成の変化、多様化する市民の価値観、デジタル技術の進展、地域経済や財政状況の制約といった複雑な課題に直面する中で、博物館は単に「何のために存在するのか」だけではなく、「これからどこへ向かおうとしているのか」という視点を持つことが求められるようになっています。つまり、ミッションに加えて「ヴィジョン(vision)」という概念を明確に描く必要があるのです(American Alliance of Museums, 2018)。
ヴィジョンとは、組織が中長期的に目指す未来の姿を明文化したものです。博物館にとってのヴィジョンは、単なる理想像の表明ではなく、「どのような社会課題に向き合い、いかなる価値を提供し続けるのか」という、未来への意思を社会と共有する行為でもあります。ミッションが博物館の「現在地」を示す羅針盤の原点であるとすれば、ヴィジョンはそこから導かれる「目的地」を指し示すものです。そしてその間をどう進むかを設計するのが、戦略計画に他なりません(Lord & Markert, 2017)。
実際、戦略的な博物館経営を行っている多くの機関では、ヴィジョンが組織の意思決定や優先順位の設定、外部との協働のあり方にまで影響を与えています。たとえば、展示のテーマ設定や教育普及プログラムの設計、施設の改修や新館建設、人材育成や資金調達の戦略などは、すべて「私たちはどこに向かおうとしているのか」という問いへの答えと整合的に設計される必要があります。ヴィジョンが不明確であれば、日々の判断や中長期の計画は場当たり的になり、組織としての一貫性や説得力を欠いてしまいます(Bradburne, 2001)。
本稿では、この「ヴィジョン」という概念が博物館経営においてどのような意味を持ち、どのように策定・活用されるのかについて、理論と実践の両面から考察していきます。ミッションを基盤としながらも、未来に向けた戦略と価値創造を導く道標として、ヴィジョンがいかに機能するのか。その構造、プロセス、実例、そして課題を通じて、ヴィジョンの持つ力を見直してみたいと思います。
ヴィジョンとは何か ― 理念を超えた戦略の起点
博物館における「ヴィジョン(vision)」とは、単に理念や夢を語るものではなく、組織が中長期的に目指すべき未来の姿を具体的に描いたものです。来館者や地域社会に対して、どのような価値を提供していきたいのか、また、組織として将来的にどのような存在でありたいのかを、言葉によって明文化したものがヴィジョンです。言い換えれば、「私たちはどこへ向かっているのか?」という問いへの答えが、ヴィジョンなのです(Fleming, 2015)。
ヴィジョンは、ミッション(使命)やバリュー(価値観)とともに、博物館経営における根幹を成す要素のひとつです。ミッションが「私たちはなぜ存在するのか?」という根源的な問いに答えるものであり、バリューが「私たちは何を大切にして行動するのか?」を示すものだとすれば、ヴィジョンは「私たちはどのような未来をつくりたいのか?」という前向きな意志を表現するものです。三者は独立しているようでいて、実際には密接に結びついています。ミッションとバリューに支えられたヴィジョンこそが、戦略や日々の判断を導く「羅針盤」となります(Lord & Markert, 2017)。
たとえば、ある博物館が「地域の文化遺産を保存し、市民に開かれた学びの場を提供すること」をミッションとして掲げているとします。その価値観に「対話」「共創」「多様性の尊重」などが含まれていれば、ヴィジョンとしては「誰もが自らの地域と誇りを持ってつながる、対話型ミュージアムの実現を目指す」といった文言が考えられます。このようにヴィジョンは、ミッションに基づいた将来像を示すとともに、具体的な変化の方向性を社会に伝える役割を果たします。
博物館経営においてヴィジョンが果たす役割は、大きく分けて三つあると考えられます。第一に、組織内部においては、職員一人ひとりの行動や意思決定を統一する「基準」となります。組織が一体となって同じ未来を目指すためには、「何を大切にし、どこを目指すのか」という共通理解が欠かせません。ヴィジョンはそのための道しるべとなります。
第二に、外部の関係者に対しては、博物館がどのような存在でありたいのか、そして何のために活動しているのかを伝える手段となります。ヴィジョンが明確であることで、支援者や協力者、行政、地域住民との信頼関係を築きやすくなり、共感や支援を得る土台にもなります。特に公共性の高い博物館にとって、外部との関係性をデザインするうえで、ヴィジョンは欠かせないツールなのです。
第三に、戦略計画や事業評価において、ヴィジョンは「何をもって成功とするか」を判断する基準になります。どれほど多くの来館者があっても、どれほど多くの展示やイベントを開催しても、それがヴィジョンの実現につながっていなければ、本質的な意味では成果とは言えません。ヴィジョンは、数量的な指標だけでは測れない、組織の方向性と整合した価値創出の判断軸になります(American Alliance of Museums, 2018)。
一方で、ヴィジョンが曖昧であったり、組織の中で共有されていなかったりする場合、さまざまな問題が生じます。展示企画が単発的になり、教育普及の方針も年ごとに変わり、組織としての一貫性が失われてしまいます。これは、来館者や地域社会に対して「この博物館は何を目指しているのか分からない」という印象を与える要因にもなります。また、組織内でも優先順位が見えにくくなり、結果として計画や人材配置、資源投入が場当たり的になる恐れがあります(Bradburne, 2001)。
ヴィジョンは経営者や幹部職員だけのものではありません。本来は、学芸員や教育担当、受付やショップのスタッフまで含め、すべての関係者が「自分たちはどこに向かっているのか」を理解し、共感できるものである必要があります。そして、そのヴィジョンが実現したとき、どのような未来が訪れるのかを、関係者一人ひとりが想像できるようになっていることが理想です。
博物館という公共性の高い文化施設にとって、ヴィジョンは経営理念や広報用の言葉以上の意味を持ちます。それは、未来に向かって社会とどのようにつながり、どのような価値を提供し続けるのかを問い続けるための「共通の物語」であり、未来の来館者や支援者に対する約束でもあるのです。
ヴィジョンはどのように策定されるのか ― 参加と対話のプロセス
ヴィジョンは、ただ経営陣が言葉を考えて発表すればよいというものではありません。むしろ、どのようなプロセスを経てその言葉が形づくられるかこそが重要です。なぜなら、ヴィジョンは組織のすべての人々に共有され、共に目指す未来像である必要があるからです。そのため、策定の過程では「対話」や「参加」が不可欠です。組織の内側と外側の両方からの視点を取り入れ、多様な価値観をつなぎあわせることで、ヴィジョンは初めて“生きた指針”になります。
ヴィジョンを策定する理由にはさまざまなものがあります。たとえば、館長の交代、新しい施設の整備計画、大規模な展示リニューアルなど、組織の転換点に立ったとき、ヴィジョンの見直しや再策定が検討されることが多くなります。また、経営資源が限られる中で「何を優先するか」を判断する基準としても、ヴィジョンは重要です。目的地が明確であればこそ、進むべき道筋も定まりやすくなるのです(Lord & Markert, 2017)。
実際の策定プロセスは、以下のようなステップで進められます。まず初めに行うべきは、組織の現状を丁寧に分析することです。内部の強みや弱み、外部の機会や脅威を整理する「SWOT分析」は、非常に有効な手法です。来館者の傾向、地域との関係、職員の構成やスキル、資金面での状況など、定量・定性の両面から情報を集め、現在の立ち位置を把握します。あわせて、既存のミッションや価値観が現場の実態と一致しているかどうかも再確認します。ここでの分析結果が、ヴィジョンの“足元”となるのです。
次に行うのが、将来像についてのブレインストーミングです。この段階では、まだ答えを急がずに、「私たちの博物館は、10年後にどのような姿になっていたいか」「来館者や地域社会にとって、どんな存在でありたいか」といった問いを軸に、自由に意見を出し合います。ここで重要なのは、現場職員や中堅層、若手スタッフも含め、可能な限り幅広い層を参加させることです。異なる立場や経験を持つ人々の視点が交差することで、ヴィジョンに深みとリアリティが生まれます。
こうして出された多様な意見を整理し、言葉としてのヴィジョン文案に落とし込んでいく作業が続きます。単なる“美しい理想”にならないよう、実現可能性や組織の資源とも照らし合わせながら調整を重ねていきます。また、言葉の選び方も非常に重要です。抽象的すぎても浸透しづらく、具体的すぎると限定的になってしまいます。したがって、「方向性が伝わる」「行動を導く」「共感を生む」ようなバランスが求められます。
完成したヴィジョン案は、関係者との対話を通じてさらに洗練されます。経営陣だけでなく、学芸員、教育普及担当、事務職員、理事会、自治体、場合によっては市民やボランティアとの意見交換の機会を設けることが有効です。近年では、公開ワークショップやパブリックコメントを取り入れる事例も増えており、組織と社会がともに未来を描く場としての役割を果たしています。こうしたプロセスを通じて合意形成を図ることは、ヴィジョンの信頼性と実効性を高めるだけでなく、策定段階からすでに「共有」が始まっていることを意味します(Lord & Markert, 2017)。
たとえば、カナダ自然博物館では、ヴィジョン策定の過程で館内の職員だけでなく、来館者や地域住民、専門家との対話を重ねながら将来像を練り上げました。その結果生まれたヴィジョンは、「科学を通じて自然とのつながりを深め、持続可能な社会の実現に貢献する」という、社会的にも説得力のあるものとなりました。このように、ヴィジョンは単なる言葉ではなく、策定プロセスそのものが組織の学びと変化を促す機会でもあるのです。
また、グッゲンハイム美術館ビルバオでは、都市再生という大きな枠組みの中で、芸術と経済、地域戦略を結びつけたヴィジョンが打ち出されました。「芸術を通じて都市と人々の未来を再構築する」という目標は、美術館単独のヴィジョンではなく、行政や市民社会と連携した長期的ヴィジョンの好例といえます(Lord & Markert, 2017)。
一方で、注意すべき点もあります。経営層による一方的な押し付けになってしまえば、たとえ言葉が立派でも、現場での共感や実行力を得ることは難しくなります。また、理念的すぎて日々の業務に結びつかないヴィジョンも、やがて形骸化し、誰からも参照されない“飾り”になってしまいます(Zolberg, 1981)。
ヴィジョンとは、策定して終わるものではありません。むしろ、そこからが本当のスタートです。定期的に見直し、運用し、問い直し続けることで、ヴィジョンは組織の中に根づき、変化し続ける社会の中でも機能し続けるものとなるのです。つまり、ヴィジョンづくりとは「未来をともに描き続ける営み」であり、博物館が公共性を担う組織である以上、その営みには、組織と社会の双方の参加が不可欠なのです。
ヴィジョンの実践と課題
ヴィジョンは、策定された段階で完成するものではありません。本当に意味のあるヴィジョンとは、組織の中で日々の意思決定や行動に影響を与え、職員一人ひとりの考え方や行動指針として機能するものです。つまり、ヴィジョンが生きているかどうかは、それが「語られているか」ではなく、「使われているか」で判断されるべきなのです(Lord & Markert, 2017)。
ヴィジョンを実際に組織に根づかせるためには、まず職員の日常業務との接点を意識することが重要です。たとえば、展示企画を立てる際に「この展示はヴィジョンの実現にどう貢献するか?」と問い直す習慣を設けることで、ヴィジョンが単なる装飾ではなく判断の枠組みとして機能します(Fleming, 2015)。教育普及、調査研究、広報、施設運営といった異なる部門の間でも、ヴィジョンを「共通言語」として共有できれば、組織全体の連携力は大きく向上します(American Alliance of Museums, 2018)。
実務の場では、ヴィジョンを浸透させるための工夫がさまざまに行われています。たとえば、新任職員研修の中でヴィジョンを深く読み解くセッションを設けたり、各職員が自身の業務目標をヴィジョンと結びつけて記述する仕組みを導入したりする例が挙げられます。また、定例の朝礼や部門ミーティングの冒頭でヴィジョンを確認し、議題と照らし合わせるような実践も有効です。
来館者との関係でも、ヴィジョンを可視化することは大きな意味を持ちます。館内にヴィジョンを掲示する、パンフレットや年次報告書に掲載する、ウェブサイトのトップページに記載するといった方法が考えられます(Fleming, 2015)。さらに踏み込んだ実践としては、来館者の体験そのものがヴィジョンに触れる機会となるよう設計することも可能です。たとえば、展示やイベントに「この活動は〇〇というヴィジョンに基づいています」と明示することで、来館者も博物館の未来像を共有する一員となります(American Alliance of Museums, 2018)。
ロンドン自然史博物館では、ヴィジョンの浸透を目的としてブランド再設計が行われ、館内の掲示物や職員の制服、情報端末の表示に至るまで統一的なメッセージが反映されました。施設全体がヴィジョンを体現する空間となることで、職員と来館者の双方にとって「目指す未来」が日常の中で意識されやすくなります(Lord & Markert, 2017)。
とはいえ、理想と現実の間にはしばしばギャップが存在します。予算や人員、制度上の制約によって、ヴィジョンに基づいた施策が実行できないという声は少なくありません。また、ヴィジョンを掲げても、現場にはその背景が十分に共有されておらず、「やっているつもり」「言っているだけ」といった状態に陥ってしまうこともあります。
このような状況を乗り越えるには、ヴィジョンを一気に実現しようとするのではなく、段階的なステップと柔軟な運用を意識することが必要です。すべてを一度に変えるのではなく、小さな行動や判断にヴィジョンの視点を取り入れることから始めるのです。また、職員自らが策定に関わったヴィジョンであれば、納得感や主体性も高まり、浸透のスピードは格段に上がります。
特に注意したいのは、ヴィジョンの「形骸化」です。これは、ヴィジョンが掲げられていても誰も覚えていなかったり、業務の中でまったく参照されなかったりする状態です。こうした「理念の空洞化」は、ヴィジョンをただの装飾にしてしまうリスクであり、単に言葉を作るだけで満足してしまう組織に見られる傾向でもあります(Bradburne, 2001)。
このような事態を防ぐには、定期的にヴィジョンの内容を見直し、言葉と現実のギャップを確認する機会を設けることが大切です。また、ヴィジョンの背景やストーリーを繰り返し語る「ストーリーテリング」も有効です。理念を抽象的な言葉で終わらせず、具体的な実例やエピソードとして語ることで、職員の理解と共感は深まり、日常の判断にも結びついていきます(Zolberg, 1981)。
最後に、ヴィジョンを「育てる」ものと捉える視点が重要です。社会の状況は日々変化し、博物館の役割や期待もそれに伴って変わっていきます。こうした変化に対応するためには、一度定めたヴィジョンを固定化するのではなく、実践を通して問い直し、必要に応じて再定義する柔軟さが必要です。つまり、ヴィジョンとは“完成された文書”ではなく、“共有される問い”なのです(Lord & Markert, 2017)。
実践し、共有し、問い直し、また実践する。この循環の中でヴィジョンは育ち、組織に根づいていきます。そしてそのプロセスこそが、博物館の持続可能性と公共性を支える経営の基盤になるのです(American Alliance of Museums, 2018)。
おわりに:未来の方向をともに描く
本記事を通じて見てきたように、ヴィジョンは単なる理想を描いた言葉ではありません。それは、博物館という組織が「どこへ向かうのか」「何を目指すのか」を明確に示すものであり、日々の業務や戦略的な意思決定の土台となるものです。経営資源が限られる中で、判断の軸となるヴィジョンを持つことは、選択と集中を可能にし、組織としての一貫性と柔軟性を同時に実現するうえで不可欠です。
ヴィジョンはまた、博物館の公共性を支える約束でもあります。来館者、地域住民、支援者、行政との関係性を築き、信頼を得るためには、組織としての「未来像」を明確にし、それを社会と共有する必要があります。ヴィジョンは、そうした対話の枠組みを提供し、博物館が何のために存在し、どのような価値を生み出そうとしているのかを伝える手段となります。
重要なのは、ヴィジョンを一度定めたら終わりではないということです。むしろ、そこからが本当のスタートです。戦略計画、個別の事業、日常の判断、成果の評価、組織の語るメッセージ――それらすべてがヴィジョンとつながっているかを、常に問い直す必要があります。その問い続ける営みこそが、ヴィジョンを「生きた指針」として育てる唯一の方法です。
そして最後に、ヴィジョンとは一部の人がつくるものではなく、職員や支援者、地域の人々と「ともに描いていく」ものであるという視点が欠かせません。対話の中から育まれ、共有され、変化を許容しながらも、組織の軸となり続ける。それが、信頼され、進化するミュージアムの姿です。
ヴィジョンを描くことは、未来を語ることです。そしてその未来は、博物館に関わるすべての人とともに形づくられていくものなのです。
参考文献
- American Alliance of Museums. (2018). Developing a strategic institutional plan. AAM Press.
- Bradburne, J. M. (2001). A new strategic approach to the museum and its relationship to society. Museum Management and Curatorship, 19(1), 75–84.
- Fleming, D. (2006). Managing change in museums: Key concepts and case studies. In S. Macdonald (Ed.), A companion to museum studies (pp. 296–310). Wiley-Blackwell.
- Lord, G. D., & Markert, K. (2017). The manual of strategic planning for cultural organizations: A guide for museums, performing arts, science centers, public gardens, heritage sites, libraries, archives. Rowman & Littlefield.
- Zolberg, V. L. (1981). Conflicting visions in American art museums. Theory and Society, 10(1), 103–125.