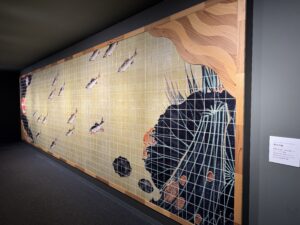はじめに
博物館は一般に、静かで安全な場所という印象を持たれることが多いです。実際、多くの人にとって博物館は穏やかな環境の中で知的な刺激を受けられる空間であり、喧噪や危険とは無縁に見えるかもしれません。しかしその一方で、博物館の内部には常に多様なリスクが存在しています。地震や洪水、火災といった自然災害はもちろんのこと、建物や設備の老朽化、盗難やテロリズムの脅威、保存環境の悪化や人的ミスといった要因も、資料や施設に深刻な損害を与えかねません。
特に博物館が扱う資料の多くは、唯一無二の存在であることにその特性があります。古文書、考古遺物、標本、美術品、写真、映像資料など、これらの多くは複製が不可能であり、喪失すればその意味や価値の再構築は極めて困難です。一度の事故や災害が、長年にわたる収集・研究の成果を一瞬にして奪ってしまう可能性があることは、国内外の事例が繰り返し示しています(Lee & Castles, 2013)。さらに、失われるのは資料だけではありません。博物館が社会から信頼される存在であり続けるためには、資料を守る責任を果たすことそのものが組織の使命と直結しています。
こうした背景から、博物館における危機管理は、単に火災報知器を設置したり避難訓練を行ったりするだけでは足りません。危機管理とは、「予防」「即応」「回復」という一連の段階を含む体系的な取り組みであり、資料の保存だけでなく、人的体制の整備や組織内の情報共有、外部機関との連携も含んだ広範なマネジメント活動です(Dişli & Bacak, 2021)。危機の発生そのものを完全に防ぐことはできませんが、備えの有無によって被害の大きさは大きく変わります。そして、その備えはあらかじめ用意された計画と、日々の業務の中に組み込まれた対応力によって支えられるのです。
本記事では、博物館における危機管理を「組織的アプローチ」としてとらえ、リスク評価の手法や計画の構築方法、さらには実際に危機管理を導入・実践している博物館の事例までを紹介します。特に、イギリスのフィッツウィリアム美術館、カナダのロイヤルBC博物館、トルコのコンヤ考古学博物館など、国際的な事例を通して、多様な組織規模や環境における対応の違いと共通点を明らかにしていきます。危機管理は、単に不測の事態への保険ではなく、博物館が将来にわたってその使命を果たし続けるための基盤であるという認識のもとに、その本質を考えていきたいと思います。
危機管理とは何か ― 博物館における定義と役割
私たちは博物館に対して、安心して過ごせる静謐な空間というイメージを抱きがちです。しかしその一方で、博物館という組織や空間の内部には、日常的にさまざまなリスクが潜んでいます。地震、洪水、火災などの自然災害はもちろんのこと、人的なミスによる事故、設備の老朽化、収蔵庫内の環境異常、さらには盗難やテロリズムといった意図的な加害行為まで、博物館が直面する可能性のある危機は多岐にわたります。しかもその多くは、発生頻度は低いものの、ひとたび起これば甚大な被害をもたらす「ハイインパクト・ローリスク」型の危機である点が特徴的です。
このようなリスクに備えるために必要なのが、危機管理(クライシスマネジメント)です。危機管理とは、突発的に発生しうる危険な事象に対して、被害を最小限に抑え、できるだけ早く通常の活動に復帰するための一連の計画的な取り組みを指します。多くの企業や行政機関で導入されている概念ですが、博物館のように公共的な性格を持ち、かつ代替不能な文化資源を扱う機関においては、その意義は一層大きなものとなります。なぜなら、博物館が管理する資料の多くは一度損傷・喪失すれば、二度と元には戻らず、その資料が持っていた学術的・歴史的・文化的価値が永久に失われてしまうからです。
つまり、博物館にとって危機管理とは、万が一の際に「どう反応するか」だけではなく、日常的に「どう備えるか」「どう防ぐか」、そして「どう回復するか」という広い意味合いをもった活動です。そのため、単なる災害対策ではなく、資料保存、人的体制、組織運営、安全保障、情報共有などを含んだ、包括的で戦略的なマネジメントと位置づける必要があります。危機管理は、計画を立てるだけで機能するものではなく、組織全体が継続的に関与し、実行可能な体制として維持されてはじめて効果を発揮します(Dişli & Bacak, 2021)。
このような考え方を整理する枠組みとして、危機管理は一般に「予防(Preparedness)」「即応(Response)」「回復(Recovery)」の3つの段階に分けて理解されます。第一段階の「予防」では、リスクを見極めて事前に備えることが目的となります。具体的には、建物や収蔵庫の脆弱性の点検、収蔵品のリスト化、職員の避難誘導訓練、連絡体制の整備、外部機関との協定締結などが挙げられます。第二段階の「即応」は、実際に災害や事故が発生した際に、被害を最小限に抑えるための迅速な行動を指します。ここでは、誰がどのような指示を出すか、何を優先的に守るかといった初動体制が明確であることが重要です。そして第三段階の「回復」では、損傷した収蔵品の修復や建物設備の復旧、被害記録の作成、業務再開に向けた調整が行われます。この3段階は単発的な対応ではなく、継続的に点検・改善される「循環するプロセス」であることが求められます(Dişli & Bacak, 2021)。
さらに重要なのは、危機管理が単にモノを守るための技術的措置にとどまらないという点です。博物館は、展示、教育、研究、社会参加といった多様な機能を果たす公共的な文化施設であり、それらの活動を継続していくためには、安全で安定した運営基盤が必要不可欠です。たとえば災害時に来館者をどのように避難させるのか、緊急時の対応指揮系統が明確になっているか、組織内で情報が共有されているかといった点は、博物館の公共性を支える基盤そのものです。危機管理は、資料や建物を守るだけでなく、「博物館の信頼性と社会的責任」を維持するための行動であるといえます。
近年では、気候変動の影響による災害の激甚化、感染症の世界的流行、情報システムの障害、さらには政治的暴力によるテロリズムといった新たな脅威が加わり、博物館のリスク環境はこれまで以上に複雑化しています。こうした状況においては、危機管理を「特殊な時の対策」ではなく、通常の業務の一部として日常的に位置づけておくことが求められます。たとえ小規模であっても、予算や人員に限りがあっても、できる範囲でリスクを認識し、備える意識を持つことが何より大切です。実際、小規模な博物館こそ、危機に対する脆弱性が高いため、最小限でも「いざというときに何ができるか」を明確にしておく必要があります(Gardiner, 2009)。
このように、博物館における危機管理は、単なる防災マニュアルや避難訓練にとどまらず、組織の存続とその社会的使命の継続を支えるための、根幹をなす経営課題のひとつです。次の節では、この危機管理の実効性を高めるために欠かせない「リスク評価」の手法と、その具体的な活用事例について掘り下げていきます。
CPRAMとは何か ― リスクを可視化する方法
危機管理の第一歩は、「何がどの程度危険なのか」を把握することです。しかしながら、博物館におけるリスクは多岐にわたるため、直感や経験に頼った判断だけでは、対策の優先順位をつけるのが難しいという現実があります。火災、地震、水害、盗難、湿度の変化、光による劣化など、それぞれのリスクは発生確率も被害の大きさも異なり、単純に比較することができません。そのため、危機管理の現場では、リスクを「見える化」し、体系的に整理するための評価手法が求められてきました。
こうした背景のもとで開発されたのが、CPRAM(Cultural Property Risk Analysis Model)と呼ばれるリスク評価モデルです。これは、文化財を対象としたリスク評価のために、国際的な保存修復機関であるICCROM(文化財保存修復研究国際センター)と、カナダ保存センター(Canadian Conservation Institute)が共同で開発した方法であり、現在では世界各国の博物館や文化機関で採用されています。CPRAMの最大の特長は、異なる性質のリスクを共通の基準で評価し、定量的に比較できる点にあります。これにより、従来は主観的になりがちだった「どのリスクを優先すべきか」という判断に、客観的な裏付けを与えることが可能となりました。
CPRAMの基本的な考え方は、リスクの大きさを数値で表し、それをもとに意思決定を行うというものです。具体的には、次の4つの要素を掛け合わせることで、リスクの大きさ(MR:Magnitude of Risk)を算出します。
MR = FS × LV × P × Eそれぞれの要素は以下のように定義されます:
- FS(Fraction Susceptible):リスクの影響を受ける資料の割合。たとえば、ある収蔵庫に保管されている資料のうち、湿度変化の影響を受けやすいものがどれだけあるかを示します。
- LV(Loss of Value):その資料が損傷を受けた場合に、どれだけ価値が失われるかの割合。資料の重要性や代替可能性などを考慮して設定されます。
- P(Probability):そのリスクが一定期間内に発生する確率。たとえば、地震の発生頻度や建物の耐震性などを基に判断されます。
- E(Extent):そのリスクを防ぐことの難しさ。たとえば、湿度管理が非常に困難であれば、この値は高くなります。
これらの要素を掛け合わせることで、各リスクの深刻度を一つの数値として算出し、それぞれを横並びで比較することができます(Lee & Castles, 2013)。
CPRAMでは、評価の対象となるリスクを10のカテゴリに分類して整理します。たとえば、火災、地震、水害、極端な湿度変化、温度の上昇、光や紫外線による曝露、昆虫やカビといった生物的要因、盗難や破壊行為、人的ミス、管理体制の不備などが挙げられます。これにより、物理的環境に起因するリスクだけでなく、制度的・人的なリスクも包括的に評価の対象とすることが可能になります。たとえば、「資料が無秩序に積み上げられている」「保管場所が分散しており移動時に損傷リスクが高い」といった管理面の問題も、CPRAMの枠組みの中で扱うことができます。
また、評価作業を円滑に行うために、CPRAMではコレクションを「RACU(Risk Assessment Collection Unit)」と呼ばれる単位に分割して扱います。これは、リスク特性や保存環境、資料の価値などに応じて分類された評価単位であり、それぞれのRACUごとに個別にリスクを評価します。たとえば、「油彩画」「紙資料」「陶器」「写真」といった分類や、特定の収蔵室単位での分割など、現場の事情に応じた柔軟な設定が可能です。このように、コレクションを細分化することで、限られた時間と人材の中でも、効率的かつ戦略的な評価が可能になります。
実際にCPRAMは、実務の現場でも高く評価されています。たとえば、カナダのロイヤルBC博物館では、館全体を対象としてCPRAMを導入し、リスク評価チーム(CRAT)を組織して詳細な分析を行いました。その結果、収蔵庫の空間整理、保存資材の見直し、耐震補強の優先順位づけといった具体的な改善策が導かれています(Lee & Castles, 2013)。
CPRAMの導入によって得られる最大の利点は、博物館が直面するさまざまなリスクを論理的・数値的に比較し、「どこから対策を講じるべきか」という判断を明確にできる点にあります。リスク管理は、ときに感情や経験に左右されがちですが、CPRAMはその意思決定に客観的な根拠を与えてくれます。これは、予算や人員が限られた組織にとって特に重要な機能であり、限られた資源を最大限に活かすための強力なツールとなります。
一方で、CPRAMの導入には一定のハードルも存在します。評価のためには、資料の特性に関する知識、環境条件の測定、リスクに関する統計情報の把握など、多くの準備と時間が必要です。特に小規模な博物館では、人員や専門知識の不足が導入の妨げとなることもあるでしょう。しかし、CPRAMの考え方そのものは、部分的な導入や簡易的な評価にも応用可能であり、外部の専門家と連携することで実施することも十分に可能です。まずは一部の資料群から始めてみる、あるいは過去の事故や損傷の傾向をもとに重点リスクを洗い出すといった形で、段階的に取り入れていくことが現実的なアプローチとなります。
CPRAMは、すべてを数値で管理することが目的ではありません。むしろその真価は、「どのようにリスクを捉え、組織としてどう向き合うか」を問い直すための思考の枠組みにあります。リスクに関する情報を共有し、合理的な対策を協働で進めていく文化を育むことこそが、CPRAMがもたらす最も重要な成果なのです。
実例に学ぶ危機管理の実装 ― 組織的な備えの現場から
危機管理は、計画を策定しただけでは機能しません。いかに綿密なマニュアルや評価手法が整っていても、それが現場で実際に機能しなければ、危機が発生した際に被害を防ぐことはできません。危機管理とは、制度や枠組みの整備とともに、それを支える組織の体制、職員の理解と協働、そして日常業務との統合を通じて初めて実効性を持つものです。本節では、海外の博物館における具体的な実践事例を通して、危機管理がいかに組織の中に実装され、成果を生んでいるのかを詳しく見ていきます。
カナダ・ロイヤルBC博物館 ― CPRAMを活用した全館的リスク評価
最初に紹介するのは、カナダ・ブリティッシュコロンビア州にあるロイヤルBC博物館の事例です。この館では、文化財を対象とした体系的なリスク評価手法であるCPRAM(Cultural Property Risk Analysis Model)を全館的に導入し、全所蔵資料を対象としたリスク評価を実施しました。評価にあたっては、館内の保存科学担当者や収蔵部門の学芸員、建物の管理責任者などから構成される専門チーム「CRAT(Collection Risk Assessment Team)」が編成されました。このチームは、すべての資料を「RACU(Risk Assessment Collection Unit)」という評価単位に分け、それぞれについて火災、湿度変化、振動、害虫被害、盗難などのリスクを個別に評価しました。
評価の結果、特に重大なリスクとして浮かび上がったのが、(1)収蔵庫内の棚の収納密度が高く物理的な破損の危険があること、(2)特定の区域で害虫被害のリスクが高いこと、そして(3)地震に対する建物や什器の耐震性が不十分であるという3点でした。これらの分析結果に基づき、保存資材の刷新、収蔵品の再配置、地震対策の優先順位づけといった具体的な対策が実施されました。特に注目されるのは、これらの改善が単なる現場対応ではなく、組織全体で優先順位を共有し、計画的に段階的実施された点です。評価から実行までのプロセスを組織内で一貫して担える体制が整備されたことで、危機管理が「部門の一部業務」から「全館的な戦略」へと昇華していったのです(Lee & Castles, 2013)。
イギリス・フィッツウィリアム美術館 ― 展示事故から始まった体制強化
続いて、イギリスのフィッツウィリアム美術館における事例をご紹介します。同館は、ケンブリッジ大学の一部門として運営されており、歴史的・芸術的に貴重なコレクションを多数保有しています。この館では、展示中の美術品が展示ケースから落下し、損傷するという事故が発生しました。この出来事を契機に、館内では危機管理体制全体を見直す動きが始まりました。注目すべきは、対応が単なる展示什器の見直しにとどまらず、「事故がなぜ起きたのか」を深く検証し、物理的要因だけでなく組織的要因にまで踏み込んだ再設計が行われた点です。
具体的には、職員間のコミュニケーション体制が不十分で、情報の共有や確認手続きがあいまいだったことが事故の背景にあるとされました。そのため、館では展示準備・変更に関わるプロセスを文書化し、関係者の責任範囲と確認フローを明確化するとともに、危機対応マニュアルの再整備を行いました。さらに、緊急時の対応訓練や報告体制の強化も実施され、「危機管理は全職員の責任である」という共通認識を醸成するための研修も行われました(Muething, 2005)。このように、偶発的な事故をきっかけに、博物館の組織文化そのものを変えていく取り組みへと発展していったのです。危機管理を単なる「防御策」ではなく、「学びと改善のプロセス」として組織的に位置づけた好例といえるでしょう。
トルコ・コンヤ考古学博物館 ― 地震対応を軸とした施設と体制の再設計
3つ目の事例は、トルコにあるコンヤ考古学博物館の取り組みです。トルコは地震多発地帯に位置しており、特に文化財の保護において耐震性の確保は喫緊の課題となっています。同館では、地震を含む自然災害への対応を中心に、保存環境の評価と改善に重点を置いた危機管理体制を整備してきました。具体的には、収蔵庫の構造的な補強、資料の配置変更、落下防止のための棚の固定といったハード面の対応に加え、スタッフの緊急対応体制の構築やマニュアルの整備にも力が注がれました。
また、同館ではスタッフ間で役割分担を明確化し、災害発生時に誰がどのような行動を取るかを事前に定めた行動計画を作成しました。そのうえで、定期的な避難訓練やシナリオに基づくシミュレーションを行い、計画の実効性を確認しながら継続的に改善を重ねていく体制を確立しています。これにより、危機管理は「紙の上の計画」ではなく、「現場で機能する日常的な取り組み」へと発展しました(Dişli & Bacak, 2021)。この事例は、制度と現場の行動が密接に連動しているという点で、災害に強い博物館づくりの一つのモデルを示しています。
共通点と学び ― 危機管理を「実行可能な文化」に
以上の事例から明らかなように、危機管理の実効性は、単に評価を行うことではなく、その結果をもとに具体的な行動に移し、それを継続的に組織の中に定着させるプロセスにかかっています。評価→計画→実行→見直しというサイクルが組織全体で回されていること、そして危機管理が「一部の担当者の業務」ではなく「組織全体の責任」として認識されていることが、成功事例に共通する特徴といえるでしょう。
また、ここで紹介した館はいずれも比較的規模の大きな博物館ではありますが、小規模館にとっても学べる点は多くあります。むしろ限られた人員・予算で運営されているからこそ、リスクの可視化と優先順位づけ、そして実行可能な範囲での着実な改善が重要になります。「まずは何から始めるか」を明確にするための評価、そして小さな改善の積み重ねが、持続可能な危機管理体制の構築へとつながっていきます。
小規模館の現実と課題 ― 制約の中でもできる危機管理の第一歩
危機管理の重要性は、多くの博物館関係者が理解しているところです。しかし、実際の運用となると、とりわけ小規模な博物館にとっては高いハードルが存在します。限られた人員と予算のなかで、展示・教育・管理といった日常業務を回すだけでも手一杯という声は少なくありません。日本国内でも、小規模な地域博物館や資料館は多数を占めており、その多くが非常勤職員中心で運営されているのが実情です。専門的な保存科学の知識や、危機管理計画の策定経験をもつ人材が配置されていないことも多く、「理想的な備え」が遠い目標に見えることは珍しくありません。
しかしながら、たとえリソースに制約があっても、「危機管理はまったくできない」と結論づける必要はありません。むしろ、現実的な制約のなかで「何ができるか」「どこから始めるか」を見極めることこそ、小規模館の危機管理において重要な視点です。小規模館における現実的な危機管理の方法として、「最小限の備えから始める」ことが提案されています(Gardiner, 2009)。たとえば、館内の脆弱なポイントをあらかじめ点検してリスト化することや、災害発生時の連絡先を壁に掲示しておくこと、避難経路を整理し、非常口の前をふさがないように日常的に確認することなど、小さな一歩でも効果は大きいのです。こうした行動は、大きな予算や特別なスキルがなくても始められる、実践的な危機管理の入り口になります。
危機管理の第一歩は、複雑な計画の策定ではなく、館内で「リスクを共有する文化」を育てることにあります。たとえば、月に一度のスタッフミーティングで「最近ヒヤリとしたこと」を共有するだけでも、潜在的なリスクへの意識を高めるきっかけになります。また、緊急時の対応マニュアルを掲示する、館内放送の使い方を確認しておく、連絡ツールを整理するといった「可視化」も、緊急対応の初動に大きな影響を及ぼします。危機はしばしば「想定外」のかたちで現れるものですが、その多くは「予測できたこと」に後から分類されることが少なくありません。だからこそ、「あたりまえ」の日常の中で、どれだけ危機を意識し、共有できているかが重要なのです。
また、小規模館においては、外部との連携によって危機対応力を高めることも大きな戦略となります。たとえば、地域の消防署や警察署と連携し、定期的な防災訓練を実施したり、地元の自治体と協力してハザードマップを共有したりすることは、実効性のある対策につながります。さらに、地域の大学や文化財専門機関とネットワークを持つことで、非常時に助言や支援を得る体制を整えることも可能です。こうした取り組みは、単に災害に強くなるだけでなく、地域との関係性を深めるという副次的な効果ももたらします。危機管理を地域社会との協働のなかで捉えることは、博物館の社会的役割を拡張するチャンスにもなり得るのです。
小規模館における危機管理は、決して「大規模館の真似」ではありません。重要なのは、自館の規模・体制・資源に見合った実行可能な方策を選び、それを継続的に育てていくことです。「完璧な備え」ではなく、「できることから始める」姿勢が、危機管理の第一歩になります。そしてその小さな一歩が、いざというときに組織の行動力を支える基盤となるのです。
計画を「動かす」ための組織的条件 ― 危機管理を機能させるしくみとは
危機管理計画は、ただ存在するだけでは機能しません。多くの博物館では、計画やマニュアルを一応は整備していても、それが日常業務と結びつかず、実際の危機時に活用されないという課題を抱えています。形式的に整備された文書が、現場では忘れられ、訓練も行われないまま時間が過ぎてしまうというのは、決して珍しいことではありません。こうした「動かない計画」が生まれてしまう背景には、内容の複雑さや時間的・人的余裕の欠如だけでなく、組織全体の体制や文化が影響していることが多いのです。危機管理を真に機能させるためには、制度設計だけでなく、それを支える組織のしくみに目を向ける必要があります。
まず重要なのは、危機管理を一部の担当者に任せきりにせず、館全体の取り組みとして進めるための部門横断的な体制づくりです。多くの博物館では、収蔵・展示・教育・施設管理といった部門がそれぞれに分かれていますが、危機が発生した際にはこれらが一体となって対応する必要があります。そのため、事前に各部門をまたぐチームを編成し、役割や責任を明確化しておくことが不可欠です。実際に、小規模館においても職員が複数の業務を兼任していることが多く、それぞれの担当範囲を明文化しておくことで混乱を防ぐことができます。このような部門横断的な協働体制は、危機管理だけでなく、日常業務の円滑化にもつながるとされています(Hunter, 1986)。
次に挙げられるのは、継続的な訓練と職員のモチベーション維持です。計画があっても、職員がそれを理解し、実践できる状態になっていなければ意味がありません。一度きりの研修や講義ではなく、定期的な訓練やシミュレーションを通じて、職員が計画内容を体感し、身につけていくプロセスが求められます。また、危機管理は「本番」が訪れるまで成果が見えにくいため、職員の関心や意欲を持続させる工夫も必要です。たとえば、訓練を定期行事化したり、ヒヤリ・ハット事例の共有を通じて職員同士で気づきを高め合う仕組みを整えたりすることが有効です。これにより、危機管理は「押しつけられた義務」ではなく、「現場のための活動」として位置づけられていきます(Muething, 2005)。
さらに忘れてはならないのが、マネジメント層の理解と支援です。危機管理の成否を大きく左右するのは、トップの関与と支援体制の有無です。組織の上層部が危機管理を重要な経営課題と認識し、予算や時間、人的資源を配分する意思があるかどうかは、現場の実行力に直結します。たとえば、危機管理に関する会議への出席、研修参加の推奨、外部専門家の招聘といった具体的な支援を通じて、マネジメント層が「これは重要だ」と示すことで、組織全体の姿勢も変わっていきます。危機管理を一時的なプロジェクトとしてではなく、継続的な取り組みとして位置づけるためには、このような経営レベルでの支援が不可欠です(Lee & Castles, 2013)。
これらの要素――部門横断の体制、継続的な訓練、マネジメント層の支援――はいずれも、危機管理を「実行可能な計画」として組織に根づかせるための基盤となります。逆にいえば、これらが欠けている限り、どれほど優れた計画を策定しても、それは「動かない計画」にとどまってしまう可能性があります。危機管理は、一部門や特定の担当者の業務ではなく、館全体が関与する組織的営みとして設計されてはじめて、現実の危機に対応できる力を持つのです。
おわりに:危機管理は「生きている計画」である
危機管理計画は、ただ存在するだけでは機能しません。多くの博物館では計画やマニュアルが一度策定されたまま、更新されることなく放置されているケースも少なくありません。紙の上では整っていても、内容が古く、担当者も変わっていて、いざというときに使いものにならない。これは、危機管理が「静的な文書」として扱われてきたことに起因しています。本来、危機管理とは、変化するリスク環境や組織の状況に応じて進化し続ける「動的な文書」であるべきです。定期的な訓練、見直し、評価を通じて、計画が現実に即した形で「生きている」状態を維持することが求められます。
また、危機管理は、展示や教育といった博物館の中核的な活動と同じく、組織の使命を支える重要な要素です。ときに「緊急時にしか使わないもの」として後回しにされがちですが、保存・展示・教育という日常業務を継続するためには、その基盤となる危機対応体制が欠かせません。予算や人員が限られる中で、どの業務を優先すべきかを決めるのは「何が館の使命にとって本質的か」という判断です。その意味で、危機管理は単なる保険ではなく、「公共資源を守り抜く責任」を果たすための業務の一つとして位置づけられるべきです。
危機管理が実効性を持つためには、計画や訓練の仕組み以上に、それが「組織文化として根づいているかどうか」が鍵を握ります。たとえば、毎朝の点検時に非常口を確認する、展示変更時に耐震性を意識する、スタッフ間で気づいたリスクを共有する――こうした日々の小さな行動の積み重ねが、危機に強い組織文化を育てます。いくら精緻なマニュアルがあっても、職員がそれを自分ごととして捉えていなければ、緊急時には役立ちません。危機管理とは、習慣や行動のなかに浸透していくことで初めて機能する「文化」なのです。
すべてを一度に整える必要はありません。むしろ、今できることから着実に始めることが、持続可能な危機管理の出発点です。たとえば、館内の備品を点検して一覧にする、ハザードマップを掲示する、自治体の防災担当と顔をつなぐ。そうした小さな行動の一つひとつが、未来の被害を防ぐ礎になります。そして、危機管理を単なる「防御策」としてではなく、「博物館の未来を守るための投資」として捉えることが、私たちにとって最も大切な視点ではないでしょうか。
危機管理は、静かで地味な活動かもしれません。しかし、それは間違いなく、博物館という公共機関がその使命を果たし続けるための、不可欠な土台です。変化する社会のなかで、リスクをゼロにすることはできません。それでも、備えることはできます。そして、その備えを日々の業務とつなぎ、文化として育てていくことが、これからの博物館経営において最も信頼される姿勢なのです。
参考文献
- Gardiner, H. (2009). Planning for disasters: A how-to-do-it manual for librarians and archivists. Neal-Schuman Publishers.
- Hunter, G. S. (1986). Developing and maintaining practical archives: A how-to-do-it manual. Neal-Schuman Publishers.
- Lee, K., & Castles, J. (2013). Collections risk assessment at the Royal BC Museum. Journal of the American Institute for Conservation, 52(1), 48–59.
- Muething, A. (2005). Risk management in museums: Protecting the collection and the people. Collections: A Journal for Museum and Archives Professionals, 1(2), 45–58.
- Dişli, S., & Bacak, S. (2021). An evaluation of disaster preparedness and response planning in museums: The case of Konya Archaeological Museum. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, 11(4), 463–478.