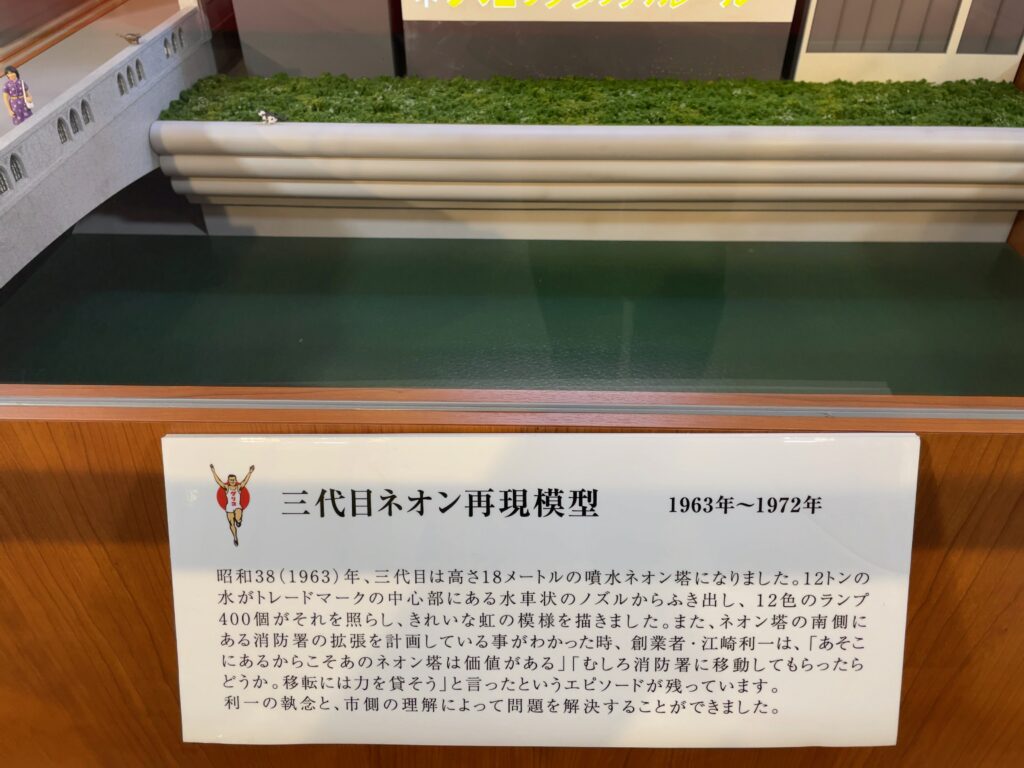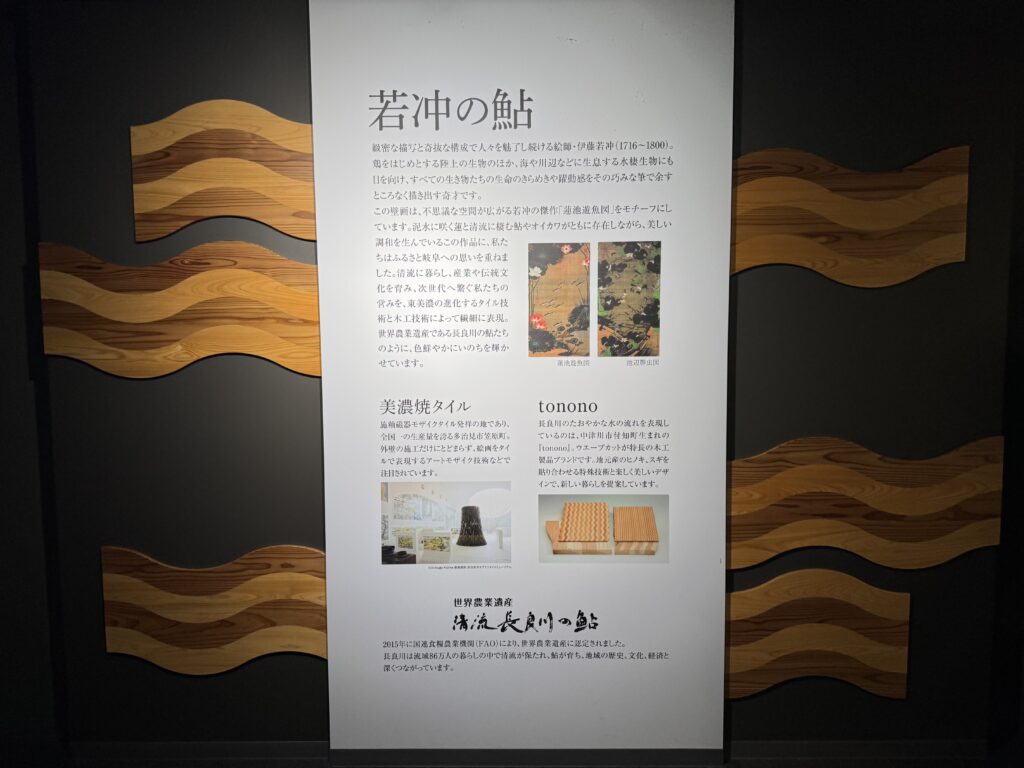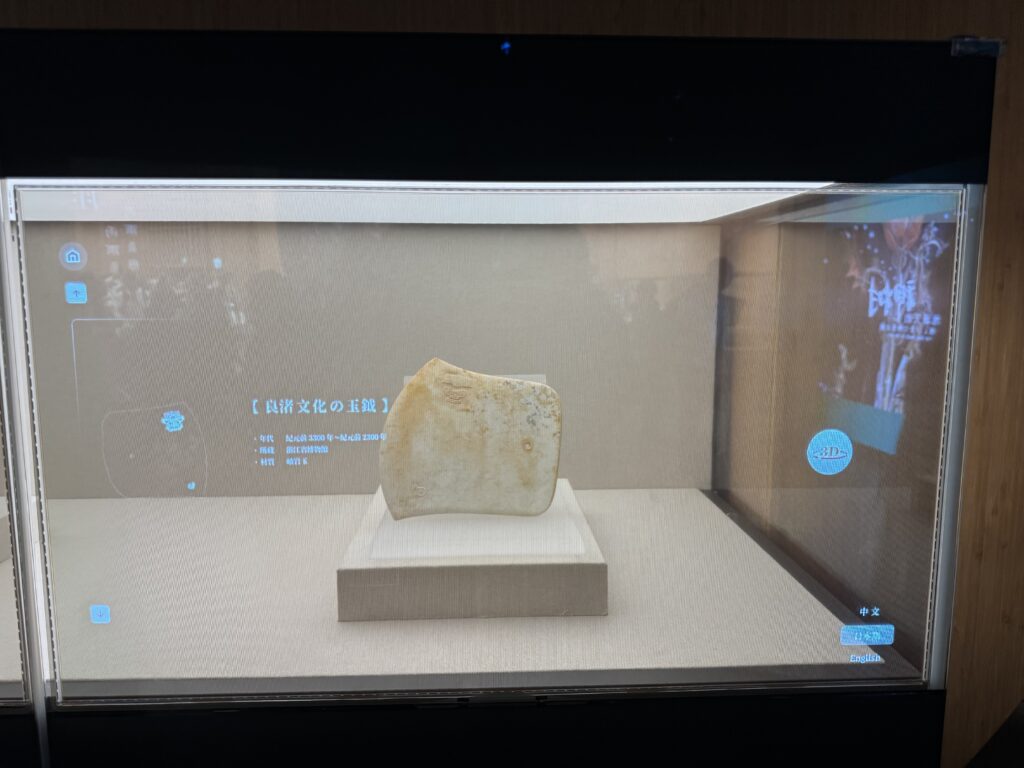博物館展示論– category –
-

来館者体験とは何か ―「意味生成のプロセス」から博物館体験を理解する
来館者体験とは何かが分からなくなる理由 「来館者体験」という言葉は、近年の博物館・美術館をめぐる議論において、ほとんど欠かすことのできないキーワードになっています。しかし一方で、この言葉は非常に使われやすく、同時に分かったつもりになりやす... -

展示解説の歴史とは何か― 博物館におけるラベル・キャプション・解説パネルの成立と変遷 ―
展示解説とは何か 博物館を訪れたとき、多くの人がまず思い浮かべる「展示解説」とは、展示物のそばに置かれた親切な説明文でしょう。作品名や制作年代、簡単な背景知識が書かれており、「読めば分かる」「理解を助けてくれる」ものとして受け取られがちで... -

企業博物館における負の歴史展示は可能か ― Mercedes-Benz Museum の展示デザインから考える
企業博物館はどこまで「負の歴史」を扱えるのか 企業博物館は、企業の歴史や技術の発展を来館者にわかりやすく伝える場として発展してきました。多くの館では、自社の歩みを肯定的に描き、製品の優れた特徴や技術革新の成果を中心に紹介する構造が採られて... -

スミソニアン博物館とトランプ政権 ― 展示への政治的介入と表現の自由を考える
スミソニアン博物館と政治的介入 ― 展示をめぐる最新動向 スミソニアン博物館は、アメリカ合衆国を代表する文化機関として、長年にわたり「国民の記憶」を形成する役割を担ってきました。19の博物館や美術館、国立動物園や研究施設からなるこの巨大な複合... -

博物館でメタ認知能力は伸ばせるのか ― 理論・展示設計・親子の関わりから考える
はじめに メタ認知能力とは、自分や他者の思考プロセスを意識し、その流れをモニターし、必要に応じて修正や調整を行う能力のことです。この力は「考えることについて考える」能力とも表現され、単に知識を得るだけでなく、自分の理解の状態を客観的に把握... -

“読む・語る・記憶する”を生む解説パネルとは? 博物館展示の現場から学ぶ設計術
読まれるパネル・素通りされるパネル――展示解説の現場で見える来館者の多様な行動 博物館や美術館の展示解説パネルの前では、パネルを素通りする人や、立ち止まってじっくり読み込む人など、来館者の反応はさまざまです。こうした光景から、どんなパネルが... -

博物館展示デザインの本質とは ― 理論・視点・原則から考える展示のあり方
博物館展示デザインとは何か 展示デザインの定義と現代的な意義 博物館展示デザインとは、博物館が持つ多様な資料やコレクションを、どのように空間の中で構成し、来館者が主体的に体験し、理解や発見を深められるように設計する一連のプロセスを指します... -

なぜ万博の展示は“忘れられない体験”になるのか ― 博物館展示論から読み解く記憶の力
万博の展示体験はなぜ人々の記憶に深く刻まれるのか 万博を訪れた人々が、何十年経ってもその体験を鮮明に語る光景は珍しくありません。1970年の大阪万博や2005年の愛知万博、さらには1967年のモントリオール万博など、歴史に名を残す博覧会を体験した多く... -

博物館とアイデンティティの構築 ― 国民的・社会的・デジタルな意味生成とその実践
はじめに ― 博物館は「アイデンティティ」をどう形成するか? 博物館は、社会において単なる資料や文化財の収蔵・展示を行う場所ではなく、時代や地域の「意味」を構築し、社会的な価値観や記憶を未来へ伝える重要な機関です。現代においては、「博物館 ... -

博物館疲労(museum fatigue)とは ― 原因・メカニズム・対策と展示デザインの実践ポイント
博物館疲労(museum fatigue)とは ― 定義と基礎知識 博物館疲労の定義と用語の起源 博物館疲労(museum fatigue)という言葉は、博物館を訪れる多くの人が体験する現象を表すために生まれました。最初は欧米の博物館関係者によって用いられ始めた言葉で、... -

動物園におけるアニマルウェルフェアとは ― 福祉と展示のあいだで揺れる経営課題
動物園とアニマルウェルフェア ― なぜいま注目されているのか 現代の動物園は、単なる娯楽施設や動物の展示場ではなく、教育・研究・保全・福祉といった多面的な役割を担う存在として再定義されつつあります。こうした変化の中で、特に注目を集めているの... -

展示の歴史とは何か ― 博物館展示の形式・空間・思想の変遷をたどる
展示史を学ぶ意味 ― なぜ展示の変遷を知る必要があるのか 博物館において展示は、来館者が最も直接的に接する機能であり、「博物館の顔」ともいえる存在です。収蔵や教育、研究などの活動が舞台裏で行われる一方、展示はそれらの成果を可視化し、社会と接... -

展示は社会を映す鏡か? ― 博物館展示と社会性をめぐる意味と構造を読み解く
はじめに:なぜ今「展示と社会性」なのか? 現代社会では、ジェンダー、差別、多文化共生といった社会的課題がますます可視化されるようになりました。そうした文脈の中で、博物館における展示の役割も再定義されています。展示はもはや中立的な情報提供の... -

美術館体験を設計する ― 展示空間と鑑賞行動の科学
なぜ「展示空間の設計」が博物館経営にとって重要なのか 多くの博物館では、良い展示とは展示物の質や学術的価値にあるとされてきました。しかし近年、来館者の体験における満足度や印象は、展示内容そのものよりも、どのように空間が構成され、どのように... -

博物館の展示評価とは何か?― 成果を可視化し、改善につなげる実践ガイド
はじめに:なぜ今、展示評価が必要なのか? 「展示を評価する」という言葉に、どこか違和感を覚える方もいるかもしれません。博物館の展示は、訪れる人に知識や感動を届けることを目的としていますが、その体験を「評価」するという行為は、まるで点数をつ... -

博物館展示における関係者との協力 ― 共創・協働が生み出す新しい展示のかたち
はじめに:展示は「ひとりではつくれない」 博物館の展示は、長らく学芸員の専門的知見に基づいて構成されるものであり、その制作の主導権は館内に完結していることが一般的でした。しかし近年では、この前提そのものが大きく揺らぎつつあります。展示の現... -

子どもにやさしい博物館とは? ― 遊び・学び・親子の体験がつながる空間設計の工夫
はじめに:子どもと博物館 ―「やさしさ」とは何か? 近年、多くの博物館で子ども向け展示やキッズスペースの充実が図られています。家族連れの来館者を意識した体験型の展示が増え、親子で楽しめるイベントやワークショップの導入も一般化しつつあります。... -

ICTを活用した展示とは? ― 博物館が提供する新しい鑑賞体験とその可能性
はじめに:展示体験はどう変わるのか? かつて、博物館の展示は「見ること」を前提とした静的なものでした。展示ケースの中に収められた資料と、その横に添えられた説明文。来館者は、ある程度の知識や文脈理解を前提に、それらを読み取り、自分なりに意味... -

コミュニケーションとしての展示とは何か ― 博物館展示の意味と役割を考える
はじめに:展示は「モノを見せる」だけではない 博物館の展示とは、いったい何のためにあるのでしょうか。多くの方は、「資料を見せるため」「知識を伝えるため」と考えるかもしれません。確かに、展示は貴重な文化財や美術品、自然資料を来館者に提示し、... -

博物館展示の政治性とは何か ― 権力・表象・経済の視点から読み解く
はじめに 博物館は、知識や文化を社会に広く伝える場として、多くの人々に親しまれてきました。展示室を歩きながら、私たちは歴史や美術、自然科学の豊かな世界に触れ、学び、驚き、感動する機会を得ています。博物館は、知識の宝庫であると同時に、公共の... -

博物館展示の歴史とは何か ― 『見せる』から『伝える』への変遷と経営の視点
はじめに 博物館において「展示」は、単なる空間演出や情報提供の手段ではなく、博物館の存在意義や社会的役割を最も端的に表現する中核的な営みです。展示は来館者との対話を生み出す装置であり、知識と文化を社会へと橋渡しする仕組みとして、長い歴史の... -

ミュージアムのインタラクティブ展示の理論と実践
はじめに 博物館の展示は、単に資料を陳列するだけではなく、来館者に対して知的な刺激を与え、学習の機会を提供することが求められています。従来の展示は、展示物をガラスケースの中に収め、それを解説するキャプションとともに提示する形式が一般的でし... -

空港に飛び出すミュージアム
オランダのスキポール空港ではアムステルダム国立博物館のコレクションを色々な角度で楽しむことができる用になっています。 まずスキポール空港のことを簡単に説明するとスキポール空港とはオランダの国際空港で一番大きいものになります。 つまり、オラ...
1