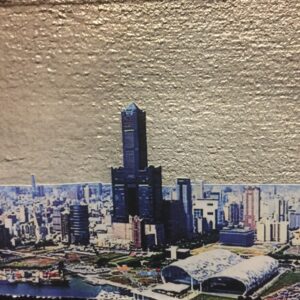はじめに
ミュージアムは単なる文化施設ではなく、都市の象徴的な存在として、観光資源、経済活性化の起爆剤、そして都市空間の再生装置としての役割を果たしています。古代から都市と文化施設は密接な関係を持ち、ルネサンス期のヨーロッパでは美術館や図書館が都市の知的・文化的発展の中心となりました。現代においても、ミュージアムは都市の魅力を向上させる重要な要素として位置付けられています。
特に、近年の都市計画では、ミュージアムを都市のブランド形成や観光誘致に活用する動きが顕著です。例えば、スペインのビルバオでは、グッゲンハイム美術館の建設が都市の経済と文化の再生に大きな影響を与え、「ビルバオ効果」と呼ばれる現象を生み出しました(Plaza & Haarich, 2013)1。このように、ミュージアムは単に文化を保存・展示する場にとどまらず、都市のアイデンティティを確立し、地域経済の発展を支える役割を果たしています。
また、デジタル技術の発展により、ミュージアムの役割はさらに拡大しています。オンライン展示やバーチャルツアーが普及することで、従来の物理的な展示空間を超えた新たな観光・文化体験の提供が可能になりました。特にCOVID-19のパンデミック以降、ミュージアムはデジタル技術を活用しながら、新たな来館者層を開拓する試みを積極的に進めています(Buljubasic et al., 2016)2。
本記事では、世界各地のミュージアムを事例として取り上げ、その経済的・社会的影響を分析します。観光誘致や都市ブランドの形成、地域社会との関係構築など、多角的な視点からミュージアムが都市にもたらす恩恵を考察し、持続可能な都市開発におけるミュージアムの可能性について探ります。
ミュージアムの都市経済への影響
ミュージアムと観光産業
文化遺産観光は都市観光の主要な柱となっており、特に歴史的建造物や美術館、博物館などの文化施設は、多くの観光客を引きつける重要な要素です。観光地としての魅力を高めるだけでなく、宿泊、飲食、交通、土産物販売など、都市の幅広い経済分野にも影響を与えます。
例えば、ニュージーランドの「Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa」は、開館以来、年間約150万人の来館者を記録しており、都市の宿泊産業や飲食業に大きな経済効果をもたらしています(Carey, 2012)3。同美術館では、国の文化遺産を展示するだけでなく、地域特有のアートや歴史的資料を活用した企画展を開催することで、観光客の関心を引き続けています。これにより、ミュージアム単体ではなく、周辺の商業施設や地元経済全体にも利益が波及しています。
また、調査によると、都市訪問者の約50%がミュージアムを訪れることが明らかになっており、これは都市観光の成功にとって文化施設が欠かせない存在であることを示しています(Carey, 2012)4。特に、ヨーロッパや北米の主要都市では、美術館や博物館が観光の目玉となり、観光客の滞在時間を延ばす要因にもなっています。パリのルーブル美術館やアムステルダムのゴッホ美術館のように、都市の象徴となる文化施設は、世界的な観光資源としての役割を果たしています。
ミュージアムクラスターと都市ブランディング
近年、多くの都市では、単体のミュージアムを設立するだけでなく、複数の文化施設を集積させた「ミュージアムクラスター」の形成が進められています。これは、観光客に多様な文化体験を提供し、都市全体のブランド価値を高める狙いがあります。
例えば、アムステルダムの「ミュージアム広場(Museumplein)」には、国立美術館(Rijksmuseum)、ゴッホ美術館(Van Gogh Museum)、アムステルダム市立美術館(Stedelijk Museum)など、世界的に有名な文化施設が集積しています。このクラスター化により、訪問者は1日で複数の施設を巡ることができ、都市の滞在時間を延ばす効果が生まれています(Van Aalst & Boogaarts, 2002)5。観光客にとって利便性が高まるだけでなく、各施設が相互にプロモーションを行うことで、都市全体の観光マーケティングの効果を最大化できます。
同様の成功例として、ベルリンの「ミュージアム・インゼル(博物館島)」が挙げられます。ここには、ペルガモン博物館(Pergamonmuseum)、ボーデ博物館(Bode-Museum)、旧国立美術館(Alte Nationalgalerie)など、ドイツの歴史や文化を代表する施設が集中しています。この地域は、ユネスコ世界遺産にも登録されており、ベルリンの文化的アイデンティティを形成する重要な要素となっています。
また、都市ブランディングの観点から、ミュージアムは地域特有の文化を反映したオリジナル商品や土産品の開発にも注力しています。例えば、サンクトペテルブルクのミュージアムでは、地元の工芸品や歴史的デザインを取り入れた商品を販売し、都市ブランドの形成と観光促進に貢献しています(Trabskaia et al., 2019)6。このように、ミュージアムは観光客に対して地域の文化を印象づける役割を果たし、都市のブランド力を向上させることができます。
ミュージアムの所有形態と経営戦略
ミュージアムの所有形態は、公立・民間・自治体委託など多岐にわたりますが、それぞれの形態によって運営戦略や財務の安定性、観光への影響が大きく異なります。近年では、公的資金に依存しない持続可能な経営モデルが求められており、多くのミュージアムが新たな収益源を模索しています。
イタリアのミュージアムに関する研究では、自治体が独立運営する美術館や、民間企業が運営する施設の方が、政府の文化部門に直接管理されている施設よりも効果的に観光客を引き寄せ、地域経済に貢献していることが明らかになっています(Bertacchini et al., 2018)7。例えば、ローマの「MAXXI(国立21世紀美術館)」は、政府資金だけでなく、企業スポンサーや民間寄付を積極的に活用することで、革新的な展示や教育プログラムを展開しています。
また、民間資本が関与することで、マーケティングやブランディング戦略が強化され、来館者数の増加に繋がることが多いです。例えば、ロンドンの「テート・モダン(Tate Modern)」は、企業スポンサーとの提携を通じて、多様な展示やイベントを開催し、年間500万人以上の訪問者を獲得しています。これに対し、政府直轄のミュージアムは、財政的な制約があるため、企画の自由度が低く、運営が硬直化する傾向があります。
さらに、近年のデジタル化の進展により、オンラインプラットフォームを活用した新たな収益モデルが生まれています。特にCOVID-19の影響で、オンライン展示やバーチャルツアーが急速に普及し、来館者の減少を補う手段として活用されています。このようなデジタル戦略を取り入れることで、物理的な来館者数に依存しない持続可能な運営モデルを確立することが可能となります。
このように、ミュージアムの所有形態や運営戦略は、その成功に直結し、地域経済への貢献度を左右する重要な要素となっています。今後も、民間資本との連携やデジタル技術の活用を通じて、新たなビジネスモデルが求められるでしょう。
都市再生とミュージアム
ビルバオ効果とグローバルネットワーク
スペイン・ビルバオのグッゲンハイム美術館の成功は、都市再生の代表例として広く知られています。1997年に開館したこの美術館は、それまで衰退した工業都市であったビルバオに新たな観光資源を提供し、都市の経済的な復興をもたらしました(Plaza & Haarich, 2013)8。グッゲンハイム美術館の設立は、単に芸術作品を展示する場としてではなく、都市再生プロジェクトの一環として位置づけられ、当時の市政府と国際的な文化機関が連携し、大規模なインフラ整備とともに推進されました。
この成功により、「ビルバオ効果」と呼ばれる現象が生まれ、文化施設が都市のブランド力を向上させ、観光産業を活性化させるモデルケースとして多くの都市に影響を与えました(Plaza & Haarich, 2013)9。ビルバオでは、グッゲンハイム美術館を核とした都市開発が行われ、ホテル、レストラン、商業施設の新設が進み、地域経済全体に波及効果をもたらしました。実際、ビルバオの観光客数は美術館開館前と比較して飛躍的に増加し、年間100万人以上が同美術館を訪れるようになりました。さらに、美術館周辺の地価も上昇し、不動産市場の活性化にも寄与しています。
ビルバオの事例は、文化施設がグローバルなネットワークの一部として機能する可能性を示しています。グッゲンハイム美術館は、ニューヨーク、ヴェネツィア、アブダビなどにあるグッゲンハイム系列の美術館と連携し、国際的な展覧会やアートイベントを開催することで、世界的な文化都市としての地位を確立しました。これは、ミュージアムが地域社会に根ざしながらも、国際的な文化ネットワークの一部として機能し、都市のブランド価値をさらに高める好例と言えるでしょう。
また、「ビルバオ効果」に触発された他の都市も、類似のプロジェクトを推進しています。例えば、フランスのルーヴル・アブダビや、ドイツ・ハンブルクのエルプフィルハーモニーなど、文化施設を活用した都市再生の事例が増えています。これらの成功例から、ミュージアムは単なる文化施設ではなく、都市の競争力を強化し、持続可能な成長を促進する戦略的な要素であることが明らかになっています。
ミュージアムと都市景観
近年のミュージアム建築は、単なる展示スペースではなく、都市空間との融合を図るデザインが求められています。従来の閉鎖的な建物とは異なり、開放的な空間設計が重視され、都市環境と調和しながら、市民や観光客に新たな公共空間を提供する役割を果たしています。
その代表例のひとつが、ローマのMAXXI(国立21世紀美術館)です。建築家ザハ・ハディドによって設計されたこの美術館は、都市空間と一体化した「セミ・アーバン・キャンパス」として構想されました(Tzortzi, 2015)10。このデザインは、従来の美術館のように単に展示を行う場所ではなく、市民が自由に行き来し、芸術や文化と触れ合うことができる開かれた空間として機能しています。館内には、広々としたオープンスペースや屋外展示エリアが設けられ、都市の一部として溶け込むような設計が施されています。
また、都市景観との調和を重視したミュージアムの事例として、ルーヴル・アブダビも挙げられます。この美術館は、アブダビ政府とフランスのルーヴル美術館の協力により設立され、湾岸地域の伝統的な建築様式と近代的なデザインが融合した独特の構造を持っています。美術館のドーム屋根は、日光を透過しながら、イスラム建築の伝統的な装飾模様を彷彿とさせる光のパターンを作り出す設計となっており、地域文化とモダンデザインが調和した建築の成功例となっています。
さらに、ベルギーのM Leuven(ミュージアム・ルーヴェン)は、来館者が都市の風景を楽しめるように設計されています。美術館内の大きなガラス窓からは、ルーヴェン市街を一望でき、都市と文化施設の一体化を強調しています。これにより、美術館は都市のランドマークとしての役割を果たし、観光客にとっても印象的な体験を提供する場となっています(Tzortzi, 2015)11。
都市とミュージアムの関係を考える際に、もう一つ重要なポイントは、ミュージアムが都市の歴史的・文化的なアイデンティティを形成する役割を担うという点です。例えば、ロンドンのテート・モダンは、旧火力発電所をリノベーションして美術館として再生させたものであり、産業遺産を活用した都市景観の一例として知られています。このように、既存の都市資産を活かしながら、文化施設としての機能を持たせることで、都市の景観に新たな価値をもたらすことが可能となります。
また、近年では、デジタル技術を活用したミュージアムが増えており、建物の外観だけでなく、都市空間の中でインタラクティブな体験を提供する試みも進められています。例えば、オランダのNemo Science Museumでは、屋上が展望デッキとして開放されており、都市の風景を眺めながら、科学技術に関するインタラクティブな展示が楽しめるようになっています。このような設計は、ミュージアムが都市景観と調和しつつ、訪問者に新たな体験を提供する可能性を広げています。
このように、現代のミュージアムは単なる展示空間にとどまらず、都市の公共空間としての役割を担いながら、新たな観光資源としての価値を創出しています。今後も、建築デザインや都市計画との連携を強化し、持続可能で魅力的な都市空間の一部として機能するミュージアムのあり方が求められるでしょう。
ミュージアムと地域社会
コミュニティとの連携
都市のミュージアムは、単なる観光施設ではなく、地域住民との関係構築が成功の鍵となります。市民の文化的なアイデンティティを形成し、地域の歴史や伝統を継承する場として、コミュニティと密接に連携することが求められます。そのため、多くのミュージアムが地元の住民やアーティストと協力し、ワークショップや教育プログラム、フェスティバルなどのイベントを開催しています。
例えば、エストニアやハンガリーの美術館では、地域住民と協力したアートプロジェクトや歴史展示を実施し、市民が自らの文化遺産に誇りを持てるような取り組みを行っています(Tali & Pierantoni, 2011)12。エストニアのクム美術館(Kumu Art Museum)では、地域の学校と連携し、子どもたちに芸術の歴史や技法を学ぶ機会を提供しています。また、ハンガリーのリスト音楽院付属博物館では、地域の音楽家と連携し、伝統音楽をテーマにしたライブパフォーマンスを定期的に開催しており、地域住民が積極的に参加する場を提供しています。
さらに、地域住民の意見を取り入れながら展示内容を充実させる手法も増えています。例えば、英国のマンチェスター博物館(Manchester Museum)では、コミュニティの意見を反映した「共創型展示」を導入し、市民が自らのストーリーを展示に組み込める仕組みを構築しました。このような試みは、ミュージアムが一方的に情報を発信する場ではなく、市民との対話を生むプラットフォームとなることを示しています。
また、コミュニティとの連携を深めるため、ミュージアムは無料開放日や地域イベントの開催などを積極的に取り入れています。例えば、米国のスミソニアン博物館(Smithsonian Museums)では、地域住民を対象とした無料入館日を設け、市民が気軽に文化施設を訪れられるよう配慮しています。このような取り組みは、地域住民が文化に触れる機会を増やし、ミュージアムへの親しみを深める効果を生んでいます。
このように、都市のミュージアムは地域住民との結びつきを強化することで、単なる観光施設を超え、地域コミュニティの一部として機能しています。今後は、デジタル技術の活用や、市民参加型の展示の増加が期待されるでしょう。
中小都市におけるミュージアムの役割
中小都市においても、ミュージアムは地域社会に密着し、文化の継承や観光資源として重要な役割を担っています。特に、大都市に比べて観光資源が限られる中小都市では、ミュージアムが地域の特色を活かした文化発信の拠点となることが求められます。
例えば、スペインのタラゴナでは、地元の小規模な美術館が地域社会に密着した活動を行い、市民とのつながりを強化しています(Capriotti, 2010)13。タラゴナ考古学博物館(Museu Nacional Arqueològic de Tarragona)では、地元の歴史を伝える展示を充実させるとともに、地域住民を対象にした考古学体験プログラムを提供しています。これにより、地元住民が自らの地域の歴史に親しみ、観光客とともに文化を共有する機会を増やしています。
また、イタリアのシエナでは、中世の街並みとともに歴史的な美術館や博物館が点在し、地域の文化遺産を活用した観光戦略が進められています。シエナ美術館(Pinacoteca Nazionale di Siena)は、中世の宗教画や地元の芸術家の作品を展示し、地域の芸術文化を後世に伝える役割を果たしています。特に、地域住民がボランティアとして展示解説に参加することで、観光客との交流が生まれ、文化的な対話の場となっています。
さらに、中小都市では、ミュージアムが地域の教育機関や企業と協力し、地域振興に貢献する例も増えています。例えば、スウェーデンのファルン(Falun)にあるダーラナ博物館(Dalarnas Museum)では、地元の伝統工芸であるダーラナホース(Dala Horse)をテーマにしたワークショップを開催し、職人の技術を若い世代に継承する取り組みを行っています。このような活動は、地域の経済にも貢献し、観光客向けの新たな体験型コンテンツを生み出す要因となっています。
中小都市におけるミュージアムのもう一つの特徴は、地域住民の交流の場としての役割を担うことです。例えば、フランスのアルビにあるトゥールーズ=ロートレック美術館(Musée Toulouse-Lautrec)は、地元の文化イベントやコンサートを開催し、地域住民が気軽に集える空間を提供しています。こうした取り組みは、文化施設が地域コミュニティにとって身近な存在となり、市民の誇りやアイデンティティの形成にも寄与します。
さらに、近年では、中小都市のミュージアムがデジタル技術を活用し、観光客の誘致に取り組む例も増えています。例えば、ポルトガルの小都市であるエヴォラ(Évora)では、歴史地区にあるミュージアムが拡張現実(AR)技術を導入し、訪問者がスマートフォンを使って歴史的建造物の再現映像を楽しめる仕組みを導入しました。これにより、限られた展示スペースを補完し、観光客に対して新たな体験価値を提供しています。
このように、中小都市のミュージアムは、地域の文化を発信し、観光資源としての役割を果たすだけでなく、住民の交流や教育、経済活性化にも貢献する多面的な役割を担っています。今後は、地域固有の文化資源を活用し、ミュージアムが持続可能な地域社会の形成に寄与することが期待されます。
ミュージアムのプロモーションとマーケティング
創造産業としてのミュージアムと都市
近年、ミュージアムは単なる文化施設としての役割を超え、都市の創造産業(Creative Industry) のハブとして機能するようになっています。創造産業とは、文化、芸術、デザイン、デジタルコンテンツ、テクノロジーを活用し、新たな経済的価値を生み出す分野を指します。ミュージアムは、都市の創造性を活性化させ、アーティスト、デザイナー、テクノロジー企業とのコラボレーションを促進することで、都市の競争力を向上させる役割を果たしています。
例えば、クロアチアの美術館では、デジタルマーケティングやソーシャルメディアを活用 することで、観光客を引きつける戦略を実施しています(Buljubasic et al., 2016)14。都市の公式プロモーションと連携し、InstagramやFacebook、Twitterを通じて、展覧会の舞台裏や制作プロセスを紹介することで、地域の文化に対する関心を高めています。また、バーチャルツアーやオンライン展示の提供により、物理的に訪問できない観光客にも都市の文化遺産を発信することが可能となりました。
さらに、ミュージアムは、都市ブランドの向上に貢献する文化的なアイコン としての役割を果たしています。ロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館(Victoria and Albert Museum) では、ファッションデザイナーや現代アーティストとのコラボレーションを行い、都市の創造的な魅力を発信しています。都市がミュージアムを戦略的に活用することで、観光客だけでなく、クリエイターや企業を惹きつける効果も生まれています。
また、ニューヨークのMoMA(近代美術館) は、都市の創造産業の中核施設として、ギフトショップをデザインプロダクトの発信拠点と位置づけています。MoMA Design Storeでは、都市のクリエイターが制作した商品を販売し、ミュージアムのブランド力向上と地域経済の活性化に貢献しています。こうした取り組みは、ミュージアムが都市のデザイン文化を支える存在であることを示しています。
さらに、ミュージアムとゲーム・アニメーション産業の連携 も増えています。例えば、フランスのルーヴル美術館 は、人気ゲーム「アサシン クリード」とコラボレーションし、ゲーム内でルーヴルの建築や展示品をリアルに再現しました。このような取り組みは、都市の文化遺産をデジタルコンテンツとして広め、新たな層の観光客を呼び込む効果を生み出しています。
このように、ミュージアムは、都市の創造的な資産を活用し、新たな経済モデルを生み出す場として機能 しています。今後、都市がミュージアムと連携し、デジタル技術を活用した創造的なプロジェクトを推進することで、文化と経済のシナジーを強化することが期待されます。
体験型マーケティングと都市空間の融合
都市におけるミュージアムの役割は、展示の提供にとどまらず、市民や観光客が直接体験できる場を提供すること にシフトしています。これにより、都市とミュージアムの関係は、よりインタラクティブでダイナミックなものになっています。来館者が能動的に関与し、都市の歴史や文化を体験しながら学ぶことができる環境が求められています。
例えば、ベルギーのM Leuven(ミュージアム・ルーヴェン) では、都市の景観とミュージアム空間を統合し、訪問者に新たな体験を提供しています(Tzortzi, 2015)15。AR(拡張現実)やVR(仮想現実)技術を活用し、来館者がスマートフォンを使用して歴史的な都市の風景をリアルタイムで再現できる仕組みを導入。これにより、ミュージアムと都市がシームレスに融合し、新たな観光体験を生み出しています。
また、ニューヨークのアメリカ自然史博物館(American Museum of Natural History) では、VR技術を活用した宇宙探査プログラムを実施し、来館者が仮想空間内で宇宙旅行を体験できるようになっています。このような取り組みは、特に都市観光において、ミュージアムを訪れる理由を強化する重要な要素となっています。
さらに、ロンドンのテート・モダン(Tate Modern) では、来館者が自らアート作品を作成し、それを展示する「参加型アートプログラム」を展開しています。都市の創造的エネルギーを反映したこの取り組みは、ミュージアムが単なる観光施設ではなく、都市住民の創造活動の場 でもあることを示しています。
都市とミュージアムの融合は、食文化や音楽など、他の文化要素との統合 にも広がっています。例えば、フランスのボルドー・ワイン博物館(La Cité du Vin) では、ワインの歴史や製造プロセスを学びながら、試飲体験ができるプログラムを提供。都市の産業と文化を結びつけ、観光資源としての価値を最大化しています。
また、都市空間におけるミュージアムの役割は、デジタル技術の進化とともに変化しています。例えば、オランダのNemo Science Museum では、屋上が展望デッキとして開放され、来館者が都市の景観を眺めながら、科学に関するインタラクティブな展示を体験できるようになっています。このように、都市の風景を取り込みながら、体験型コンテンツを提供するミュージアムが増加 しています。
このように、ミュージアムは単なる展示施設ではなく、都市空間と融合し、市民や観光客が都市の歴史や文化を体験できるインタラクティブな場 へと進化しています。今後は、より高度なテクノロジーの導入や、パーソナライズされた体験プログラムの展開によって、ミュージアムと都市の関係がさらに強化されることが期待されます。
このように、都市とミュージアムの関係は、創造産業や体験型マーケティングを通じて深化 しています。ミュージアムは、都市の文化的・経済的なアイデンティティを形成する要素であり、新たな都市観光のあり方を創出する重要なプラットフォームとなっているのです。
まとめと展望
本記事では、ミュージアムが都市に与える経済的・文化的影響について多角的に考察しました。ミュージアムは単なる文化施設にとどまらず、都市観光の重要な要素として、また都市ブランドを形成するシンボルとして機能しています。さらに、都市再生プロジェクトの中心的な存在として、産業の活性化や都市景観の向上にも寄与しています。
ミュージアムと都市の関係は、歴史的な文脈の中で進化し続けており、近年では地域コミュニティとの連携強化や、創造産業としての役割拡大が顕著です。特に、デジタル技術の進展により、都市におけるミュージアムの役割はこれまでにない変化を遂げています。オンライン展示やバーチャルツアー、インタラクティブなデジタル体験など、来館者の物理的な移動に依存しない新たなミュージアムの形が模索されています。
今後の展望
1. スマートミュージアムの導入
デジタル技術を活用したインタラクティブな展示の強化が求められます。特に、AR(拡張現実)やVR(仮想現実)技術を活用することで、都市の歴史や文化を体験型で学べる環境が整備されつつあります。例えば、ベルギーのMeMuseumでは、来館者が都市の景観と展示をリアルタイムで結びつけることができる仕組みを導入し、都市空間とミュージアムの融合を促進しています(Tzortzi, 2015)16。
また、スマートミュージアムは、単に展示をデジタル化するだけでなく、データ分析を通じて訪問者の行動を把握し、より個別化された体験を提供する可能性を秘めています。ニューヨークのMoMAでは、AIを活用したガイドツアーが導入され、訪問者の興味に応じて最適な展示ルートを提案するシステムが開発されています。こうした技術の進化は、今後のミュージアムと都市の関係をよりダイナミックなものにしていくでしょう。
2. 持続可能な運営モデル
従来、ミュージアムは公的資金に依存する傾向が強かったものの、財政的な課題を背景に、民間パートナーシップや多様な資金調達手法を採用するケースが増えています。特に、企業スポンサーやクラウドファンディング、寄付プログラムの活用が進んでおり、持続可能な運営のための新しい財務モデルが求められています。
例えば、ロンドンのテート・モダンでは、民間企業とのパートナーシップを積極的に活用し、新たな展示スペースの拡張や特別企画展の開催を実現しています。また、ニューヨークのメトロポリタン美術館(Metropolitan Museum of Art)では、サブスクリプション型の会員制度を導入し、安定した収益を確保する試みを行っています。
さらに、エコフレンドリーな展示手法やカーボンニュートラルな運営を実現することで、環境負荷を抑えつつ、ミュージアムが地域社会に貢献するモデルの確立も重要です。パリのルーヴル美術館では、館内のエネルギー使用を最適化する取り組みを進めており、持続可能な文化施設としてのモデルケースとなっています。
3. 地域とのさらなる統合
ミュージアムと都市の関係をより深化させるため、市民参加型プログラムの強化が求められます。特に、地域住民が企画に関与する共創型展示や、地元アーティストとのコラボレーションが都市文化の発展に寄与する重要な要素となっています。
また、ミュージアムは、地域の教育機関や商業施設とも連携し、より広範な都市生活と結びついた形で活動を展開することが重要です。例えば、サンクトペテルブルクのミュージアムでは、地域の伝統工芸品を活用したオリジナル商品の開発を行い、都市ブランドの形成と観光促進に貢献しています(Trabskaia et al., 2019)。
都市におけるミュージアムの役割は、今後ますます多様化していくでしょう。地域社会と共存し、デジタル技術を活用しながら持続可能な運営を模索することで、未来の都市とミュージアムの関係がより強固なものになることが期待されます。
ミュージアムは、都市の文化的・経済的な発展に不可欠な要素であり、観光、都市再生、創造産業の発展に寄与する存在です。デジタル技術の進化や持続可能な運営モデルの導入、市民参加型プログラムの強化によって、都市とミュージアムの関係は今後さらに深化していくでしょう。未来のミュージアムは、単なる展示施設ではなく、都市全体と連携し、新たな価値を生み出す創造的なプラットフォームへと進化していくことが求められています。
参考文献
- Plaza, Beatriz, and Silke N. Haarich. “The Guggenheim Museum Bilbao: Between Regional Embeddedness and Global Networking.” European Planning Studies, vol. 23, no. 8, 2013, pp. 1456-1475.https://doi.org/10.1080/09654313.2013.817543 ↩︎
- Buljubasic, Iva, Marta Boric, and Ivana Hartmann Tolic. “The Impact of Promotion in Creative Industries: The Case of Museum Attendance.” Economic Research, vol. 29, no. 1, 2016, pp. 109-124.https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/ekonomski-vjesnik/article/view/4081 ↩︎
- Carey, Simon, Lee Davidson, and Mondher Sahli. “Capital City Museums and Tourism Flows: An Empirical Study of the Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa.” International Journal of Tourism Research, vol. 14, no. 4, 2012, pp. 1-16.https://doi.org/10.1002/jtr.1874 ↩︎
- Carey, Simon, Lee Davidson, and Mondher Sahli. “Capital City Museums and Tourism Flows: An Empirical Study of the Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa.” International Journal of Tourism Research, vol. 14, no. 4, 2012, pp. 1-16.https://doi.org/10.1002/jtr.1874 ↩︎
- Van Aalst, Irina, and Inez Boogaarts. “From Museum to Mass Entertainment: The Evolution of the Role of Museums in Cities.” European Urban and Regional Studies, vol. 9, no. 3, 2002, pp. 195-209.https://doi.org/10.1177/096977640200900301 ↩︎
- Trabskaia, Iuliia, et al. “City Branding and Museum Souvenirs: Towards Improving the St. Petersburg City Brand.” Journal of Place Management and Development, vol. 12, no. 4, 2019, pp. 529-544.https://doi.org/10.1108/JPMD-06-2017-0049 ↩︎
- Bertacchini, Enrico E., Chiara Dalle Nogare, and Raffaele Scuderi. “Ownership, Organization Structure and Public Service Provision: The Case of Museums.” Journal of Cultural Economics, vol. 42, no. 2, 2018, pp. 1-20.https://doi.org/10.1007/s10824-018-9321-9 ↩︎
- Plaza, Beatriz, and Silke N. Haarich. “The Guggenheim Museum Bilbao: Between Regional Embeddedness and Global Networking.” European Planning Studies, vol. 23, no. 8, 2013, pp. 1456-1475.https://doi.org/10.1080/09654313.2013.817543 ↩︎
- Plaza, Beatriz, and Silke N. Haarich. “The Guggenheim Museum Bilbao: Between Regional Embeddedness and Global Networking.” European Planning Studies, vol. 23, no. 8, 2013, pp. 1456-1475.https://doi.org/10.1080/09654313.2013.817543 ↩︎
- Tzortzi, Kali. “The Museum and the City: Towards a New Architectural and Museological Model for the Museum?” City, Culture and Society, vol. 6, no. 1, 2015, pp. 1-7.https://doi.org/10.1016/j.ccs.2015.07.005 ↩︎
- Tzortzi, Kali. “The Museum and the City: Towards a New Architectural and Museological Model for the Museum?” City, Culture and Society, vol. 6, no. 1, 2015, pp. 1-7.https://doi.org/10.1016/j.ccs.2015.07.005 ↩︎
- Tali, Margaret, and Laura Pierantoni. “New Art Museums in Central and Eastern Europe and the Ideologies of Urban Space Production.” Cultural Trends, vol. 20, no. 2, 2011, pp. 167-182.https://doi.org/10.1080/09548963.2011.563910 ↩︎
- Capriotti, Paul. “Museums’ Communication in Small- and Medium-Sized Cities.” Corporate Communications: An International Journal, vol. 15, no. 3, 2010, pp. 281-298.https://doi.org/10.1108/13563281011068131 ↩︎
- Buljubasic, Iva, Marta Boric, and Ivana Hartmann Tolic. “The Impact of Promotion in Creative Industries: The Case of Museum Attendance.” Economic Research, vol. 29, no. 1, 2016, pp. 109-124.https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/ekonomski-vjesnik/article/view/4081 ↩︎
- Tzortzi, Kali. “The Museum and the City: Towards a New Architectural and Museological Model for the Museum?” City, Culture and Society, vol. 6, no. 1, 2015, pp. 1-7.https://doi.org/10.1016/j.ccs.2015.07.005 ↩︎
- Tzortzi, Kali. “The Museum and the City: Towards a New Architectural and Museological Model for the Museum?” City, Culture and Society, vol. 6, no. 1, 2015, pp. 1-7.https://doi.org/10.1016/j.ccs.2015.07.005 ↩︎