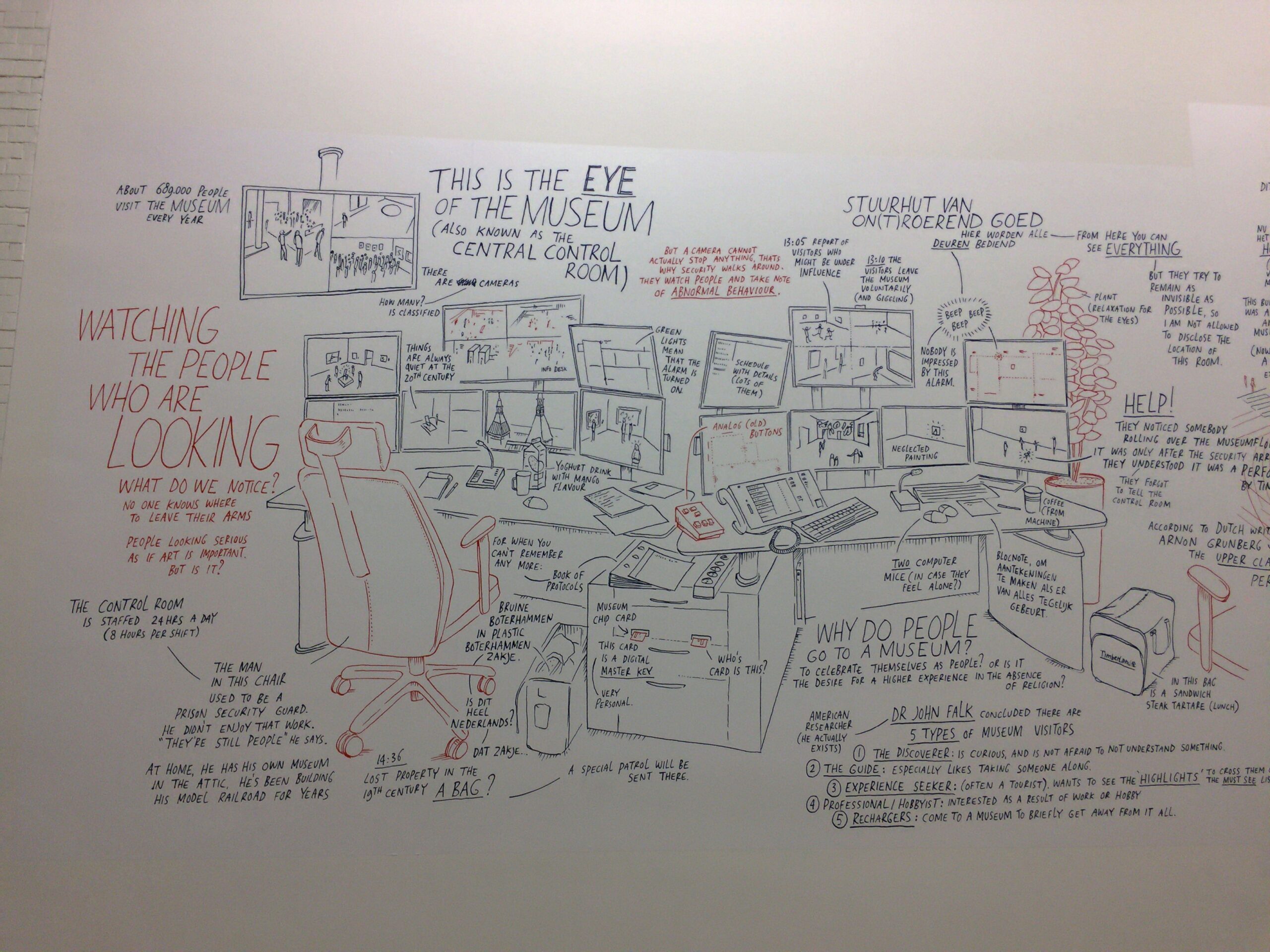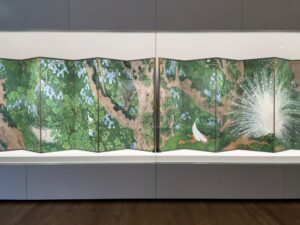はじめに:展示を超えた学びの空間へ
かつて、ミュージアムの主たる使命は「文化財や美術品の収集・保存・展示」にあるとされていました。いわばミュージアムとは、貴重な遺産を厳格に管理し、それを一般に公開することで文化的価値を社会に伝える場であったのです。展示物は、専門知識に基づいて厳選された対象であり、来館者はそれを静かに鑑賞し、知識を受け取る“受け手”として位置づけられてきました。
しかし、21世紀に入り、このような前提は大きく揺らぎ始めています。ミュージアムは、もはや「ものを見せる場所」ではなく、「人が学び、問いを持ち、他者とつながる場」として再定義されつつあります。社会の多様化や教育観の変化、情報技術の進展、そして公共性への関心の高まりなど、さまざまな要因がこの変化を後押ししています。とりわけ近年では、地域社会や学校との連携、異文化交流、世代間のコミュニケーションの促進といった文脈において、ミュージアムが果たすべき役割は、より複雑で広範なものになっています。
このような流れの中で、ミュージアムにおける教育の位置づけも大きく変化しています。教育はもはや付属的なサービスや一部門の業務ではなく、ミュージアム全体を貫く中核的な理念としてとらえられるようになっています。Barbara Franco は、「教育はミュージアムの存在理由そのものである」と明言しており(Franco, 2010)1、この考え方は国際的にも支持を集めています。教育を重視するということは、単に子ども向けのプログラムを充実させることにとどまらず、展示・空間・スタッフ・運営方針のすべてにおいて、「誰が、何を、どのように学ぶのか」という問いを組み込むことを意味しています。
本記事では、ミュージアムにおける教育活動の中でも、特に「学習プログラムの設計」に焦点を当てて考えていきます。学習プログラムは、来館者の知的・感情的・身体的な関与を引き出すための具体的な仕組みであり、同時にミュージアムの教育理念を実際に形にする手段でもあります。ミュージアム教育とは、何を目的とし、どのような理論に基づき、そしてどのように実践されるべきなのでしょうか。本章では、この問いに対して理論と実践の両面からアプローチしていきます。
私たちが特に注目したいのは、「何を学ぶか」という教育内容の選定にとどまらず、「どのように学びが生まれるのか」「その学びは誰の視点から構築されているのか」といった、教育の構造そのものへのまなざしです。つまり、教育を「一方向に与えるもの」ではなく、「ともに構築し、デザインしていくもの」としてとらえる視点が重要になるのです。
この記事の冒頭にこうした視座を据えることは、ミュージアムを単なる教育機関ではなく、参加と探究、そして対話の場として再構成していくための第一歩になると考えています。本章を通じて、教育という営みをあらためて見つめ直し、その本質に迫っていきたいと思います。
ミュージアムと教育の接点 —— 静かな革命
21世紀に入り、教育のあり方そのものが大きな転換期を迎えています。これまで長らく続いてきた「知識を伝達する教育」から、「問いを立て、他者と協働しながら学ぶ教育」へと教育のパラダイムが変化しつつあります。このような変化は、世界各国の教育政策や実践の中に広がりを見せており、学校教育だけでなく、ミュージアムをはじめとするあらゆる学習の場にも影響を与えています。
従来の学校教育では、読み・書き・計算といった、いわゆる「3つのR(Reading, Writing, Arithmetic)」を中心に据え、標準化された知識の習得を目的としてきました。これは、産業社会における人材育成のニーズに応じて構築された教育モデルであり、一定の効率性と秩序を保つうえでは有効な仕組みでした。しかしながら、今日の情報社会やグローバル社会においては、こうしたモデルだけでは不十分であるという認識が広がっています。創造的な思考力や他者との対話力、さらには複雑な問題に柔軟に向き合う姿勢などが、教室の外でも強く求められているのです。
こうした新たな学力像を表すキーワードとして、「4つのC(Communication=コミュニケーション力、Critical Thinking=批判的思考力、Collaboration=協働力、Creativity=創造性)」が国際的に注目されています。これは、OECDやユネスコといった機関が提唱するもので、21世紀を生きる学習者に求められる基礎的な力として位置づけられています。
これらの能力は、学校の教室だけで養われるものではありません。むしろ、教科の枠を超えた総合的な体験や、他者との対話の機会、さらには自分のペースで探究を進められる余白のある学習環境においてこそ、自然に育まれていくものだと言えるでしょう。その意味で、ミュージアムが提供する体験——自由度の高い探索、実物との出会い、解釈や対話を通じた気づき——は、4つのCとの親和性が極めて高いのです(Franco, 2010)2。
たとえば、美術館におけるギャラリートークでは、来館者が作品の背景や作者の意図について学ぶだけでなく、自分自身の感情や経験と重ね合わせながら、独自の解釈を深めていくことが求められます。科学館の実験ワークショップでは、子どもたちが自ら仮説を立て、試行錯誤しながら検証していくプロセスそのものが、学びとなっていきます。いずれの場合も、知識の「正解」を一方的に教えるのではなく、学び手自身の参加と対話を重視している点において、現代の教育理念と深く共鳴しているのです。
しかし一方で、ミュージアムと学校教育のあいだには、いまだに越えがたい壁が存在しているのも現実です。たとえば、教育政策とミュージアムの現場との間には、目的や言語においてズレが生じやすく、両者が協働するための共通の基盤が十分に整っていないという課題があります。学校側にとっても、時間割の制約や予算・人手の不足、カリキュラムとの整合性といった理由から、外部機関と継続的に連携することは容易ではありません。結果として、ミュージアム訪問は「特別な行事」として年に数回実施されるにとどまり、日常的な学びの一部として根づくには至っていないのが実情です。
さらに、日本を含む多くの国々では、「学び」と「遊び」、あるいは「形式的教育」と「非形式的学習」とを明確に分けて捉える傾向があります。そのため、ミュージアムの自由な体験は「教育的ではない」「遊びに過ぎない」と見なされがちです。また、学びの成果がテストの点数や知識量で測られる傾向が根強い限り、ミュージアムとの協働の可能性は限定されたままであるといえるでしょう。
このような現状を踏まえたとき、ミュージアムは自らの教育的役割を再定義し、独自の視点から「学び」を構想し直す必要があります。それは、学校教育の補完にとどまるものではなく、学びの多様性を保障し、社会全体の教育文化を広げていくための先導的な取り組みとして位置づけられるべきです。
教育の主導権を“制度”から“場”へと移していく——そのような静かな革命の舞台として、ミュージアムは今、新たな局面に立たされているのです。
構成主義とミュージアムの学習観
前節で述べたように、現代の教育は大きな転換点に立たされています。その中心には、「学びとは何か」「学習者はどのように知識を得るのか」という根本的な問い直しが存在しています。そしてこの転換には、単なる実践上の工夫だけではなく、理論的な背景が深く関わっています。教育の方法やミュージアムの役割を再定義するためには、まずその基盤となる学習理論の理解が欠かせません。
このような理論的基盤のひとつとして、Eilean Hooper-Greenhillが提唱した「構成主義的アプローチ(constructivist approach)」があります。これは、従来のように教育者や専門家が正しい知識を一方的に伝えるという「伝達モデル(transmission model)」に代わり、学習者自身が経験や背景、興味に応じて能動的に知識や意味を構築していくという考え方に立脚したものです(Hooper-Greenhill, 2000)3。
構成主義では、学習は単なる情報の受け取りではなく、学習者の中で再構成されるプロセスと考えられます。学びは個人の過去の経験、文化的背景、認知的枠組みによって異なり、同じ展示を見ても、そこから導かれる理解や感情は一人ひとり異なるものになります。したがって、教育の場は、画一的な“正解”を提供する場ではなく、それぞれの学習者が自分なりの意味を見出すことを支援する開かれた空間でなければなりません。
この視点に立てば、ミュージアムはもはや「正しい情報をわかりやすく提供する場所」ではありません。むしろそれは、来館者が自らの問いを見つけ、考え、感じ、他者と対話する中で、自分なりの理解や意味を育んでいくための意味生成の場(site of meaning-making)となります。展示や教育活動は、そうしたプロセスを促す“きっかけ”や“触媒(catalyst)”として設計されるべきものなのです。
さらに、学びは個人の内部だけで完結するものではなく、他者とのやりとり、文化的文脈との関係性の中で生成される社会的・対話的プロセスであるという点も、構成主義的立場の大きな特徴です。例えば、美術作品を鑑賞する際に、他の来館者や教育スタッフ、家族との対話を通じて新たな視点に気づいたり、自分の解釈を言葉にすることで理解が深まったりするという現象は、多くの人が日常的に経験していることでしょう。
このような観点から、ミュージアムにおける教育プログラムの設計は、単なる情報伝達や知識の習得を目的とするのではなく、探究心を引き出し、個人の経験と展示との接点をつくり、対話を促す構造として構想されなければなりません。例えば、問いかけのあるキャプション、複数の解釈が可能な展示構成、来館者同士が関われる仕組みなどが、それを実現するための有効な要素です。
構成主義的アプローチは、ミュージアム教育の「何を教えるか」ではなく、「どのように学びを起こすか」という視点を提供します。そしてこの視点こそが、学び手の主体性を尊重し、多様な来館者にとって意味のある教育を実現するための出発点となるのです。
実践例:Museum Makers に見る子ども中心の学び
構成主義的学習理論を具体的に体現した事例として、ニューヨーク科学館(New York Hall of Science)が実施した「Museum Makers」プログラムは、非常に示唆に富む取り組みです(Letourneau et al., 2019)4。このプログラムは、5〜8歳の子どもたちとその家族を対象とした、ミュージアム滞在型のアフタースクール・ワークショップとして設計されました。子どもたちは、館内の展示を観察・分析し、得られたデータを用いて、自らの理想の展示を構想し、模型として表現するという一連のプロジェクト型学習(project-based learning)に取り組みます。
本プログラムでは、以下のような探究的な学びのサイクルが重視されていました。
• 観察と思考:子どもたちはまず、ミュージアムにあるさまざまな展示を観察し、その大きさや色、配置、使用されている素材、さらには来場者の反応や滞在時間といった行動面の特徴に注目しました。大人にとっては見過ごしてしまいがちな細かな点に対しても、子どもたちは鋭く気づき、自発的に問いを立てていきます。たとえば「なぜこの展示の前にたくさんの人が集まっているのだろう?」といった素朴な疑問が、学習の出発点となりました。
• データの活用:立てた問いに対する答えを探るため、子どもたちは実際に情報を収集し、それを図表やリスト、簡単なグラフなどの形で整理しました。ここで注目すべきなのは、数学的な技能や分析力が自然な形で用いられている点です。プログラムは、子どもたちの数的リテラシー(numeracy)やデータリテラシーといった、STEM教育の基盤となる力を、強制的ではなく、遊びの延長として引き出していました。
• 創造と表現:集めた情報と得られた気づきをもとに、子どもたちは「こんな展示があったら面白い」と思うアイデアを自由に発想しました。そして、紙、木材、粘土、デジタルツールなどを使って、それを模型という形で可視化していきました。中には、来館者の流れを考慮して展示の位置や角度を工夫する子どももおり、「学習者としての自分」だけでなく、「設計者(デザイナー)」や「来館者の視点」も同時に持つ姿勢が見られました。
このように「Museum Makers」は、単なる科学知識の導入を目的としたワークショップではありません。むしろ、「展示づくり」というミュージアム固有の活動を媒介として、子どもたちが自ら問いを立て、データを使って仮説を検証し、創造的に表現する一連の学びのプロセスを体験できるように設計されていました。
また、本プログラムの特筆すべき点は、家族も一緒に参加するスタイルであったことです。子どもが主役となりつつも、大人は観察の手助けをしたり、図表を整理するサポートをしたりすることで、家庭内の対話や学びの継続性を自然に促していました。このような学習環境は、親子が「ともに学ぶ」機会を生み出し、家庭の中でも科学的・探究的な視点が根づく基盤となります。
さらに、「Museum Makers」は、子どもたちが自分自身の興味を出発点として学びを進める、いわば子ども中心の学び(learner-centered learning)を実現している点においても重要です。教育が「他者から与えられるもの」ではなく、「自ら構築していくもの」であるという構成主義的な学習観が、子どもたち自身の行動と作品を通じて実際に体現されていました。
このようなプログラムは、教育と展示、制作と評価、自己と他者を結びつけながら、学習の枠を広げる実践として、今後のミュージアム教育に大きな示唆を与えてくれます。知識を“教える”のではなく、学びを“デザインする”という発想が、まさにこのプログラムには凝縮されていたと言えるでしょう。
誰が教育を担うのか —— 教育者の再定義
前節までに見てきたように、ミュージアムにおける教育は、単なる知識の伝達ではなく、来館者一人ひとりが自らの経験や背景に応じて意味を構築していく、対話的で探究的なプロセスとして再定義されつつあります。そしてそのような学びの場を成立させるためには、教育プログラムの設計そのものが構成主義的な観点から工夫されている必要があります。しかし、学びの質を支えるのはプログラムの構造だけではありません。それを構想し、運営し、現場で支える「教育者」自身のあり方も、同じくらい重要な要素です。
ミュージアムにおける教育実践は、人を介して初めて意味を持つものです。展示やワークショップの設計、参加者への声がけ、ファシリテーションのスタイル、教育目標の解釈と実装など、あらゆる段階において、教育者の意図や価値観が反映されます。したがって、誰が教育を担っているのか、つまり「教育者は何者なのか」という問いは、教育の中身やその効果と直結する極めて本質的な問題であるといえます。
この点について、アメリカの美術館教育を専門とする研究者 Dana Kletchka は、極めて示唆的な問題提起を行っています。彼女の調査によると、アートミュージアムに勤務する教育担当者の多くは、中産階級出身の白人女性で構成されており、他の人種的・文化的背景を持つ人々の参加は限られているという現状が浮き彫りになっています(Kletchka, 2021)5。このような構成の偏りは、決して個人の資質や能力の問題ではなく、採用制度、専門職育成の仕組み、文化資本へのアクセスの不均衡といった、構造的な問題に起因するものです。
Kletchkaは、この偏りが教育現場にもたらすリスクとして、無意識のうちに特定の文化的視点や価値観が前提化され、他の視点が見落とされる危険性を挙げています。たとえば、「標準的」な鑑賞態度や「適切な」ふるまいとされるものが、実はある特定の社会階層や文化的背景に根ざした規範であり、それ以外の来館者の感性や態度が“逸脱”とみなされてしまう場合があります。そうした排除は、明示的でなくとも、プログラムや展示、案内の言葉遣い、スタッフの振る舞いなどを通じて伝わり、来館者の居心地の悪さや疎外感につながりかねません。
したがって、ミュージアム教育が本当に多様な来館者に開かれたものであるためには、教育者自身が多様な社会的・文化的背景を持つ人々から構成されていることが不可欠です。それだけでなく、教育者が持つ視点そのものが、特定の枠組みに閉じるのではなく、つねに他者の視点や社会的背景に対して開かれていること、つまり教育者が学び続ける存在であることも重要です。
多文化教育の観点から言えば、教育者は単に「知識の伝達者」ではなく、「文化的仲介者(cultural mediator)」としての役割も果たしています。来館者の多様性に対応し、その経験を尊重しながら学びの場を共に構築していくためには、教育者自身が複数の文化や視点のあいだを行き来できるような感性と態度を備えている必要があります。これは、あらゆるミュージアムにおいて、インクルーシブな教育実践を実現するための鍵ともなるでしょう。
近年では、こうした課題に応えるかたちで、多様な人材の採用、育成、キャリアパスの整備に取り組むミュージアムも少しずつ増えてきました。また、コミュニティと協働するプログラムや、来館者自身が教育活動に参加する共創型の取り組みも広がりを見せています。教育者の役割は変化しつつあり、もはや“教える人”にとどまらず、“共に学び、共に場をつくる人”へと再定義されつつあるのです。
つまり、教育者の「誰であるか」は、「何を、どう学ぶか」に直結する時代が訪れています。ミュージアム教育を真に包摂的で豊かなものとするためには、教育者自身の多様性と変容可能性を認識し、制度として支えていく姿勢が求められているのです。
教育プログラムを「設計する」ということ
ミュージアムにおける教育は、単なる「イベントの提供」や「情報の伝達」ではありません。それは、来館者の能動的な関与を促し、学びを支えるための場や機会を意図的に構成し、デザインする営みです。こうした視点に立ったとき、教育は“偶発的に起こるもの”ではなく、“設計されるもの”として理解されるべきであるという認識が重要になります。
この考え方を裏づける知見のひとつとして、科学館の実践と研究の両面から長年にわたって活動してきたSue Allenの仕事が挙げられます。Allenは、来館者が展示を通じて主体的に関与し、深い学びを得るために必要な要素を、実証的な研究と観察に基づいて抽出しました。そして、効果的な展示や教育環境に共通する4つの条件を以下のように整理しています(Allen, 2004)6。
1. 即時的な理解可能性(Immediate Apprehendability)
展示の意図や操作方法、目的などが、初見でも直感的に理解できるようになっていること。これにより、来館者が“どう関わればよいか”を迷うことなく、自信を持って体験に入っていくことができます。
2. 身体を伴うインタラクション(Physical Interactivity)
単に情報を見る・読むのではなく、身体を使って操作したり実験したりできる設計。身体感覚を通じた関与は、記憶や思考をより深く定着させ、学習を体験的かつ印象的なものにします。
3. 展示全体の概念的一貫性(Conceptual Coherence)
個々の展示要素がバラバラに存在するのではなく、全体として一つのテーマや問いを支えるように構成されていること。訪問者は、自分がどのような学びの流れの中にいるのかを認識できるようになります。
4. 多様な学習者への配慮(Diversity of Learners)
年齢、言語、文化的背景、身体的条件、学習スタイルの違いに対応し、すべての人に学びの機会が開かれていること。包摂的な設計がなされていれば、来館者は自分のペースや関心に合わせて学びを深めることができます。
Allenがこれらの指針を示したのは、展示という具体的な構造物に対する研究の中でのことでしたが、この4つの原則は、ワークショップ、ガイドツアー、教育教材、インタープリターによる対話型活動など、あらゆるミュージアム教育の実践に適用できる汎用的な設計思想といえます。つまり、教育的な場を構築するにあたっては、あらかじめ「どのような学習体験を意図しているのか」「そのためにどのような物理的・心理的環境が必要か」といった視点をもとに、設計・計画・検証のプロセスが求められるのです。
この意味で、「教育とは即興ではなく、構成されるものである」という言葉は、ミュージアム教育の本質を端的に表しています。もちろん、現場での柔軟な対応や、来館者の反応に応じた即興的な調整も重要です。しかしそれは、設計された枠組みの中で起こる“創造的な逸脱”であり、偶然に頼った場当たり的な対応とは根本的に異なります。
また、設計には教育の哲学や価値観が深く反映されるという点も見逃せません。たとえば、どのような問いを中心に据えるのか、どのような順序で体験が展開されるのか、学習成果をどう測るのかといった判断の一つひとつが、ミュージアムの教育観をかたちづくっていきます。来館者に対してどのような“学びの経験”を用意するかという問いは、すなわちミュージアムが「どのような社会を目指すのか」という問いとも重なってくるのです。
したがって、ミュージアムにおける教育プログラムの設計とは、単なる技術やノウハウではなく、文化的・倫理的・社会的意図を伴う創造行為であるともいえるでしょう。設計された空間の中で来館者がどのように意味を見出すのか、その可能性を拓くことこそが、教育のデザインの真の役割なのです。
おわりに:学びを構想するミュージアムへ
ミュージアム教育とは、単に何かを「教える」ことではありません。それは、あらかじめ決められた知識や情報を来館者に一方的に伝える営みではなく、むしろ、来館者一人ひとりが自らの興味や経験、背景をもとに問いを立て、その問いに向き合いながら学びを深めていくプロセスを支える環境を構築することに他なりません。言い換えれば、ミュージアム教育とは、学びのための構造と文脈を「デザイン」する行為なのです。
このデザインには、複数の要素が関与します。たとえば、展示の構成や配置は、来館者の動線や集中力の持続を左右します。プログラムのテーマや進行方法は、参加者の関心の引き出し方を左右します。ファシリテーターの姿勢や言葉の選び方ひとつで、来館者の安心感や参加意欲も変わってくるでしょう。そして、対話やフィードバックの設計は、来館者の思考の深化を促すきっかけとなり得ます。
教育という営みは、それ自体が「学習者中心」であることを求められますが、そこには高度な設計思考と柔軟な対応力が必要です。学びは、来館者とミュージアムとの相互作用の中で生成されていく動的な現象であり、その都度、個々の状況や関係性に応じて変化していきます。だからこそ、教育プログラムや展示の「設計」は、静的な設計図のようなものではなく、“更新されつづける“開かれた構造”として構想される必要があります。
本記事では、ミュージアム教育の現代的な意義と、その理論的背景、実践の枠組みとしての「学習プログラムの設計」という視点を中心に考察してきました。構成主義的学習観が提起する「学びとは構築されるものである」という理念、そして教育者の役割の再定義、多様な来館者に応じたデザイン原則の重要性など、ミュージアム教育の根幹に関わる複数の論点を取り上げてきました。
このように見てくると、ミュージアムにおける学びは決して偶発的なものではなく、意図的に設計され、継続的に問い直されるべき実践であることが明らかになります。そして、その設計は単に施設内の学習機会にとどまらず、学校教育、地域社会、グローバルな課題意識といった外部との関係性の中で構想されていくべきものです。
参考文献
- Franco, Barbara. “Advocacy for Education in Museums.” Journal of Museum Education, vol. 35, no. 3, 2010, pp. 229–236.https://doi.org/10.1080/10598650.2010.11510670 ↩︎
- Franco, Barbara. “Advocacy for Education in Museums.” Journal of Museum Education, vol. 35, no. 3, 2010, pp. 229–236.https://doi.org/10.1080/10598650.2010.11510670 ↩︎
- Hooper-Greenhill, Eilean. “Changing Values in the Art Museum: Rethinking Communication and Learning.” International Journal of Heritage Studies, vol. 6, no. 1, 2000, pp. 9–31.https://doi.org/10.1080/135272500363715 ↩︎
- Letourneau, Susan M., et al. “Museum Makers: Family Explorations of Data Science through Making and Exhibit Design.” Curator: The Museum Journal, vol. 62, no. 4, 2019, pp. 491–512.https://doi.org/10.1111/cura.12348 ↩︎
- Kletchka, Dana Carlisle. “Art Museum Educators: Who Are They Now?” Curator: The Museum Journal, vol. 64, no. 1, 2021, pp. 79–108. Wiley Periodicals.https://doi.org/10.1111/cura.12399 ↩︎
- Allen, Sue. “Designs for Learning: Studying Science Museum Exhibits That Do More Than Entertain.” Science Education, vol. 88, suppl. 1, 2004, pp. S17–S33. Wiley Periodicals.https://doi.org/10.1002/sce.20016. ↩︎