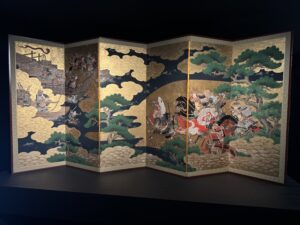はじめに:文化とブランドの交差点
ミュージアムは本来、文化財の収集・保存・研究・展示といった専門的かつ学術的な活動を中心的な使命とする公共性の高い機関として位置づけられてきました。そこでは、人類が築いてきた歴史・芸術・科学の遺産を後世に伝えることが何よりも重要とされ、来館者に対しては知的な教育機会を提供することが第一義的な目的とされてきたのです。そのため、ミュージアムの価値は、所蔵品の質や学術的貢献度、研究成果など、主に内部からの視点で評価されることが一般的でした。
しかし近年、社会的・経済的環境の変化にともない、ミュージアムのあり方にも大きな転換が求められるようになっています。とりわけ、来館者数の伸び悩みや、公共予算の縮小による運営資金の確保といった課題に直面する中で、ミュージアムは自らの存在意義を社会に対して積極的に問い直す必要に迫られています。また、地域社会との連携、観光振興との接続、市民参加の促進など、従来以上に多様な期待が寄せられるようになっており、それに応える形で、ミュージアム自身がより開かれた存在として再構築されつつあります。
このような流れの中で近年とくに注目されているのが、「ミュージアムのブランド化」という概念です。ブランドとは、単なるロゴや視覚的な記号のことではなく、そのミュージアムが社会に対してどのような価値を提示し、どのような体験を通じて記憶される存在であるかという、統合的なイメージやメッセージのことを指します。つまり、「選ばれるミュージアム」であるためには、ブランドを通じて来館者や地域社会に向けて明確な個性や理念を伝える力が不可欠になってきたのです。
本記事では、こうした現代的なミュージアムの課題に応えるため、ブランドという視点からそのあり方を捉え直します。具体的には、ミュージアムにおけるブランドの概念的背景を明らかにするとともに、どのようにしてブランドが形成・運用されていくのか、そのプロセスを理論と事例の両面から検討していきます。あわせて、ブランディングがミュージアムにもたらす社会的・経済的な波及効果にも目を向け、ミュージアムが文化的拠点としてのみならず、地域創生や都市戦略における重要な存在となりうる可能性についても考察していきます。
ミュージアムが「ブランド」として語られる時代
20世紀後半まで、ミュージアムに対する評価は、主にそのコレクションの質や希少性、学術的な研究への貢献度といった要素に集約されていました。つまり、ミュージアムは「知の殿堂」としての役割が重視され、専門家によるキュレーションや研究活動こそが存在意義であり、価値の源泉とされていたのです。
しかしながら、1990年代以降、公共機関全体に広がった「市場化(marketization)」の波は、ミュージアムの世界にも少なからぬ影響を与えるようになりました。この市場化の潮流により、ミュージアムの運営にはマーケティング的な視点が導入されはじめ、運営のあり方そのものが大きく変化してきました。今日では、来館者数や収益性、地域社会への貢献度といった数値的な成果が問われるようになり、ミュージアムは「文化施設」から「文化ビジネス」へと変容を遂げつつあります。
Niall Caldwellはこの変化を「ミュージアムにおけるブランドの出現(The Emergence of Museum Brands)」と表現し、ミュージアムが自らのアイデンティティや理念を社会に向けて発信し、他の施設との差異化を図るためには、「ブランド」の構築が不可欠であると述べています(Caldwell, 2000)1。
このような動向を象徴する代表的な事例として、アメリカ・ニューヨークのグッゲンハイム美術館が挙げられます。同館は、建築家フランク・ロイド・ライトによる象徴的な建築デザイン、革新的な展示構成、さらに国際的な分館展開を通じて、単なる美術館の枠を超えた「ブランドとしてのミュージアム」を確立することに成功しました。スペイン・ビルバオに開館した姉妹館は、建築、文化、観光の要素を融合させ、ミュージアムそのものを「訪れること自体が目的」となるような“目的地(destination)”として位置づけています。こうした戦略は、ブランド化された文化資本の具体例として、各国の注目を集めています。
一方、イギリスの大英博物館は、このような拡張的な展開とは一線を画し、あくまでも学術的厳密性やコレクションの網羅性を中心とした「保守的なブランディング戦略」を堅持しています。同館は年間600万人以上の来館者を迎えており、その魅力の源は知的好奇心を刺激する深い展示内容と、歴史的資料に対する圧倒的な信頼性にあります。このように、大英博物館は「変わらないこと」こそをブランドの中心に据えており、現代のブランディングにおいても多様な戦略が存在することを示しています。
このように、ミュージアムが自らの使命や価値をどのように社会と共有するかを考える上で、「ブランド」は単なる商業的な装飾ではなく、文化的な理念や哲学を可視化し、社会との接点をつくるための重要な手段となっているのです。ロゴやスローガンといった視覚的要素にとどまらず、ブランドはミュージアムの運営哲学や来館者が得る体験のすべてを包括的に伝える「文化的言語」として機能しているといえるでしょう。
ブランド価値を構成する4つの要素
現代のミュージアムにおいて、ブランドの重要性が増す中、その価値をどのように測定・理解するかは極めて重要な課題となっています。ブランドの存在は目に見えるものではなく、来館者の認識や感情、記憶といった主観的・内面的な要素に深く関わっています。そのため、ブランド価値(ブランド・エクイティ)を構成する要素を明確にすることは、戦略的なブランド形成やマネジメントの基盤を整えるうえで不可欠だと言えるでしょう。
この点に関して、Camareroらは、ミュージアムにおけるブランド・エクイティを分析するにあたって、4つの主要な構成要素を提示しています(Camarero, Garrido, & Vicente, 2010)2。それぞれの要素は、来館者の主観的な評価や感情的な結びつきに基づいており、ミュージアムという空間での「体験」がいかにブランドの印象に直結しているかを浮き彫りにしています。
• ブランド・イメージ:これは、来館者がミュージアムという存在に対して抱く総合的な印象や期待を指します。たとえば、「革新的で現代的」「格式高く知的」といったイメージは、事前の情報、メディア露出、他者の口コミなどを通じて形成され、来館前の期待値にも大きな影響を及ぼします。ブランド・イメージは、ミュージアムの第一印象とも言えるものであり、訪問の動機づけに直結する要素です。
• 知覚品質:来館者が実際にミュージアムを訪れた際に体験する内容やサービスの質をどう認識するかを示します。展示の構成や情報の分かりやすさ、学芸員やスタッフの対応、建築や照明、導線の工夫といった物理的・人的サービスのあらゆる側面が対象となります。知覚品質は、来館者の満足度を左右し、ブランドへの信頼感や好意的な評価の形成に大きく寄与します。
• ブランド・バリュー:これは、来館者が入館料や移動時間などの「コスト」と引き換えに得られる価値をどう捉えるかを意味します。たとえば、展示の充実度が高く、学びや感動があれば「支払った価値があった」と感じられ、ブランド・バリューは高まります。また、社会的意義(地域文化の継承や教育的貢献など)を評価する来館者にとっては、金銭以上の価値が見出される場合もあります。
• ロイヤルティ(忠誠心):ミュージアムに対する来館者の継続的な支持の意思を指します。具体的には、再訪意欲の有無や、他者への積極的な推薦の行動が該当します。ロイヤルティの高い来館者は、単に繰り返し訪れるだけでなく、SNSで情報を共有したり、友人や家族に紹介したりすることで、ブランドの認知拡大にも貢献します。ミュージアムにとっては、最も貴重な支持層であり、持続的な関係構築の鍵となる存在です。
これら4つの構成要素は、単独ではなく相互に関係しながら、総合的なブランド価値を形成しています。たとえば、知覚品質が高ければ、ブランド・イメージの向上につながり、やがてブランド・バリューの評価を押し上げ、ロイヤルティの強化へとつながるといった好循環が期待されます。
ミュージアムのブランドとは、単に「有名である」「デザインが美しい」といった表層的な印象にとどまらず、来館者が体験を通じて感じた信頼や共感、満足感といった感覚的・感情的反応の集積によって成立するものです。言い換えれば、ブランドとはミュージアムが「何を展示しているか」ではなく、「来館者に何を感じさせているか」によって築かれる“体験の総体”なのです。
そのため、ブランド価値を高めていくためには、マーケティング部門だけでなく、展示企画や施設管理、教育普及、受付応対といったすべての部門が一体となって、来館者にとっての一貫したポジティブな体験を提供することが求められます。ブランドは、ミュージアムの「顔」であると同時に、「内面」そのものでもあるのです。
内発的ブランド文化と組織マネジメント
ブランド戦略というと、広告や広報活動といった外部に向けた発信に焦点が当たりがちです。しかしながら、ミュージアムにおけるブランドの本質は、単に外部に良い印象を与えることだけではありません。むしろ、ブランドの持続的な価値を生み出し、信頼される存在として定着させるためには、組織内部における文化との一貫性、すなわち「内発的なブランド文化」の構築と、それを支えるマネジメントの在り方が極めて重要になります。
ブランドとは、ロゴやデザインなどの外見的な要素だけでなく、「その組織がどのような価値観を持ち、どのような理念のもとに行動しているか」といった、内面的な姿勢が外部ににじみ出たものでもあります。そのため、外向きのブランド・メッセージと、組織内部の実態との間にズレがあれば、来館者の信頼を損ね、ブランドの信用性が揺らぐことになりかねません。
この点について、Carsten Baumgarthは、ブランド戦略が真に機能するためには、単に表層的な統一感やデザイン性だけでは不十分であり、ブランドの理念が組織内部にまで深く浸透していることが不可欠であると強調しています(Baumgarth, 2009)3。言い換えれば、ミュージアムに勤務するすべてのスタッフが、ブランドが体現する価値観を理解し、それを日々の業務の中で実践している状態が理想であるということです。
たとえば、来館者がミュージアムに対して「居心地がよかった」「信頼できる」「また来たい」と感じるとき、それは必ずしも展示内容や建築の美しさだけによるものではありません。受付での丁寧な対応、展示解説でのわかりやすい言葉遣い、施設内で迷ったときにさりげなく声をかけてくれるスタッフの気配り――そうした日常的な接点のひとつひとつが、来館者の体験をかたちづくり、最終的にミュージアム全体への印象、すなわち「ブランド」そのものへと昇華していくのです。
つまり、ミュージアムにおけるブランド構築は、マーケティング部門や広報担当者だけに任せるべき仕事ではなく、現場で働く全スタッフが参加し、共有するべき「組織的プロセス」であると言えます。職員一人ひとりが、自らの役割を通じてブランドの一部を体現しているという意識を持ち、その行動が全体のブランド価値につながっていることを理解することが重要です。
さらに、こうした内発的ブランド文化の形成には、組織としてのマネジメントの工夫も求められます。例えば、ミッションやビジョンを職員と共有するワークショップの実施、職員教育や人材育成の中にブランドに関する研修を組み込むこと、定期的なフィードバックを通じてブランドの実践度を振り返る仕組みを導入することなどが考えられます。こうした取り組みによって、職員の中に自然とブランド意識が根付き、組織全体として統一感のあるブランド体験が提供できるようになります。
このように、ミュージアムのブランド構築は、見せかけのイメージ戦略ではなく、日々の業務や職員の意識の中に根を張り、時間をかけて育まれていく文化的プロセスです。そのためには、組織の隅々にまで理念が共有され、実践されるようなマネジメント体制と、継続的な努力が欠かせません。ブランドとは、単に語られるべきものではなく、「生きられるもの」である――それが、内発的ブランド文化の本質だと言えるでしょう。
“ライトユーザー”へのアプローチと体験設計
近年、ミュージアムが抱える大きな課題のひとつとして、既存の来館者層にとどまらず、新たな層、特にミュージアムに対する関心が比較的低い層、いわゆる“ライトユーザー”をいかにして引き寄せるかという点が挙げられます。従来の来館者の多くは、歴史や芸術に対して一定の興味や教養を持った“ヘビー・ユーザー”であり、展示の内容そのものに惹かれてミュージアムを訪れてきました。しかし、ライトユーザー層は、知的好奇心よりもむしろ娯楽性や共感性、感覚的な満足といった体験の側面に重きを置く傾向が強く、これまでのミュージアム運営では十分に対応しきれていなかった層でもあります。
こうした背景を受けて、ブランド認知を広げ、新しい来館者層を取り込む戦略として注目されているのが、「体験設計(experiential design)」に基づいた展示手法です。これは、単に情報や知識を伝達することにとどまらず、五感や感情を刺激するような空間演出や参加型の展示構成を通じて、来館者が“体験を通して学び、感じる”ことに重きを置いたアプローチです。
この点について、Ober-Heilig、Bekmeier-Feuerhahn、Sikkengaらによる研究は示唆に富んでいます(Ober-Heilig, Bekmeier-Feuerhahn, & Sikkenga, 2014)4。彼らは、ミュージアムに対する関与度が比較的低いライトユーザー層に焦点を当て、伝統的な展示と体験型展示の効果を比較する実験を行いました。その結果、体験型の展示は、来館者の感情的関与を高めるだけでなく、ブランドの「差別性(distinctiveness)」を印象づけ、再訪意欲やポジティブな口コミ意識の向上にも顕著な効果をもたらすことが明らかになりました。
具体的には、展示空間のデザインやインタラクティブ技術の導入によって、「ただ見る」から「自ら参加する」「感じ取る」といった能動的な体験へと変化させることで、ミュージアムが従来持っていた「静的」「難しそう」「敷居が高い」といった印象を払拭することが可能になるのです。こうした展示は、来館者が記憶に残るユニークな体験を持ち帰ることを可能にし、それがブランドに対する好意や親近感として蓄積されていきます。
このように、体験設計は単なる演出技術ではなく、ブランド構築の本質に深く関わる要素です。ミュージアムのブランドは、もはや「情報を説明するもの」ではなく、「感情を喚起し、印象を残すもの」へとシフトしています。言い換えれば、来館者がそのミュージアムで「何を学んだか」ではなく、「何を感じ、どのように記憶したか」がブランド価値の中心となっているのです。
今後、ライトユーザー層へのアプローチを本格化させていくうえで、ミュージアムには空間デザイン、展示方法、演出技術などを横断的に統合し、総合的な体験価値を提供する力が求められるでしょう。ブランドは“語るもの”ではなく、“感じさせるもの”へ――この変化をどれだけ的確に捉えられるかが、これからのミュージアムにとって大きな分かれ目になるはずです。
ミュージアムブランドと都市戦略
近年、ミュージアムのブランド価値は、単なる文化施設の魅力にとどまらず、地域の都市戦略やまちづくりの方針とも密接に関係する重要な要素として注目されています。特に都市再生や地域経済の活性化といった政策課題において、ミュージアムは「文化的インフラ」としての役割を超え、「都市ブランドの核」として機能するようになってきています。
このような潮流に注目し、世界的なミュージアムの分館誘致が都市再開発戦略の一環として進められている実態に着目し、その背景と影響について詳細に次のように論じられています(Vivant, 2011)5。かつては各都市が自らの文化的独自性や歴史的資源を軸にした博物館や美術館の整備を目指していたのに対し、今日では「すでに国際的な認知を得ているブランド・ミュージアム」の誘致が重視される傾向にあるといいます。これは、都市が自らの個性を内側から育てるのではなく、すでに強固な文化ブランドを“輸入”することで、即効的な集客力と国際的な注目を獲得しようとする戦略の表れです。
代表的な事例としては、フランス北部の旧工業都市ランスにおける「ルーブル・ランス(Louvre-Lens)」の開設が挙げられます。パリのルーブル美術館の分館として2012年にオープンしたこの施設は、もともと経済衰退の進んでいた地域に新たな文化的磁力を創出することを目的とした都市再生プロジェクトの一環として整備されました。ルーブルの名を冠することで、ランスという地方都市に一気に国際的な知名度と文化的格をもたらし、観光客の誘致や地元経済の活性化につながることが期待されたのです。
また、スペイン・バスク地方のビルバオ市における「グッゲンハイム・ビルバオ」も、都市ブランド形成とミュージアム誘致の成功例としてしばしば取り上げられます。1997年の開館以来、同館はその象徴的な建築デザイン(フランク・ゲーリー設計)と、グッゲンハイムという国際的ブランドの力によって、ビルバオという一地方都市を一躍“世界の文化都市”へと押し上げました。この成功は「ビルバオ・エフェクト(Bilbao Effect)」と呼ばれ、以降、他都市においても同様の戦略が模倣されるようになりました。
こうした事例からわかるように、ミュージアムブランドは観光振興や経済成長といった都市の現実的な課題と結びつけられ、単なる文化施設以上の意味と機能を担うようになっています。行政にとっては、世界的ブランドの導入によって都市の外部イメージを刷新し、投資や人材の呼び込みにつなげることができる。また、経済面でも宿泊業や飲食業、交通、商業といった周辺産業への波及効果が期待され、雇用創出にも寄与します。さらには、住民にとっても、国際的に評価される施設が自分たちの街にあることへの誇りや、文化的資源へのアクセス向上といったメリットが得られる可能性があります。
しかし一方で、このような外来型のブランド戦略には課題も伴います。文化的アイデンティティの均質化や、地元の文化資源の軽視、維持費の高騰といったリスクも指摘されています。そのため、誘致されたミュージアムと地域との関係性をどう築き、単なる“ランドマーク”ではなく、地域社会と連携した持続可能な文化的拠点として機能させていけるかが、今後の都市戦略の成否を左右する重要なポイントになるでしょう。
このように、ミュージアムブランドはもはや文化セクターの内部問題にとどまらず、都市政策、観光政策、経済戦略など、さまざまな領域と連携しながら、その都市の未来像を象徴する重要な資源となっています。世界的ブランドをいかにローカルの文脈に落とし込み、地域住民の生活や誇りと結びつけていけるか――その問いに対する答えこそが、文化政策と都市戦略の次なる挑戦であると言えるでしょう。
おわりに:ブランドはミュージアムの「価値の語り手」である
本記事を通じて明らかになったように、ミュージアムにおけるブランドとは、単なるロゴやネーミング、あるいはマーケティング上の装飾ではありません。それはむしろ、ミュージアムが内包する理念、社会的使命、来館者に提供する体験価値、そして地域や世界とのつながりを象徴する、包括的な文化的メッセージであると言えます。ブランドは、「このミュージアムは何のために存在しているのか」「どのような価値を誰に届けようとしているのか」といった根源的な問いに対する、組織全体からの一貫した応答でもあるのです。
今日のミュージアムは、単に展示物を並べる空間ではなくなりました。訪れる人々にとって、それは学びの場であり、癒しの場であり、地域の文化や歴史と出会う舞台でもあります。そして、その多様な機能を有機的に統合し、外部に向けて明確に伝える力を持つのが「ブランド」なのです。ブランドは、ミュージアムが「見せたいもの」だけでなく、「感じさせたいこと」「共有したい価値観」までを含んだ、総体的な語り手としての役割を担っています。
来館者がミュージアムで受け取る印象は、展示内容だけで決まるものではありません。建築空間のあり方、スタッフのふるまい、案内の表現、デジタル技術の活用、地域社会との連携――こうした多くの要素が複合的に絡み合い、来館者一人ひとりに固有の「体験」が生まれます。これらの体験が積み重なり、記憶に残り、やがてミュージアムのブランドとして定着していくのです。したがって、ブランドとは表面的な“外見”ではなく、内側からにじみ出る“人格”であり、日々の実践と対話の中で育まれていく「文化そのもの」であるとも言えるでしょう。
また、ブランドは外部社会との関係性を築くための架け橋でもあります。ミュージアムはしばしば「専門家の領域」と見なされ、一般の人々には距離を感じさせてしまうことがあります。しかし、ブランドが「共感」や「参加」を促すものであれば、その距離は縮まり、より多くの人々にとって開かれた文化の場となることができます。ブランドは、学術と大衆、グローバルとローカル、過去と未来をつなぐための「翻訳者」としての機能も果たしうるのです。
さらに、ブランドは地域とともに成長する存在でもあります。地域の歴史や文化的資源を掘り起こし、それを世界とつなげるための戦略的な媒体として、ミュージアムブランドは都市の価値創造に貢献することができます。都市におけるミュージアムブランドの事例で見たように、施設の存在が都市そのもののアイデンティティや未来像と連動して語られる時代において、ブランドは単なる文化的ラベルではなく、社会を動かす力を秘めた戦略的資産となっているのです。
未来のミュージアムは、「展示」だけでなく、「ブランド」そのものが語りかけ、体験され、記憶される場へと進化していくことでしょう。ブランドは、静的な“表示”ではなく、動的な“対話”であり、来館者一人ひとりとの出会いを通じて日々更新されていく生きた物語です。その物語をいかに豊かに紡ぎ、いかに社会と共有していけるかが、これからのミュージアムの可能性を決定づける鍵となるのです。備したり、章番号や書籍全体の構成に合わせた調整も可能です。必要であればお申し付けください。
参考文献
- Caldwell, Niall G. “The Emergence of Museum Brands.” International Journal of Arts Management, vol. 2, no. 3, Spring 2000, pp. 28–34.https://www.jstor.org/stable/41064698 ↩︎
- Camarero, Carmen, María José Garrido, and Eva Vicente. “Components of Art Exhibition Brand Equity for Internal and External Visitors.” Tourism Management, vol. 31, no. 4, 2010, pp. 495–504.https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.05.011 ↩︎
- Baumgarth, Carsten. “Brand Orientation of Museums: Model and Empirical Results.” International Journal of Arts Management, vol. 11, no. 3, 2009, pp. 30–45.https://www.jstor.org/stable/41064996 ↩︎
- Ober-Heilig, Nadine, Sigrid Bekmeier-Feuerhahn, and Joerg Sikkenga. “Enhancing Museum Brands with Experiential Design to Attract Low-Involvement Visitors.” Arts Marketing: An International Journal, vol. 4, no. 1/2, 2014, pp. 67–86.https://doi.org/10.1108/AM-01-2014-0006 ↩︎
- Vivant, Elsa. “Who Brands Whom? The Role of Local Authorities in the Branching of Art Museums.” Town Planning Review, vol. 82, no. 1, 2011, pp. 99–115.https://doi.org/10.3828/tpr.2011.6 ↩︎