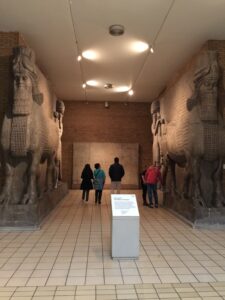現代において、ミュージアムの存在意義は、これまで以上に多角的かつ深く問われるようになっています。高度経済成長期以降、多くの国や地域では、ミュージアムが知識や芸術文化を収蔵・保存・展示するための「専門機関」として整備されてきました。来館者はそこに足を運び、過去の遺産を「鑑賞する」ことによって学び、感動し、教養を深めてきました。しかし、21世紀に入り、社会構造や価値観が大きく変化する中で、ミュージアムが担うべき役割はより複雑で多様なものへと変貌しています。
今、私たちがミュージアムに求めるものは、単なる「展示の場」や「モノを保存する場所」としての役割にとどまりません。たとえば、地域社会における対話の場としての機能、異なる文化的背景を持つ人々をつなぐ橋渡しとしての役割、あるいは、過去と現在、そして未来を結び付ける公共的空間としての可能性など、ミュージアムに期待されるミッションはますます拡張しています。
では、こうした変化の中で、ミュージアムが自らの立ち位置や社会的価値を見つめ直すための「核」とは何でしょうか。その答えの一つが「ミッション(使命)」という言葉に込められています。ミッションとは、ミュージアムが存在する根本的な理由であり、その組織が社会に対して何をもたらし、何を目指しているのかを明確にする「羅針盤」ともいえる概念です。
しかし、「ミッション」という言葉は、しばしば抽象的で、理念的な響きを持ちます。では、それは実際のミュージアム運営において、どのように機能するのでしょうか。そして、そのミッションが強く意識されたとき、あるいは逆に曖昧なままであるとき、ミュージアムの活動や社会的影響力にはどのような違いが生じるのでしょうか。
本記事では、海外の先進的なミュージアムの事例や、近年の研究成果をもとに、「ミッション」という言葉の持つ本質的な意味と、その具体的な実践のかたちを多面的に探っていきます。そして、現代社会において、ミュージアムがどのように自らのミッションを再定義し、展開していくべきかについて考察していきたいと思います。
ミッションとは「存在理由」であり「行動の指針」
ミュージアムにおける「ミッション」とは、その組織がなぜ存在するのかという根本的な問いに対する答えです。単なる展示や収蔵の活動を行うためではなく、どのような目的のもとに社会と関わり、どのような価値を生み出そうとしているのか。その核心を言語化したものが、ミッションであると言えます。
特に、営利を目的としないミュージアムにとって、明確なミッションは組織の存在意義を支える重要な柱です。企業であれば「利益の追求」という共通の目標がありますが、ミュージアムが目指すのは、文化の継承、知識の共有、教育活動、社会的包摂といった、多様で定量化しにくい価値の創造です。そのため、こうした活動を一貫性を持って展開していくためには、まず「私たちはなぜこの活動を行うのか」という共通の軸が必要になります(Spencer, 2011)1。
また、ミッションは外部との関係づくりにおいても欠かせない役割を果たします。来館者、地域住民、行政機関、支援者、研究者、教育関係者、ボランティアなど、ミュージアムを取り巻く多様なステークホルダーに対して、自館の立場や価値観を明確に伝えることは、信頼や協働の基盤を築く上で非常に重要です(Jacobsen, 2014)2。
さらに、ミッションは組織内部の意思決定においても判断基準となります。たとえば、新しい展示を企画する際や教育プログラムを立ち上げる際、あるいは外部との連携を検討する際に、その取り組みがミッションと整合しているかを確認することで、方向性のぶれない活動が可能になります。言い換えれば、ミッションは日々の判断に「軸」を与えるものなのです(Fleming, 2015)3。
このように、ミッションは単なる理念やスローガンではありません。ミュージアムの価値を内外に伝え、行動に方向性を与える「行動の指針」であり、その根本には「なぜ私たちはこの活動をしているのか?」という存在理由が息づいています。
現代のミュージアムは、保存や研究、教育にとどまらず、観光資源としての活用や地域コミュニティとの連携、社会的課題へのアプローチなど、複数の役割を同時に果たすことが求められています。このように多様な活動を一つの理念で束ねるためにも、ミッションは組織の中核として位置づけられなければなりません(Paulus, 2010)4。
ミッションは、あらかじめ決められた静的な目標ではなく、時代や社会の変化に応じて見直し、進化していくべき「生きた理念」として捉えることが大切です。つまり、変わらぬ価値を守りつつ、変わりゆく社会に応答し続ける柔軟さを併せ持つことこそ、現代のミュージアムにふさわしいミッションのあり方なのです。
似たようなミッションばかりでは意味がない?
ミッションが組織の「存在理由」であり、あらゆる行動に方向性を与える「指針」であるということは、すでに述べたとおりです。しかし、それが単に「一般論」にとどまってしまっては、本来の意義を十分に発揮することはできません。社会に対して自館の立場や価値観を伝え、信頼や協働の基盤を築くためには、ミッションはあくまでそのミュージアム固有の文脈とビジョンに根ざしたものである必要があります。
ところが実際には、多くのミュージアムが画一的な表現に陥っているという現状があります。たとえば、アメリカにある140の美術館を対象としたミッション・ステートメントの分析研究によると、それらの多くが「文化」「教育」「保存」といった共通のキーワードを使用しており、言い換えれば、ほぼ同じような内容の文言が並んでいるという結果が示されています(Paulus, 2010)5。
このような傾向は、いわば「同調的な安心感」の表れでもあると言えるかもしれません。ミュージアムにおいては、専門性や公共性が重視されるため、既存の枠組みや標準的な表現に従うことで正統性(legitimacy)を得やすくなるという側面があります。特に、認証や助成の審査、行政や業界団体との関係においては、「逸脱しすぎないこと」が評価される場面も少なくありません。
しかしながら、そうした「同質化(isomorphism)」に傾きすぎた場合、本来ミッションが果たすべき差別化の機能は損なわれてしまいます。ミッションには、社会に対して「このミュージアムは何を目指しているのか」「どんな価値を提供しているのか」を明確に伝える役割があります。他館と似たような言葉を並べるだけでは、独自の魅力や方向性が伝わりにくくなり、結果として資金調達や観客の獲得といった点においても競争力を失いかねません。
特に、地域性やコレクションの特色、対象とする来館者層、あるいは関与する社会課題が異なる中で、画一的なミッションではそのミュージアムが本来果たせるはずの役割が曖昧になってしまいます。たとえば、移民の歴史をテーマにした都市型のミュージアムと、自然環境保護を掲げる地方の博物館とでは、その存在意義も社会的責任も大きく異なるはずです。しかし、それらがいずれも「文化の保存と教育の推進」といった共通の表現に終始していたとしたら、来館者にも支援者にもその違いは伝わりません。
したがって、ミッションには「正統性の確保」と「独自性の確立」という、相反するようでいて両立すべき二つの要素が内包されています。前者はミュージアムとしての信頼を支えるものであり、後者はそのミュージアムを他と区別し、存在感を際立たせるためのものです。この二つのバランスをどうとるかは、ミュージアムの性質や置かれた文脈によって異なりますが、少なくとも他館の「焼き直し」のようなミッションでは、地域社会や来館者に対する本質的な訴求力は生まれにくいと言えるでしょう。
ミッションは、形式として「ある」ことが目的なのではなく、ミュージアムの個性や哲学、社会との関係性を言葉として立ち上げ、「伝わる」ものでなければなりません。その意味で、似たようなミッションばかりが並ぶ現状は、ミュージアム自身が自らの存在を問い直し、社会の中で果たすべき役割を再定義する必要性を、私たちに改めて示しているのかもしれません。
このように、ミッションは「あること」そのものが目的ではなく、「どうあるか」が本質的に問われるべきものです。そのミッションがどのように表現され、どのように実際の活動に息づいているかによって、ミュージアムの社会的影響力や信頼性、そして未来に向けた可能性が大きく変わってくるのです。
それでは、理念としてのミッションが、現実のミュージアムの運営や展示、教育活動にどのように結びついているのでしょうか。次章では、具体的な事例を取り上げながら、ミッションが実際の活動にどのように生きているのかを詳しく見ていきます。
事例に見るミッションの実践
ミッションは抽象的な理念でありながら、その本質は実践にこそ現れます。いかに立派な言葉を掲げていても、それが展示、プログラム、来館者対応、地域連携といった具体的な行動に反映されていなければ、そのミッションは単なる「お飾り」にすぎません。ここでは、特にミッションが活動に根ざし、社会に対して独自の価値を発揮している例として注目されるいくつかのミュージアムを紹介し、その実践から学べる点を探っていきたいと思います。
「移民の声」を伝える:ロウアー・イースト・サイド・テネメント博物館(アメリカ)
ニューヨーク市にあるロウアー・イースト・サイド・テネメント博物館は、「移民の経験を通して、寛容と歴史的理解を育む」という明確なミッションを掲げています。この博物館の特筆すべき点は、そのミッションが展示や教育活動のあらゆる局面に一貫して表現されているということです(Abram, 2007)6。
たとえば、展示室には当時の移民家族が実際に暮らしていた部屋が再現されており、単なる物語の提示ではなく、来館者が当時の生活空間に「入り込む」ことで、体験的な共感を育むよう設計されています。加えて、ガイドは単なる解説者ではなく、社会問題について対話を促すファシリテーターとしての役割を担っています。
このような取り組みは、ミッションを「理解させる」だけでなく、「感じさせ、考えさせる」ものとして来館者に届けようとする意志の現れです。ここには、ミッションを中心に据えた展示設計と教育哲学が強く反映されています。
「地域とともにある」:C.H.ナッシュ博物館(アメリカ)
テネシー州メンフィスにあるC.H.ナッシュ博物館では、地域社会との双方向的な関係づくりを重視し、「ボランティアや住民とともにミュージアムを形づくる」ことを明確な方針として掲げています(Connolly and Tate, 2011)7。ここでのボランティアは、単なる作業補助者ではなく、展示の共同企画者や教育プログラムの共同設計者として扱われています。
このミュージアムでは、「誰のための、誰によるミュージアムなのか」という問いに対して、実際の運営構造そのものが答えになっています。つまり、ミッションにおける「公共性」や「参加型」の価値が、組織運営のあり方そのものに組み込まれているのです。
このような事例は、ミッションが組織の理念にとどまらず、運営形態や人的ネットワークの構築、資源の分配にまで及ぶ重要な方針となっていることを示しています。
「社会を映す鏡」としての現代美術館:ヨーロッパの事例
また、近年注目されているのが、現代美術館における「社会変革への関与」を明確に打ち出すミッションの傾向です。中央・東欧を含むヨーロッパの現代美術館では、「サステナビリティ」「社会的包摂」「多様性の尊重」といった概念が、ミッション・ステートメントの中核に据えられているケースが増えています(Fehér and Ásványi, 2023)8。
たとえば、一部の館では、単なる展示活動にとどまらず、難民やマイノリティとの協働プロジェクト、環境保全活動への市民参加型プログラムなどが展開されており、それらが明確に「ミッションに基づく取り組み」として位置づけられています。
このように、現代美術館が芸術という枠を越えて、地域社会や地球規模の課題に向き合う「社会のアクター」としてミッションを自覚し始めている点は、注目すべき変化と言えるでしょう。
これらの事例から見えてくるのは、強いミッションは単に言葉のうえで立派であることではなく、それが「活動の中にどう生きているか」が最も重要であるということです。展示の方法、教育プログラムの設計、地域との関係、館内外の人々との協働――そうした実践のひとつひとつに、ミッションがどれだけ浸透しているかが問われているのです。
ミッションを失ったミュージアムの苦悩
前節では、ミッションが明確で、それが展示や運営のあらゆる側面に実際的に反映されているミュージアムの事例を取り上げました。それらの館に共通していたのは、ミッションが単なる理念ではなく、日々の判断や行動を導く「生きた軸」として機能していたことです。このように、ミッションが組織の内外において共有され、具現化されている場合には、来館者との関係も深まり、社会的信頼も高まっていく傾向があります。
しかし残念ながら、すべてのミュージアムがこのようにミッションをうまく運用できているわけではありません。中には、ミッションが曖昧なまま活動を続けた結果、方向性を見失い、内外に混乱を生じてしまうケースも見られます。ここではその代表例として、ニューヨーク市立博物館の事例を紹介し、ミッションの不在がもたらす影響について考察していきます。
ニューヨーク市立博物館(Museum of the City of New York)は、長い歴史を持つ都市型ミュージアムの一つであり、その建築や所蔵コレクションの質は非常に高く、学芸面でも一定の評価を受けていました。2000年代初頭には建物の改修やコレクションの整理・再編も進められ、外形的には組織が順調に整備されつつあるように見えていました。
ところがその裏では、「この博物館は今後、どのような社会的役割を果たすべきなのか」という核心的な問いに対する明確な答えが欠けていました。館としてのビジョンや方針が曖昧であったため、展示のテーマやトーンにも一貫性がなく、企画が場当たり的になりがちだったのです。さらに、寄付者や助成団体に対しても、ミュージアムの意義や方向性を説得力を持って説明することができず、資金調達にも困難が生じるようになりました(Spencer, 2011)9。
このように、ミッションが明文化されていない、あるいは明文化されていても共有されていない組織においては、日々の業務において判断基準が定まらず、関係者間での意思疎通も困難になります。結果として、内部の職員や関係者のモチベーションが低下し、来館者に対しても明確なメッセージを発信できなくなるという、負のスパイラルに陥ってしまうのです。
特に、現代のミュージアムが多様な社会的役割を担うようになった今、ミッションの明確さはますます重要になっています。展示の企画や教育事業の方向性、パートナーシップの構築、行政や地域社会との関係づくり、さらにはサステナビリティや社会包摂といった新たなテーマへの対応――これらのすべてを統合し、一本の軸として貫くためには、強く共有されたミッションが不可欠です。
この事例は、「整備された建物」や「立派なコレクション」だけでは、ミュージアムが社会的意義を持ち続けることはできないという事実を私たちに示しています。むしろ問われるのは、そのハード面や歴史的実績の背後にある「理念」や「目的」の明確さであり、それが実際の活動にどう反映されているかです。外側がいくら立派であっても、内なる指針が不明瞭なままでは、ミュージアムは容易に軸を失ってしまいます。
ミッションとは、単に組織の「名刺代わり」となる文言ではありません。それは、館内外のすべての人々と「何のために、どこへ向かうのか」を共有するための基盤であり、未来に向けた「約束」でもあるのです。その「約束」が曖昧であればあるほど、ミュージアムは不安定な立場に追い込まれ、やがて社会からの支持も失っていくことになるでしょう。
ミッションを再定義するために
前節で見たように、ミッションが不明確なままでは、ミュージアムの運営における意思決定がぶれやすくなり、展示企画や資金調達、さらには来館者や地域社会との関係づくりにも深刻な影響を及ぼします。反対に、明確で組織全体に共有されたミッションは、活動全体に一貫性と方向性を与え、関係者の信頼と協力を引き出す重要な要素となります。
では、そのような強固なミッションをいかにして築き上げることができるのでしょうか。あるいは、既存のミッションを見直し、より時代や社会の変化に即したものへと更新していくには、どのようなプロセスが必要なのでしょうか。
本節では、ミュージアムがミッションを「再定義」する際に重要となる視点や実践的アプローチについて考察し、理念の見直しがどのように組織の再構築や社会的信頼の回復につながっていくかを検討します。
「誰のためのミッションか」を問う
ミッションを再定義するにあたり、まず必要なのは「このミュージアムは誰のために存在するのか」という問いを明確にすることです。これまでの多くのミッションは、館内の専門職員や経営層によって策定され、時に外部との対話が欠けていたケースも少なくありません。しかし今日、ミュージアムは多様なステークホルダーに開かれた公共的な空間として再評価されており、ミッションの見直しもまた「共創的なプロセス」であるべきだと考えられています。
たとえば、来館者、地域住民、ボランティア、学校関係者、支援者、行政職員など、ミュージアムに関わる多様な人々の声を丁寧に汲み取り、それぞれが「この場所に何を求めているのか」「どのような価値を受け取っているのか」を理解することが、より実効性のあるミッション策定につながります。
ミッションとは、組織の内側から一方的に宣言するものではなく、関係者との対話の中から「浮かび上がってくる」ものでもあるのです。
内部対話と意思統一のプロセス
外部との対話に加え、ミュージアムの内部における丁寧な対話と合意形成もまた、ミッション再定義においては欠かせません。特に学芸員、教育担当、事務スタッフ、ボランティアコーディネーターなど、部署や役割が異なる職員が共通の認識を持つためには、「組織として何を大切にしているのか」を率直に話し合う時間が必要です。
このプロセスは、単に理念を確認するだけでなく、組織文化そのものを見つめ直すきっかけにもなります。たとえば、「教育を重視しているつもりだが、実際には展示中心になっていないか?」「多様性をうたっているが、運営体制は画一的ではないか?」といった内省的な問いを通じて、表面的な文言ではない「本音のミッション」に近づいていくことができます。
こうした対話を通じて、ミッションは抽象的な理念から、日々の行動を導く「具体的な羅針盤」へと転換していきます。
時代の変化に応答する柔軟さ
ミッションを再定義するにあたり、時代や社会の変化にどのように応答するかも極めて重要です。たとえば、近年では「持続可能性(サステナビリティ)」「多様性と包摂(ダイバーシティ&インクルージョン)」「デジタル社会への対応」といった課題が、ミュージアムの運営にも直結しています。これらの要素がミッションにどのように組み込まれているか、あるいは逆に軽視されていないかを検証することも、現代的なミッションの在り方を考えるうえで不可欠です。
特にICOM(国際博物館会議)が2022年に採択した新しい「ミュージアムの定義」では、従来の「収集・保存・展示・研究」に加え、「社会的包摂」や「持続可能な発展」への貢献が明記され、グローバルな基準そのものが更新されつつあります。このような潮流に照らして、自館のミッションが現代的な文脈に適応できているかどうかを見直すことが求められます(Fehér and Ásványi, 2023)10。
ミッションを「生かす」ための仕組みづくり
再定義されたミッションは、ただ策定して終わりではありません。それをいかに組織内に浸透させ、実際の活動に結びつけていくかが最も重要です。そのためには、ミッションを定期的に確認する場を設ける、業務評価や企画立案の際に「ミッションとの整合性」を検証する、研修やオリエンテーションで活用するなど、制度的な「定着の仕組み」が必要です。
また、対外的にもミッションを分かりやすく伝える努力が求められます。館内表示やウェブサイト、パンフレットなど、あらゆる媒体を通して、ミッションが自然に可視化されることで、来館者や支援者との信頼関係も深まります。
おわりに:ミッションは社会への「約束」である
ミッションとは、ミュージアムが社会に対して果たす「約束」であり、その理念はすべての活動の根底に流れるものです。展示、収集、保存、研究といった伝統的な機能に加えて、教育、地域連携、ボランティアの育成、環境への配慮、そして社会的包摂といった新しい役割に至るまで──今日のミュージアムに求められるすべての実践の出発点には、ミッションという内なる指針が存在しています。
ミッションは単なる「掲げられた言葉」ではありません。それは、組織の存在理由を明確にし、日々の行動に方向性と意味を与えるものです。内部においては、スタッフやボランティアの判断基準や価値観を整えるとともに、外部に向けては、来館者や地域社会、行政、パートナー機関に対してその存在意義をわかりやすく伝える役割を果たします。
とりわけ現代社会は、複雑で変化の激しい時代を迎えています。多文化化、人口動態の変化、気候危機、テクノロジーの進展──こうした課題の中で、ミュージアムが果たすべき役割はますます多様化し、かつ重層的なものとなっています。そのような時代にあって、組織のブレない軸となるのが、他ならぬ「ミッション」なのです。
「私たちは、なぜこの活動をするのか?」「このミュージアムは何のために存在しているのか?」「誰のために、何を目指しているのか?」──これらの根源的な問いに対して、言葉と行動の両面から、誠実に、そして継続的に答え続けること。それこそが、ミュージアムが今、そしてこれからの社会に対して果たすべき責任であり、その信頼を得る唯一の道でもあります。
ミッションは、組織の過去を受け継ぎ、現在を見つめ、そして未来へとつなげていくための「思想的な架け橋」と言えるでしょう。その内容は時に変化し、更新されるものでありながらも、常にミュージアムが何を大切にし、どのように社会と関わっていくかという「意思の表明」であり続けます。
私たちの社会が複雑であるほどに、文化の力、記憶の力、学びの力が求められます。だからこそ、ミュージアムは単なる「保管庫」ではなく、変化を受け止め、対話を生み出し、未来を共に考える「公共の知の場」であり続けなければなりません。その基盤となるのが、「ミッション」という確かな約束なのです。
参考文献
- Spencer, Stacy L. “MUSEUM WITHOUT A MISSION: A Case Study on The Role of Mission in a 21st-Century Nonprofit Arts Organization.” American Journal of Arts Management 4.1 (2016). ↩︎
- Jacobsen, John W. “The Community Service Museum: Owning up to Our Multiple Missions.” Museum Management and Curatorship, vol. 29, no. 1, 2014, pp. 1–18. https://doi.org/10.1080/09647775.2013.869851. ↩︎
- Fleming, David. “The Essence of the Museum: Mission, Values, Vision.” The International Handbooks of Museum Studies: Museum Practice, edited by Conal McCarthy, John Wiley & Sons, 2015, pp. 1–17.https://doi.org/10.1002/9781118829059.wbihms201 ↩︎
- Paulus, Odile. “Museums as Serigraphs or Unique Masterpieces: Do American Art Museums Display Differentiation in Their Mission Statements?.” International Journal of Arts Management (2010): 12-28.https://www.jstor.org/stable/41057870 ↩︎
- Paulus, Odile. “Museums as Serigraphs or Unique Masterpieces: Do American Art Museums Display Differentiation in Their Mission Statements?.” International Journal of Arts Management (2010): 12-28.https://www.jstor.org/stable/41057870 ↩︎
- Abram, Ruth J. “History Is as History Does: The Evolution of a Mission-Driven Museum.” Ideas of Museums, edited by Ruth Phillips, University of Calgary Press, 2007, pp. 19–30. ↩︎
- Connolly, Robert P., and Natalye B. Tate. “Volunteers and collections as viewed from the museum mission statement.” Collections 7.3 (2011): 325-345.https://doi.org/10.1177/155019061100700307 ↩︎
- Fehér, Zsuzsanna, and Katalin Ásványi. “Differences in Sustainability Approaches from the Mission Statements of Museums: The Case of CEE and Other European Contemporary Art Museums.” Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, vol. 31, no. 3, 2023, pp. 683–701. Taylor & Francis Online, https://doi.org/10.1080/25739638.2023.2258610. ↩︎
- Spencer, Stacy L. “MUSEUM WITHOUT A MISSION: A Case Study on The Role of Mission in a 21st-Century Nonprofit Arts Organization.” American Journal of Arts Management 4.1 (2016). ↩︎
- Fehér, Zsuzsanna, and Katalin Ásványi. “Differences in Sustainability Approaches from the Mission Statements of Museums: The Case of CEE and Other European Contemporary Art Museums.” Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, vol. 31, no. 3, 2023, pp. 683–701. Taylor & Francis Online, https://doi.org/10.1080/25739638.2023.2258610. ↩︎