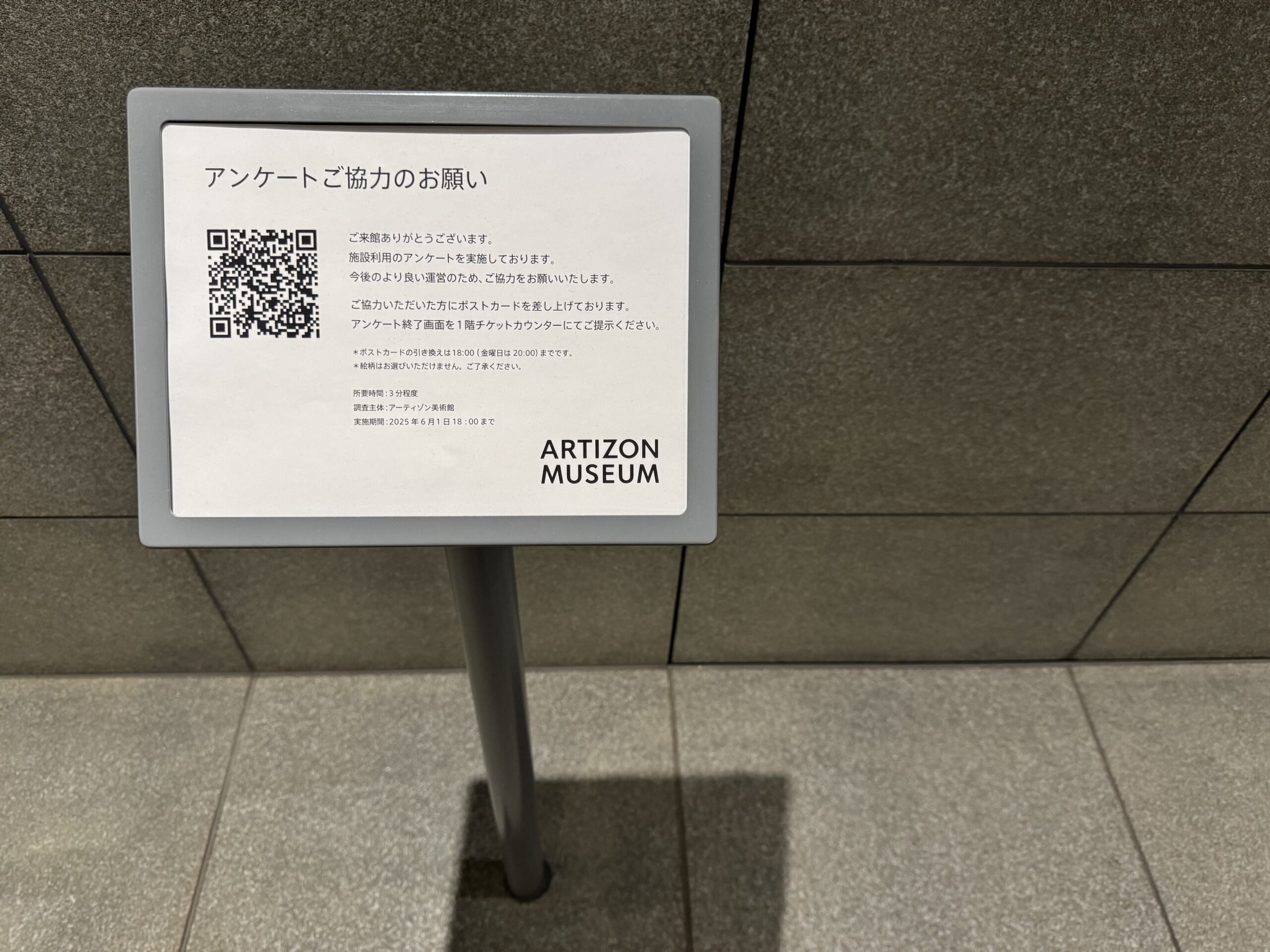ミュージアムという言葉から、皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。絵画や彫刻、歴史的な遺物が静かに展示されている空間。あるいは、ガラス越しに貴重な資料を眺めながら、時の重みを感じる場所。そうしたイメージを持つ方も多いかもしれません。
しかし、現代のミュージアムは、もはや「静かに見てまわる展示施設」ではありません。子どもたちが参加できるワークショップ、デジタルガイドによるインタラクティブな展示、来館者の意見や体験を取り入れた共創的な企画など、多様な活動が日々行われています。つまり、ミュージアムは今や、学びと体験を通じて人々の知的好奇心を刺激し、感情を揺さぶる「社会的な体験の場」として進化を遂げているのです。
このような進化の中で、重要な問いが浮かび上がってきます。それは、「ミュージアムは誰のためにあるのか?」という問いです。展示の内容や技術の進歩がいくら進んでも、それを享受する「人」、すなわち来館者の存在を無視しては、真に意味のあるミュージアム活動は成り立ちません。
来館者は、年齢、国籍、興味関心、学習スタイル、来館の動機など、さまざまな背景を持っています。その多様な来館者一人ひとりが、どのような期待を胸に来館し、館内で何を見て、どこに立ち止まり、何を感じて帰っていくのか――こうした「来館者の行動や思考、感情のパターン」を深く理解することが、ミュージアムの活動をよりよいものへと進化させる鍵となります。
実際、来館者に関する研究が進むことで、次のようなさまざまな改善が可能になります。
• 展示デザインの改善(例えば、どこで来館者が立ち止まり、どこを素通りするか)
• 解説や案内表示の工夫(理解しやすさや、多言語対応など)
• サービス全体の質の向上(導線、混雑緩和、アクセシビリティの確保)
• 教育プログラムのターゲット化(子ども向け、専門家向けなど)
• マーケティング戦略の見直し(来館者層に応じた発信やイベント企画)
これらは、単なる運営上の工夫にとどまらず、「ミュージアムの社会的な役割」を再定義し、より公共性の高い場としての発展につながります。ミュージアムは公的資源を多く用いる施設であり、限られた予算や人材の中で最大限の社会的価値を発揮する必要があります。そのためには、来館者の声に耳を傾け、データに基づいた意思決定を行うことが、不可欠なのです。
本記事では、近年の来館者研究に焦点をあてながら、「来館者を知ること」がミュージアムの持続的な成長、そして社会全体における公共性の拡充にどのように寄与するのかを、いくつかの具体的な事例や研究成果を通じて読み解いていきます。初めてこのテーマに触れる方でも理解しやすいように、用語や背景知識にも丁寧にふれながら、実践的な視点とともに紹介していきます。
「展示」や「技術」の向上だけではない、もう一つのミュージアムの成長軸――それが「来館者理解」です。ミュージアムが未来に向かって歩むための第一歩として、いま、私たちは「来館者を見る目」をアップデートする必要があるのではないでしょうか。
来館者行動の可視化から得られるもの
前節では、来館者の多様な背景や期待に応えるためには、その行動や思考、感情を深く理解することが大切であると述べました。では、その「来館者を理解する」ためには、具体的にどのようなアプローチが有効なのでしょうか。ここで重要となるのが、「来館者の行動を可視化する」という視点です。
ミュージアムを訪れる来館者は、それぞれ異なる関心や目的を持って館内を巡ります。しかし、その行動の一つひとつを人の目で追い、すべてを記録するのは現実的ではありません。また、目視による観察では見逃されてしまう細かな行動やパターンも数多く存在します。たとえば、来館者がどの展示にどのくらいの時間滞在したのか、どのような順路を選んだのか、どの空間で混雑が発生していたのかといった情報は、日常の運営の中ではなかなか把握しにくいものです。
こうした課題に対して有効なのが、センサーやICT技術を用いた来館者行動の「可視化(ビジュアライゼーション)」です。これは、来館者の位置情報や移動経路、滞在時間などを定量的に収集・分析し、それを視覚的なデータとして表現する方法です。来館者の動線をデジタルで“見える化”することによって、展示や空間の使われ方を客観的かつ詳細に把握することができます。
この分野で注目される事例の一つに、Lanirら(2016)の研究があります。彼らは、館内に設置されたセンサーを用いて来館者の移動パターンや滞在行動を自動的に記録・解析するシステムを開発しました。このシステムでは、来館者がどの展示に立ち寄り、どれだけの時間を費やしていたのかといった情報を視覚的に表現することで、展示の人気傾向や動線設計の効果、混雑の発生地点などを定量的に把握することが可能になります(Lanir et al., 2016)1。
このようなデータは、「どの展示が人気か」といった単純なランキングだけでなく、来館者の学習行動を読み解く上でも非常に有効です。たとえば、ある展示に多くの来館者が集まっても滞在時間が短ければ、視覚的な引きつけは強くても内容が伝わりにくい可能性が考えられます。一方で、少数の来館者が長時間滞在している展示は、特定の層にとって深い学びを提供しているとも解釈できます。
さらに、来館者の行動パターンを可視化することで、館内の導線のわかりやすさや休憩スペースの配置など、空間設計の改善点を具体的に検証することができます。たとえば、あるゾーンで多くの来館者が疲労し、立ち止まりにくくなっている場合、その前後にベンチや休憩所を設けることで回遊性を高めるといった施策が考えられます。また、特定の展示が他の展示と比べて素通りされている場合、その要因が位置や解説の内容にあるのかを検討するきっかけにもなります。
このような行動データの蓄積と分析は、学習支援の視点からも非常に有意義です。来館者が限られた時間の中で「どこに惹かれ」「何を避けているのか」を知ることは、展示内容の再構成や補助的な解説ツールの設置にもつながります。たとえば、難解で理解されにくい展示に対しては、子ども向けの解説パネルやマルチメディアガイドの導入を検討することで、学びの裾野を広げることができます。
つまり、来館者行動の可視化は、展示評価、空間デザイン、サービス改善、学びの支援など、ミュージアムのさまざまな側面において改善の根拠を提供する重要な手法なのです。それは、感覚や経験に頼る従来の運営から、データに基づいた意思決定へと移行するための強力なツールであるといえるでしょう。
次の節では、こうした来館者の行動パターンが、個々の来館者の「認知スタイル」や「情報処理の傾向」とどのように結びついているのかを探っていきます。来館者の個性に応じた展示や学びの支援を設計するうえで、認知の特性に着目することは欠かせない視点です。
認知スタイルと移動スタイルの関係
前節では、来館者の行動をデータとして「可視化」することで、展示や空間設計の改善に活用できる可能性について述べました。来館者が館内でどこに立ち止まり、どのような順序で展示を見ているのかを知ることは、ミュージアムの学びの場としての質を高める上で非常に有益です。しかし、こうした行動の背後には、もっと深い「思考のスタイル」や「認知の特性」が関係している可能性があります。
この点に注目したのが、AntoniouとLepourasによる研究です。彼らは、来館者の「移動スタイル」と「情報処理の好み(認知スタイル)」との間に一定の関連性があることを明らかにしました(Antoniou & Lepouras, 2010)2。つまり、人はそれぞれ独自の「学びの癖」や「情報の受け取り方」に従って館内を巡っているということです。
彼らの研究では、館内での動き方を動物の行動に例えて、いくつかの代表的なタイプが提示されています。たとえば、展示を順序どおりに丁寧に、しかもすべて網羅するように見ていく来館者は「アリ型」と呼ばれます。一方、興味を惹かれた展示だけを飛び飛びに見る来館者は「蝶型」とされます。さらに、入り口付近や目立つ展示のみをさらりと見てすぐに帰る「バッファロー型」、特定の展示にのみ強い関心を持ち、その周辺に長時間とどまる「フィッシュ型」などもあり、移動スタイルには多様な傾向があることがわかっています。
こうした移動スタイルは、単なる行動パターンにとどまらず、その人の情報処理や認知の仕方と密接に関わっていると考えられます。たとえば、アリ型の来館者は、体系的・論理的に情報を構築していくことを好み、すべての情報を漏らさず受け取りたいという傾向を持っている可能性があります。一方、蝶型の来館者は、感覚的・直感的に興味を持ったものを優先し、自分なりの流れで情報を拾い集めるタイプであるともいえます。
このような認知スタイルの違いを理解することは、展示のインターフェース設計やナビゲーション設計にとって非常に重要です。たとえば、アリ型の来館者には、順路がはっきりと示されていたり、全体構成が明示された展示が適しています。逆に、蝶型の来館者には、どこからでも自由にアクセスできるようなレイアウトや、インスピレーションを誘発するビジュアルの工夫が有効です。
さらに注目すべき点は、こうした来館者の「プロファイリング」が、個人情報を直接収集することなく実施できるという点です。来館者がどのような経路で館内を移動したのか、どの展示に長く滞在したのかといった行動データをもとに、匿名のまま「その人に合った情報の届け方」を考えることができます。これは、プライバシーへの配慮が求められる現代において、非常に有効なアプローチです。
実際、多くのミュージアムが導入を進めているモバイルガイドや音声解説アプリなども、この「認知スタイルに合わせた情報提供」を取り入れることで、より効果的な学びの支援ツールとなります。たとえば、ある来館者には詳細な解説を段階的に提供し、別の来館者にはポイントを絞った音声ナビゲーションを用意するといった工夫です。
このように、来館者の移動スタイルと認知スタイルの関係を理解することで、ミュージアムは「一律の情報提供」から脱却し、より個別化された、来館者一人ひとりに寄り添った展示体験の提供が可能となります。
次の節では、こうした来館者理解が、展示やサービスの最適化を超えて、どのようにミュージアム全体の戦略や経営判断に活かされるのかを、「セグメント分析」の視点から見ていきます。
サービス満足とセグメント分析の重要性
前節では、来館者の移動スタイルと認知スタイルの関係についてご紹介しました。ミュージアムは、そうした行動傾向や思考の特性に応じて情報提供や展示構成を柔軟に設計することで、個別化された学びの体験を提供できるようになります。しかし、来館者理解を深めるうえで、もう一つ欠かせない視点があります。それは、「来館者をセグメント(分類)して考える」というアプローチです。
多くのミュージアムでは、来館者を一括りにして「一般来館者」として捉える傾向があります。しかし、実際には来館者の目的や関心、訪問動機は非常に多様です。学術的な知識を求めて来館する人もいれば、子どもとのレジャー体験として訪れる人もいます。また、文化芸術への高い関心を持つ層もいれば、旅先の観光の一環としてふらりと立ち寄った人もいます。こうした来館者一人ひとりの期待や価値観の違いを把握することは、展示の満足度を高め、リピート訪問やクチコミといった来館後の行動にも大きく影響を与えるのです。
この点を明らかにしたのが、Bridaら(2016)による実証研究です。彼らは、イタリアの二つのミュージアム――一つはアルプス地域の考古学博物館、もう一つは地中海沿岸の歴史博物館――において、来館者の体験をもとにしたセグメント分析を実施しました。この研究では、来館者アンケートの回答内容をもとに、まず満足・不満足の要因を抽出し、さらに統計的手法(因子分析やクラスタリング)によって来館者をいくつかのセグメントに分類しました。
その結果、展示内容や学びの深さを重視する層、施設の快適さやサービス面を重視する層、家族での楽しみやエンターテインメント性を重視する層など、明確に異なる価値基準を持った来館者グループが浮かび上がりました。さらに、各セグメントごとに再来訪の意欲や他人への推奨意識(口コミ効果)なども大きく異なっていたことが示されています(Brida et al., 2016)3。
この研究が示唆しているのは、来館者の満足度を高めるには、単に展示の質を上げるだけでは不十分であるということです。重要なのは、「誰に、どのような体験を届けるのか」という“ターゲットとのマッチング”です。たとえば、学術的な知見を求める層には、研究成果や専門的な解説を充実させる必要があります。一方で、ファミリー層には、子どもが楽しく学べる体験型展示や、ベビーカー対応の施設環境、親子で安心して休憩できるスペースの整備が求められます。
このように、来館者を「ひとくくり」にせず、ニーズや期待に応じて分類・理解することは、マーケティング戦略の立案、展示構成の再設計、施設サービスの向上といったあらゆる場面で有効です。言い換えれば、「来館者セグメントごとに適切な体験を届ける」ことが、ミュージアム全体の満足度と評価を高める最短ルートなのです。
また、セグメント分析は、来館者アンケートや館内行動ログなど、既存のデータからでも比較的容易に実施できます。現在の来館者像を定量的に把握し、それぞれの層に向けた最適なアプローチを設計することは、限られた資源で最大の効果を生み出すミュージアム経営において、ますます重要な視点になってきています。
次の節では、この「来館者の満足と再来訪意欲」の背景にある、より主観的で動機的な要素――つまり「来館前の期待」や「体験の意味づけ」について掘り下げていきます。来館者がどのような想いでミュージアムに足を運ぶのかを知ることは、その体験をより豊かなものにするための鍵となります。
「期待」と「体験」のギャップを埋めるために
前節では、来館者を多様なセグメントとして捉え、それぞれのニーズに応じた体験を設計することの重要性を確認しました。しかし、来館者がミュージアムに足を運ぶ際、彼らは「現地で何かを体験する前」から、すでに一定の「期待」を抱いていることを忘れてはなりません。その期待が、来館後の満足度や評価、さらには再訪意欲にまで強く影響するという事実は、近年の来館者研究において繰り返し指摘されています。
この「体験前の期待」に着目した代表的な研究のひとつが、ShengとChenによる調査研究です。彼らは、ミュージアム来館者が持つ「経験への期待」が、具体的にどのような内容で構成されているのかを明らかにするため、質的・量的な手法を組み合わせて分析を行いました。その結果、来館者の期待は主に5つの要素に分類できることが分かりました。それが、「楽しさ」「文化的娯楽性」「自己同一性」「歴史的回想」、そして「現実逃避」です(Sheng & Chen, 2012)4。
まず「楽しさ」は、展示を見たり、参加型のコンテンツに触れたりすることで純粋な喜びや好奇心を満たしたいという感情的な期待を指します。「文化的娯楽性」は、芸術や歴史といった文化資源に触れることを通じて、知識とエンターテインメントの両方を得たいという複合的な期待です。「自己同一性」は、展示と自分自身との関係性に焦点を当てたもので、たとえば出身地や家族の歴史と重なる展示に共感を覚えるような体験を意味します。「歴史的回想」は、過去の出来事を思い出したり、懐かしさを感じたりするような、記憶と結びついた期待です。そして「現実逃避」は、日常から離れ、非日常的な空間で心をリフレッシュさせたいという心理的欲求を指しています。
これらの期待は、来館者ごとに強弱が異なり、また複数の要素が同時に存在することもあります。そして、こうした期待に応えられるかどうかが、来館後の評価に大きな差を生み出します。たとえば、「家族で楽しい時間を過ごせると思っていたのに、展示が難解で子どもが退屈してしまった」という場合、期待と体験のギャップが生まれ、不満につながってしまいます。一方で、「自分の故郷にまつわる展示に偶然出会い、深く感動した」というような体験は、予想を超える満足感を生み、来館者との絆を強くします。
だからこそ、ミュージアムにとって重要なのは、来館者が何を期待して訪れるのかを「事前に知ろうとする姿勢」です。具体的には、来館者アンケートで訪問理由や期待内容を尋ねたり、SNSやレビューサイトに寄せられる来館前の声を分析したりすることが有効です。また、複数の来館者セグメントに応じて、展示解説や館内案内を複線化する工夫も必要です。たとえば、専門性の高い解説とは別に、「○○ってなに?小学生にもわかる5分ガイド」のような簡易資料を用意することで、来館者の知識レベルや目的に応じた体験の提供が可能になります。
このように、来館者の「期待」と、実際に得られる「体験」とのギャップを埋める努力は、単なるサービスの向上を超えて、来館者との信頼関係の構築につながります。一度「期待を裏切られた」と感じた来館者は、再びミュージアムに戻ってくる可能性が低くなりますが、「期待を上回る体験を得られた」と感じた来館者は、リピーターとなり、他者にも積極的にミュージアムを勧める存在になります。
そして何より、来館者の期待に丁寧に向き合い、それに応える体験設計を行うことは、ミュージアムの社会的役割――すなわち「多様な人々に開かれた、公共性の高い文化施設」としての価値を、より一層高めることにもつながるのです。
次の節では、こうした来館者体験全体の質を高めるうえで、今あらためて注目されている「ミッション」の視点から、ミュージアムが果たすべき役割と方向性について考えていきます。
ミュージアムの「顧客理解」がもたらす変化
これまで見てきたように、来館者の行動を可視化する試みや、認知スタイルに基づくプロファイリング、体験セグメントごとの分析、そして期待と実際の体験とのギャップを埋める視点は、いずれもミュージアムの「顧客理解」の深化を意味しています。そして、この顧客理解は単なる運営のテクニックではなく、ミュージアムという存在そのものの在り方を見つめ直す鍵になるものです。
来館者を理解すること。それは「展示の効果を高めるため」「サービス満足度を上げるため」といった目先の改善を超えて、「ミュージアムは誰のために存在するのか?」という根本的な問いに立ち返ることでもあります。ミュージアムは教育施設であり、文化の保存装置であり、地域に根ざした社会的空間でもあります。しかしそのいずれの役割も、「利用する人=来館者」の存在なくしては成り立ちません。
たとえば、来館者の移動パターンや滞在時間を分析することは、展示の再構成や案内表示の最適化に貢献します(Lanir et al., 2016)5。また、来館者の認知特性に応じて情報提供の手段を複線化することは、より多様な学びのスタイルに応えるための土台となります(Antoniou & Lepouras, 2010)6。加えて、来館者の価値観や目的に応じたセグメント分析は、展示やサービスを「誰に届けるのか」を明確にし、再訪やクチコミの活性化を促します(Brida et al., 2016)7。そして来館前の期待を丁寧に読み取り、それに応じた体験を設計することは、来館者との信頼関係を築き、長期的な関係性を育む力を持っています(Sheng & Chen, 2012)8。
こうした一連の取り組みを支えているのが、「直感」や「慣習」ではなく、「データに基づく意思決定」です。かつてのミュージアム運営は、学芸員や管理者の経験に支えられてきた面が大きく、それはそれで大切な蓄積でもありました。しかし、来館者の多様化が進む現代においては、経験や主観だけに頼らず、来館者から得られる客観的なデータに基づいて戦略を立てていく必要があります。
アンケート調査、観察、ログの収集と分析、プロファイル分類とセグメンテーション、さらに期待値調査や満足度測定といった手法は、いずれも「来館者の声」を具体的に捉え、可視化するためのツールです。それらを活用することで、ミュージアムは本当の意味で「来館者の視点に立つ」施設へと進化することができます。
そしてその結果として、ミュージアムはより開かれた、包摂的(インクルーシブ)な空間へと近づいていきます。言い換えれば、誰もが自分自身を重ねられる展示、誰もが安心して過ごせる空間、誰もが「また来たい」と思える体験を提供する場所へと変わっていくのです。
顧客理解とは、決して市場原理に迎合するという意味ではありません。むしろ、それは文化施設としての社会的責任を果たすための出発点です。来館者の多様な声に耳を傾け、その期待に応えようとする姿勢こそが、ミュージアムの持続可能な未来を支える力となります。
これからのミュージアムに求められるのは、単に収蔵品や展示の質を高めることだけではありません。そこに「誰に、どのように届けるか」という視点を加えること。それこそが、ミュージアムが社会に開かれ、真に意味のある文化体験を提供するための道なのです。
参考文献
- Lanir, Joel, et al. “Visualizing Museum Visitors’ Behavior: Where Do They Go and What Do They Do There?” Personal and Ubiquitous Computing, vol. 21, no. 2, 2016, pp. 301–314. Springer, https://doi.org/10.1007/s00779-016-0994-9. ↩︎
- Antoniou, Angeliki, and George Lepouras. “Modeling Visitors’ Profiles: A Study to Investigate Adaptation Aspects for Museum Learning Technologies.” ACM Journal on Computing and Cultural Heritage, vol. 3, no. 2, Sept. 2010, Article 7, pp. 1–19. ACM, https://doi.org/10.1145/1841317.1841322. ↩︎
- Brida, Juan Gabriel, Marta Meleddu, and Manuela Pulina. “Understanding Museum Visitors’ Experience: A Comparative Study.” Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, vol. 6, no. 1, 2016, pp. 1–19. Emerald Insight, https://doi.org/10.1108/JCHMSD-07-2015-0025. ↩︎
- Sheng, Chieh-Wen, and Ming-Chia Chen. “A Study of Experience Expectations of Museum Visitors.” Tourism Management, vol. 33, no. 1, Feb. 2012, pp. 53–60. Elsevier, https://doi.org/10.1016/j.tourman.2011.01.023. ↩︎
- Lanir, Joel, et al. “Visualizing Museum Visitors’ Behavior: Where Do They Go and What Do They Do There?” Personal and Ubiquitous Computing, vol. 21, no. 2, 2016, pp. 301–314. Springer, https://doi.org/10.1007/s00779-016-0994-9. ↩︎
- Antoniou, Angeliki, and George Lepouras. “Modeling Visitors’ Profiles: A Study to Investigate Adaptation Aspects for Museum Learning Technologies.” ACM Journal on Computing and Cultural Heritage, vol. 3, no. 2, Sept. 2010, Article 7, pp. 1–19. ACM, https://doi.org/10.1145/1841317.1841322. ↩︎
- Brida, Juan Gabriel, Marta Meleddu, and Manuela Pulina. “Understanding Museum Visitors’ Experience: A Comparative Study.” Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, vol. 6, no. 1, 2016, pp. 1–19. Emerald Insight, https://doi.org/10.1108/JCHMSD-07-2015-0025. ↩︎
- Sheng, Chieh-Wen, and Ming-Chia Chen. “A Study of Experience Expectations of Museum Visitors.” Tourism Management, vol. 33, no. 1, Feb. 2012, pp. 53–60. Elsevier, https://doi.org/10.1016/j.tourman.2011.01.023. ↩︎