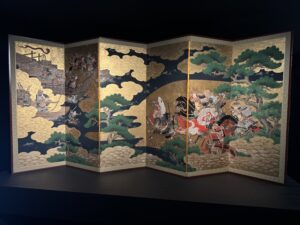はじめに
観光産業における「文化観光」の存在感は、この数十年で大きく変化しました。世界観光機関(UNWTO)によると、文化観光は国際観光全体の約39%を占めるとされており、その割合は年々増加傾向にあります(UNWTO, 2018)。また、OECDの分析でも、文化施設や芸術イベントが都市や地域の経済活性化に大きく貢献していることが示されています(OECD, 2009)。こうした状況の中、博物館は文化観光の中核を担う存在として再評価されつつあります。中でも博物館は、文化観光の中核を担う存在として注目されており、来館者にとっての魅力や、地域とのつながりが再評価されつつあります。
一方で、単に「文化的資源としての博物館」にとどまらず、「観光地としての戦略的価値」をどのように構築し、発信するかが問われる時代となりました。来館者の動機や体験、そしてその先にある地域への波及効果をいかに可視化し、博物館の運営に取り込むか。これは文化政策・観光政策の接点であり、同時に博物館経営における重要な課題です。
本記事では、文化観光という枠組みの中で博物館が果たす「戦略的価値」とは何かを問い直します。具体的には、来館者の観光動機や体験価値、口コミに現れる評価の構造、さらには地域経済への波及といった視点を取り上げながら、博物館が文化観光においていかなる意義と可能性を持つのかを多角的に検討していきます。
博物館と文化観光の関係をどう捉えるか
文化観光という言葉は広く使われているものの、その定義は一様ではありません。国際的には、日常生活圏を離れて文化的動機に基づいて観光地を訪れ、新たな知識や経験を得ようとする旅行形態として文化観光が位置づけられています(Richards, 2018)。この定義においては、「文化的動機」が主たる理由であるか否かを問わず、多様な観光者が対象となります。
このように文化観光の概念が拡張されるなかで、博物館はその中核的な役割を果たしてきました。文化観光の中心的資源として博物館が位置づけられており、特に都市部では観光インフラと結びついた文化施設として、来訪者の誘引力を発揮しています(OECD, 2009)。また、文化観光の研究動向を整理した報告では、博物館が創造産業や都市再生と結びつく戦略的資源として位置づけられていることが示されています(Richards, 2018)。
さらに、博物館と観光者の関係性をより詳細に理解するために、観光動機に応じた分類モデルも提案されています。観光者の訪問動機を「主たる動機」「部分的動機」「付随的体験」「偶発的訪問」の4類型に整理した分析は、文化観光における来館者の多様な関わり方を明らかにするものです(Silberberg, 1995)。このモデルは、博物館が観光者にとって「目的地」にも「偶然の出会い」にもなり得ることを示唆しています。
つまり、博物館は観光の“目的地”としての力を持ちながらも、同時に“副次的な発見”として機能する柔軟性を備えています。こうした多様な関わり方が、文化観光における博物館の特異な価値を形づくっているのです。
観光者の動機と博物館来館の心理
文化観光において、来訪者が何を求めて博物館を訪れるのかという「動機」は、体験の設計において極めて重要な視点です。単なる展示物の鑑賞だけではなく、訪問者はそこに「学び」「感動」「癒し」といった多様な価値を期待しており、そうした内面的な動機は体験の質に強く影響を及ぼします。
近年の観光心理学における研究では、来館者の動機は機能的な要因(知識を得る、旅行のルートに組み込まれているなど)に加えて、感情的・象徴的な側面が強調されつつあります。例えば「地域の歴史に触れたい」「自分の興味・趣味と重なるものを発見したい」「日常とは異なる時間を過ごしたい」といった期待が、博物館来館の動機として重要になっています(Chen & Rahman, 2018)。
また、旅先での博物館体験は、旅行全体の記憶や印象にも大きく関与します。特に文化的接触の要素が強い場合、訪問者は他者や異文化とのつながりを感じ、自身の価値観に変化をもたらすこともあります。このように、博物館は「情報を提供する場所」であると同時に、「自己の内面と向き合う場」としても機能しているのです。
したがって、観光者の心理的な動機を正確に理解することは、展示デザインやナラティブの構成、サービスの在り方において戦略的な意味を持ちます。単に展示を見せるのではなく、「どのような動機で訪れたか」に応じた体験の提案が求められているのです。
記憶に残る体験とオーセンティシティの追求
文化観光における満足度やリピート意向を高める上で、体験が「記憶に残るかどうか」は極めて重要な要素です。とりわけ博物館は、学術的な情報提供にとどまらず、訪問者の感情や記憶に訴える体験価値の創出が求められる場でもあります。そのため近年では、来館者の主観的体験の質を測定する概念として「記憶に残る観光体験(Memorable Tourism Experience, MTE)」が注目されています(Chen & Rahman, 2018)。
MTEは、訪問後も鮮明に思い出されるような感情的インパクトを持つ体験を指し、来館者の満足度、再訪意向、さらには口コミ行動などに直接的な影響を与えるとされています。博物館においては、展示の内容だけでなく、空間の演出、職員とのやりとり、個人的な発見など、複数の要素が複雑に絡み合って体験の印象を形づくります(Chen & Rahman, 2018)。
こうした記憶に残る体験を生み出す上で、「オーセンティシティ(authenticity)」という概念は非常に重要です。オーセンティシティとは、「本物らしさ」や「真正性」と訳され、訪問者が展示や空間、物語に対して感じる“信頼できるリアリティ”を意味します。観光研究においては、観光体験が「本物」であるように見えることそのものが重要視されており、事実性そのものよりも「本物らしく感じられる体験」に価値が置かれるとされています(Wang, 1999)。また、観光空間があらかじめ演出されたものとして知覚されるプロセスも、観光者の信頼感に影響を与えるとされています(MacCannell, 1976)。
博物館における文化観光は、来館者が感情的・象徴的な意味に惹かれる“新ロマン主義”的な体験として捉えられており、そこではオーセンティックな物語や感情への接続が深い体験をもたらすとされています(Prentice, 2001)。実際、多くの博物館が「共感できる物語」や「自己との関係性を感じられる展示」の創出に力を入れており、これは体験価値を単なる情報提供から、情動的・内省的なプロセスへと深化させる試みだといえます。
博物館サービスの質と課題
前節では、来館者が記憶に残る体験を得るためには、感情や物語性、そしてオーセンティシティといった内面的な要素が重要であることを確認しました。では、こうした体験の基盤となる環境や運営体制は、どのように構築されるべきなのでしょうか。ここで注目すべき視点が「サービス」としての博物館です。
博物館は文化的価値を提供する場であると同時に、来館者に対して多様なサービスを提供する場でもあります。展示内容の充実や解説の質だけでなく、受付対応、館内の快適性、情報提供のわかりやすさといった運営面のサービス品質は、来館者の全体的な満足度に大きく影響します。こうした観点から、博物館におけるサービスの在り方を体系的に見直す必要性が高まっています。
近年では、来館者の評価をオンラインで確認できるプラットフォームが整備されており、博物館に関する否定的なレビューを分析する研究も進められています。特にTripAdvisorなどに投稿された「非常に悪い」評価に着目した調査では、来館者が不満を感じる要因として、案内表示の不備、施設の老朽化、スタッフの態度、展示の難解さ、音声ガイドの不足などが指摘されています(Su & Teng, 2018)。
この研究では、博物館サービスの品質を構成する12の次元が抽出されており、それぞれが来館者の期待と実際の体験とのギャップに深く関わっているとされています。たとえば「信頼性」「共感性」「物理的な環境(サービススケープ)」「レスポンシブネス」などの要素は、企業のサービス業と共通する部分も多く、博物館がサービス提供機関として再定義されつつある現状を示しています(Su & Teng, 2018)。
一方で、博物館は単なる娯楽施設ではなく、学びや探究の場でもあるため、すべてを「顧客満足」の論理に還元することには慎重な視点も必要です。しかし、来館者の声を真摯に受け止め、体験の質を継続的に向上させることは、公共的な文化施設としての信頼性を高める意味でも重要です。サービスの視点を取り入れたマネジメントは、博物館が多様な来館者にとって開かれた空間となるための土台を築く手段となるのです。
博物館がもたらす地域的波及効果
博物館は、文化的な拠点としての役割に加えて、地域社会や都市経済に対してさまざまな波及効果をもたらす存在でもあります。展示や教育普及といった本来的な機能を果たしながら、観光振興、雇用創出、都市ブランドの向上など、経済的・社会的価値を生み出す装置としても注目されています。
たとえばスペインのビルバオでは、グッゲンハイム美術館が都市イメージの刷新と経済活性化の手段として導入され、大きな成果を上げました。開館後の来訪者増加や地域経済の成長は「ビルバオ効果」と呼ばれるようになり、博物館が都市の再生に寄与する代表的な事例とされています(Plaza, 2000)。
こうした波及効果は、大都市の大規模施設だけに見られるものではありません。地方都市や中小規模の博物館においても、地域住民との協働や教育機関との連携、地場産業や観光資源との接続といった取り組みを通じて、地域社会に根ざした価値創出が実現されています。文化施設が観光の主たる動機になり得ると同時に、他の地域資源と連動して相乗効果を生み出す可能性があることも指摘されています(Silberberg, 1995)。
さらに、博物館は地域にとっての「誇り」や「共有財」としての機能も担っており、その存在は地域住民のアイデンティティ形成や来訪者との関係構築にも寄与しています。文化観光を通じた経済的波及と、地域社会への社会的貢献を両立させることは、現代の博物館に求められる重要な役割のひとつといえるでしょう。
おわりに
本記事では、文化観光の文脈において博物館が果たす戦略的価値について、観光者の動機や体験、サービスの質、地域への波及効果といった複数の視点から検討してきました。博物館は単なる文化資源にとどまらず、観光者の心理的欲求に応える場であり、地域社会との関係性を築く拠点でもあります。
来館者の動機を理解し、記憶に残る体験を提供し、信頼性のあるサービス環境を整えることは、博物館の価値を最大化するための重要な要素です。また、博物館が地域経済やまちづくりに果たす役割は、文化の保存・継承と経済的持続可能性の両立という観点からも再評価されるべきでしょう。
観光のなかで博物館が担う意義は、今後ますます多様化していきます。そのなかで問われるのは、どのようにして来館者との意味ある接点をつくり、地域との共生を実現していくかという視点です。文化観光の時代において、博物館は“文化を見せる場所”から、“文化と関係を築く場”へと変化しているのです。
参考文献
- Chen, H., & Rahman, I. (2018). Cultural tourism: An analysis of engagement, cultural contact, memorable tourism experience and destination loyalty. Tourism Management Perspectives, 26, 153–163.
- MacCannell, D. (1976). The tourist: A new theory of the leisure class. Schocken Books.
- OECD. (2009). The impact of culture on tourism. OECD Publishing.
- Plaza, B. (2000). Evaluating the influence of a large cultural artifact in the attraction of tourism: The Guggenheim Museum Bilbao case. Urban Affairs Review, 36(2), 264–274.
- Prentice, R. (2001). Experiential cultural tourism: Museums and the marketing of the new romanticism of evoked authenticity. Museum Management and Curatorship, 19(1), 5–26.
- Richards, G. (2018). Cultural tourism: A review of recent research and trends. Journal of Hospitality and Tourism Management, 36, 12–21.
- Silberberg, T. (1995). Cultural tourism and business opportunities for museums and heritage sites. Tourism Management, 16(5), 361–365.
- Su, Y., & Teng, Y.-M. (2018). Contemplating museums’ service failure through the eyes of Tripadvisor reviewers. Journal of Hospitality and Tourism Management, 36, 34–43.
- UNWTO. (2018). Tourism and culture synergies. World Tourism Organization.
- Wang, N. (1999). Rethinking authenticity in tourism experience. Annals of Tourism Research, 26(2), 349–370.