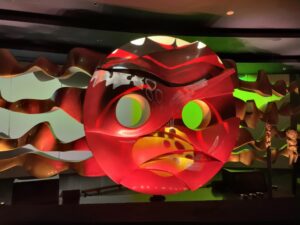はじめに
現代の博物館は、その存在意義を問い直される時代にあります。展示や収蔵といった伝統的な機能に加え、教育支援、地域づくり、社会的包摂といった多様な役割が求められ、単なる「文化の保存装置」ではなく、社会の変化に応答する公共的な文化拠点としての機能が拡張されています。
こうしたなかで注目されているのが、博物館の活動によってもたらされる「成果(outcomes)」が、いかに社会へと還元されているのかという視点です。たとえば、来館者の学びや意識の変化、地域との信頼関係の構築、あるいは福祉的なサポートといった、目に見えにくいが確かな影響が、どのように広く社会に共有されているのかという問いです。
これまで博物館に関する成果評価は、来館者数や展示数などの定量的な業績指標(outputs)に依存する傾向が強く、それらがいかなる社会的価値を生み出しているかについては、十分に検討されてきたとは言いがたい側面があります。特に、新公共経営(New Public Management)の導入以降、公共施設としてのアカウンタビリティ(説明責任)が求められるようになった一方で、「何が成果なのか」を定義すること自体が曖昧なまま制度が進んできたという批判も存在します(Newman, 2013)。
本稿では、こうした問題意識をふまえ、博物館の「成果」がいかにして社会に還元されうるのかを、公共性・教育・地域貢献という三つの視点から検討します。まず、社会還元という概念そのものを丁寧に捉え直したうえで、博物館がどのような形で社会に価値を提供しているのかを考察します。そのうえで、成果をいかに「見える化」し、どのように共有・循環していくかという実践的課題についても論じていきます。
社会還元とは何か ― 現代の博物館に求められる役割
「社会還元(social return)」とは、公共的な組織や事業体が、自らの活動を通じて社会全体にどのような価値や利益をもたらしているかを示し、それを社会に再配分・共有する営みを指します。単なるサービスの提供にとどまらず、知識・体験・文化的資源といった非金銭的な成果を、より多くの人々が享受できるように届けていくことが本質です。
博物館における社会還元は、主に以下の三つの観点から捉えることができます。
- 公共性の実現としての社会還元
博物館は多くの場合、公共資源(税金、寄付、文化助成)によって支えられており、その成果は社会に対して「説明可能であること(accountability)」と「共有可能であること(accessibility)」が求められている(Scott, 2003)。この観点では、博物館の存在意義そのものが社会との関係性によって定義される。 - 教育的成果の波及としての社会還元
博物館は知識の発信地であると同時に、探究学習やリテラシー向上を支援する教育機関としての役割も担っている。これにより、来館者や地域住民が自己形成を深めたり、新たな視点を獲得したりする契機を提供することが、教育的な社会還元といえる(Nelson et al., 2022)。 - 地域資源としての貢献としての社会還元
博物館は文化観光やまちづくりの担い手として、地域の経済やコミュニティ形成にも寄与している。特に近年は、博物館が地域社会と共にイベントや事業を共創する中で、文化資源の活用と社会的ネットワークの構築が進められている(Jackson & McManus, 2019)。
博物館に期待される社会的成果は、しばしば政策的な目標や制度的な枠組みの中で構築されており、それ自体が社会の価値観や政治的判断を反映したものであるとされている(Newman, 2013)。そのため、成果評価の手法や対象が、必ずしも来館者や地域社会の実感と一致するとは限らない。博物館がいかなる成果を重視し、それをどのように社会と共有するかは、制度的要求への対応であると同時に、公共性に対するその館の姿勢を示すものである。
公共性の実現としての社会還元
博物館が社会に対してどのような価値を還元しているのかを考えるうえで、まず前提となるのは「公共性」という概念です。博物館は、税金や公的助成、寄付など、社会的な資源によって支えられており、その成果は社会に対して説明可能でなければなりません。つまり、博物館は「誰のために、何を行っているのか」を明らかにする責務を持っています。
この点において、来館者数や展示件数といった業績指標だけで博物館の価値を測ることは不十分です。たとえば、ある自治体立の自然史博物館が、来館者数の減少を理由に予算削減や再編の対象となったと仮定した場合、館側がその存続意義を示すには、単なる入館者数だけでは不十分かもしれません。こうした場面では、「学校教育との連携回数」や「災害時の避難所としての機能」など、定量評価では見えにくい公共的貢献を可視化し、社会に共有することが重要になると考えられます。このような対応は、博物館が社会のインフラとしていかに機能しているかを説明する努力の一つといえるでしょう。
文化施設に求められる公共性とは、単に無料開放や誰でも入れることだけではありません。むしろ、「その施設が社会全体の中でどのような役割を果たし、その成果をどのように社会に戻しているのか」を説明し、共感や納得を得るプロセスそのものが、公共性の実現につながるのです(Scott, 2003)。
一方で、近年の制度設計においては、公共文化施設の評価指標が政策的・財政的な目的に即して定められる傾向が強まり、博物館の社会的成果があらかじめ「望ましいもの」として想定された枠組みの中に押し込められてしまう危うさも指摘されています(Newman, 2013)。たとえば「地域活性化への貢献」「経済効果の可視化」といった成果が強調される一方で、本来的な博物館の使命である長期的な教育的・文化的役割が軽視される可能性もあります。
博物館に求められる公共性とは、制度が期待する成果に単に従うのではなく、むしろ館自身がその社会的役割を自律的に定義し、社会と対話しながら成果をつくり出し、還元していくプロセスにあります。それは、単なる評価項目の達成ではなく、「なぜそれを行うのか」「誰にどのような意味があるのか」といった問いに、丁寧に応答していく姿勢にほかなりません。
教育的成果の波及としての社会還元
博物館は、来館者に新たな視点や知識を提供する場であると同時に、対話や探究を通じて学びを深める「教育の空間」として機能しています。近年、多くの博物館では、単に展示を見せるだけでなく、来館者が自らの生活や社会に引き寄せて考えられるような参加型・対話型のプログラムを展開しています。
たとえば、ある地域の歴史博物館が、地元中学校と連携して、古写真を手がかりに地域の戦後復興の歩みを調べるワークショップを行ったとします。生徒たちはその過程で家族や地域の高齢者にインタビューを重ね、地域の歴史を自らの視点で再構成していきます。こうした活動は、生徒にとって「知識を得る」だけでなく、自分たちの暮らす地域への理解と誇りを育む機会となり、地域社会とのつながりを深める効果も期待されます。
また、美術館では、認知症の高齢者とその家族を対象にした「アートを通じた対話プログラム」が実施されることがあります。展示された作品を前に語り合うことで、参加者が安心して自己表現し、他者とつながる体験が生まれています。このような教育的活動は、医療や福祉の分野とも連携しながら、個人の尊厳や社会的つながりを支えるものとなっています。
こうした教育的成果を社会的価値として捉え、定量的に可視化する枠組みとしてSROI(社会的投資収益率)も注目されています。たとえば、英国の美術館Turner Contemporaryでは、地域住民を巻き込んだ教育プログラムによって、若者の就労意欲や地域への帰属意識が向上したことが報告され、その社会的効果がSROIで計測されました(Jackson & McManus, 2019)。
このように、博物館における教育的活動は、来館者一人ひとりの学びにとどまらず、地域全体の関係性や価値観の再構築にもつながっていきます。教育は成果そのものであると同時に、それを社会に開くための「手段」でもあります。博物館の教育的成果とは、展示室の中にとどまることなく、社会全体にじわじわと広がっていく還元のプロセスでもあるのです。
地域資源としての貢献としての社会還元
博物館は、地域に存在する文化資源を活用しながら、観光、まちづくり、コミュニティ形成といった多様な分野において貢献することが期待されています。特に近年では、来館者サービスの充実だけでなく、地域住民との関係構築や、行政・企業・市民団体との連携による共創型の取り組みが注目を集めています。
たとえば、ある地方都市の博物館が、地元商店街と連携して地域の産業史をテーマとした企画展を開催し、期間中にスタンプラリーやトークイベントを併催したとします。このような活動は、地域の経済に一定の波及効果をもたらすだけでなく、住民の記憶や経験を展示の一部として取り込むことで、文化資源の再発見と共有につながる効果も期待されます。
また、博物館が地域の課題解決に寄与する「文化的中間支援組織」として機能するケースもあります。たとえば、人口減少や高齢化が進む地域において、博物館が他の文化施設や学校、福祉団体とネットワークを形成し、「地域のこれからを考える対話の場」を提供する取り組みが模索されています。こうした活動は、展示や講座といった従来の枠組みを超えて、地域住民との関係性そのものを成果として評価する視点を必要とします。
地域資源としての博物館の貢献を可視化するうえでは、定量的な経済波及効果に加えて、文化的・社会的ネットワークの構築や住民の帰属意識といった定性的な成果にも注目する必要があります。SROIの枠組みでは、地域住民の参加意欲の向上、協働による新たな社会関係の構築といった点が、重要な社会的リターンとして位置づけられています(Whelan, 2015)。
このように、博物館は単なる文化の「保管庫」ではなく、地域社会の一員として信頼と共感を築きながら、社会的価値をともに創出していく存在です。地域の課題や文脈に応じた多様な連携のあり方が、博物館の成果を社会へと還元する力となるのです。
博物館の成果をどう「見える化」するか ― SROIという視点
これまでの節で見てきたように、博物館の成果は、公共性の実現、教育的インパクト、地域社会とのつながりといった多様な形で社会に還元されています。しかし、こうした成果の多くは、数値化が難しい「見えにくい価値」であることが多く、第三者にわかりやすく伝えることが困難とされてきました。そこで注目されているのが、社会的投資収益率(SROI:Social Return on Investment)という枠組みです。
SROIは、活動によって生じる社会的・環境的・文化的な成果を金銭的価値として可視化し、どれだけの「社会的リターン」が得られたかを分析する手法です。単に経済的な効果を測るのではなく、人々の行動変容や意識の変化、つながりの創出といった無形の価値を数値として提示できる点に特徴があります(Whelan, 2015)。
SROIの分析は一般に、以下の6つのステップで構成されます。
- 目的とステークホルダーの明確化
- 成果のマッピング(アウトカムの特定)
- インディケーター(指標)の設定とデータ収集
- 成果の金銭的換算(マネタイズ)
- 因果関係の分析(死重、代替効果、帰属など)
- 最終的なSROI比率の算出と報告
たとえば、英国のTurner Contemporaryでは、若年層を対象にしたアートプログラムを通じて、自己肯定感や社会参加意欲の向上といった成果が確認されました。その影響を「将来的な雇用確率の上昇」や「メンタルヘルスコストの軽減」といった経済指標に翻訳し、1ポンドの投資に対して4ポンドの社会的価値が生まれたとするSROI比が示されています(Jackson & McManus, 2019)。
このような評価枠組みは、従来の来館者数や満足度調査とは異なり、成果を「外部との関係性の中で再定義」することを可能にします。特に、博物館が行政や助成機関と連携する際や、寄付・ファンドレイジングを行う際には、こうした説明責任と成果の「見える化」が重要な意味を持つようになっています。
一方で、SROIはすべての成果を測定可能にする魔法のツールではありません。成果の金銭換算には主観的判断が含まれ、また過度な定量化が現場の創造性や柔軟性を損なう可能性も指摘されています。さらに、SROIは実施に一定のコストとスキルを要するため、小規模館では導入が難しい場合もあります。
それでも、SROIという視点は、博物館が「何を大切な成果と考え、それをどのように社会と共有するか」という問いを立て直す契機となります。博物館の社会的意義を伝えることは、単なる報告義務ではなく、公共機関としての自己定義であり、社会との信頼関係を築く営みでもあるのです。
まとめ:博物館の社会還元をどう捉えるか
本稿では、博物館の活動によって生まれる成果が、どのように社会へと還元されているのかを、「公共性」「教育」「地域貢献」という三つの視点から考察してきました。博物館は、公共資源としての説明責任を果たす存在であると同時に、来館者一人ひとりの学びや気づきを支える教育の場であり、地域の課題解決や文化創造に貢献する拠点でもあります。
このような多面的な役割を担うなかで、博物館の成果は単なる「イベント数」や「来館者数」といった数値では捉えきれない複雑な意味を持ちます。社会的関係の構築や、個人の意識変容、地域への帰属感といった成果は、しばしば制度的には評価しにくい「見えにくい価値」として扱われてきました。しかし、まさにそうした成果こそが、博物館が社会のなかで果たしている本質的な役割を映し出しています。
近年注目されているSROIのような枠組みは、こうした社会的・文化的価値を定量・定性の両面から捉え直し、第三者に伝えやすい形で可視化する手法として有効です。同時に、評価の手段だけでなく、博物館自身が「何を成果と考えるのか」「なぜそれを社会に届けるのか」といった根本的な問いを持ち続けることもまた重要です。
社会還元とは、単に活動の結果を報告する行為ではありません。それは、博物館という存在が、社会とともに価値を創り、共有し続けるプロセスそのものなのです。成果を測ることは、博物館と社会との関係性を見つめ直すことであり、公共性・教育・地域性といった軸を通じて、博物館が果たす役割の核心に迫る行為でもあります。参考文献
Jackson, A., & McManus, J. (2019). Museum activism. Routledge.
Newman, A. (2013). Imagining the social impact of museums and galleries: Interrogating cultural policy through an empirical study. International Journal of Cultural Policy, 19(1), 120–137.
Scott, C. (2003). Museums and impact. Curator: The Museum Journal, 46(3), 293–310.
Whelan, G. (2015). Measuring the immeasurable: Capturing intangible outcomes in museums using SROI. Museum Management and Curatorship, 30(2), 105–126.
参考文献
- Jackson, A., & McManus, J. (2019). Museum activism. Routledge.
- Newman, A. (2013). Imagining the social impact of museums and galleries: Interrogating cultural policy through an empirical study. International Journal of Cultural Policy, 19(1), 120–137.
- Scott, C. (2003). Museums and impact. Curator: The Museum Journal, 46(3), 293–310.
- Whelan, G. (2015). Measuring the immeasurable: Capturing intangible outcomes in museums using SROI. Museum Management and Curatorship, 30(2), 105–126.