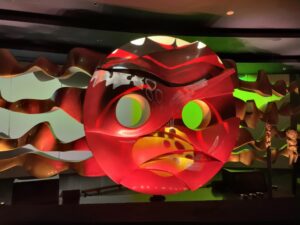はじめに
デジタル技術の進展は、私たちの文化資源との向き合い方を根本から変えようとしています。博物館における資料のデジタル化もその一端であり、近年では「デジタルアーカイブ」としての構築が急速に進められています。かつては、デジタル化といえば主に保存のための記録作業という印象が強かったかもしれません。しかし現在では、所蔵資料を未来に伝えるための手段としてだけでなく、誰もがアクセスできる「知のインフラ」としての性格を強めています。
このような状況を受け、博物館の制度的枠組みにも変化が起きています。2022年に公布された改正博物館法(2024年度施行)では、博物館の役割として「資料の保存および活用に関する措置を講ずること」が明記され、さらに「博物館資料その他の情報のデジタル技術を活用した管理および提供」が努力義務として盛り込まれました(文化庁 博物館総合サイト)。この改正は、博物館がデジタル環境に適応し、地域や社会との関係性をより開かれたものへと再構築していく必要があるという、政策的メッセージの表れといえます。
しかし、デジタルアーカイブの推進には多くの課題が伴います。例えば、保存の観点では、デジタルデータの形式や保存環境が技術革新によって短期間で陳腐化するという問題があります(Rivero Moreno, 2018)。また、オンラインで公開されたアーカイブが、どのような利用者にどのように使われているのかを把握し、柔軟に対応していく必要もあります(Villaespesa, 2019)。加えて、デジタル化に対応できる専門人材の不足や、博物館・図書館・文書館など複数の専門分野との協働の難しさも、制度的・運用的な課題として無視できません(Trant, 2009)。
このように、デジタルアーカイブの構築と運用は、単なる技術の導入にとどまらず、博物館のあり方そのものを問い直すテーマといえるでしょう。私たちは、何を残し、どのように伝え、誰と共有するのか。その問いの先にあるのが、アーカイブという営みなのです。
本記事では、博物館におけるデジタルアーカイブをめぐる諸課題について、以下の3つの視点から整理していきます。第1に、デジタル保存をめぐる技術的・理論的課題。第2に、ユーザーアクセスと社会的利活用をめぐる課題。第3に、制度・人材・組織といった持続可能性の課題です。これらの視点を通じて、改正博物館法の背景にある現代的要請を読み解き、博物館経営におけるアーカイブ戦略の今後を展望していきます。
保存の課題 ― 技術は永遠ではないという前提から出発する
デジタルアーカイブは、その語感から「完璧な保存」や「永続的な記録」を連想させるかもしれません。しかし現実には、デジタル技術に依存した保存は決して万能ではなく、むしろ多くの不確実性を内包しています。保存形式の選択や保存環境の整備、そして将来のアクセス可能性に至るまで、あらゆる局面で博物館は「保存とは何か」を再定義することを迫られているのです。
とりわけ、ファイル形式やメディアの脆弱性は深刻な課題の一つです。例えば、現在主流となっている画像フォーマットや動画形式であっても、将来的にその再生環境が失われる可能性は高く、定期的な「フォーマット移行(migration)」や「エミュレーション(emulation)」といった技術的対応が不可欠になります。さらに、保存媒体自体も永続的ではなく、ハードディスクや光ディスク、さらにはクラウド環境においても、物理的損耗やシステム移行による情報損失のリスクは避けられません(Rivero Moreno, 2018)。
このように、デジタルデータの保存は一度完了すれば終わるものではなく、「変化を通じた保存(permanence through change)」という動的な視点が求められます。データの継続的な再構築を通じてこそ、文化資料としての価値が未来に継承されるのです。
さらに注目すべきは、保存対象が「データそのもの」だけではないという点です。博物館資料の持つ意味や文脈、背景情報、いわば資料の「物語」そのものもまた、アーカイブ化において不可欠な要素となります(Cameron & Kenderdine, 2007)。たとえば、ある工芸品の高解像度画像だけが保存されても、その制作背景や使用目的、過去の展示歴などの情報が欠けていれば、将来的にその文化的意味を正確に読み取ることは困難になるでしょう。
このため、アーカイブにはメタデータの設計と管理が極めて重要となります。作品名、作者、制作年といった基本的事項だけでなく、キュレーターによる解釈や、関連文献、展示コンテキストなど、文脈を豊かにする多層的情報が求められます。デジタル化とは、単に物理的資料をスキャンする作業ではなく、知識の構造をデザインし直す営みでもあるのです。
国際的にも、こうした保存課題に対応するための標準化や枠組みづくりが進められています。Dublin CoreやCDWA(Categories for the Description of Works of Art)などのメタデータ標準は、アーカイブの相互運用性を高める基盤として広く採用されています。また、UNESCOによる「デジタル遺産憲章」や、欧州連合のEuropeanaプロジェクトなどは、文化資源のオープンアクセスと長期保存を両立する仕組みの整備を推進しています。
しかしながら、実際の現場では、予算や人材の限界により、こうした理想的な保存体制をすぐに整えることは容易ではありません。何を保存し、何を選別するかという判断は、限られたリソースの中で常に行われており、その判断には一定の倫理性や社会的責任が伴います。すなわち、保存とは選別の行為でもあり、そこには「見えなくなるもの」への想像力も求められるのです(Trant, 2009)。
このように、デジタルアーカイブにおける保存は、単なる技術的課題ではなく、文化の意味と継承のあり方そのものにかかわる根本的な問いを含んでいます。未来に何を残すのか。その問いに対する答えを支えるためにも、博物館は保存という営みを不断に問い直し続ける必要があるのです。
アクセスと利用の課題 ― 情報の「ひらかれ方」を問い直す
保存されたデジタルアーカイブは、それ自体が文化資源としての価値をもつ一方で、実際にどのように利用されるかによって、その意味や機能が大きく変化します。博物館におけるアーカイブが本来果たすべき役割は、単なる記録の蓄積にとどまらず、来館者や市民、研究者、教育関係者など多様な利用者との知的な対話を可能にする「共有の基盤」となることです。しかし、その実現にはいくつかの課題が存在します。
第一の課題は、アーカイブが想定する「利用者像」の多様性です。オンラインで公開された資料群は、研究者や専門家だけでなく、教育目的の利用や、趣味としての閲覧、創作活動の参考資料といったさまざまな動機をもつ人々によって利用されます。メトロポリタン美術館の調査では、ウェブ利用者が少なくとも6つのセグメントに分類されることが示されており、それぞれが異なる目的や関心を持っていることが明らかになっています(Villaespesa, 2019)。このような多様なユーザー層に向けて情報を整理し、届ける設計が求められているのです。
次に、情報設計のあり方も課題となります。博物館のウェブサイトでは、多くの場合、専門的な分類法や検索機能が用いられていますが、それが非専門家にとってはアクセス障壁となることがあります。利用者は何らかの目的や期待をもってアクセスしているにもかかわらず、分類体系や用語、ナビゲーションの難解さによって目的の情報にたどり着けないケースも少なくありません(Marty, 2008)。こうした事態を避けるためには、専門性と一般性のバランスをとった情報設計が必要です。
また、技術的なアクセスの壁も見逃せません。アーカイブの構築や公開においては、高解像度画像やインタラクティブな機能を搭載することが多くなっていますが、それらは高速通信環境や高性能端末の利用を前提としています。しかし、こうした設計は一部の利用者、特に高齢者や地域的制約のある人々にとってはアクセス障害となりかねません。デジタルアートの保存や活用に関する議論においても、技術に依存しすぎない設計と、公共性に配慮したオープンなアクセス環境の重要性が指摘されています(Rivero Moreno, 2018)。
一方で、アーカイブの利用は単なる「閲覧」にとどまらず、「参加」や「再解釈」へと拡張しつつあります。博物館の展示に連動して、デジタルデータを視覚的・触覚的に体験できるような「Tangible Data Souvenirs」のような事例は、利用者が記憶や発見を持ち帰ることを可能にしています(Petrelli et al., 2017)。このようなアプローチは、アーカイブが一方向的な情報提供ではなく、利用者との関係性の中で価値を再構築する場であることを示しています。
さらに、アーカイブは文化的・政治的文脈において「誰がアクセスできるのか」「誰が語る権利をもつのか」という問題とも密接に関係しています。デジタルアーカイブは一見中立的に見えますが、そこに含まれる資料の選定、記述のあり方、検索可能性などは、潜在的に排除や偏りを生む可能性があります。この点においても、情報は単に保存されるべきものではなく、継続的に問い直され、対話されるべきものであるという視点が必要です(Geismar & Knox, 2021)。
現代の博物館は、こうした情報環境=「インフォスフィア」において、単なる情報の保管庫ではなく、社会とつながる知的な交差点となることが期待されています。アーカイブは閉じられた記録ではなく、ひらかれた関係性のプラットフォームとして設計されるべきなのです(Simone et al., 2021)。
持続可能性の課題 ― 技術を支える「人と仕組み」をどう育てるか
どれほど優れたデジタルアーカイブが構築されたとしても、それを維持し続ける体制がなければ、数年後には更新が止まり、アクセスできなくなる可能性があります。デジタル技術の進展は速く、環境も日々変化する中で、アーカイブを継続的に機能させるためには、長期的な視野での体制整備が不可欠です。保存技術や公開システムの整備だけでなく、それらを日常的に「支える人」と「動かす仕組み」がなければ、アーカイブは持続しません。
多くの博物館において、アーカイブ事業は外部からの補助金や短期的なプロジェクトによって進められてきました。事業期間中は外部の専門家や技術者の協力を得て一定の成果が得られる一方で、その後の保守や更新は現場の通常業務として吸収され、時間や人材の不足によって機能不全に陥る例も見られます。技術が進歩する一方で、それを継続的に使いこなす体制づくりは後手に回りがちです。
こうした状況を制度的に支えていくためには、職能のあり方を見直す必要があります。従来、博物館・図書館・文書館はそれぞれ独立した専門性と組織体制を持っており、デジタルアーカイブのように分野を横断する業務においては、担当者の位置づけが曖昧になりやすいという指摘があります(Trant, 2009)。デジタル技術の運用は「情報システム部門」や「外注」に任せるものとされがちですが、実際には資料の意味理解や保存価値の判断を伴うため、学芸員や資料管理担当者との連携が不可欠です。
この点で重要になるのが、アーカイブに関する実務を担う人材の育成です。情報科学、保存論、博物館学、メディア工学といった複数領域にまたがる知識が求められるため、個人に過度な負担をかけるのではなく、専門性の異なるメンバーがチームとして関与できる体制が望まれます。さらに、誰がアーカイブを「語る」か、「操作する」かという権限や責任の所在も明確にする必要があります(Geismar & Knox, 2021)。このためには、制度内での職階や業務分担においてアーカイブ業務の重要性を正当に評価し、継続的な研修機会を確保することが求められます。
また、博物館内部での意思決定構造も見直す必要があります。アーカイブ関連の方針が一部の上層部やIT部門だけで決められてしまうと、現場の実務と乖離した形で運用されるリスクが高まります。アーカイブは資料の収集・記録・保存・活用のすべてに関わる横断的な業務であるため、組織内の多部門が連携し、共有責任を持つ体制が必要です。博物館を価値創造のプロセスとして捉えるバリューチェーンの視点からも、こうした部門間の連携は組織の持続可能性に直結します(Simone et al., 2021)。
さらに、アーカイブの継続性を支えるうえで、外部との協働は不可欠です。技術の更新やノウハウの蓄積には限界があるため、研究機関、IT企業、他の博物館・文化機関とのネットワークを活用することで、リスクを分散しながら質の高いアーカイブを維持することが可能となります。デジタル文化資源は、単館単独で完結するものではなく、複数の主体が共創し、共有する社会的インフラであるべきだという考え方は、国際的にも広まりつつあります(Cameron & Kenderdine, 2007)。
このように、デジタルアーカイブの持続可能性は、単なるシステム運用の問題ではありません。それは、人材育成、職能設計、組織構造、そして外部連携といった、博物館経営の基盤全体に関わる課題なのです。未来に開かれたアーカイブを実現するためには、技術だけでなく、それを支える人と仕組みのあり方を問い直し、戦略的に構築していくことが求められます。
アーカイブは未来への橋 ― 博物館に求められる戦略的視座
デジタルアーカイブは、文化資源を未来へと橋渡しする手段であると同時に、その社会的な意味を再構築する営みでもあります。保存、アクセス、持続性といった基本的な課題を乗り越えるためには、単なる技術導入や資料整理の延長ではなく、アーカイブを「活用される知の基盤」として捉える視点が必要です。博物館がどのような戦略的意図をもってアーカイブを構築し、どう社会と共有するのかが、今後の重要なテーマとなっていくでしょう。
アーカイブは、保存されるだけではその価値を十分に発揮できません。むしろ、使われることでその意味が立ち現れ、再評価されていくという特性を持っています。デジタルアーカイブによって、資料へのアクセスが時空を超えて可能になり、検索や分析、再編集といった多様な活用が生まれます。教育や研究はもちろん、創作や市民参加型プロジェクトなど、想定される活用の幅は広がり続けています。こうした活用こそが、アーカイブを「文化的リソース」として位置づける鍵となるのです。
その一方で、アーカイブに蓄積された情報は中立的なものではなく、収集・記述・分類の過程で博物館の価値観や判断が反映されています。何を保存し、どのように記録するかという選択は、同時に何を見えなくしているかという問いでもあります。つまり、博物館はアーカイブを通して社会に語りかける「編集者」の役割を担っているのです。情報をどう意味づけ、どのような文脈で提供するのか。そこには、文化資源の継承を担う立場としての倫理的責任も含まれています。
このように考えると、デジタルアーカイブは単なる技術的インフラではなく、博物館のミッションを体現する戦略的資源であることが分かります。展示、教育、調査研究、地域連携といった活動と密接に関係しながら、アーカイブはそれらの基盤を支える存在です。したがって、アーカイブの整備・活用は、ITや資料部門の個別施策ではなく、博物館全体の経営戦略の中に明確に位置づけられるべきでしょう。
さらに、アーカイブの未来を考えるうえで欠かせないのが、「共創」という視点です。博物館が独占的に知識を管理・提供するのではなく、来館者、地域社会、他機関、あるいはAIのような技術的主体とともに、知識を再構築していく場としてのアーカイブのあり方が求められています。こうした考え方は、文化人類学やデジタルヘリテージの分野でも強く提起されており、アーカイブを「動的で対話的な文化的実践」として捉えるべきだという主張がなされています(Geismar & Knox, 2021;Cameron & Kenderdine, 2007)。
これからの博物館は、単に資料を保存し、説明するだけの存在ではありません。知識を社会と共有し、未来へとつなぐ「知の仲介者」としての役割がますます求められています。デジタルアーカイブは、その中核を担う構造の一つです。何を保存し、どう伝えるか。その選択の積み重ねが、将来の社会にとっての「文化のかたち」をつくっていくのです。
デジタルアーカイブを戦略的に設計し、運用し続けることは、技術的課題への対応だけでなく、社会的責任を果たす行為でもあります。アーカイブは、単なる蓄積ではなく、未来社会に対する「責任ある編集」の営みである。その認識を出発点として、制度・人材・組織のすべてを結びつける統合的な取り組みが、今後の博物館経営においてますます求められていくでしょう。
参考文献
- Cameron, F., & Kenderdine, S. (Eds.). (2007). Theorizing digital cultural heritage: A critical discourse. MIT Press.
- Geismar, H., & Knox, H. (2021). Digital objects in context: Working with digital heritage. UCL Press.
- Marty, P. F. (2008). Museum websites and museum visitors: Digital museum resources and their use. Museum Management and Curatorship, 23(1), 81–99.
- Petrelli, D., Ciolfi, L., van Dijk, D., Hornecker, E., Not, E., & Schmidt, A. (2017). Integrating material and digital: A new way for cultural heritage. Interactions, 24(4), 36–39.
- Rivero Moreno, M. J. (2018). Preservation strategies for digital art: Permanence through change. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, 8(2), 229–241.
- Simone, L., Tamm Hallström, K., & Gustafsson, I. (2021). The value of museums: Enhancing societal relevance through value creation. Museum Management and Curatorship, 36(3), 209–226.
- Trant, J. (2009). Emerging convergence? Thoughts on museums, archives, libraries, and professional training. Museum Management and Curatorship, 24(4), 369–387.
- Villaespesa, E. (2019). Deepening engagement through digital tools: A case study of The Met’s online audiences. Journal of Digital & Social Media Marketing, 6(3), 257–267.