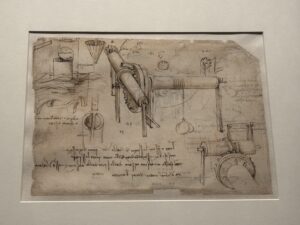はじめに:教育活動の場としての博物館、そして「連携」の意味
博物館は、単に資料を展示・保存する空間にとどまらず、来館者にとっての学びの場としても重要な役割を果たしています。近年では、学校教育や地域社会における学習機会の多様化に対応するかたちで、博物館の教育的機能が再評価されるようになってきました。とりわけ探究学習やSTEAM教育の進展を背景に、博物館は「学習を補完する場」から「共に学ぶパートナー」へと、その位置づけを変えつつあります。
学校団体による博物館訪問に関する研究では、展示を見るという行為だけでなく、そこで交わされる対話や協働的な活動の中に学びの本質があることが指摘されています。とくに、教育的成果は生徒と教師、そして博物館職員との相互作用によって形成される社会的なプロセスであるという視点が重視されています(Griffin, 2004)。
しかし、単独の博物館だけで多様な教育ニーズに応え続けることは容易ではありません。財源や人材、時間といった資源には限りがあるため、外部との連携によって教育活動の幅と深みを広げる必要性が高まっています。他館、学校や大学、地域の社会教育施設、さらには企業などと連携することで、それぞれの強みを生かし合いながら、より豊かな学習環境を創出することが可能になります。
実際に、博物館と大学が連携し、障害のある来館者へのアクセシビリティ向上をテーマとした教育プログラムを共に開発・実施した事例では、両者の専門性が補完的に作用し、社会的包摂を促す学習の枠組みが形成されました(Silverman & Bartley, 2013)。また、教育機関との協働によって学芸員の専門知や教育理論が現場に還元される循環も生まれています。
こうした連携は単に「一緒に取り組む」ことにとどまらず、より深い水準での協働へと発展する可能性を持っています。連携の段階は、基本的な情報交換にとどまる「連絡(cooperation)」から、調整をともなう「調整(coordination)」、そして目標や価値観を共有し合意のもとに取り組む「協働(collaboration)」へと段階的に深化していきます(Kampschulte & Hatcher, 2021)。教育分野におけるリサーチ・プラクティス・パートナーシップ(RPP)という概念もまた、長期的かつ対等な関係性の中で学びの成果を高めていく枠組みとして注目されています(Coburn & Penuel, 2016)。
本記事では、博物館がいかにして他館や教育機関、企業等と連携しながら教育活動を展開しているのかについて、国内外の実践事例を取り上げつつ、連携の意義と可能性について考察していきます。連携による教育活動が、どのように社会とつながり、来館者の学びを支えているのかを明らかにすることが、本稿の目的です。
他館との連携:専門性の共有と教育資源の拡充
博物館は、展示や資料の保存だけでなく、社会における学びの場としての役割も担っています。とくに教育活動においては、来館者の年齢や関心、学習目的が多様であるため、すべてのニーズに一館で対応するのは難しいのが現実です。限られた人材や予算の中で柔軟かつ質の高い学習機会を提供していくためには、他の博物館との連携が極めて有効な手段となります。
他館との連携では、教育資源の共有や人的交流を通じて、学習内容の広がりと深まりが実現します。専門的なコレクションや展示技術、教育ノウハウを持ち寄ることで、単独の博物館では実現が難しい多角的な学習プログラムを構築することができます。例えば、複数の博物館が協力して巡回展を実施したり、地域連携型の出前授業を展開したりする事例では、展示を届ける範囲や対象者の層が拡大し、学びの機会が地域全体に広がっています。
具体的な実践例としては、「ミュージアム・イン・スクール」と呼ばれる取り組みが挙げられます。これは博物館が学校の教室に出張し、そこを一時的に展示空間へと変えることで、児童生徒に身近な学びを届けようとするものです。このプログラムでは、学芸員と教員が連携して教室展示を構成し、子どもたちは教室にいながら展示と対話的に関わる体験を得ることができます(Bailey, 1998)。このような事例は、教育現場と博物館が物理的にも心理的にも接近し、より豊かな学習環境を創出していることを示しています。
さらに、展示そのものを複数の機関が協働して設計するようなプロジェクトもあります。たとえばEXPOneerプロジェクトでは、異なる博物館や大学の専門家が集まり、展示のコンセプト立案から解説文の作成、関連教育プログラムの設計までを共に行っています。このプロジェクトでは、展示が単なる情報提供の手段ではなく、「共に問い、共に考える」学びの場として設計されており、関係者のあいだで知見や価値観を共有する過程そのものが教育活動の一部となっています(Kampschulte & Hatcher, 2021)。
このように、他館との連携は単なる資源のやりとりではなく、教育の目的や方法を共に考え、実践を重ねることで深まっていく関係性です。しかしながら、連携にはいくつかの課題も存在します。たとえば、関係機関ごとの目的のずれや役割分担の不明確さ、またスケジュールや組織文化の違いなどが、協働の障壁となることがあります。こうした課題に対処するためには、事前に目的や期待値を明確にし、丁寧な調整と継続的な対話を重ねることが求められます。
他館との連携は、博物館教育の質と射程を大きく広げる可能性を持っています。異なる専門性や視点を取り込むことによって、展示や教育プログラムはより多様で柔軟なものとなり、来館者にとっての学びも一層深まります。今後、こうした連携が一過性の取り組みにとどまらず、持続的で信頼に基づく協働へと育っていくことが、博物館の社会的役割をより豊かにする鍵になるといえるでしょう。
学校や大学との連携:双方向の学びを実現するために
博物館が果たす教育的な役割は、学校や大学との連携を通じてさらに深まりを見せています。かつては、博物館が学校の授業を「補完する存在」として扱われていた時期もありましたが、現在では、相互に学び合いながら共に教育の価値を高めていく「対等なパートナー」としての関係性が重視されるようになってきました。このような変化の背景には、教育現場における探究的学習やアクティブ・ラーニングの浸透があり、博物館の空間や資料が、教室では得られない体験的な学びを提供できる場として再評価されていることが挙げられます。
学校との連携においては、単なる「見学」や「鑑賞」にとどまらず、博物館スタッフと教員が事前に目的を共有し、訪問後の振り返りまでを含めた連携が効果を生みます。生徒の学習効果を高めるには、博物館訪問の前・中・後の三段階すべてにおいて教育的支援が求められます(Griffin, 2004)。また、博物館の教育スタッフと生徒との対話も重要な要素です。科学館における観察では、生徒の発言に対してエデュケーターが問い返しや深掘りを行うことで、科学的思考が活性化し、単なる知識の受け取りを超えた学びが成立していました(Shaby et al., 2018)。
大学との連携では、より専門的なテーマに基づく教育プログラムが展開されています。たとえば、障害者のアクセシビリティに関する教育活動では、博物館と大学の研究者が共同でプログラムを設計し、学生と来館者が共に学ぶ場を創出する取り組みが行われました。この実践では、大学の研究知と博物館の実務経験が補完的に機能し、教育の社会的意義と実効性が高められています(Silverman & Bartley, 2013)。こうした事例は、博物館が社会課題に対する教育的応答力を持つ機関であることを示す好例といえます。
また、教職大学院との連携を通じて、教育者養成に博物館が積極的に関与する動きもみられます。美術館と大学が協力し、教職課程の学生に向けた実習型プログラムを提供する取り組みでは、学生が美術館教育の現場に入り、実践を通じて理論を学び直す機会が提供されていました。一方、美術館側にとっても、教育者を目指す学生の視点を取り入れることで、教育プログラムの改善や発展につなげることができるという相乗効果が生まれています(Bobick & Hornby, 2013)。
このような学校・大学との連携は、知識や資源の提供にとどまらず、博物館と教育機関の双方が学び合う「共学的パートナーシップ」として発展していくことが期待されます。ただし、連携の持続にはいくつかの課題もあります。たとえば、学校ごとのカリキュラムとの整合性、時間的制約、学習成果の評価方法などが挙げられます。加えて、博物館側も教育制度や学校文化を十分に理解し、教育機関のニーズに応じた柔軟な対応が求められます。
博物館と教育機関が双方向の学びを重ねていくことで、展示やプログラムはより教育的に意味のあるものとなり、来館者にとっても深く記憶に残る体験を提供できるようになります。今後は、こうした連携をさらに深化させ、持続的かつ対等な協働の仕組みを構築していくことが、博物館教育の質を高めるうえで不可欠になるでしょう。
企業との連携:職場学習と博物館教育の融合
博物館が企業と連携して教育活動を展開する動きは、近年注目を集める分野の一つです。生涯学習の重要性が高まり、社会人を対象とした学びの機会が求められる中で、職場を離れた「非日常の学びの空間」としての博物館の価値が再評価されています。企業における人材育成や組織開発においても、創造性や共感力といった能力の向上が重視されており、それらを育む環境として、博物館が新たなパートナーとなり得る可能性を示しています。
企業との連携は、単なるスポンサーシップやイベント協賛といった資金的関係にとどまらず、教育的な協働を含む実践へと発展しています。たとえば、企業の新入社員研修やリーダーシップ研修、チームビルディングといった能力開発の一環として、博物館空間を活用する事例が増えつつあります。作品を用いた観察力トレーニングや、展示を通じた価値観の共有活動などは、企業が求める人材育成と博物館が提供できる学びとが交差する領域です。
代表的な事例として、アメリカ・テネシー州のハンター美術館における企業研修プログラムが挙げられます。この美術館では、地域企業向けに独自の教育プログラムを提供しており、観察力や創造性、コミュニケーション能力を高めるためのセッションが展開されています。たとえば、美術作品を見ながら参加者が感じたことを言語化し、それをもとに議論することによって、相互理解や視点の多様性を養う構成がなされています。これらのプログラムは、企業の人材戦略と博物館の教育理念が重なり合う点に特徴があります(Causey, 2011)。
こうした取り組みによって、博物館にとっては新たな来館層の開拓や財政基盤の強化といった利点が生まれます。一方、企業にとっても、職場とは異なる環境で思考や対話を深めることができるため、組織の活性化や人材の成長にとって有意義な機会となります。このように、博物館と企業が協働することで、雇用主・従業員・地域社会の三者すべてに恩恵がもたらされる「三方よし」の学びの場が実現されているのです。
ただし、企業との連携には慎重な配慮も必要です。収益性を重視するあまり、博物館の公共性や中立性が損なわれる懸念も指摘されています。また、連携プログラムが一過性のイベントに終わってしまうケースや、企業側の期待と博物館側の教育的意図とのあいだにズレが生じることもあります。だからこそ、博物館は教育機関としての理念と責任を明確にしながら、連携の質と持続性を見極める視点を持つ必要があります。
今後は、教育と経営を両立させる枠組みの設計が求められます。たとえば、単発の研修にとどまらず、企業内教育との連携を長期的に継続していくプログラム設計や、成果を可視化する評価指標の導入が考えられます。また、地域の企業と協働して市民向けの公開講座を開催するなど、社会貢献活動と結びつけた展開も有効です。企業との連携は、博物館に新たな教育的フィールドを開くと同時に、社会に対して博物館の価値を発信する力強い手段となるのです。
連携による教育活動の意義と今後の展望
これまで見てきたように、博物館が他館や教育機関、企業などと連携して教育活動を展開することには、多くの意義があります。こうした連携は、単に外部の力を借りるというものではなく、博物館そのものの教育的価値や社会的役割を再定義する重要な契機となります。ここでは、連携によって広がる学びの射程、組織的な変化、評価の課題、そして今後の展望について整理し、教育的連携の可能性を総括します。
まず、連携によって博物館の学びの射程は大きく拡張します。学校や大学、社会教育施設との協働を通じて、児童生徒や学生はもちろん、現職の教員、障害者、高齢者、企業人など、これまでアプローチが難しかった多様な学習者層とつながることが可能になります。また、展示や教育プログラムに他者の視点や専門性が加わることで、博物館が提供する学びはより豊かで多角的なものになります。展示やワークショップが、来館者と職員、外部の協働者が共に考え合う「共創」の場となることは、まさに博物館の社会的価値を広げる取り組みといえるでしょう。
次に、こうした連携は博物館内部にも変化をもたらします。連携事業が教育部門だけにとどまらず、学芸・広報・経営といった他部門との協働を必要とすることで、組織の横断的な連携が促されます。さらに、外部との対話を通じて、博物館が自らのミッションや目指す方向性を見直す機会にもなります。連携によって新たな問いが持ち込まれ、それに応えるかたちで内部の仕組みや方針が見直されるという循環は、博物館の組織的柔軟性や応答力を高め、持続可能な経営にもつながります。
しかし、教育的連携の成果を適切に評価・可視化することは依然として課題です。ワークショップへの参加者数や満足度といった定量的指標だけでは、学習者の深い理解や価値観の変化、社会への波及効果などを捉えることはできません。とくに、博物館が果たす教育的貢献は長期的で非形式的な性質を持つため、その効果を証明するには多面的な視点が求められます。今後は、学習成果の質的評価やストーリーテリングによる事例共有、参加者の声を反映した報告の工夫などが、教育の「見えにくい価値」を伝える手段として重要になるでしょう。
このような状況を踏まえると、今後の連携は単なる「プロジェクト型」から、「関係性構築型」へと転換することが求められます。つまり、短期的な成果やイベント的な連携にとどまらず、信頼と対話に基づく長期的なパートナーシップを構築することが必要です。そのためには、博物館の職員自身が単なる運営者や伝達者ではなく、「ファシリテーター」「コーディネーター」として、関係各所をつなぐ役割を担うことが求められます。
そして最も重要なのは、博物館を「共学共同体(learning community)」として再定義することです。学校、大学、企業、地域団体、市民――こうした多様な主体が、博物館という場を共有しながら学び合う関係性のなかで、博物館は単なる教育の提供者ではなく、共に考え、共に成長する社会のパートナーとなるのです。
このような視点に立つとき、連携による教育活動は、博物館の未来を切り拓く鍵となるといえるでしょう。
参考文献
- Bailey, E. G. (1998). Museum in the school: Developing museum–school programs. The Journal of Museum Education, 23(2), 20–24.
- Bobick, B., & Hornby, H. (2013). From exposure to integration: The arts and teacher education in a museum-based learning context. International Journal of Education & the Arts, 14(19), 1–21.
- Causey, K. (2011). A museum as a training ground for corporate America: Hunter Museum of American Art. Journal of Museum Education, 36(2), 141–151.
- Griffin, J. (2004). Research on students and museums: Looking more closely at the students in school groups. Science Education, 88(S1), S59–S70.
- Kampschulte, L., & Hatcher, B. (2021). Making exhibits together: Teachers and museum educators as co-creators in the EXPOneer project. Journal of Museum Education, 46(1), 23–36.
- Shaby, N., Assaraf, O. B. Z., & Tal, T. (2018). Museum educators as learning partners: Changes in their beliefs and knowledge in the course of an academic course. International Journal of Science Education, Part B, 8(4), 307–323.
- Silverman, L. H., & Bartley, D. L. (2013). Accessibility and collaboration: Museum–university partnerships for universal design. The International Journal of the Inclusive Museum, 6(3), 1–14.