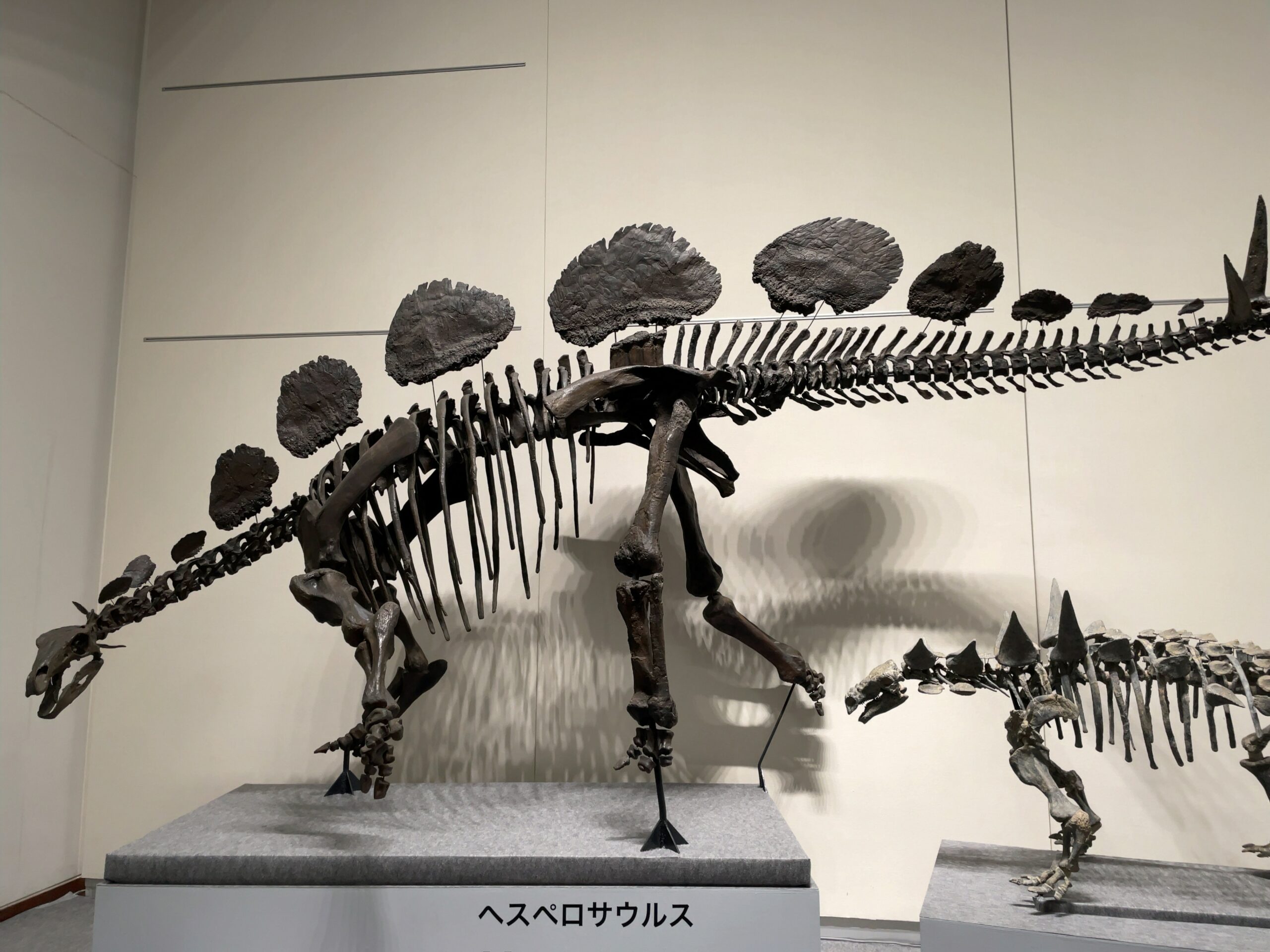はじめに
ICTが博物館経営にもたらす変化
近年、博物館におけるICT(情報通信技術)の導入は急速に進展しており、世界各地のミュージアムでその動きが加速しています。従来は展示や教育プログラムへの活用が主流でしたが、今日では運営管理や来館者対応、広報活動など、経営全体を変革する要素としても位置づけられるようになっています。特に新型コロナウイルス感染症の影響により、オンラインサービスや非接触型の館内ICTの需要が高まり、デジタル化の波は一層強まっています。日本国内でも、政府や自治体によるDX(デジタルトランスフォーメーション)推進の方針や、文化庁によるICT活用支援策などが整備されつつあり、博物館現場では実際の導入事例が着実に増えています。
なぜ「効率性」と「来館者体験」が重要なのか
現代の博物館経営においては、限られた人的・財政的リソースをいかに有効活用するかという「効率性」の向上が大きな課題となっています。公的施設としての社会的役割や公共性を守りながら、持続可能な経営を実現するためには、業務の合理化やサービスの質的向上が不可欠です。また、来館者のニーズや価値観の多様化が進む中で、「来館者体験」の質が集客力やリピーター獲得のカギとなっています。デジタル技術を活用することで、展示やガイダンスの個別化、参加型プログラムの展開、アクセシビリティ向上など、従来にはないサービス提供が可能となりました。これらは単なる運営効率化にとどまらず、博物館の社会的価値や存在意義を再定義する重要な要素となりつつあります。
本記事の目的とアプローチ
本記事では、ICTの導入が博物館経営にどのような変化をもたらすのかを、「効率性」「来館者体験」「デジタル戦略」という三つの視点から総合的に考察します。特に、近年の海外における実証的な研究成果や、先進的なデジタル施策を展開する博物館の事例、日本国内で進行する政策や現場の動向など、国際的かつ多角的な知見を参照しながら、経営実践と理論双方の観点から分析を行います。また、既存記事 「ICTを活用した展示とは? ― 博物館が提供する新しい鑑賞体験とその可能性」 では展示体験や来館者サービスの質的変化に主眼を置いていましたが、本記事は経営効率や組織戦略にも焦点を広げて解説する点に特色があります。今後の持続可能な博物館経営にとって、ICTの最適活用がどのような可能性と課題を内包しているのか、多角的に検討していきます。

博物館経営における「効率性」とデジタル戦略
博物館における効率性とは何か
博物館経営において「効率性」という言葉は、限られた人的・物的リソースを最大限に活用し、来館者数やサービスの質などの成果を高めるための経営指標を指します。従来、博物館は教育や文化の担い手として、その公共性や社会的価値が重視されてきましたが、近年は財政状況の厳しさや社会の多様な要請を受けて、より持続可能な運営が求められるようになっています。そのため、効率性の観点から、職員数や運営費といったインプットに対し、どれだけ多くのアウトプット(来館者数、イベント参加者数、収益など)を生み出しているかを評価する動きが強まっています。効率的な経営は、公共的価値の実現と経営の持続可能性を両立するための重要な基盤となっています。
デジタル化が注目される背景
現代社会ではデジタル技術の進歩が著しく、ICT(情報通信技術)導入による業務の効率化やサービス向上がさまざまな分野で推進されています。博物館も例外ではなく、DX(デジタルトランスフォーメーション)への取り組みが国内外で広がっています。背景には、財政的制約や来館者数の減少といった課題だけでなく、多様化する来館者の期待や新しい学びのスタイルへの対応、さらには新型コロナウイルス感染症の影響による非接触サービスへのニーズの高まりなど、社会的な要請が複合的に存在しています。また、文化庁や自治体による制度的支援や補助金も拡充されており、博物館現場でのICT導入は今や選択肢ではなく必須の経営戦略となりつつあります。こうした動向を受け、効率性とデジタル化の両立を目指す取り組みが加速しています。
ICT活用と経営効率化の基本構造
ICTは博物館の経営効率化にさまざまな形で寄与します。例えば、来館者の予約管理や展示解説、館内ナビゲーションなどの運営業務を自動化・省力化することで、職員の負担を軽減し、限られたリソースをより効果的に配分することが可能です。また、広報活動やデータ分析の分野でもデジタル技術が活躍しており、SNSを活用した情報発信や、来館者データの蓄積・分析によるマーケティングの高度化など、経営判断の質を高める取り組みが進んでいます。効率性指標としては、例えば「来館者数/職員数」や「来館者単価」「稼働率」などが用いられ、これらの指標改善に向けたICT活用が、持続的な博物館運営のカギを握るといえるでしょう。
実証研究にみるICT導入の効率化効果
イタリア国立博物館におけるICT導入の実践的示唆
博物館の現場では、限られた人員や予算の中で、どうすれば効率的かつ魅力的なサービスを来館者に提供できるのかという課題が常にあります。特に人手不足や経費削減の要請が強まる近年、多くの現場がICTの力に期待を寄せています。イタリア国立博物館の調査事例は、こうした現場の悩みに応えるヒントを多く含んでいます。この研究では、ICT導入の有無や種類ごとに、来館者数や業務効率がどう変化したかを具体的なデータで検証しています。
イタリアの現場では、スタッフの数や館の広さなど物理的な制約を補うために、館内ICTの導入が積極的に進められています。たとえば、スマートフォンを活用した館内ガイドアプリや、展示ごとに設置されたQRコードによるセルフ解説、多言語に対応したマルチメディア端末などは、来館者一人ひとりに合わせた情報提供や、個別ペースでの鑑賞を可能にしています。これにより、スタッフの説明業務が軽減され、混雑時にも案内の質が低下しにくいといったメリットが生まれています。また、障害者向けのバリアフリー案内や、子ども向けのインタラクティブなコンテンツもデジタルで簡単に追加でき、現場の多様なニーズに柔軟に対応できるようになっています(Guccio et al., 2020)。
館内ICTとオンラインICTの役割分担
ICTとひとくちに言っても、現場での使い方や目的には大きな違いがあります。特に重要なのは、「ICTなら何でもよい」のではなく、来館者が実際に館内で使うデジタル技術が、経営効率や来館促進に強く影響するということです。オンラインICT――たとえばウェブサイト、バーチャルツアー、SNSによる発信など――は、来館前の情報提供や事前学習、遠方からのアクセスといった点で役立ちます。新規顧客の獲得や認知度アップにも貢献しますが、来館者が「実際に足を運ぶ」動機や現場体験そのものを高めるには限界があることが実証研究から分かっています。
一方、館内ICTは、来館者の滞在中に直接働きかけることで、鑑賞体験を充実させ、リピーター獲得や評価向上に大きく寄与します。例えば、クイズ形式で展示を巡るデジタルスタンプラリーや、来館者が自分の興味関心に合わせて選べる解説メニューなどは、「また来たい」「家族や友人に勧めたい」という気持ちを自然に高めます。このような施策は、職員の数が限られる小規模館や、繁忙期に人手が足りない現場ほど、効果が実感しやすいでしょう。
効率的な館の特徴と、今すぐ実践できるポイント
イタリア国立博物館で効率性が高い館にはいくつか共通する実践ポイントがあります。まず、ICT導入が単なる省力化やデジタル化の“流行”ではなく、現場スタッフの働き方やサービス設計と一体化していることが挙げられます。例えば、タブレットやスマートフォンを使った自動解説は、案内スタッフの負担を減らすだけでなく、来館者一人ひとりに最適な情報提供を実現します。館内の案内表示もデジタルサイネージで統一すれば、イベントや展示変更にも即座に対応できるため、運営の柔軟性と効率が向上します。
また、館内での来館者の動線や滞在時間などのデータを収集・分析することで、次回の展示企画やサービス改善にも役立ちます。実際に現地では、来館者アンケートやアプリの利用ログを活用し、人気展示や改善点を客観的に把握しながら、限られたリソースを重点配分する戦略を取る館が増えています。こうした工夫は、日本の地方館や小規模館でもすぐに応用できるノウハウです。予算や人員が限られる現場ほど、ICTの力を「効率よく」使うことで、スタッフの負担を軽くし、来館者満足度も高める好循環を生み出すことが可能です。
現場にとってのヒントと今後の課題
ICT導入の効果を最大化するためには、「自館の課題や強みに合わせて技術を選択し、無理のない範囲から段階的に導入する」ことが大切です。オンラインICTは広報や遠隔サービス、来館前後の情報提供で力を発揮し、館内ICTは現場サービスと満足度の底上げに直結します。「どの分野をICT化すれば最大効果があるのか」をスタッフ全員で話し合い、現場に合った仕組みから始めてみることが、持続的な経営改善の第一歩となります。イタリアの博物館の事例は、その道筋と具体的な手法を示してくれます(Guccio et al., 2020)。今後は各館の運営方針や目標に合わせて、ICT活用と効率化のベストバランスを追求することが重要です。
来館者体験とICT活用の現状・課題
来館者はICTに何を求めているのか
博物館を訪れる来館者が、ICTにどのような価値や期待を持っているかは、現場のサービス設計にとって極めて重要なヒントとなります。近年の調査によれば、多くの来館者はICTを「情報を補足するための便利なツール」として認識しています。例えば、展示解説の読みやすさや、展示物にまつわる背景情報の取得、館内のナビゲーションなど、分かりやすく手軽に情報が得られることへの満足度は高い傾向にあります。一方で、博物館本来の魅力である「実物を目の前で見る体験」や、「スタッフ・他の来館者と直接対話する体験」への志向も依然として強く、ICTはあくまで“補助的な役割”であると捉えている来館者が多いのも事実です(Braña Rey & Casado-Neira, 2013)。
現場でのICT利用実態とその課題
実際の現場では、音声ガイドや情報パネル、タブレット端末など、ICTが活用される場面は確実に増えていますが、その多くが「受動的な利用」にとどまっています。来館者が自ら機器を操作したり、自分のペースで解説を聞いたりできる点は利便性向上に役立っていますが、利用率にはばらつきがあり、特に高齢者や小さな子どもなど、ICT機器への抵抗感がある層には十分に浸透していない現状も見受けられます。また、SNSやオンラインコンテンツを通じた情報発信は広がりつつあるものの、来館者自身が能動的に参加・発信する仕組みはまだ発展途上です。参加型展示やワークショップへのICT活用事例も増えてきましたが、現場のリソースやノウハウ不足がボトルネックとなるケースも多いです。
体験価値向上・参加型ICTへの期待とギャップ
近年、来館者からは「もっとワクワクする体験を」「自分らしい関わり方ができるサービスを」といった潜在的なニーズも高まっています。デジタルスタンプラリーやクイズ形式のガイド、ARやVRを使った展示体験など、参加型ICTの事例は国内外で増えてきました。こうした取り組みは、特に子どもや家族連れの来館者、外国人観光客の満足度向上につながりやすく、リピーター獲得やクチコミ拡大にも効果的です。しかし、現場でこれらを本格的に導入・運用するには、初期投資や日常的なメンテナンス、コンテンツ開発など、クリアすべき課題も多く残っています。結果として、多くの館では「やりたいけどできていない」「アイデアはあるが体制が追いつかない」といったギャップが生じやすいのが現状です。
現場が今後取り組めること
こうした状況を踏まえ、現場ではまず「小さなICT活用」からスタートし、段階的に体験価値の向上を目指すアプローチが現実的です。例えば、既存の音声ガイドや解説パネルにクイズ要素や発見ミッションを加える、SNS投稿を促す仕掛けを作る、簡単なアンケートをデジタル化して来館者の声を集める――こうした小規模な工夫でも、来館者の参加感や満足度は確実に高まります。大がかりなシステム導入が難しい館でも、現場スタッフのアイデアや試行錯誤次第で、ICTの活用範囲を広げていくことは十分可能です。大切なのは、「ICTはあくまで目的ではなく、来館者の体験をより豊かにするための手段である」という意識を持ち、現場の課題や強みに応じた無理のない改善を積み重ねていくことです。今後も来館者の声や利用実態を丁寧に観察しながら、ICTを活かしたサービス改善に取り組むことが、持続的な経営や地域からの信頼獲得につながっていきます。
組織特性とデジタル化―企業博物館の実践と比較分析
組織特性によるICT活用の違い
ICTをどう使いこなすかは、博物館の運営主体や文化によって大きく変わります。たとえば、企業博物館は自社の歴史やブランドを来館者に強く印象づけるため、ICT導入にもスピード感や独自色が出やすい傾向にあります。対して公立館や私立館では、地域の文化資源や市民サービスのためにICTを活用しながらも、意思決定や予算配分に慎重さが求められることも多いでしょう。
こうした違いをふまえ、「自館の組織特性を見つめ直し、ICTをどう活かすと来館者や地域に最大の価値をもたらせるか?」という発想で考えてみることが、現場での第一歩になります。
企業博物館におけるデジタル化の特徴
企業博物館は、IT部門と連携しやすい環境や、経営資源を活用できるメリットを活かして、館内Wi-Fiや専用アプリ、QRコード解説、SNS運用など多様なICTサービスを次々と取り入れています。例えば、来館者がスマートフォンで展示を深掘りできる仕掛けや、SNSを使った情報発信・ファン作りが積極的に行われています。こうした柔軟な導入は、来館者へのサービス向上やリピーター獲得、企業ブランドの浸透にもつながっています。
現場で参考にできるポイントは、「親会社のリソースやネットワークをうまく活かす」「新しいサービスをまず小規模に試し、成果を見ながら拡大する」という実践的な姿勢です。ICT導入が“目的”にならないよう、常に「誰のために・何のために使うのか」をスタッフ間で話し合いながら進めていることが現場力につながっています。
公立館・私立館と企業博物館の事例比較
もちろん、企業博物館だけがICT活用のモデルケースではありません。公立館や私立館でも、予算や人手の制約がある中で、既存の機器を活かした解説サービスや、SNS・ウェブを使った情報発信、地元企業やボランティアと連携したデジタル事業など、独自の工夫がたくさん見られます。「大がかりなシステム導入は難しいけれど、できる範囲でICTを使って現場を改善する」という現実的な視点こそ、どの組織にも共通するポイントです。
たとえば、「常連来館者の声を集めて、分かりやすい案内サインやミニ動画を作る」「子ども向けイベントでデジタルアンケートやクイズを試してみる」など、小さな取り組みの積み重ねが、結果的に来館者サービスの底上げや効率化につながります。
一般館が参考にできるポイントと今後の展望
企業博物館のような豊富なリソースがない場合でも、各館の現状や地域性に応じたICT活用の方法は必ず見つかります。たとえば、他館の事例から着想を得て、身近なパートナー(地域IT企業や図書館、大学の研究室など)と協力し、小規模な実証実験やイベントを試すことが第一歩です。単独で難しい施策も、外部ネットワークを活用することで無理なく始められます。また、すでに導入しているツールの活用法を定期的に見直し、実際の来館者の声やスタッフのアイデアを反映させることで、少しずつ現場に合った改善を重ねていくことが効果的です。
今後は、地域コミュニティや異業種との連携を深めながら、ICTを「外部資源との橋渡し」や「地域ブランドの育成」にも活かしていく視点が求められます。組織の大小を問わず、「自館のミッションに直結するICT活用は何か?」を明確にし、地道な実践を積み重ねることが、持続的な発展と新しい博物館価値の創出につながります。
まとめと今後の展望
ICT活用がもたらす経営・サービス両面での意義
本記事を通じて、ICTの活用が博物館経営において「効率性の向上」と「来館者体験の充実」という両面で大きな可能性を持つことが明らかになりました。デジタル技術は、限られたリソースの有効活用や業務の合理化だけでなく、来館者一人ひとりに合わせた情報提供や体験価値の創出、さらには地域コミュニティとの新しい連携にも貢献しています。また、組織特性に応じた柔軟な導入・運用によって、民間流のイノベーションや新サービスの創出も期待されます。今やICT活用は単なる効率化手段にとどまらず、博物館の存在意義や社会的役割を再定義する原動力にもなり得るのです。
日本の現場が直面する今後の課題とチャンス
一方で、日本の博物館現場がICT活用を進める上では、いくつかの課題も残されています。たとえば、予算や人材不足、運用ノウハウの蓄積といった壁は、今後も克服すべき重要なテーマです。特に小規模館や地方館では、先進的な事例の模倣だけではなく、自館の現状や強みを見極めた独自のステップが求められます。しかし同時に、ICTがもたらす新たな可能性も広がっています。異業種や地域コミュニティ、ボランティアなどとの連携によるプロジェクト推進や、来館者データの分析を活用したサービス改善など、現場に即した工夫とチャレンジが今後ますます重要となるでしょう。
持続可能な博物館経営へのヒント
これからの博物館経営において最も大切なのは、「小さな工夫の積み重ね」と「現場の声を大切にする姿勢」です。ICT導入は大きな投資や完璧なシステムを一度に目指す必要はなく、まずは現場で無理なく始められる改善から段階的に進めることが現実的です。日々の運用の中で新しいヒントを見つけ、スタッフ同士・来館者との対話を通じて改善を重ねていくプロセスこそが、持続的な経営と信頼の獲得につながります。今後も現場が主体的に変革を進め、多様な立場の人々と共に新しい博物館の価値を築いていくために、ICT活用を柔軟かつ前向きに取り入れていくことが求められます。
参考文献
- Braña Rey, F., & Casado-Neira, D. (2013). Participation and technology: perception and public expectations about the use of ICTs in museums. Procedia Technology, 9, 697–704.
- Guccio, C., Martorana, M. F., Mazza, I., Pignataro, G., & Rizzo, I. (2023). Is innovation in ICT valuable for the efficiency of Italian museums? In Rethinking Culture and Creativity in the Digital Transformation (pp. 88–109). Routledge.
- Dalle Nogare, C., & Murzyn-Kupisz, M. (2024). Core functions, visitor friendliness and digitalisation: a comparative analysis of corporate museums’ performance. Journal of Cultural Economics, 48(3), 405–437.