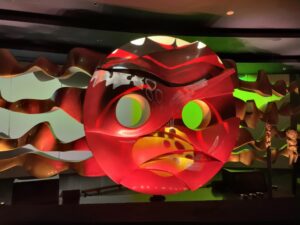はじめに ― 博物館、テクノロジー、価値共創の新潮流
現代の博物館経営では、「テクノロジー」や「価値共創」という視点がこれまで以上に重視されるようになっています。デジタル技術やビッグデータの活用、ICTを取り入れた展示や運営は、来館者体験を大きく変化させています。従来の博物館は、コレクションの保管や公開が中心でしたが、サービス・ドミナント・ロジック(SDL)の考え方が浸透する中で、来館者とともに新しい価値を共に生み出す場へと進化しています(Romanelli, 2020)。
こうした変化の背景には、バーチャルミュージアムやデジタル体験、オンラインとオフラインを組み合わせた新しい鑑賞スタイルの拡大があります。ICTやAR、AIなどの技術を活用することで、来館者が主体的に学び、博物館とさまざまな形で関わる機会が広がっています。これにより、知的資本の拡張や多様な学びの場としての役割も高まっています(Romanelli, 2018)。
本記事では、博物館におけるテクノロジー活用の動向や価値共創の理論、現場の実践事例、ビッグデータの導入効果、ICTを活かした体験設計、そして運用上の課題まで、近年の研究成果をもとに具体的に解説します(Romanelli, 2020, 2018; Marini & Agostino, 2022)。理論だけでなく、現場で活かせる実践的な視点やノウハウにも触れることで、専門的な理解と実務の両面から最新の博物館経営を考えるヒントを得られる内容としています。
記事全体の流れとしては、テクノロジー活用の歴史や背景、価値共創理論と知的資本の考え方、デジタル技術を活用した事例分析、ICT展示と体験設計、ビッグデータの戦略的活用、そして導入現場の課題と今後の展望について順に解説します。ICT展示の実際については、関連記事 ICTを活用した展示とは? でも詳しく紹介していますので、あわせてご参照いただくとより実践的なイメージを持つことができます。

博物館におけるテクノロジー活用と知識基盤の進化
博物館は、長い歴史の中でさまざまなテクノロジーを取り入れながら、知識基盤と社会的役割を進化させてきました。インターネットの登場は博物館の情報発信に革命をもたらし、各館が独自のウェブサイトを開設することで、世界中の利用者にコレクションや企画展の情報を提供できるようになりました。これにより、博物館は単なる物理空間を超え、「バーチャルミュージアム」としての側面を強化しています。デジタルアーカイブの構築やデータベースの整備により、過去の展示や収蔵品、調査資料などを幅広く公開し、多様な来館者がいつでもどこからでもアクセスできる環境が整ってきました(Romanelli, 2020)。
また、近年ではWeb2.0やソーシャルメディアの普及が「博物館 テクノロジー」というキーワードの意味をさらに広げています。従来は博物館から来館者への一方向的な情報提供が中心でしたが、SNSやオンラインプラットフォームの活用により、利用者同士の交流や知識共有、双方向的な対話が日常的に行われるようになりました。例えば、SNSを通じた展示解説や来館者の感想投稿、オンラインワークショップの開催など、リアルとデジタルを融合した新たなコミュニケーションが生まれています。こうした動きは、博物館の社会的イノベーションやエンゲージメント向上に直結しています。
デジタル技術の進展は、博物館の知識基盤の在り方も大きく変えています。従来の「物理コレクション中心」の知識管理から、「デジタル資源」と「リアル展示」が相互に補完し合う複合的な基盤へと発展しています。収蔵品や調査資料をデジタル化し、クラウド型のアーカイブやオープンデータとして一般に公開することで、より多くの人々が博物館の知識資源にアクセスできるようになりました。また、デジタル教材やオンラインガイド、VR・ARコンテンツなど、学習環境の多様化も急速に進んでいます。これにより、学芸員による解説や参加型プログラム、遠隔地からのバーチャルツアーなど、多様なニーズに応じた教育・学習活動が展開可能になっています(Romanelli, 2020)。
さらに、テクノロジーの導入は来館者体験の質や多様性を大きく向上させています。インタラクティブな展示やICTを活用した体験設計により、来館者が能動的・参加的に学ぶことができる環境が整い、「学びの場」「対話の場」としての博物館の価値が高まっています。特に、デジタルサイネージやタブレット、AR技術を活用したガイドコンテンツの提供は、従来の一方向的な展示解説から、個々の興味やレベルに合わせたパーソナライズドな学びへと進化しています。こうした取り組みは、インクルーシブ(包摂的)な学習環境の構築や、多文化・多世代のコミュニティ形成にもつながっています。
一方で、テクノロジー導入の加速に伴い、各館ごとのデジタル成熟度や運用体制、予算面での格差も浮き彫りになっています。先進的なICTやAI、AR/VR技術を導入する博物館が増える一方、十分な人的リソースや資金を確保できない小規模館も少なくありません。また、技術の更新やデータ管理、セキュリティの課題など、運用面での新たなチャレンジも生じています。今後の博物館経営には、こうした課題への対応や、持続可能なデジタル戦略の構築がますます求められるでしょう(Romanelli, 2020)。
このように、博物館におけるテクノロジー活用と知識基盤の進化は、単なるデジタル化にとどまらず、学習環境や社会的役割の変革、来館者との新たな関係構築へとつながっています。今後も「博物館 テクノロジー 知識基盤」を中心としたイノベーションが、博物館の発展を支える重要な要素となっていくと考えられます。
価値共創理論と知的資本マネジメントの最前線
現代の博物館経営では、「価値共創(Value Co-creation)」という考え方が大きな注目を集めています。これは、博物館が一方的に知識やサービスを提供するだけでなく、来館者や地域社会、さまざまなパートナーと協働しながら新しい価値を生み出すプロセスを重視するものです。近年、サービス・ドミナント・ロジック(SDL)が広く普及しつつあり、従来の「提供者」と「受け手」という役割分担から、「共創者」としての関係に進化しています。博物館の活動においても、来館者が展示の設計やプログラムづくりに参加したり、ワークショップやアンケートを通じて意見を反映させたりする場面が増えています(Romanelli, 2020)。
こうした価値共創の推進には、デジタル技術の進展が大きな役割を果たしています。例えば、オンライン上での展示体験や遠隔参加型イベント、SNSを通じたリアルタイムの意見交換など、テクノロジーを活用することで、物理的な制約を超えた多様な協働の機会が生まれています。最近では、博物館のウェブサイトや専用アプリを使った体験型プログラム、ARやVRを活用した参加型展示、来館者自身がコンテンツを投稿できるデジタルプラットフォームなども普及しています。これらは、利用者が受動的な鑑賞者から、積極的な「共創者」として関わるきっかけとなり、学びや体験の質を高めています(Romanelli, 2018)。
さらに、価値共創の実現には「知的資本(Intellectual Capital, IC)」のマネジメントが不可欠です。知的資本とは、博物館が持つ無形資産全体を指し、大きく分けて三つの要素から成り立っています。第一は、学芸員や専門職員の知識・スキル・経験などの「人的資本」。第二は、組織内の情報システムやノウハウ、データベース、マニュアル類などの「構造資本」。第三は、来館者・地域社会・企業・大学など外部のネットワークや信頼関係から成る「関係資本」です。ビッグデータやICTを活用することで、これらの資本を可視化し、有効に活用する動きが加速しています。たとえば、来館者のフィードバックや行動履歴を蓄積・分析することで、プログラムやサービスの質を継続的に向上させることができます(Romanelli, 2018)。
知的資本の強化は、単に内部の組織力や業務効率を高めるだけでなく、博物館が社会の中で持続的なインパクトを生み出すためにも欠かせません。来館者の多様化や地域との連携強化が進むなかで、デジタルプラットフォームを活用した参加型プロジェクトや、共同研究・共同制作を通じて新しいネットワークが構築されています。たとえば、特別展や教育プログラムを市民や学生と共創したり、外部機関と連携したオープンデータ化を進めたりする事例も増えています。こうした動きは、知的資本の活用範囲を広げ、組織としてのレジリエンスや社会的価値の向上につながっています(Romanelli, 2020)。
データ分析やICT活用が進む中で、博物館は「データドリブン経営」へと移行しつつあります。例えば、来館者の滞在時間や展示の人気度、アンケート結果などのデータをもとに展示やサービスを柔軟に改善したり、利用者属性ごとに最適な情報提供を行ったりする取り組みが一般化しています。こうした「価値共創型経営」と「知的資本マネジメント」を組み合わせることで、博物館は組織としての発展だけでなく、地域や社会全体の課題解決にも積極的に関わることができるようになります(Romanelli, 2020)。
今後の博物館経営にとって、価値共創の視点と知的資本を意識したマネジメントはますます重要になるでしょう。多様なステークホルダーと協働しながら新たな価値を創造し、変化し続ける社会の中で持続的な役割を果たすためには、こうした先進的な理論や実践を現場に根付かせていくことが求められます。
博物館×テクノロジー×価値共創:デジタル体験の具体事例と分析
近年、テクノロジーの進化は博物館の来館者体験や学びの場を大きく変えています。ICT(情報通信技術)、AR(拡張現実)、VR(仮想現実)、AI(人工知能)などの先進的なデジタル技術が、展示やプログラムの設計、サービスの提供に積極的に導入されるようになりました。これにより、「博物館 テクノロジー 価値共創」という観点から、新しい来館者体験や学びの形が次々に生み出されています。バーチャルミュージアムの普及、オンライン展示の拡充、インタラクティブなデジタル体験の多様化は、物理的な博物館の壁を越えて、より多くの人々に文化資源へのアクセスと参加の機会を提供しています。
イタリアでは、デジタル技術を活用した価値共創型の事例が数多く生まれています。例えば、現代美術館Martでは音声AIアシスタントAlexaを導入し、来館者が声でガイドや解説を得られる「声の博物館」体験を実現しています。また、レオナルド・ダ・ヴィンチの博物館ではARアプリを活用し、スマートフォンをかざすことで、現実の展示物と連動した解説や映像が楽しめる仕組みが導入されています。さらに、ユーザー参加型のデジタルプラットフォームを用いたプロジェクトでは、来館者が展示内容や物語に意見や記録を投稿でき、博物館と利用者が一緒に知識やストーリーを構築する環境が整えられています。これらの先進事例は、Co-Creation Framework(CCF)という枠組みに基づき、展示物・体験プロセス・デジタルインターフェース・人(パーソン)の相互作用を重視し、来館者自身が体験の「共創者」として参加できる設計になっています(Marini & Agostino, 2022)。
このようなデジタル技術を活用した体験設計は、博物館にとって包摂性(インクルーシブネス)や多様性の向上にも大きく貢献しています。例えば、ARやICTを用いたガイドやコンテンツは、子どもから高齢者、外国語話者や障がいのある利用者まで幅広い層がアクセスしやすい工夫がなされています。家族や友人と一緒に楽しめるインタラクティブ展示や、オンラインとオフラインのイベントを組み合わせたハイブリッド型プログラムも拡充されており、多世代・多文化に対応した参加型学びの場が形成されています。こうした取り組みは、教育的効果やエンゲージメント向上のみならず、博物館の社会的包摂機能やコミュニティ形成にもつながっています(Marini & Agostino, 2022)。
デジタル体験は世界中の多くの博物館にも広がりを見せています。大規模美術館では来館者の動線データや展示閲覧履歴をビッグデータとして分析し、人気コンテンツや混雑状況に応じて展示設計や誘導案内を最適化する取り組みが進められています。また、オンライン展示やバーチャルツアーを通じて、遠隔地の学校や個人にも文化資源を届ける活動も一般化しています。ICTやデジタル技術の導入は、各館の規模や資源に応じて柔軟に進められており、ビッグデータやAIの活用を含めた「データドリブン戦略」が博物館の価値共創モデルを進化させています(Romanelli, 2020; Romanelli, 2018)。
今後は、グローバルな視点でのデジタル戦略や共創モデルの確立がますます重要になります。ICTやデジタル体験の先進事例を共有・評価し、地域やコミュニティごとの課題に合わせたデジタル化を進めていくことが、博物館経営の持続的発展や社会的価値の向上に直結します。博物館、テクノロジー、価値共創の関係を深化させながら、誰もがアクセスし学び合える社会の実現を目指す取り組みが、今後も各地で広がっていくと考えられます。
デジタル技術とICT展示の体験設計 ― ICT展示の可能性と実践例
デジタル技術の急速な進化は、博物館の展示や体験設計のあり方を根本から変えつつあります。ICT(情報通信技術)を活用した展示は、来館者一人ひとりの関心やニーズに応じた多様な体験の提供を可能にしています。現代の博物館運営においては、「デジタル技術」「ICT展示」「体験設計」「インタラクティブ」「パーソナライズド体験」「アクセシビリティ」などのキーワードが重要な戦略要素となっています。コ・クリエーション・フレームワーク(CCF)の導入も進み、物理的な展示空間とデジタル環境が有機的に融合するハイブリッド型の体験設計が主流となりつつあります(Marini & Agostino, 2022)。
ICT展示を設計する際には、AR(拡張現実)やVR(仮想現実)、デジタルサイネージ、タブレット端末、音声ガイドなど、多様なデジタルツールを組み合わせて活用することが効果的です。たとえば、ARを使って展示物の背後に3Dモデルや映像を重ねて表示したり、タブレットを通じて複数言語や音声読み上げに対応した解説を提供したりする取り組みが広がっています。デジタルサイネージは、展示室の導線案内やインタラクティブなクイズ、リアルタイム情報表示に活用され、来館者の学びと好奇心を刺激しています。インタラクティブなICT展示では、直感的に操作できるユーザーインターフェースや、身体的ハンディキャップを持つ方にも配慮したアクセシビリティ設計が求められます。年齢・言語・障がいの有無など、多様な属性に対応するパーソナライズドな体験の提供は、包摂的な博物館づくりに直結しています。
さらに、デジタル技術とICT展示の導入によって、来館者のエンゲージメントや学びの質が飛躍的に向上しています。インタラクティブな体験を通じて、来館者が自ら発見したことをその場で共有できるデジタル掲示板や、他者と協力して取り組む体験型デジタルゲームなどは、世代や文化を越えた交流を促進します。ICT展示を活用したワークショップや参加型イベントは、学校教育や生涯学習、地域連携の分野でも高く評価されています。例えば、遠隔地の学校と博物館をオンラインでつなぐバーチャル校外学習や、地域住民が制作に参加するデジタルアーカイブプロジェクトなど、多彩なプログラムが展開されています。こうしたICT展示は、来館者の能動的な参加を引き出すだけでなく、社会的包摂性やコミュニティの活性化にも寄与しています(Romanelli, 2020)。
今後もデジタル技術とICT展示を活用したハイブリッド展示やパーソナライズド体験の広がりは続き、博物館経営と価値共創の新しい可能性を切り拓いていくでしょう。
ビッグデータ活用の戦略的メリット
ビッグデータの活用は、近年の博物館経営において最も注目される戦略の一つです。ビッグデータとは、膨大な量の多様なデータが短期間で集まり、その情報を分析することで新しい価値を生み出せるものを指します。デジタル技術やICTの進展により、博物館では来館者の行動記録や鑑賞データ、オンラインチケットの販売履歴、館内のWi-Fi利用状況、さらにはSNSやウェブサイト上の反応など、さまざまな形でビッグデータが日々蓄積されています。こうしたデータを効果的に活用することで、データに基づいた経営判断や、来館者ごとに最適化された体験の提供が可能となり、博物館の価値創出や競争力の強化につながっています(Romanelli, 2018)。
博物館におけるビッグデータ活用の例としては、まず来館者データや行動分析が挙げられます。展示ごとの滞在時間や移動経路、人気の展示に集まる人の傾向、アンケートやフィードバック内容を分析することで、展示レイアウトや解説パネルの配置をより効果的に調整できます。たとえば、混雑状況をリアルタイムで把握して混雑緩和の工夫を行う館や、来館者の年齢や興味に応じて体験内容やイベントを個別に最適化する取り組みも広がっています。こうした工夫により、一人ひとりの来館者が自分に合った学びや体験を得られるようになり、満足度やリピート率の向上にもつながっています。
また、ビッグデータは博物館の経営判断やマーケティングにも大きな役割を果たしています。来館者数や収益の分析、イベントごとの集客効果の可視化、さらにはSNSやウェブサイトでの話題の広がり具合を把握することで、より科学的で柔軟な経営判断が可能となります。たとえば、SNS分析で特定の展示やイベントの注目度を把握し、タイミングよく広報活動やイベント展開につなげる事例も増えています。このようなデータに基づいた経営は、資源の配分やスタッフ配置、長期的な戦略の策定にも役立ちます。
さらに、ビッグデータの活用は、価値共創や知的資本の強化にもつながっています。学芸員やスタッフの専門性、情報システムやデータベース、地域社会や外部パートナーとのネットワークなど、博物館が持つ無形の資産をデータで可視化し、より効果的に活用することができます。来館者や地域住民、学校や企業など多様な関係者と協力するプログラムをデータで裏付けることで、説得力ある企画や助成金の申請、社会的インパクトの説明などにも役立ちます。コミュニティ形成や社会貢献の測定にも、ビッグデータは重要な役割を担っています(Romanelli, 2018)。
一方で、ビッグデータを活用する際には、来館者データや個人情報の保護、倫理的な配慮、セキュリティの確保などの課題もあります。法律を守り、利用者に十分説明したうえで適切に運用することが求められます。加えて、小規模な博物館では、データの収集や分析を担う人材や予算が限られるため、外部の専門家やクラウドサービス、他館との協力による対応も重要です。
今後は、人工知能や各種センサーによる自動分析、他分野との連携など、さらに高度なデータ活用が進むと考えられます。データに基づいた経営判断やサービスの改善を積み重ねることで、知的資本とコミュニティを強化し、持続可能で開かれた博物館づくりを実現していくことが、今後ますます重要になっていくでしょう。
テクノロジー導入の課題と対策
博物館がテクノロジーやICTを導入する際には、多くの現場でさまざまな課題が浮かび上がっています。まず最初に大きな壁となるのが、導入コストや予算の確保です。ICT展示やデジタルサイネージ、データベースシステム、アクセシビリティ対応のツールなどは導入や運用に多額のコストがかかるため、限られた予算の中でどこまでテクノロジーに投資できるかは重要な経営判断となります。特に新しいICT機器やシステムを一度に導入する場合、初期費用が大きく、運用コストや維持管理費も無視できません。助成金や補助金の活用、自治体との協働などが有効な手段ですが、申請手続きや報告義務など運用面での負担も発生します。
次に、人的リソースの不足と専門知識の格差も深刻な課題です。現場にはICTやデジタル技術に詳しい人材が少なく、導入後の運用やトラブル対応が現場任せになりがちです。システムの互換性やソフトウェア更新、メンテナンス対応などに追われると、通常業務との両立が難しくなります。また、機器やシステムの選定時にカスタマイズが不十分な場合、現場のニーズやアクセシビリティへの配慮が不十分となる恐れもあります。デジタル機器の導入が進んだ結果、逆に現場スタッフの負担が増すといった事例も珍しくありません。
多様化する来館者属性やアクセシビリティへの配慮も、テクノロジー導入時に必ず考慮すべきポイントです。年齢や障がいの有無、言語、ITリテラシーの違いに対応するためには、ユニバーサルデザインを前提とした設計や多言語対応、誰もが使いやすいインターフェースの整備が不可欠です。セキュリティやプライバシー、倫理的な配慮も、来館者データや個人情報を扱ううえで重要な観点となります。データの取り扱いや管理方法、アクセス権限の設計など、ICT戦略の中で明確に位置付ける必要があります。
とくに小規模館や地域館では、これらの課題がより顕著になります。導入や維持管理に十分な予算が確保できず、人材育成や外部連携のノウハウも限られています。また、テクノロジー活用に対する現場の不安や抵抗感が根強いことも多いです。こうした場合には、いきなり大規模導入を目指すのではなく、まずはスモールスタートとして一部展示や事務作業からICTを導入し、現場スタッフや利用者の声を反映しながら段階的に拡張する戦略が有効です。他館や外部専門家とネットワークを形成し、最新の成功事例や運用ノウハウを積極的に学ぶことも、ICT導入のリスクを減らし、現場の理解や合意形成につながります。
テクノロジー導入を成功させるためには、助成金や補助金といった外部資源の獲得だけでなく、職員研修やリスキリングなど人材育成の推進が欠かせません。ICTスキルやアクセシビリティ設計、セキュリティ意識など、現場スタッフが実践的に学べる機会を用意することで、運用力や対応力が着実に高まります。加えて、システム選定時には現場の声や利用者の多様性を反映したカスタマイズを重視し、使い勝手や拡張性にも配慮した選択を行うことが大切です。
今後の展望としては、テクノロジーの活用状況や導入効果を定期的に評価し、PDCAサイクルを継続的に回すことで、より良いICT戦略と組織運営が実現します。利用者やコミュニティの声をサービス改善や新たな価値共創に生かし、外部連携や地域ネットワークとも積極的に関わることで、持続可能なデジタル基盤の整備につながります。長期的な視点でのデジタル人材育成やICT基盤のアップデートを推進し、誰もが安心して利用できる博物館の実現を目指すことが重要です。
まとめ
本記事では、博物館におけるテクノロジー活用と価値共創の最前線について、理論的背景から実践事例、ビッグデータやICT展示の活用、テクノロジー導入の課題とその対策まで幅広く解説しました。近年、デジタル技術やICTの発展により、博物館は単なる「展示の場」から、来館者と共に新しい価値を創り出す「共創の場」「知のプラットフォーム」へと進化しています。サービス・ドミナント・ロジックや知的資本のマネジメント、ビッグデータに基づくデータドリブン経営、インタラクティブでパーソナライズドな体験設計など、多様なアプローチが博物館の経営や現場実務に組み込まれるようになりました。
デジタル技術やICTの導入は、来館者エンゲージメントやコミュニティ形成、社会的包摂、知的資本の拡張といった観点からも大きな意義を持っています。実際に、AR・VR・デジタルサイネージ・データ分析などの先進的な取り組みが国内外の博物館で急速に普及し、さまざまな来館者層へのアクセスや多様な学び・交流を生み出しています。その一方で、コスト・人材育成・セキュリティ・アクセシビリティなどの課題も明らかになっており、持続可能なICT戦略の構築が不可欠です。
今後の博物館経営には、テクノロジーと価値共創の視点をさらに深化させ、多様なステークホルダーとの協働やコミュニティとの対話を重視することが求められます。人材育成や現場のリスキリング、データ活用と倫理的配慮、ユニバーサルデザインの追求など、継続的なイノベーションに取り組むことが、持続可能で開かれた博物館の未来につながるでしょう。
参考文献
- Marini, C., & Agostino, D. (2022). Humanized museums? How digital technologies become relational tools. Museum Management and Curatorship, 37(6), 598–615.
- Romanelli, M. (2018). Museums creating value and developing intellectual capital by technology: From virtual environments to Big Data. Meditari Accountancy Research, 26(3), 420–434.
- Romanelli, M. (2020). Museums and Technology for Value Creation. In M. Caputo, G. Schiavone, & A. Tirabeni (Eds.), Technology and Creativity (pp. 181–200). Springer.