200周年のナショナルギャラリーが選んだのは“インフルエンサー”だった
ロンドンのナショナルギャラリーは、世界的に名高い美術館として知られ、2024年に創設200周年という節目を迎えました。伝統と格式を誇る一方で、近年は「美術館は堅苦しい場所」というイメージや若者世代の来館減少といった課題に直面しています(The Times, 2024)。
若者世代の集客は世界共通の課題であり、日本でも同様に若者が博物館に行きたくなる施策を模索する動きが広がっています。ナショナルギャラリーの試みは、その具体的な実践例として注目すべきものです。
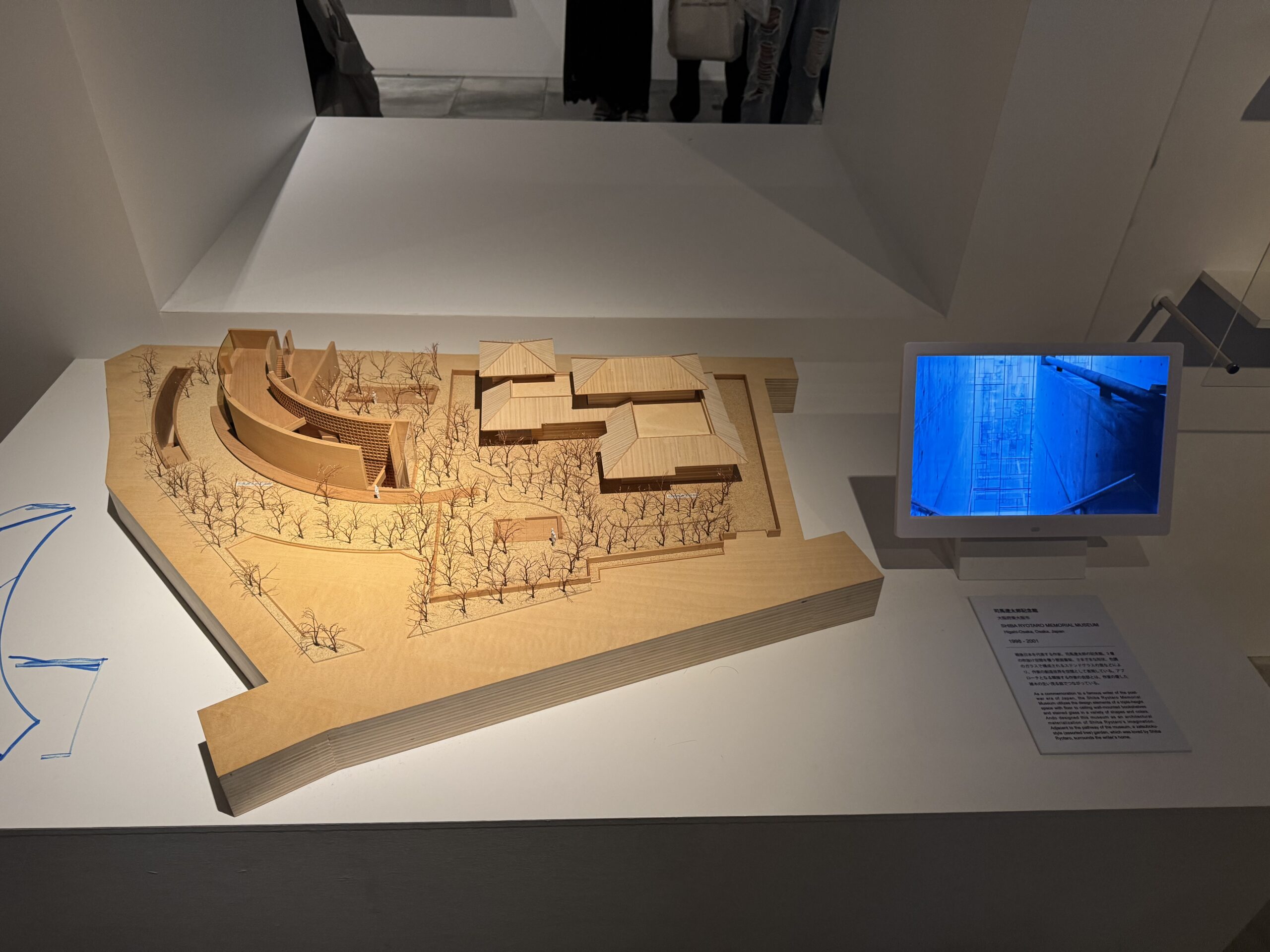
同館は200周年記念事業の一環として「200 Creators」プログラムを立ち上げ、多様な分野のクリエイターを起用しました。彼らはInstagramやTikTok、YouTubeといったプラットフォームを通じて、美術館の作品や空間を題材にしたコンテンツを発信し、特にジェネレーションZと呼ばれる若い世代へのアプローチを狙っています(National Gallery, 2024)。
初年度だけで4,200万回以上の視聴数を獲得するなど、その影響力はすでに大きな成果を上げています(Museums + Heritage Advisor, 2025)。こうした取り組みは、美術館の広報手法に新しい可能性を示すと同時に、「文化機関とSNS時代の関係性」を象徴する事例として注目を集めています。
ナショナルギャラリーの「200 Creators」プログラムとは?
ナショナルギャラリーは、200周年という大きな節目を迎えるにあたり、従来の展覧会や記念出版にとどまらず、デジタル時代にふさわしい新しい挑戦を打ち出しました。それが「200 Creators」プログラムです。この取り組みは、美術館のイメージを「格式ばって敷居が高い場所」から「親しみやすく身近な文化体験の場」へと転換することを目指しています。特にSNSを日常的に利用するジェネレーションZに向けて、美術館を再発見してもらうことが狙いとされています(National Gallery, 2024)。
200 Creators Networkの仕組み
プログラムの土台となるのが「200 Creators Network」です。これは、ナショナルギャラリーがオープンコールを行い、SNSで活動するクリエイター200人を選出する仕組みです。応募条件にはフォロワー数や活動実績が含まれ、一定の影響力を持つ人々が選ばれました。選ばれたクリエイターには、美術館の年間メンバーシップや限定イベントへの招待が提供され、彼らはInstagramやTikTok、YouTubeといったプラットフォームを通じて、ギャラリーの魅力を紹介する役割を担います(Blooloop, 2024)。
この仕組みの特徴は、必ずしも「アート専門」のインフルエンサーに限定していない点です。旅行系、料理系、ファッション系、ライフスタイル系など、幅広いジャンルのクリエイターを受け入れることで、多様な視点から美術館を語ることを可能にしています。その結果、これまで美術館に縁がなかった人々にも、SNSを通じて自然に情報が届く仕掛けになっています。
Creative Collaborators 20名の役割
200人の中からさらに選ばれるのが「Creative Collaborators」と呼ばれる20名です。彼らはプログラムの中核を担う存在であり、1人あたり約£4,000の報酬を受け取って、ナショナルギャラリーを題材にしたオリジナルコンテンツを制作します(The Art Newspaper, 2024)。
この20名の選出はジャンルの幅広さが際立っています。例えば、コメディアンがユーモアを交えて名画を紹介する動画を発信したり、料理系インフルエンサーが名画に描かれた食文化を再現するコンテンツを制作したりしています。さらに、歴史家が建物そのものの魅力や屋上の意匠を解説するケースもあれば、アーティストがナショナルギャラリーの所蔵作品を自分の創作活動と関連づける発信を行うこともあります(The Times, 2024)。
このように、多様なバックグラウンドを持つクリエイターが関わることで、ナショナルギャラリーの空間や作品は単なる「展示物」としてではなく、現代的な生活や文化とつながる存在として再提示されています。
コンテンツの特徴と表現方法
「200 Creators」プログラムで発信されるコンテンツは、SNSの特性に合わせた形式が中心です。TikTokの短尺動画やInstagramのリール、YouTubeのショート動画といった形で、テンポよく視聴できる工夫がなされています。これにより、美術館に興味が薄い人でも、数十秒の動画をきっかけに「この作品をもっと知りたい」「実際に行ってみたい」と思う可能性が生まれます。
また、SNS世代に親しみやすい語り口で作品を紹介することも大きな特徴です。難解な専門用語ではなく、日常生活に近い言葉やユーモラスな切り口を用いることで、美術館の敷居を下げています。これは、従来の学芸員解説では届きにくかった層への新しいアプローチとなっています。
初年度の成果と今後の展開
プログラムは初年度から大きな注目を集め、SNS上で発信されたコンテンツの合計視聴数は4,200万回を超えました(Museums + Heritage Advisor, 2025)。これは、ナショナルギャラリーの広報活動として前例のない規模であり、デジタル上での存在感を一気に高める成果となりました。
こうした成功を受けて、ナショナルギャラリーは2025年にも新たに50名以上のクリエイターを追加し、プログラムを拡張しています。単なる一過性のキャンペーンではなく、継続的な取り組みとして位置づけている点に、このプロジェクトの本気度が表れています。
なぜインフルエンサーを起用するのか?
ナショナルギャラリーが200周年を記念してインフルエンサーを起用した背景には、若い世代へのリーチという切実な課題があります。特にジェネレーションZと呼ばれる層は、情報収集や娯楽の多くをSNSから得ており、従来型の新聞広告やポスター、さらには美術館の公式ウェブサイトだけでは十分に届きません。SNS上で影響力を持つ人々の発信は、同世代にとって「共感できる体験」として受け取られる傾向が強く、公式発信よりも親しみやすく“本物感”を伴って受け止められるのです(The Times, 2024)。
従来の広報活動には限界があります。プレスリリースや報道発表は一定の注目を集めるものの、主な受け手はすでに美術館に関心を持っている層に偏りがちです。一方で、TikTokやInstagramといったSNSでは、利用者が「意図せずに」流れてくるコンテンツに触れる機会が多く、潜在的に美術館に興味を持っていなかった人々にも情報が届く可能性があります。つまり、SNSは従来の広報手法ではつかめなかった層への“偶然の出会い”を演出できる媒体であり、その橋渡し役としてインフルエンサーが重要な存在となっています(Museums + Heritage Advisor, 2025)。
また、ナショナルギャラリーが重視したのは「真正性(Authenticity)」と「多様性」です。近年の調査では、ジェネレーションZは企業や組織の宣伝よりも、個人が発信するリアルで等身大のコンテンツを信頼する傾向が強いとされています(The Guardian, 2021)。そのため、学芸員や広報担当者が一方的に語るよりも、普段からフォローしている料理系インフルエンサーやコメディアンが美術館を紹介した方が「自分ごと」として受け止められやすいのです。さらに、アート専門家に限らず、ファッションやライフスタイル、旅行など異なるバックグラウンドを持つ人々を巻き込むことで、美術館の魅力を日常生活や現代文化の延長線上に位置づけることができます(Blooloop, 2024)。
ナショナルギャラリーにとって、この戦略のメリットは明確です。第一に、若年層との接点が広がることで、これまで足を運ばなかった層を来館へと誘導できる可能性が高まります。第二に、デジタル空間での存在感を強化することは、美術館のブランド価値を高め、長期的な観客育成にもつながります。第三に、インフルエンサーを通じて展開される多様な表現は、美術館そのものの「堅苦しいイメージ」を刷新し、文化機関としての社会的役割を拡張するものとなります(The Art Newspaper, 2024)。
このように、インフルエンサーの起用は単なる話題づくりではなく、若者世代にアプローチするための必然的な戦略といえます。ナショナルギャラリーは、デジタル時代における美術館の広報のあり方を大きく変えようとしているのです。
実際の成果とデータ
ナショナルギャラリーの「200 Creators」プログラムは、初年度から目に見える成果を上げました。とりわけ注目すべきは、SNS上で発信されたコンテンツの合計視聴数が4,200万回を超えたという数字です(Museums + Heritage Advisor, 2025)。この数値は、単に一部のフォロワーに届いたにとどまらず、幅広い層にリーチしていることを示しています。特にTikTokやInstagramの短尺動画は拡散性が高く、従来の広報活動では接点を持ちにくかった若者層に自然に届く仕組みとなりました。
この成果は、観客層の変化にも表れています。従来の美術館来館者は、文化に高い関心を持つ中高年層が中心でした。しかし「200 Creators」を通じて、SNSでナショナルギャラリーの動画を偶然目にした若者が「実際に行ってみたい」と来館するケースが増えたと報告されています。インフルエンサーのフォロワーにとって、美術館の紹介は単なる広告ではなく、信頼する人物が体験を共有しているものとして受け取られます。その結果、料理やファッション、コメディといった一見アートと距離のある分野からも、新しい来館動機が生まれました(Blooloop, 2024)。
こうした取り組みは、社会やメディアからも注目を集めました。The Times紙は、美術館が伝統的な広報手法にとらわれず、親しみやすさを前面に出した点を「革新的なアプローチ」と評価しています(The Times, 2024)。一方で批判も存在します。短尺動画はアート作品を「映える背景」として消費させてしまい、深い鑑賞体験を阻害するのではないかという懸念が指摘されています(The Times, 2024)。つまり、この成果は評価と批判が両立する性質を持っており、SNS時代の博物館経営が抱えるジレンマを象徴しているといえます。
さらに、このプログラムは単発のキャンペーンで終わるものではありません。初年度の成果を受けて、ナショナルギャラリーは第2年度に新たに50名以上のクリエイターを追加する拡張を発表しました(Museums + Heritage Advisor, 2025)。これは、SNS活用を長期的な観客育成戦略として位置づけ、美術館のブランド価値を持続的に高めていこうとする姿勢の表れです。今後は、多様なクリエイターを巻き込みながら、美術館と社会の新しい関係性を築くモデルケースとなる可能性があります。
このように「200 Creators」プログラムは、数字の成果、観客層の広がり、メディアでの評価、そして継続的な展望という複数の側面から注目すべき結果を生み出しました。その一方で、アート体験の質とのバランスをどう取るかという課題も残されており、この成功と課題の両面こそが次世代の博物館戦略を考えるうえで重要な論点となります。
クリエイターの多様性と発信事例
ナショナルギャラリーの「200 Creators」プログラムを特徴づけているのは、参加するクリエイターの幅広さです。従来の美術館広報では、美術史家や研究者など専門的な立場からの解説が中心でした。しかしこのプログラムでは、あえて異なる分野で活躍する人物を巻き込み、日常や文化の延長線上でアートを紹介することを目指しています。選ばれた20人の「Creative Collaborators」には、コメディアン、料理系インフルエンサー、ファッション・ヒストリーの専門家、歴史家、アーティスト、さらにはドラァグパフォーマーなど、実に多彩な顔ぶれが揃いました(The Art Newspaper, 2024)。
具体的な発信事例を見ると、その多様性は一層際立ちます。コメディアンは、名画を題材にユーモアを交えた寸劇を披露し、作品の時代背景や登場人物を親しみやすく紹介しました。これにより、美術館を「学びの場」というより「笑いと気づきの場」として体験できる新しい切り口が生まれました。また料理やベイキングのインフルエンサーは、絵画に描かれた食材や食卓の様子を現代に再現し、アートと食文化を結びつけるコンテンツを制作しました。作品鑑賞が単なる視覚体験にとどまらず、味覚や生活の記憶に結びつくことで、観客にとってより立体的な理解が可能になります(Blooloop, 2024)。
さらに歴史家は、美術館の所蔵作品だけでなく、建物そのものを題材にしました。屋上やモザイク装飾など普段は見過ごされがちな要素を取り上げ、「建築自体がアートである」という視点をSNSで共有しました。これにより、来館者は作品鑑賞に加えて建物を探索する楽しみを見いだすようになり、ナショナルギャラリーが持つ総合的な魅力が強調されました(The Times, 2024)。一方、現役アーティストは自らの作品制作とギャラリーのコレクションを関連づけ、古典と現代の対話を示すような発信を行いました。こうした活動は、若い世代のクリエイターが自分の表現と歴史的作品を重ね合わせることで、アートが「過去のもの」ではなく「今とつながるもの」であることを訴えかけています。
発信手法のバリエーションもまた豊かです。TikTokでは数十秒の短尺動画で視覚的インパクトを与え、Instagramのリールやストーリーでは日常的なテンポ感に合わせたコンテンツが展開されました。さらにYouTubeではシリーズ企画として複数回に分けて深掘りする発信が行われるなど、プラットフォームごとの特性を生かした取り組みが進められています。ライブ配信を通じてフォロワーがコメントで参加できる仕組みも導入され、双方向的な体験が可能になりました(National Gallery, 2024)。
このような多様性がもたらした効果は大きいといえます。従来「美術館=美術に関心のある人のための場所」というイメージを持っていた層が、笑いや料理、ファッションといった身近なテーマを通じて自然に美術館へ関心を持つようになりました。異なる興味を持つ人々がSNSでアートに触れ、その後に来館するきっかけとなることで、美術館の観客層が広がったのです。結果として、ナショナルギャラリーのブランドイメージは「学術的に権威ある存在」でありながら「多様で親しみやすい空間」へと変化しつつあります。
批判と課題:SNSとアート鑑賞のギャップ
ナショナルギャラリーの「200 Creators」プログラムは大きな成果を上げた一方で、さまざまな批判や課題も指摘されています。その多くは、SNSという媒体の特性と、美術館に求められる本質的な役割との間に横たわるギャップに起因しています。
まず最も大きな懸念として挙げられるのが、短尺動画による「アートの背景化」です。TikTokやInstagramリールのような数十秒単位の動画は拡散性に優れている一方で、作品が単なる映える背景として扱われてしまう危険性があります。視聴者は画面に流れるテンポの良い映像やクリエイターのパフォーマンスに注目し、肝心の絵画や美術品そのものに意識を向ける時間が十分に確保されないのではないか、という指摘がなされています(The Times, 2024)。
この問題は、美術館体験の本質とも深く関わります。アート鑑賞は、本来、作品の細部をじっくり眺め、時間をかけて解釈を深める「対話的な行為」です。しかし、SNSの文化はスワイプして次々と新しいコンテンツに移っていく消費スタイルを前提としており、アート鑑賞に必要な集中力や持続的な関心とは相性がよくありません。結果として、SNSでの露出が増えても、それが必ずしも美術館での深い体験に結びつくとは限らないのです(The Times, 2024)。
また、美術館の教育的・公共的な価値とのバランスも重要な論点です。美術館は単なる娯楽施設ではなく、知識の蓄積や文化資源の継承を担う機関です。そのため、SNSでの発信が「フォロワー数の多いインフルエンサーに頼る形」に偏りすぎると、学術性や教育的意義が軽視されるのではないかという懸念が出ています。短期的な話題づくりに終始するのではなく、来館者が実際に学びを深められる仕組みと結びつけることが不可欠といえます(Blooloop, 2024)。
こうした批判に対し、ナショナルギャラリー側も一定の対応を進めています。プログラムではインフルエンサーの自主性を尊重しながらも、学芸員による監修やガイドラインを整備し、コンテンツが美術館の理念から逸脱しないよう配慮がなされています。また、作品紹介の際には透明性を確保することを重視し、「本物の文化体験」を伝える姿勢を打ち出しています(National Gallery, 2024)。これは単に批判を受け流すのではなく、SNS活用を教育的使命とどのように両立させるかという課題への取り組みとして評価できます。
このように、「200 Creators」プログラムは新たな観客層を獲得する大きな可能性を示した一方で、SNSの特性と美術館の本質的役割の間に生じるギャップを浮き彫りにしました。美術館が今後この矛盾をどのように解消し、短期的な話題性と長期的な教育的価値を両立させるのかが、次世代の博物館経営を考えるうえで重要なテーマとなるでしょう。
日本の博物館への示唆
ナショナルギャラリーの「200 Creators」プログラムは、伝統ある美術館が若者層にアプローチするためにSNSインフルエンサーを起用するという大胆な試みでした。この事例は、同じく来館者の高齢化や若者離れが課題とされる日本の博物館にとっても重要な示唆を与えています。
まず、日本の博物館におけるSNS活用の現状を整理する必要があります。近年、Twitter(現X)やInstagram、YouTubeを活用する館は増えてきました。しかし、その多くは展示案内やプレスリリースに準じた情報発信にとどまっており、発信内容は事務的で一方通行になりがちです。来館促進や教育普及と直接結びつく事例はまだ限定的であり、フォロワーとの双方向性やストーリーテリングの工夫は発展途上といえます。
次に、インフルエンサー戦略の可能性について考えます。日本の博物館も、若い世代に「美術館は自分とは縁遠い場所」というイメージを持たれている点では、ナショナルギャラリーと共通の課題を抱えています。そのため、インフルエンサーと協働することで、来館のハードルを下げるきっかけを作ることができるかもしれません。特に、学芸員や教育普及担当者による専門的で学術的な発信と、インフルエンサーが提供する親しみやすい語り口を組み合わせれば、幅広い層への訴求力を高められる可能性があります。
ただし、SNSはあくまで「入口」であり、深い鑑賞や学びへとどうつなげるかが重要です。例えば、インフルエンサーの投稿を見て来館した若者に対して、館内で教育普及プログラムやギャラリートークを案内する仕組みを組み込めば、SNSでの体験をより本格的な学びにつなげることができます。これは、SNSによる一過性の関心を持続的な教育活動へと昇華させるために不可欠な工夫です。
さらに、日本における課題と留意点も無視できません。多くの博物館は広報予算が限られており、インフルエンサーとの協働を長期的に続けるためには工夫が必要です。また、SNS特有の炎上リスクや発信内容のコントロールの難しさにも備えなければなりません。公共文化機関としての信頼性と透明性を損なわないためには、ガイドラインを策定し、インフルエンサーとの協働においても一貫したメッセージを維持する体制が求められます(Blooloop, 2024)。
このように、日本の博物館にとってナショナルギャラリーの事例は単なる参考事例ではなく、自館の広報・教育戦略を見直すうえで重要な問いを投げかけています。インフルエンサーとの協働は来館者拡大の有効な手段となり得ますが、教育的使命を軽視せず、SNSを学びへの導線と位置づける視点が不可欠です。成果と課題の両面を踏まえつつ、自館に適したかたちで応用することが求められるでしょう。
まとめ
ナショナルギャラリーが200周年を記念して打ち出した「200 Creators」プログラムは、伝統ある美術館が時代の変化に対応するための挑戦として大きな意義を持っています。従来の広報手法にとらわれず、SNSインフルエンサーを積極的に起用したことは、多くの人々に驚きを与えました。その結果、初年度で4,200万回以上の視聴を獲得し、若い世代の来館動機を新たに生み出す可能性を示した点は特筆に値します(Museums + Heritage Advisor, 2025)。
一方で、この取り組みには成果と課題が共存しています。成果の側面としては、ジェネレーションZに向けた新しいアプローチを確立し、来館者層を広げることに成功しました。さらに、美術館のブランドイメージを「権威的な存在」から「親しみやすい文化体験の場」へと刷新する契機となったことも重要です。しかし同時に、短尺動画が作品を「映える背景」として扱ってしまうリスクや、SNSのスワイプ文化とアート鑑賞の本質的体験との矛盾が指摘されました(The Times, 2024)。また、教育的使命や公共的価値をどう維持するかという課題も依然として残されています(Blooloop, 2024)。
こうした両面性を踏まえると、日本の博物館にとって学ぶべきポイントは明確です。SNSは新しい観客層にリーチする有効な手段であり、特にインフルエンサーとの協働は「若者を引き込む入口」として大きな可能性を秘めています。ただし、それを単なる話題づくりに終わらせず、館内の教育普及活動や学びにつなげる導線を設計することが不可欠です。例えば、SNS投稿からワークショップや展示解説へと誘導する仕組みを構築することで、来館者がより深い文化体験に進めるようになります。
ナショナルギャラリーの事例は、SNS時代における博物館経営の可能性とリスクの両方を映し出しています。日本の博物館もこの挑戦を参考にしながら、自館の目的や資源に合わせた最適な活用方法を模索することが求められるでしょう。SNSが博物館の未来を形づくる重要な要素となるのは間違いなく、今後はその効果をいかに教育的・公共的使命と両立させていくかが鍵となります。
参考文献
- Blooloop. (2024, May 1). National Gallery unveils 200 Creators for bicentenary digital programme. Blooloop. https://blooloop.com/museum/news/national-gallery-creative-influencers/
- Museums + Heritage Advisor. (2025, January 27). 42m views later, National Gallery doubles down on influencers programme. Museums + Heritage Advisor. https://museumsandheritage.com/advisor/posts/42m-views-later-national-gallery-doubles-down-on-influencers-programme/
- National Gallery. (2024, May 1). Creative collaborators announced for 200 Creators: National Gallery’s bicentenary digital programme. National Gallery. https://www.nationalgallery.org.uk/about-us/press-and-media/press-releases/creative-collaborators-announced-for-200-creators-national-gallery-s-bicentenary-digital-programme
- The Art Newspaper. (2024, August 13). The National Gallery’s birthday wish: Social media fame for its creative collaborators. The Art Newspaper. https://www.theartnewspaper.com/2024/08/13/the-national-gallerys-birthday-wish-social-media-fame-for-its-creative-collaborators
- The Times. (2024, August 7). National Gallery hires social media influencers to attract younger visitors. The Times. https://www.thetimes.co.uk/article/national-gallery-hires-social-media-influencers-to-attract-younger-visitors-0fgb8k8f2
- The Times. (2024, August 13). TikTok’s new art lovers miss the big picture. The Times. https://www.thetimes.co.uk/article/tiktoks-new-art-lovers-miss-the-big-picture-pbntc6slx
- The Guardian. (2021, August 12). Being too aspirational is repellent now: The rise of the genuinfluencers. The Guardian. https://www.theguardian.com/fashion/2021/aug/12/being-too-aspirational-is-repellent-now-the-rise-of-the-genuinfluencers














