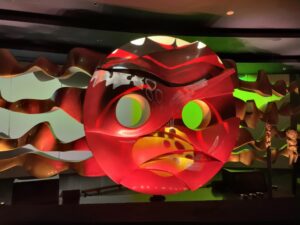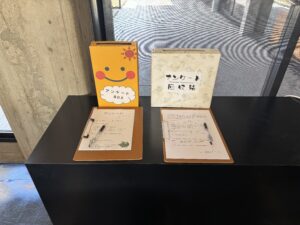はじめに
ミュージアムショップと聞くと、多くの人が「展覧会のポスターや図録を買う場所」「おみやげを探す売店」といったイメージを抱くかもしれません。確かに、ショップは来館者が記憶を形として持ち帰るための場であり、博物館の魅力を日常生活へと延長させる機能を果たしてきました。しかし、近年の研究や実務の中では、それ以上の多様な役割が強調されるようになっています。
博物館経営の視点から見ると、ショップは入館料に依存しない収益源として重要であり、経営基盤を安定させる存在とみなされてきました。とくに財政的に厳しい状況にある館にとって、ショップの売上は不可欠な柱の一つです。一方で、来館者体験の観点では、ショップは単に経済的利益を生むだけではなく、展示で得た学びや感動を「自分の生活に持ち帰る」ための教育的・文化的な装置としても位置づけられます。書籍や映像資料、あるいは収蔵品にちなんだ商品は、博物館の教育的使命を延長する効果を持ちうるのです。
さらに今日では、社会的・環境的な文脈においてもショップが注目されるようになっています。フェアトレード商品や地元アーティストの作品を扱うことで、地域社会との連携や多様な声の反映を実現する場となり、同時に環境負荷の少ない素材や製造方法を採用することによって、博物館が持続可能性を推進する拠点としての役割を果たすことができます。つまり、ミュージアムショップは「収益空間」から「体験を延長する空間」へ、そして「社会的責任を担う空間」へとその意義を拡張してきたのです。
こうした視点の広がりについては、すでに ミュージアムショップの価値と戦略 ― 経営・体験・社会性をつなぐ収益空間の再定義 でも整理されています。本記事では、その流れを踏まえつつ、過去の文献と近年の研究を比較することで、ミュージアムショップの意義がどのように変化してきたのかをたどっていきます。

収益と効率の視点 ― 2009年のマニュアル的理解
収益源としての位置づけ
2000年代までの博物館経営論において、ミュージアムショップは主に収益を確保する手段として語られてきました。入館料だけに依存した運営は長期的に不安定であり、安定的な財源を得るためにはショップが不可欠と考えられていたのです。そのため、効率的な運営体制や商品戦略が、館の経営を支える重要な要素として強調されてきました(Lord & Lord, 2009)。
ショップは来館者にとって「必ずあるべき施設」と期待される存在です。多くの人は展示鑑賞の後にショップを訪れ、図録や複製品を通じて体験を持ち帰ろうとします。書籍やポスター、映像資料などは、博物館の教育的使命と整合しつつ収益を生み出せる商品群とされ、収益性と公共性を同時に担保できる点が評価されてきました。さらに、商品ラインナップを高価格帯から低価格帯まで幅広く設定することが推奨され、来館者層の多様なニーズに応える仕組みが構築されました(Lord & Lord, 2009)。
効率的な運営戦略
運営の効率性も重要な視点として示されています。小規模な博物館では、有給のマネージャーとボランティア販売員を組み合わせることで人件費を抑え、大規模館では専門部門を持ちプロフェッショナルに運営する体制が求められました。特に、ヴィクトリア&アルバート美術館のように通信販売やライセンス商品の展開を行う事例は、収益の拡大に成功したモデルとして紹介されています。こうした手法はオンライン販売にも発展し、館の収益を補完する基盤となりました(Lord & Lord, 2009)。
立地と商品戦略の工夫
立地と商品戦略の工夫も欠かせない要素とされました。ショップを入退館動線上に配置することは、来館者の立ち寄りを自然に促す仕組みとして効果的です。また、特別展ごとに専用グッズを開発することは、展示そのものの広報効果を高めつつ収益につなげる戦略として評価されました。いわゆる「ブロックバスター展」の開催時には、ショップの売上が館全体の経営に大きな影響を及ぼすことも少なくありません(Lord & Lord, 2009)。
このように、2009年当時のミュージアムショップは、博物館の財政を支えるための経営資源として明確に位置づけられていました。収益と効率を重視した視点は、その後の議論の基盤となり、後に「体験の延長」や「持続可能性の拠点」といった新たな役割が論じられる前段階として重要な意味を持っています。
体験と学習の延長 ― 2010年の来館者調査から
来館者行動と購買傾向
来館者の多くは展示鑑賞の流れの中でショップ訪問を計画的に組み込み、図録や書籍、映像資料、文具などを選択する傾向が見られます。とりわけ書籍やDVDといった情報性の高い商品は、展示で触れたテーマの理解を深める目的で購入されることが多く、ショップが鑑賞後の行動において自然に位置づけられていることが示唆されます(Kent, 2010)。
学習と記憶の延長
ショップでの購買は、単なる消費行為にとどまらず、展示内容を日常の学びへと接続する契機として機能します。書籍や映像資料は家庭や学校、職場での再参照を可能にし、展示体験の記憶を定着させる役割を果たします。ポスターや複製品などの視覚的アイテムも、日常空間に展示テーマを持ち込み、関心の継続や家族間の対話を促す点で教育的効果を持ちます(Kent, 2010)。
環境要因と体験の質
ショップの体験価値は、品揃えだけでなく、動線設計、照明、什器配置、混雑度などの環境要因に左右されます。明るく整理された売場は来館者の探索行動を支援し、商品の触覚的・視覚的体験を通じて展示の記憶を喚起します。一方で、団体来館時の騒音やレジ前の滞留は滞在満足度を下げる可能性があり、学習行動の持続を阻害しうる点に留意が必要です(Kent, 2010)。
教育的使命との整合と限界
教育的使命との整合という観点では、展示テーマと関連性の高い良質なコンテンツ商品を核に据えることで、収益と学習支援を同時に実現できます。ただし、商品構成が商業主義に傾きすぎると、展示の真正性や知的価値との乖離が生じ、来館者の信頼を損なうリスクがあります。学習効果を高めるガイド文言、レコメンド表示、テーマ別コーナー化などの編集的工夫は、来館者の自己主導的な探究を後押しし、ショップを非公式学習のハブとして機能させます(Kent, 2010)。
以上の知見から、ミュージアムショップは来館者の体験を持続させる「延長装置」であり、記憶と学習を日常へと橋渡しする重要な接点であると位置づけられます。適切な商品編集と売場環境の設計によって、収益と教育的価値を両立させる可能性が高まります(Kent, 2010)。
持続可能性の拠点へ ― 2024年の再定義
「四本柱」で再構築するショップの役割
近年の議論では、ミュージアムショップを「文化・経済・社会・環境」の四本柱で捉え直す視点が提示されています。これは、従来の収益中心の発想を超えて、コレクション理解の促進(文化)、収益循環と地域産業支援(経済)、多様な声の可視化と関係構築(社会)、資源循環や輸送負荷の低減(環境)を同時達成する枠組みです(Larkin et al., 2024)。
ケーススタディ:地域協働と倫理的サプライチェーン
実践例として、地域クリエイターやフェアトレード事業者との協働を通じて、ショップを「社会的実践の場」として機能させる取り組みが示されています。地産地消やゼロウェイストの設計は、商品そのものを展示の延長線上に置き直し、来館者の購買行動を学びと価値選好の表明へ転換します。これにより、収益は地域に再循環し、館の使命と整合した物語性の高い商品編集が実現します(Larkin et al., 2024)。
来館者教育とコミュニケーション設計
四本柱の統合には、価格や素材、製造背景に関する情報提供が不可欠です。POPや商品タグ、トークイベントなどを通じて、購買の意味と社会的インパクトを明示することで、安価な大量生産品との比較軸を「値段」だけに限定せず、「倫理性・耐久性・文化的関連性」へと拡張できます。これらはショップを通じた持続可能な消費教育の中核をなします(Larkin et al., 2024)。
オペレーション上の課題と解決の方向性
小規模事業者との取引は供給安定性や品質保証の面で課題を伴います。発注リードタイムの可視化、少量多品種に対応した在庫設計、リスク分散のためのサプライヤーポートフォリオなど、運用面の再設計が必要です。また、価格説明と価値訴求のための販売スタッフ研修も重要であり、学芸・教育部門との連携によって商品選定の妥当性を高められます(Larkin et al., 2024)。
経営的含意:収益と公共性の同時達成
四本柱モデルは、収益性と公共性をトレードオフではなく相補的に位置づけます。館のミッションに即したキュレーション方針を商品編集へ落とし込み、指標として粗利や回転率に加えて、地域還元額、再生素材比率、教育プログラム接続率などを併置することで、経営評価を多元化できます。これにより、ショップは単なる商業空間ではなく、館の将来像を具体化する戦略拠点として機能します(Larkin et al., 2024)。
意義の変遷を比較する
収益から学習、そして持続可能性へ
ここまで見てきた三つの研究を並べると、ミュージアムショップの意義がどのように拡張されてきたかが浮かび上がります。2009年の文献では、ショップは収益と効率の観点から位置づけられ、経営資源として重視されていました。2010年の研究では、来館者体験を補完する「学びの延長装置」として再評価され、教育的使命との整合が強調されました。そして2024年の最新研究では、ショップは文化・経済・社会・環境の四本柱を担う持続可能性の拠点として再定義されています(Lord & Lord, 2009; Kent, 2010; Larkin et al., 2024)。
比較表でみる変化
| 時期 | 主な意義 | 特徴 |
|---|---|---|
| 2009年 | 収益と効率 | 商品戦略・立地設計・通信販売の拡張など、財政基盤を支える経営資源 |
| 2010年 | 体験と学習の延長 | 書籍や映像資料を通じた非公式学習、展示体験を持ち帰る装置 |
| 2024年 | 持続可能性と社会的責任 | 文化・経済・社会・環境の四本柱を担い、地域協働や環境負荷低減を実現 |
変遷の意義
このような変化は、博物館が時代に応じて役割を拡張してきたことを示しています。収益を確保するための商業空間から、来館者の学びを支援する教育空間へ、さらに社会的責任を担う持続可能性の拠点へと進化してきたのです。ショップの存在は、博物館が経営課題と公共的使命の双方に応える場として再評価されるようになりました。今後の議論では、この多面的な意義をどうバランスさせるかが、各館にとって大きな課題となるでしょう。
まとめ
本記事では、ミュージアムショップの意義が「収益と効率」を基盤にしつつ、「体験と学習の延長」へ、さらに「持続可能性の拠点」へと拡張してきた流れを整理しました。2009年の実務的視点は経営の土台を示し、2010年の来館者調査は教育的価値の可視化に寄与し、2024年の議論は社会・環境を含む多元的価値の創出を促しています(Lord & Lord, 2009; Kent, 2010; Larkin et al., 2024)。
この変遷は、ショップを単なる商業空間と捉える発想から脱し、来館者の学習を持続させ、地域や地球環境と調和する消費の在り方を提示する場として再評価することの重要性を示しています。評価指標も、売上や粗利だけでなく、学習効果や地域還元、環境配慮などを含む多面的なものへ移行する必要があります。
一方で、供給安定性や価格受容性、真正性との整合といった課題は残ります。これらに対応するためには、学芸・教育・ショップ部門の連携を前提に、商品編集の妥当性や情報提供の質、在庫・発注の設計を段階的に見直していくことが求められます。
今後は、各館のミッションと来館者層、地域資源に即したショップの役割設計を行い、経営資源・教育装置・社会的実践の三つの性格をバランスさせていきます。これにより、ショップは博物館の将来像を具体化する戦略拠点として、持続的に機能し続けるはずです。
参考文献
- Kent, T. (2010). The role of the museum shop in extending the visitor experience. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 15(1), 67–77.
- Larkin, J., Hayward, R., & Binnie, L. (2024). The role of the museum shop in sustainable futures. Museum Management and Curatorship, 39(2), 109–127.
- Lord, G. D., & Lord, B. (2009). The manual of museum management (2nd ed.). AltaMira Press.