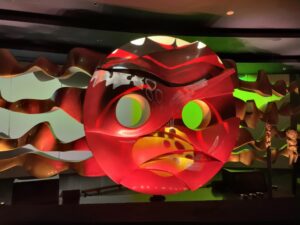デジタル化で、博物館の学びはどう変わったのか?
21世紀に入って以降、デジタル技術の進展は私たちの暮らしのあらゆる側面に浸透してきました。スマートフォンをはじめとするモバイルデバイス、クラウド技術、AR(拡張現実)やVR(仮想現実)、そして人工知能(AI)にいたるまで、情報との関わり方そのものが変化しつつあります。この変化はもちろん、博物館という学びの場にも波及しています。
博物館は、知識や文化の伝達だけでなく、来館者が展示と出会い、問いを立て、他者と共有しながら考える場としての役割を担ってきました。そして今、その教育的機能は、デジタル技術の導入によって質的な転換期を迎えています。
かつての博物館教育は、展示パネルやガイドツアー、学芸員による解説を通して、来館者にあらかじめ用意された情報を「届ける」ことが主たる目的でした。しかし現在は、来館者自らが探索し、選び、感じ、理解し、そして表現することを重視する参加型の学びへとシフトしています。このような転換を可能にしているのが、まさにデジタル技術の導入です。
とくに注目すべきは、博物館教育において「個別化された学び(personalized learning)」と「参加型体験(participatory experience)」という二つの軸が浮かび上がってきている点です。これらは、従来の一斉的・受動的な教育観とは異なり、来館者一人ひとりの関心や能力に応じた学習支援を可能にする新たな方向性を示しています。
本記事では、このようなデジタル技術による教育的変革を、「何が変わったのか?」「どんな可能性が広がっているのか?」という視点から、具体的な研究成果や博物館の実践事例を紹介しながら掘り下げていきます。
ひとりひとりに合った「学び」を届ける ― 個別化された学習体験の実現
博物館における教育活動は、長らく「集団」に対して同一の情報や体験を提供するという前提に立って設計されてきました。たとえば、展示の順路を想定した導線設計や、学校団体向けのガイドツアー、あるいは一般来館者向けの一斉解説といった形式が主流でした。このようなスタイルは、多くの来館者に対して効率的に知識を伝えるという点では効果的であった一方で、個々人の関心や学習スタイルに応じた柔軟な対応には限界がありました。
ところが、デジタル技術の導入によって、この状況は大きく変わりつつあります。来館者が手にするスマートフォンやタブレット端末は、今や「持ち運べる学習環境」として機能し、その人の興味関心、理解度、さらには感覚的特性にまで適応した学びの体験を提供できるツールへと進化しています。
たとえば、AR(拡張現実)技術を活用した展示では、実際の展示物にスマートフォンをかざすと、その上に重ねて3D映像や音声、アニメーションなどの情報が表示されます。これは、展示物に対する理解を深めるだけでなく、視覚や聴覚といった複数の感覚を通じて、直感的かつ深い学びを可能にするものです。また、来館者自身が操作のタイミングや情報の種類を選択できるため、自律的な学習姿勢を育む効果もあります。
こうした学習環境の変化について、Moorhouseら(2019)は、英国の博物館におけるAR体験プログラムを通じて詳細に検証しています。調査対象となったのは、小学生を中心とした来館者であり、AR体験後の学習者たちが、自身の学び方に気づき、より主体的に展示と関わるようになったことが確認されました。研究者らは、AR技術が来館者の学習スタイルの可視化と自己認識を促す手段となっていることを指摘しています(Moorhouse et al., 2019)1。
このような個別化のアプローチは、必ずしもデジタル技術そのものによって実現されるのではなく、技術をどのように教育設計に組み込むかという視点が問われます。たとえば、単にARコンテンツを追加するだけではなく、来館者が「どの情報を選ぶか」「どのタイミングで見るか」「そのあとどう考えるか」といったプロセスまで設計することが重要です。そこにこそ、博物館の教育活動が次の段階へと進む鍵があります。
このように、デジタル技術は「誰にでも同じ情報を届ける」ための手段ではなく、「一人ひとりに最適な学びをデザインする」ための環境として再定義されつつあります。これは、博物館が提供する教育が画一的な情報伝達から、多様な来館者の学びの可能性を引き出す場へと変化していることを意味しています。
博物館は「参加する場所」へ ― 体験型学習がひらく教育の可能性
博物館の来館者は、もはや情報を受け取るだけの存在ではありません。展示物の前で立ち止まり、ただ解説を読むのではなく、そこから何を感じ取り、どう解釈し、どのように他者と共有するか。そうした能動的な関与こそが、今後の博物館教育においてますます重要になってきています。
このような変化の背景には、「参加型体験(participatory experience)」という考え方の広がりがあります。従来の教育的アプローチは、来館者を「受け手」とみなし、学芸員や教育担当者が選定・編集した情報を一方向的に提供する構造が基本でした。しかし今日では、来館者自身が展示に意味を見出し、対話や創作といったプロセスを通じて学びを深めていく、双方向的な設計が求められています。
この方向性を象徴する実践のひとつが、ニュージーランド国立博物館テ・パパ・トンガレワで展開されている「Hīnātore Learning Laboratory」です。このラボは、博物館内に設置されたデジタル学習空間であり、来館した学校団体や児童・生徒が、展示観覧とデジタル創作を組み合わせた学習体験を行う場として設計されています。
この取り組みに関する研究報告によれば、展示の鑑賞後に子どもたちがテーマに沿ったデジタル作品を作成し、グループで発表を行う活動が行われています。ここで用いられるツールは、3Dスキャン、AR、VR、デジタルアニメーションなど多岐にわたり、単なる「体験の記録」ではなく、「学びの深化」や「他者との協働的な知識構築」を促進するための道具として機能しています(Bell & Smith, 2020)2。
特筆すべきは、これらの活動があくまで展示空間と連動している点です。すなわち、「観察する→表現する→共有する」という流れが、一貫した教育設計の中に組み込まれており、来館者の関与が“学びの成果”として形になるように設計されているのです。
こうした体験は、来館者にとって単なる娯楽や記憶に残るイベントではなく、展示内容に対する深い理解や自己の価値観の形成にもつながります。さらに、協働的な活動を通じて他者と対話し、自分の考えを言語化するというプロセスは、教育心理学や学習科学の観点からも高い学習効果が認められている手法です。
デジタル技術が果たす役割は、ここでも極めて重要です。ツールとしてのデジタルは、展示内容を補足するだけでなく、**来館者が「何を感じ、何を考え、何を創り出すか」という活動全体を支える“共創の基盤”**として活用されています。これは博物館が「知識を与える場所」から、「共に知識をつくる場所」へとシフトしている証ともいえるでしょう。
学びのプロセスを支える ― 思考を引き出す展示とデジタルの役割
参加型体験を重視する博物館教育では、来館者が展示とどのように関わり、何を感じ取り、どのように考えるかという内面的な学びのプロセスが重視されるようになってきました。来館者自身が能動的に展示を読み解き、自分なりの問いを立てていくことは、深い学びにつながると同時に、博物館に対する主体的な関与を生み出す重要なきっかけとなります。
しかしながら、そのような学びの過程は、学校のテストのように目に見える形で確認できるものではありません。とくに博物館のように、自由度が高く来館者ごとに体験の仕方が異なる場においては、「どのような学びが起きたのか」を把握することは決して容易ではないのです。
こうした“見えにくい学び”を支えるために、近年注目されているのが来館者の思考や発見を促す工夫を、展示の中に丁寧に組み込んでいくことです。とくにデジタル技術を用いることで、それぞれの来館者に合わせて、より自然に学びを深める仕掛けをつくることが可能になってきました。
たとえばYoonら(2012)は、科学館の展示にAR(拡張現実)技術を組み合わせることで、子どもたちが「なぜそうなるのか」「ほかの場合でも同じことが言えるのか」といった問いを自分の中で立てながら展示に向き合うようになったと報告しています。ここで重要なのは、情報が与えられるのではなく、問いが引き出されるような仕組みが用意されていたという点です(Yoon et al., 2012)3。
また、ARによって表示される視覚的な補足情報や、段階的に現れるヒントが、来館者それぞれの理解度や関心に応じて、自分なりに考え、試行錯誤しながら学ぶことを可能にしていたとも述べられています。このように、展示に対する「気づき」や「発見」を丁寧に引き出す設計があってこそ、デジタル技術は学びを深める力を発揮するのです。
このような事例は、博物館という自由な環境においても、適切な問いの投げかけや選択の余地を残した設計によって、より豊かな学びを支えることができるという可能性を示しています。来館者が自分のペースで考え、自らの興味に沿って情報を選び、さらにその場で考えを深める。このプロセスを促すことが、博物館教育におけるデジタル技術のもうひとつの重要な役割なのです。
すべての人に開かれた学びの場へ ― 多様性に応えるデジタル教育のデザイン
博物館教育の進化は、単に新しい技術を導入するだけでなく、「誰が、どのようにして学べるのか」という問いと真摯に向き合うことによって、はじめて意味を持ちます。近年、博物館におけるアクセシビリティやインクルーシブ・デザイン(包摂的デザイン)への関心が高まる中で、多様な背景や特性を持つ来館者にとって、学びやすく、安心して参加できる環境の整備が急務となっています。
特に注目されるのは、感覚に過敏さを抱える子どもや、自閉症スペクトラムを持つ来館者に対する配慮です。展示空間の明るさ、音、混雑状況など、来館者にとっては予期しづらい要素が多く、それがストレスや不安につながることがあります。こうした来館者にとって、「展示を見る」という行為そのものが負担となり、教育的な体験から距離を置かざるを得ない状況が少なくありません。
この課題に対し、Fletcherら(2018)は、アメリカの複数の美術館で導入された「センサリー・ギャラリー・ガイド」の効果を調査しています。このガイドは、展示空間内での音や光、混雑の程度、さらには避難可能な静かな場所などの情報を事前に提供するものであり、来館者が自分に合ったペースと方法で博物館を体験できるよう支援するツールです。
調査の結果、こうしたガイドを活用した家族は、展示に対する不安が軽減され、子どもが安心して展示に向き合えるようになったと回答しています。また、スタッフとの事前のコミュニケーションが可能になることで、来館前から教育的な関わりが始まっているという点でも大きな効果がありました(Fletcher et al., 2018)4。
このような取り組みは、特別な配慮を必要とする来館者のためだけのものではありません。「誰にとっても快適で、学びやすい」環境づくりは、結果としてすべての来館者の体験の質を向上させるという普遍的な価値を持っています。デジタル技術を活用することで、視覚的・聴覚的な情報提供の多様化、個人に合わせた情報の提示、来館前の体験予告など、柔軟な対応が可能になります。
包摂的な学びの場をつくるという視点は、博物館の社会的使命を再考する上でも極めて重要です。すべての人が等しく学びにアクセスできる環境は、文化施設としての博物館の信頼性と公共性を支える土台であり、そこにデジタル技術の役割を重ね合わせることは、未来の教育を見据えた経営戦略の一環ともいえるでしょう。
デジタル時代における博物館教育の展望
ここまで見てきたように、デジタル技術の導入は博物館教育の姿を大きく変えつつあります。しかしその変化は、単なる道具立ての刷新にとどまるものではありません。来館者の学びに対する捉え方そのものが、より個別的に、より参加的に、そしてより包摂的に捉え直されている点にこそ、本質的な変化があるといえます。
ARやアプリケーションを活用することで、ひとりひとりの興味や理解度に応じた体験が提供されるようになりました。これは、情報を一律に伝えるという旧来の教育観を離れ、学びの多様性を認め、支える教育設計へのシフトを意味します。さらに、デジタル技術は来館者の内面にある問いや思考を引き出し、展示との深い対話を可能にする構造づくりにも貢献しています。
また、教育活動が「誰にとっても開かれていること」、すなわちアクセシビリティやインクルーシブ・デザインの重要性も、デジタル化によって再認識されるようになりました。視覚や聴覚、感覚過敏といった個別のニーズに応じた支援のあり方は、特別な対応ではなく、博物館が担うべき教育的・社会的責任の一部として制度化されていくべきものです。
こうした実践は、いずれも技術的な革新を起点としながらも、その根底には「来館者中心の学びとは何か」という問いがあります。来館者が展示を通して自ら考え、他者と関わり、社会とのつながりを再発見するような経験をいかに支えるか。この問いに対する博物館の応答が、デジタル時代の教育活動の核心であるといえるでしょう。
さらに、デジタル技術は教育活動を展示室内に閉じ込めず、時間や場所を超えて拡張していく力を持っています。オンライン学習、遠隔プログラム、来館前後の補助教材、バーチャル展示など、教育の設計はより柔軟かつ持続的なものへと変化しています。これにより、博物館は一過性の訪問ではなく、継続的な学習の拠点としての役割を果たすことができるのです。
もちろん、こうした変化には新たな課題も伴います。技術への依存がもたらす教育の形式化、来館者との物理的な関係の希薄化、情報の信頼性や倫理的配慮など、多面的な検討が必要です。しかしそれでもなお、デジタル技術が開く教育の可能性は、博物館の未来にとって避けては通れない大きなテーマであることに変わりはありません。
これからの博物館教育は、技術革新を取り込みながらも、常に「人間の学びとは何か」という本質的な問いに立ち返りながら進化していく必要があります。デジタル時代においても、博物館は来館者ひとりひとりの思考と対話を支える場所であり続けるべきであり、そのための知恵と構想力が、今まさに求められています。
参考文献
- Moorhouse, N., tom Dieck, M. C., & Jung, T. (2019). An experiential view to children learning in museums with augmented reality. Museum Management and Curatorship. https://doi.org/10.1080/09647775.2019.1578991 ↩︎
- Bell, D. R., & Smith, J. K. (2020). Inside the digital learning laboratory: New directions in museum education. Curator: The Museum Journal, 63(3), 371–390. https://doi.org/10.1111/cura.12376 ↩︎
- Yoon, S. A., Elinich, K., Wang, J., Steinmeier, C., & Tucker, S. (2012). Using augmented reality and knowledge-building scaffolds to improve learning in a science museum. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 7, 519–541.https://doi.org/10.1007/s11412-012-9156-x ↩︎
- Fletcher, T. S., Blake, A. B., & Shelffo, K. E. (2018). Can sensory gallery guides for children with sensory processing challenges improve their museum experience? Journal of Museum Education, 43(1), 66–77.https://doi.org/10.1080/10598650.2017.1407915 ↩︎