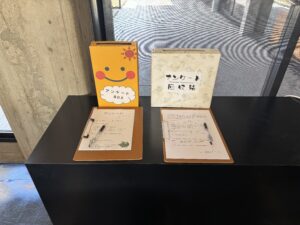はじめに
災害や感染症の拡大、経済的混乱といった社会的ショックが繰り返される現代において、「レジリエンス(resilience)」という概念がさまざまな分野で注目を集めています。元々は生態学や工学の分野で用いられてきた言葉ですが、現在では組織や地域社会、教育、福祉などの幅広い領域に拡張され、変化や困難に対して柔軟に対応し、持続的に発展し続ける力として定義されています。
このような時代背景の中で、博物館という文化施設にもまた、独自のかたちでの「レジリエンス」が求められるようになってきました。博物館は単なる展示空間や収蔵庫ではなく、文化を支え、地域とつながる公共的な拠点です。災害による被害やパンデミック下での来館制限といった危機的状況においても、その活動を止めることなく、社会にとっての存在意義を再定義し続けることが期待されています。
たとえば、地震多発地域においては収蔵庫の耐震対策が急務となり、組織面では災害時に対応可能な人員体制や連携ネットワークの構築が重要視されます。さらに、COVID-19のパンデミックでは、対面型の展示活動が制限される中で、オンライン展示やバーチャルイベントを通じて新たな来館者体験の創出が試みられました。これらの動きは、まさに博物館がそのあり方を問い直し、危機をしなやかに乗り越えようとする実践の表れといえるでしょう。
本記事では、この「レジリエンスと博物館」というテーマを、物理的・組織的・社会的という三つの視点から読み解き、博物館がいかにして危機に強い文化拠点としての姿を築いていけるのかを考察します。併せて、災害や危機のなかで実践されてきた国内外の事例や理論的枠組みにも触れながら、今後の博物館経営にとって不可欠な視座としての「レジリエンス戦略」を探っていきます。
レジリエンスとは何か ― 理論的枠組みの整理
「レジリエンス」という語は、直訳すれば「回復力」や「復元力」を意味しますが、実際にはそれ以上に広く、柔軟性・持続性・適応力といった多様な含意をもっています。この言葉が社会科学や経営論において注目されるようになったのは、環境変動や災害、経済不安などの“予測不能な変化”に対して、いかにして組織や制度が対応しうるかが問われる時代背景があるからです。
レジリエンスの分類にはさまざまな整理がありますが、その代表的なものとして、工学的・生態学的・進化論的という三つの類型が挙げられています(Martin & Sunley, 2015)。
- 工学的レジリエンス(Engineering Resilience)
元の状態に素早く戻る「弾力性」の強さに着目した考え方です。たとえば、災害に見舞われた後に施設が物理的に復旧するスピードなどがこれに該当します。 - 生態学的レジリエンス(Ecological Resilience)
一定の変化やショックを許容しながらも、全体としての機能や構造を保ち続ける力です。一定の範囲での変化にしなやかに適応する性質が評価されます。 - 進化論的レジリエンス(Evolutionary Resilience)
変化や危機を“再構築の契機”と捉え、新たな方向性へと構造を変容させていく動的なアプローチです。単なる復旧ではなく、前向きな変化=“バウンス・フォワード(bounce forward)”の概念が重視されます(Martin et al., 2016)。
近年の文化政策や博物館経営においては、こうした進化論的レジリエンスの視点がとくに重要視されています。文化遺産を守ることがレジリエンスの鍵であるという従来の考え方に対し、文化的レジリエンスとはむしろ変化や損失を受け入れながら、新たな意味や関係性を創出していく力であるとする立場も示されています(Holtorf, 2018)。
このように、博物館にとってのレジリエンスは、単なる災害への耐性や復元力にとどまらず、「未来に向かって変わり続ける力」として再定義されつつあるのです。
博物館におけるレジリエンスの3つの側面
レジリエンスという概念を博物館に応用する際、重要なのはその多層的な性質を理解することです。博物館におけるレジリエンスは、単に施設の物理的な強さや耐震性だけでなく、人的資源、組織体制、そして地域社会との関係性など、広範な要素から成り立っています。ここでは、レジリエンスを「物理的」「組織的」「社会的」という三つの側面に分けて検討します。
物理的レジリエンス:保存と安全のインフラ
物理的レジリエンスとは、建物や収蔵庫、展示設備などが外的な衝撃に耐える能力を指します。たとえば地震・火災・洪水などの自然災害に対する耐震化・防火対策は、その基本です。免震装置や可動式の展示ケースといった設備も、近年注目されています(Monaco et al., 2020)。特に小規模な地域博物館では、限られた予算の中でいかに効果的な物理的対策を講じるかが課題となっています。
組織的レジリエンス:人材・体制・運営基盤の柔軟性
次に重要なのは、組織としてのレジリエンスです。危機発生時に意思決定が迅速に行われ、適切な対策がとられるためには、職員の役割分担、情報共有の仕組み、外部とのネットワークが鍵となります。実際に地震被害を受けたマルケ州の博物館群を対象とした研究では、「構造」「人材」「関係性」という三つの視点から博物館のレジリエンスを評価する手法が提案されています(Cerquetti & Cutrini, 2022)。特に人的資源の充実度が、多くの館で改善の余地がある課題として指摘されています。
社会的レジリエンス:地域とのつながりと信頼の再構築
博物館のレジリエンスは、社会的な側面にも大きく関わります。災害やパンデミックの際、博物館が「地域の拠点」として機能できるかどうかは、その地域社会との関係性にかかっています。文化的記憶の継承や心の回復において、博物館は大きな役割を担うことができます(Holtorf, 2018)。また、COVID-19下におけるオンライン展開やバーチャルツアーは、物理的制限の中でも博物館がコミュニティとつながり続ける試みとして注目されました(Belenioti, 2022)。
このように、博物館のレジリエンスは単一の要素ではなく、インフラ・組織・社会の三層構造として捉えることで、より実践的かつ包括的に理解することが可能になります。
ケーススタディ:震災・パンデミック・経済危機と博物館の対応
博物館のレジリエンスを具体的に理解するためには、実際に危機的状況に直面した事例から学ぶことが重要です。ここでは、自然災害・感染症・経済危機という三種の異なるショックに直面した博物館の対応を取り上げ、それぞれの文脈におけるレジリエンスの在り方を検討します。
地震災害とイタリア中部の博物館群
2016年にイタリア中部で発生した地震は、多くの文化財や博物館施設に深刻な被害をもたらしました。特にマルケ州では、複数の中小規模博物館が建物損壊やアクセス不能などの課題に直面しました。これに対し、地域の文化ネットワークを活用した仮設展示や巡回展示への転換、近隣自治体との連携による再開支援など、柔軟かつ創造的な対応が取られました。
この事例を分析した研究では、博物館のレジリエンスを評価するための指標として、「物理的安全性」「人的資源」「組織的ネットワーク」の三要素が提案されています(Cerquetti & Cutrini, 2022)。とりわけ、行政と文化機関の間に信頼関係が築かれていたことが、迅速な対応の基盤となっていました。
COVID-19と博物館のデジタル展開
2020年以降の新型コロナウイルス感染拡大により、世界中の博物館は一時的な休館を余儀なくされました。この状況下で注目されたのが、デジタル技術を活用した新しい博物館活動の展開です。SNSを活用した館内紹介、バーチャルツアー、ARを活用した体験プログラムなどが急速に導入され、来館者との接点を維持するための努力が続けられました。
とくにフェスティバルや大規模イベントを伴う博物館では、デジタルへの移行が一時的な代替手段ではなく、「新しい文化消費の形」として定着しつつあります(Belenioti, 2022)。この事例は、文化機関が柔軟性をもってサービス提供の形を再設計できることを示しており、進化論的レジリエンスの典型ともいえます。
経済危機とギリシャの考古学博物館
2008年の世界金融危機は、ギリシャの公共文化機関にも深刻な影響を及ぼしました。予算削減や人員不足により、複数の国立博物館が運営困難に直面しました。こうした状況に対して、いくつかの博物館では観光業界のノウハウを取り入れた「体験型」モデルの導入や、地域企業との連携による資金確保の取り組みが始まりました。
とりわけ注目されるのは、「戦略的アジリティ(strategic agility)」という概念に基づく対応です。これは、変化の激しい環境において柔軟かつ即応的に戦略を再設計する能力を指し、従来の「安定重視」の運営スタイルとは一線を画すものです(Poulios & Touloupa, 2019)。このアプローチは、制度的に硬直しがちな文化機関における経営手法として、今後の示唆に富むものといえるでしょう。
考察:博物館はなぜレジリエンスを求められるのか
これまで見てきたように、博物館におけるレジリエンスは、物理的な安全性にとどまらず、組織体制や社会との関係性にいたるまで多面的に広がる概念です。しかしそもそも、なぜ今、博物館にこれほどまでに「レジリエンス」が求められるのでしょうか。
第一に、博物館が果たすべき役割が拡張しているという社会的背景があります。かつての博物館は、収集・保存・展示という機能を中心とした「モノの保存」の施設でした。しかし今日、博物館は文化的包摂、地域との協働、教育や福祉への貢献など、多様な社会的機能を担うことが期待されています。こうした役割を果たすためには、予期せぬ変化や社会のニーズの変化に対応できる柔軟な姿勢が不可欠です(Cerquetti & Cutrini, 2022)。
第二に、博物館は「文化のインフラ」として、災害や危機の中にあっても市民が信頼を寄せる拠点であるという点が挙げられます。パンデミックや地震、経済危機といった重大な変化が生じたとき、人々は文化を通じて安心や希望を見出そうとします。そうした場を提供するのが博物館であり、だからこそ継続的な存在であることが求められるのです(Holtorf, 2018)。
第三に、レジリエンスは博物館経営にとって「戦略的価値」として位置づけられるようになっています。たとえば、ギリシャの考古学博物館のように経済危機に直面した施設が、従来の業務を見直し、「体験型サービス」や「観光との連携」といった新たな価値提案を試みたことは、単なる復旧ではなく、組織の変革を通じた未来志向の経営への転換といえます(Poulios & Touloupa, 2019)。レジリエンスは、危機を通じて組織を強化し、新しい可能性を模索するための出発点にもなりうるのです。
このように、博物館におけるレジリエンスは、「元に戻る力(recovery)」ではなく、「よりよく変わっていく力(transformation)」として再定義されています。それは、未来に開かれた文化拠点として、どのように社会に貢献し続けられるかという問いに対する一つの答えであり、同時にこれからの博物館経営の根幹を支える概念でもあります。
まとめ
本記事では、「レジリエンスと博物館」というテーマのもと、理論的枠組みの整理から、具体的な事例、そして経営的視点に基づく考察までを多角的に検討してきました。博物館に求められるレジリエンスとは、単なる復旧力ではなく、危機を契機として変化し、持続的に成長するための組織的・社会的な柔軟性そのものです。
自然災害やパンデミック、経済危機など、想定を超える出来事が次々と押し寄せる現代において、博物館は「文化の拠点」としての役割を再定義することが求められています。そうした時代のなかで、物理的・組織的・社会的なレジリエンスを統合的に備えた博物館こそが、未来にひらかれた公共文化の担い手となるのです。
参考文献
- Cerquetti, M., & Cutrini, E. (2022). Structure, people and relationships: A multidimensional method to assess museum resilience. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, 12(4), 468–484.
- Holtorf, C. (2018). Embracing change: How cultural resilience is increased through cultural heritage. World Archaeology, 50(4), 639–650.
- Monaco, M., Pacella, G., & Formisano, A. (2020). Resilience of museum contents: Analysis and strategies to protect objects during earthquake. Journal of Cultural Heritage, 44, 91–103.
- Belenioti, Z. C. (2022). COVID-19 resilience via digital cultural heritage: Digital life in museums and festivals during the anthropause. International Journal of Technology Marketing, 16(2), 123–141.
- Poulios, I., & Touloupa, K. (2019). Museums and crisis: The imperative to achieve strategic agility. Museum International, 71(1–2), 82–91.
- Martin, R., & Sunley, P. (2015). On the notion of regional economic resilience: Conceptualization and explanation. Journal of Economic Geography, 15(1), 1–42.