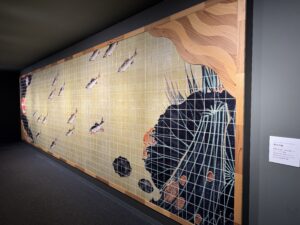はじめに
「博物館とは何か」という問いは、近年ますます複雑で多層的になっています。かつては、貴重な文化財や自然資料を集め、展示し、保存する場所としての役割が中心でした。しかし今日では、博物館は単なる「ものの収蔵庫」ではなく、地域社会における学びや対話、参加の場としての性格を強めつつあります。こうした変化を象徴する概念のひとつが「エコミュージアム(ecomuseum)」です。
エコミュージアムは、1970年代のフランスで誕生した新しい博物館モデルであり、地域そのものを博物館と見なすという革新的な考え方に基づいています。これは、従来のように建物の中にモノを収集・展示するのではなく、地域の風景や暮らし、記憶、語りといった目に見えにくい文化的要素までをも含めて博物館の対象とするものです。そして、その中心にいるのは、専門家ではなく地域に暮らす住民たち自身です。エコミュージアムは、地域の人々が自らの文化や環境に主体的に関わり、それを未来へと手渡していくプロセスそのものを博物館の営みと見なします(Rivière, 1985; Davis, 2011)。
このような理念は、博物館の公共性や持続可能性を問い直すうえで非常に示唆に富んでいます。特に、少子高齢化や都市集中化、地域経済の停滞といった課題を抱える現代社会において、エコミュージアムの発想は地域再生のヒントとして注目されています。また、文化政策や観光戦略の文脈でも「地域とともにある博物館」の重要性が語られるなか、エコミュージアム的アプローチは制度化の対象としても取り上げられるようになりました(Hsu et al., 2018)。
本記事では、エコミュージアムとはそもそも何か、通常の博物館とどのような違いがあるのか、どのように展開されてきたのかについて、理論的枠組みと国内外の実践事例をもとに検討していきます。そして、地域参加や共創、持続可能性といった視点から、現代の博物館にとってエコミュージアムがどのような意義を持ちうるのかを考察します。
エコミュージアムとは何か
エコミュージアム(ecomuseum)は、地域社会の人々が主体となって、自らの文化や自然、歴史、産業などを再発見・保存・発信する新しいタイプの博物館です。その語源は、ギリシア語の「οἶκος(oikos=住まう場所)」に由来する「エコロジー(ecology)」にあります。この概念は1970年代初頭、フランスの文化政策改革の中で生まれ、従来の博物館観に大きな変化をもたらしました(Rivière, 1985)。
従来の博物館が、主に収集・保存されたモノを専門家が管理し、建物の中で展示・解説するモデルであったのに対し、エコミュージアムは地域に暮らす人々自身が、日常の中で育まれた文化や風景を「展示」の対象と見なし、それを未来へと手渡していくプロセスそのものを博物館活動と位置づけます。したがって、建物を持たないエコミュージアムも多く、「地域全体が博物館である」という考え方が中核をなしています。
エコミュージアムの定義にはさまざまな解釈がありますが、進化的定義の中では、次のような機能が提示されています。
- 地域住民が自らの文化や環境を見つめ直すための「鏡」であること
- 新しい文化的・社会的価値を創出する「ラボラトリー」であること
- 有形・無形の遺産を未来に伝える「保存センター」であること
- 学びの場として地域と共に成長する「学校」であること(Rivière, 1985)
これらはすべて、地域住民の主体的な参加を前提としています。博物館が「提供する」ものから、「共につくる」ものへと変わっていく、その過程自体が重要なのです。
また、エコミュージアムを特徴づける要素として、「場所」「人」「時間」の三つが挙げられています(Davis, 2011)。「場所」とは地域固有の自然環境や文化的景観、「人」とはそこに暮らし語り継ぐ住民、「時間」とは過去・現在・未来をつなぐ記憶と継承を意味します。エコミュージアムは、これら三つの交差点において、生活文化の価値を可視化し、地域の自己認識と共創の場を生み出します。
近年では、文化資本の活用や地域再生、住民自治、観光振興など多様な場面でエコミュージアムの理念が活かされています。その柔軟な運営形態と参加型の性格から、持続可能な地域社会を築くための有力なモデルとして注目されているのです。
理論モデルと定義の展開
エコミュージアムの概念は、単に「地域全体を博物館と見なす」というアイデアにとどまらず、地域住民との関係性や社会的機能のあり方までを含む、包括的なモデルとして発展してきました。その理論的枠組みを理解することは、現代の博物館が果たすべき役割を再考するうえで重要です。
まず、エコミュージアムを従来型の博物館と対比的に捉えるモデルとして、5つの観点による分類が提案されています。それは、1)目的、2)展示対象、3)専門性、4)運営主体、5)訪問者の位置づけ、という視点から、博物館が「物中心」「学芸員中心」「展示中心」であるのに対し、エコミュージアムは「生活中心」「住民中心」「対話中心」であると整理するものです(Corsane et al., 2007)。
| 観点 | 従来型博物館 | エコミュージアム |
|---|---|---|
| 目的 | 収集・保存・展示 | 参加・共創・継承 |
| 対象 | モノ(美術品、資料) | 人・暮らし・風景・記憶 |
| 専門性 | 学芸員が主導 | 住民が主体的に関与 |
| 運営 | 専門職中心の体制 | 地域協働型の運営 |
| 来館者 | 消費者・観客 | 参加者・共同制作者 |
また、エコミュージアムの機能と価値を理論的に可視化する試みとして、「創造性の三角形」や「ネックレスモデル」といった概念モデルが提案されています。前者は、地域における自然資源・文化資源・社会資源を有機的に結びつけ、博物館活動を通じて新たな価値を生み出すという枠組みです。後者は、複数の展示拠点や活動拠点が「真珠のように」点在し、それらを結ぶネットワーク全体を博物館とみなす構想であり、広域型ミュージアムや地域連携の発想にもつながります(Davis, 2011)。
さらに、エコミュージアムの持続可能性や運営の評価をめぐる理論的整理も進められています。とくに、社会関係資本(social capital)、文化的資本(cultural capital)、経済的資本(economic capital)という三層構造で捉える視点は、博物館が地域社会にもたらす多元的な価値を理解するうえで有効です(Corsane et al., 2007)。この考え方は、単なる運営評価を超えて、地域の未来を形づくる文化拠点としての博物館の役割を再定義するものでもあります。
このように、エコミュージアムの理論モデルは、従来型の博物館とは異なる「参加・共創・地域密着」という特性を体系的に説明する枠組みを提供しています。現代の博物館がその理念を取り入れることで、より深く地域と結びつき、社会的価値を高める可能性が拓かれていくのです。
国内外の実践事例
エコミュージアムという理念は、特定の国や文化に限定されるものではなく、世界各地の多様な地域で実践されています。それぞれの事例は、地域の環境や歴史、文化、そして社会的課題に応じた形で展開されており、エコミュージアムというモデルの柔軟性と汎用性を示しています。
フランスでは、エコミュージアム発祥の地として、1970年代以降さまざまな地域で先駆的な取り組みが行われてきました。たとえば、ル・クレゾーでは、鉄鋼業の衰退を受けて産業遺産と地域の記憶を活用したエコミュージアムが整備され、地域の再生と住民の誇りの再構築に貢献しました。また、セヴェンヌ国立公園では、自然環境の保護と伝統的な農業文化の継承を目的に、住民参加型のエコミュージアム活動が展開されています(Davis, 2011)。
イタリアでは、ピエモンテ州を中心に制度的に整備されたエコミュージアムが数多く存在します。これらは地域行政と住民との協働によって運営され、文化資源の保全だけでなく、地場産業や教育活動とも連動しながら、持続可能な地域づくりに寄与しています。これらのエコミュージアムでは、活動の成果を評価するための指標も導入されており、社会関係資本や文化的資本といった非金銭的価値の可視化も試みられています(Corsane et al., 2007)。
一方、アジアでもエコミュージアムの考え方が導入されています。中国では、少数民族地域を中心に、言語・儀礼・住居などの無形文化遺産を地域住民自身が伝承していく場として、エコミュージアム的な運営が展開されています。これは、少数民族文化の保存とともに、観光化による一方的な消費からの脱却を目指す動きでもあります(Su, 2008)。
台湾では、竹工芸で知られる南投県竹山鎮において、地域経済の再建と文化継承を目的としたエコミュージアム構想が提案されています。このプロジェクトでは、運営評価の枠組みにFuzzy Delphi法やAnalytic Network Processを導入し、地域参加・文化伝承・地域活性といった観点からエコミュージアムの可能性を定量的に分析しています(Hsu et al., 2018)。
日本においても、北海道の炭鉱遺産を活用した地域再生や、富山県利賀村での演劇文化と生活文化の融合など、エコミュージアム的発想に基づく多様な実践が見られます。これらは制度的に「エコミュージアム」と明記されていない場合もありますが、地域資源の可視化と住民参加に基づく活動という点において、エコミュージアムの理念に通じるものです。
これらの国内外の事例は、エコミュージアムが単なる展示形式ではなく、地域社会そのものの営みに根ざした活動であることを示しています。文化の保存だけでなく、人々の暮らしや誇り、未来へのまなざしを支える場として、エコミュージアムは多様なかたちで展開されているのです。
エコミュージアム的発想がもたらす可能性
エコミュージアムは、従来の博物館の枠組みを越え、地域社会との関係性を再構築する可能性を秘めたモデルです。その根底にあるのは、「展示する」文化ではなく、「ともにつくる」文化への転換です。この発想は、博物館が果たすべき社会的な役割を問い直す視点として、現代的な意義を持っています。
第一に、エコミュージアム的アプローチは、地域住民の主体的な関与を促します。住民が単なる来館者ではなく、文化の担い手として活動に参加することで、博物館は学習と対話の場を超え、地域アイデンティティの形成や誇りの再生につながっていきます。これは、展示物の保護だけでなく、地域に根ざした知識や経験そのものを「文化資源」として扱うことを意味します(Davis, 2011)。
第二に、エコミュージアムは、地域資源の再発見と再評価を可能にします。たとえば、忘れられつつある産業遺産や伝統技術、日常の風景や語りといった「身近すぎて見えなくなっていた価値」を可視化することは、文化の多様性を守るうえでも重要です。特に、都市と農村、中心と周縁といった構造的な不均衡に対して、地域主導の文化活動を通じてバランスを取り戻す契機にもなります(Corsane et al., 2007)。
第三に、エコミュージアムの理念は、現代の博物館経営における「持続可能性(sustainability)」という課題にも応答しうる視点を提供します。来館者数や収益といった短期的な指標では測れない、地域との信頼関係や文化的厚みを築くプロセスにこそ、博物館の社会的価値があるとする考え方です。このような視点から、文化資本や社会関係資本の蓄積を評価軸に組み込む取り組みも提案されています(Hsu et al., 2018)。
一方で、エコミュージアム的手法には限界や課題もあります。地域の合意形成には時間がかかり、運営がボランティア頼みになりがちである点、また制度化や観光資源化が進むことで、本来の住民主体性が損なわれるリスクも指摘されています(Howard, 2002)。こうした側面にも目を向けながら、柔軟で継続的な関係性を築くことが求められます。
このように、エコミュージアムの発想は、単なる施設運営の方法論を超えた、文化と社会をつなぐ「関係性のデザイン」として位置づけることができます。現代の博物館が地域社会の中で果たす役割を再構築するうえで、エコミュージアム的な視点は、制度や形態にとらわれず柔軟に応用できる実践的なフレームとなるのです。
まとめ
エコミュージアムは、地域とともにある博物館の理想を体現するモデルとして、理論と実践の両面から注目されてきました。その本質は、展示や保存といった従来の博物館機能を拡張し、住民の主体的な参加と地域資源の共創を軸に据えた文化のあり方にあります。
「場所」「人」「時間」のつながりを軸に、地域に眠る物語や風景、記憶を掘り起こし、未来に手渡していく営み。そこにおいて博物館は、学びの場であり、対話の場であり、創造の場へと変化していきます。制度や建物に依存せず、関係性そのものを育てるというこのアプローチは、現代の博物館が社会に対してどのように貢献しうるかという問いに、一つの実践的な答えを提示しています。
今後、博物館が地域社会とのつながりを再構築し、より深い公共性と持続可能性を追求していくうえで、エコミュージアムの発想は有効な道しるべとなるでしょう。それは、単に新しい展示手法を導入することではなく、地域に根ざした文化の循環と、そこで生きる人々との対話を育む営みに他なりません。
参考文献
- Corsane, G., Davis, P., & Murtas, D. (2007). Ecomuseum performance in Piemonte and Liguria, Italy: The significance of capital. International Journal of Heritage Studies, 13(3), 223–239.
- Corsane, G. (2006). Using ecomuseum indicators to evaluate the Robben Island Museum and World Heritage Site. International Journal of Heritage Studies, 12(2), 157–177.
- Davis, P. (2011). Ecomuseums: A sense of place (2nd ed.). Bloomsbury Academic.
- Howard, P. (2002). The eco-museum: Innovation that risks the future. International Journal of Heritage Studies, 8(1), 63–72.
- Hsu, F.-C., Chao, L.-C., & Yeh, Y.-C. (2018). Constructing an evaluation framework for eco-museum operations-management performance. Sustainability, 10(7), 1934.
- Rivière, G. H. (1985). The ecomuseum—An evolutive definition. Museum, 37(4), 182–183.
- Su, D. (2008). The concept of the ecomuseum and its practice in China. Museum International, 60(1–2), 31–39.