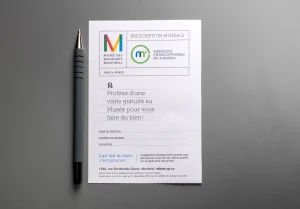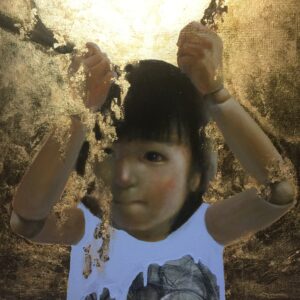はじめに
現代の地域社会は、かつてないほど多様で複雑な課題に直面しています。高齢化の進行、地域コミュニティの衰退、災害リスクの増大、外国人住民の増加に伴う多文化共生の課題、そして経済格差や教育機会の不均衡。こうした課題は、地方自治体や福祉機関だけでなく、地域に根ざすあらゆる公共機関に対して新たな役割を期待させる要因となっています。もちろん、博物館も例外ではありません。
長らく博物館は、「モノを保存し、展示し、教育する場」としてその意義を語られてきました。しかし近年では、「人と人をつなぎ、地域社会とともにある存在」としての再評価が進みつつあります。とりわけ地域住民の中には、「博物館には関係がない」「敷居が高い」と感じる人々も少なくなく、こうした認識そのものが、博物館の公共性を問い直す契機となっているのです。博物館は果たして、誰のために、何のために存在するのか。地域の課題とどう関わることができるのか。こうした問いは、今や単なる理念ではなく、具体的な実践や経営のあり方に直結する重要なテーマとなっています。
このような状況を背景に、博物館を「ケアの空間」として捉える動きが広がりつつあります。従来のように「ものを大切にする場」としての博物館に加え、「人を大切にし、関係を築く場」としての可能性に注目が集まっているのです(Munro, 2013)。特に、地域で孤立しがちな人々との対話や、福祉・医療・教育と連携した事業は、博物館が社会的な包摂や回復力の拠点となる可能性を示しています(Morse & Munro, 2015)。また、博物館が地域の声を反映しながら展示やプログラムを共に創り上げるプロセスは、単なるイベントを超えた「社会関与のかたち」として注目されています(Callahan Schreiber et al., 2023)。
本記事では、こうした国際的な議論と実践例をもとに、博物館がいかにして地域課題と向き合い、社会的使命を果たしていけるのかを探っていきます。「ケア」「参加」「共創」といったキーワードを手がかりに、博物館と地域社会との関係性を見つめ直すとともに、持続可能な地域連携の条件や課題についても考察を深めていきます。
理論的背景 ― ケア・学び・参加の視点から読み解く博物館の社会的役割
地域課題への対応が求められる中で、博物館の役割を捉え直す理論的枠組みも進化しています。かつては「モノ」を中心に据えた保存・展示・教育が博物館の主たる機能とされてきましたが、現代の社会的要請は、より人間に焦点を当てた方向へと移りつつあります。つまり、博物館が「人と人とをつなぐ場所」「学びと対話の場」「社会的ケアの場」として、地域の中でどのような意味を持ちうるのかが問われているのです。
こうした変化を読み解くためのひとつの視点が、「ケア」の概念です。グラスゴー市博物館の実践を調査した研究では、コミュニティ・エンゲージメントの活動が、来館者や地域の人々との信頼関係を築き、彼らが安心して関わることができる環境を整えるための、日々の細やかな気配りや心配りによって支えられていることが示されています(Munro, 2013)。こうした関係づくりには、単に情報を伝えるだけでなく、相手の不安に寄り添ったり、安心できる雰囲気をつくったりといった、「感情のやりとり」を伴う対応が求められます。たとえば、初めて博物館を訪れた移民の親子に対して、ゆっくりと話しかけたり、表情や態度で歓迎の気持ちを示したりといった対応も、その一つです。
このような「相手の感情に働きかける仕事」は、「感情労働(emotional labour)」と呼ばれ、医療や福祉の現場でも注目されてきた概念です。博物館の現場においても、こうした感情面のケアはしばしば見過ごされがちですが、実は地域住民との関係性を築く上で非常に重要な役割を果たしています。研究では、これらの感情労働が博物館の社会的使命の一部であることが明確にされており、その意義を職員自身が深く実感している様子も報告されています(Morse & Munro, 2015)。
また、博物館を「学び」の空間として捉える議論も進んでいます。Kimら(2016)は、博物館における成人教育と社会変革に関する研究を批判的に整理し、「成人の社会変革を促す学び(ALSCE)」という概念を導入しています。この概念は、博物館を単なる情報提供の場ではなく、地域課題に対する気づきや行動を促す学習の拠点として捉えるものです。参加者同士の対話や共同作業を通じて、個人の変容だけでなく地域全体の変革へとつながるプロセスが重視されています。
さらに、制度的・倫理的観点からも重要な論点が提起されています。参加型プロジェクトにおいて、博物館がしばしば「公共の利益(public interest)」を名目に個人の語りや表現を管理・吸収してしまうことへの懸念が示されています(Graham et al., 2013)。このような一方向的な関係性に対して、「礼節(courtesy)」という視点が提示されており、これは個人の語りを単なる資源として扱うのではなく、共に関わる対等な相手として尊重し、情報の使用や再展示に際しては確認や説明責任を果たすことを重視する姿勢です。博物館が真に地域とつながるためには、「共創」という理念の背後にある倫理性と対等性への配慮が不可欠だといえます。
このように、ケア・学び・参加といった視点を通じて見えてくるのは、博物館が単なる知の貯蔵庫ではなく、地域に根ざした関係性の中で新たな価値を生み出す社会的装置であるという姿です。そしてそれは、来館者のみに限定された関係ではなく、地域の多様な主体と協働することによって初めて実現されるものでもあります。次節では、こうした理論的枠組みがどのように具体的な実践として展開されているのかを、国内外の事例を通じて見ていきます。
実践事例 ― 博物館が地域課題に応答した取り組みをひもとく
理論的な枠組みだけでは、博物館がどのように地域課題に向き合っているのかを実感することは難しいかもしれません。実際には、多くの博物館が地域住民との関係性を丁寧に築きながら、複雑な社会的課題に対して創意工夫をこらした取り組みを展開しています。この節では、海外の博物館による2つの事例を取り上げ、長期的な視点と協働の姿勢を持ったプロジェクトの具体像を紹介します。
最初の事例は、アメリカ・ミネソタ州にあるサイエンス・ミュージアム・オブ・ミネソタが取り組んだ、地域住民と協働して設計されたメーカーズペースに関するプロジェクトです。このプロジェクトは、単なる展示の更新やワークショップの実施ではなく、地域のBIPOC(Black, Indigenous, and People of Color)コミュニティとともに約10年にわたって進められたものであり、その中心には「コミュニティ・インフォームド・デザイン(CID)」という考え方が据えられていました(Callahan Schreiber et al., 2023)。
この取り組みでは、「地域の声を聞く」ことを起点に、プロジェクトの目標や活動内容、運営体制までもが共に設計されました。たとえば、参加者の価値観や背景を尊重し、それに応じて設計を調整していく「エマージェント・プランニング(emergent planning)」というアプローチや、博物館職員だけでなくコミュニティ側のリーダーも意思決定に関与する「分散型スタッフ体制」などが実践されました。これにより、博物館が一方的に地域に働きかけるのではなく、双方向的で持続可能な関係性が築かれていったのです。
次に紹介するのは、アメリカの地方都市における気候変動対話をテーマとしたプロジェクトです。ある地方博物館では、住民が気候変動という難しいテーマについて安心して語り合える場を設け、科学的知識の一方的な提供ではなく、「住民の経験や価値観に寄り添った対話」を軸とする活動を展開しました(Steiner et al., 2023)。
このプロジェクトでは、博物館が主導するのではなく、地元の市民団体や学校、地域行政といった多様な関係者と連携しながら、参加者の話を「聞くこと」に重点を置いたセッションが継続的に行われました。特に重要とされたのは、「正しさ」を教えることよりも、「語り合うこと」を通して互いの背景や感じ方を理解することでした。その結果、住民の間に新たなつながりが生まれ、気候変動という課題が「誰かの問題」から「私たちの課題」へと転換していくプロセスが確認されています。
これらの事例に共通するのは、博物館が単に教育的・文化的な資源を提供するだけでなく、地域の人びととともに課題を共有し、持続的な関係を築いていこうとする姿勢です。一過性のイベントではなく、時間をかけて関係性を育てること。主導権を一方的に握るのではなく、相手とともに考え、ともに創っていくこと。そうした「協働」の実践こそが、博物館の社会的役割を根本から支えているのです。
考察 ― 地域とともにある博物館の可能性と課題を見つめて
これまでに見てきた事例からは、博物館が地域課題に向き合ううえで、従来の役割を超えた新たな実践を展開している姿が浮かび上がってきました。ここでは、それらの取り組みに共通する要素と、それが意味する博物館の変化、さらにはその実現に際して直面する課題と今後への展望を考察します。
まず注目されるのは、いずれの事例も「長期的な関係性の構築」を重視している点です。単発のイベントやアウトリーチではなく、数年単位のプロジェクトを通じて、地域住民との信頼関係を丁寧に築き上げていることが共通しています。加えて、博物館が一方的にプログラムを提供するのではなく、地域の声を聞き、企画・運営に反映させていくという「相互的な関係性」が意図的に設計されています。そこには、博物館が地域と対等な立場で協働する姿勢が明確に現れており、従来の「提供者」と「受け手」という構図を超えた実践であることがわかります。
こうした取り組みの中では、「共通価値の形成」と「信頼の蓄積」が成功の鍵となっています。価値観の異なる人々が集まり、ともに空間をつくり上げるプロセスは、単なる合意形成以上の意味を持ちます。特に、参加者の背景や文化を尊重し、それに応じて計画を柔軟に調整する姿勢は、地域との協働における重要な要素です。そのためには、意思決定を分散化し、博物館職員だけでなく地域のリーダーや協働相手が運営に関与できる体制が求められます。
これらの実践が示すのは、博物館の役割が変化しつつあるという現実です。従来のように「モノ」に焦点を当てるだけではなく、「人」と「関係性」に重きを置く活動が、公共施設としての博物館の新たな使命になりつつあります。地域社会との対話を重ね、共に課題を捉え、共に未来を構想する。そのプロセスそのものが、博物館の公共性を再定義していると言えるでしょう。
しかし一方で、こうした取り組みを進めるにはいくつかの現実的な課題も存在します。第一に、継続的な協働には時間と人的リソースが必要であり、博物館の業務体制が十分に対応していないケースもあります。第二に、現場レベルでの柔軟な実践が、組織の制度や評価の仕組みと折り合わないことも少なくありません。また、地域の「声」を誰が代表するのかという問題や、参加の偏り・象徴的参加にとどまるリスクも慎重に検討する必要があります。
これらの課題を踏まえたうえで重要なのは、関係性そのものを成果とみなす視点を持つことです。イベントの実施回数や来館者数といった数値指標だけでなく、関係性の質やプロセスの中で生まれた変化に目を向けることが求められます。小さな実践の積み重ねが、やがて制度や組織文化を変えていく可能性を持っているのです。
博物館はもはや、完成された知を提示する場ではなく、地域の中で対話と共創を通じて育っていく場です。「地域とともに育つ存在」としてのあり方を模索することこそが、これからの博物館にとって最も本質的な挑戦となるでしょう。
まとめ ― 地域課題に応答する博物館のこれから
本記事では、現代社会において博物館が地域課題にどう向き合うかという問いを軸に、その社会的使命と実践の在り方を理論と事例の両面から検討してきました。高齢化、社会的孤立、気候変動、多文化共生など、多様で複雑な課題が地域に広がるなかで、博物館はもはや「文化を保存・展示する場」だけではなく、「人と人とがつながる場」「地域と共に学び、変化する場」としての役割を期待されています。
理論的には、「ケア」「学び」「参加」といった視点が、博物館の新しい公共的機能を照らし出していることを確認しました。博物館が社会的に排除された人々に寄り添い、対話を促し、共感を育む場として機能する可能性は、既存の制度的枠組みを越えて新たな公共性を構築するものといえます。
実践事例においても、単なるプログラム提供を超えて、住民との協働や共創のプロセスを重視した取り組みが展開されていました。特に、長期的な関係づくり、相互的な信頼の構築、柔軟な体制設計といった要素が、地域との真のつながりを支える鍵であることが示されています。
こうした事例から見えてくるのは、博物館が単に知識を伝える施設ではなく、地域社会の中で人々と共に課題を見つめ、乗り越えるための「関係性の場」であるという姿です。そのような博物館こそが、持続可能な公共性を内包し、変化する社会の中でも信頼を得られる存在として評価されるのではないでしょうか。
もちろん、こうした取り組みには、時間や人員といったリソースの制約や、組織の制度との不整合といった現実的な困難が伴います。それでもなお、小さな実践を積み重ねることによって、制度や文化そのものを変えていく可能性があることもまた事実です。
地域課題に応答するとは、単に課題を「解決する」ことではなく、地域の人々とともに問い続け、向き合い続ける姿勢を持ち続けることです。博物館が地域とともに育ち、変わり続ける存在であること――その過程こそが、これからの博物館に求められるもっとも重要な姿勢であるといえるでしょう。
参考文献
- Callahan Schreiber, L., Paguirigan, E., Simpson, R., Zimmerman, H., Rainville, K., Hackett, C., & Macdonald, M. (2023). Community‐informed design: Blending community engagement and organizational change to shift power in museums. Curator: The Museum Journal, 66(1), 7–24.
- Graham, H., Mason, R., & Noble, G. (2013). Between a museum and a hard place: Policy, participation and the ethics of organisational change. Heritage & Society, 6(2), 113–137.
- Kim, K., Choi, H., & Greenwood, D. (2016). Adult learning for social change in museums: A literature review and implications for practice. International Journal of Lifelong Education, 35(5), 511–527.
- Morse, N., & Munro, E. (2015). Care, community and citizenship: Revisiting the role of the museum. International Journal of Heritage Studies, 21(1), 1–20.
- Munro, E. (2013). Emotion and care: The work of the curator in public space. Museum and Society, 11(1), 1–16.
- Steiner, A., Fischer, M., & Smith, J. (2023). Climate change conversations: Building climate literacy and engaged communities through dialogue. Museum & Society, 21(2), 124–138.