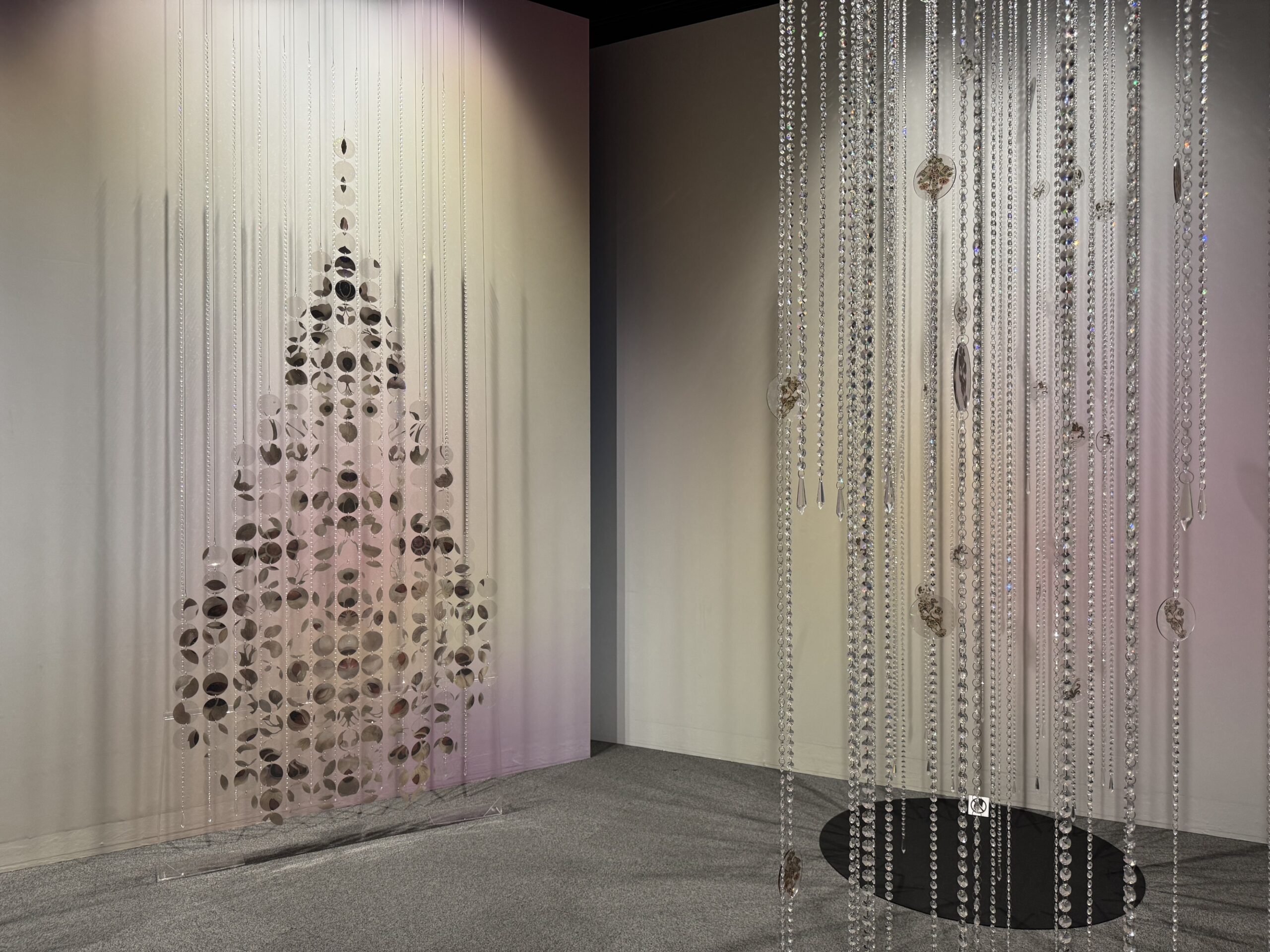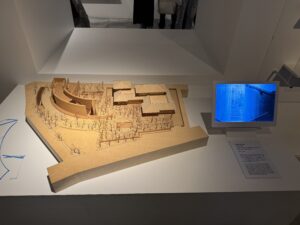はじめに:なぜ今、博物館に「経営戦略」が必要なのか
近年、博物館を取り巻く環境は大きく変化しています。来館者の行動や価値観は多様化し、オンライン展示やデジタル学習プログラムの普及によって、従来の展示中心の運営だけでは十分な社会的存在感を保つことが難しくなっています。さらに、少子高齢化、地方財政の制約、ボランティア人材の減少といった社会構造の変化も、博物館経営に直接的な影響を与えています。その一方で、博物館に対する社会の期待はむしろ拡大しており、文化財の保護、教育・観光への貢献、地域コミュニティの再生など、多面的な役割が求められるようになっています。このような変化のなかで、博物館が持続的に価値を生み出し続けるためには、日々の業務をこなすだけでなく、組織全体としての方向性を定め、社会の変化に応答しながら未来を描くための経営戦略(strategic management)が不可欠となっています。
ここで言う経営戦略とは、営利企業が利益を上げるための競争手段を意味するものではありません。むしろ、博物館という公共的で非営利的な組織が、自らの使命を持続的に果たし、社会の中で信頼と共感を築くための意思決定の枠組みを指します。戦略は、展示や教育、人材、財務、広報などの個別要素を統合し、「何を目的として、どのような変化を導くのか」という問いを中心に組織を導く考え方です。言い換えれば、経営戦略とは、博物館が自らの存在意義を再確認し、社会との関係を再構築するための「未来をデザインする力」であるといえます(Lord & Markert, 2017)。
従来の博物館運営では、「与えられた予算の中で最大限の活動を行う」という考え方が主流でした。しかし、社会的・技術的変化の速度が加速する現在、そうした“受け身の管理”では持続的な発展は難しくなっています。限られた資源をどう活かすかだけでなく、新たな価値をどのように創造し、組織をどのように変えていくかという“戦略的視点”が求められています。展示や教育普及活動も単に実施することが目的ではなく、「どのような来館者体験を生み出し、どのように社会的な学びや対話を促進するか」という意図をもって設計されるべきです。経営戦略とは、そのような意図を明確にし、組織が主体的に変化を生み出すための原動力なのです。
本稿では、こうした視点から博物館経営を捉え直し、戦略的に考えるとは何を意味するのかを考察します。まず、次の節では経営戦略の基本概念を整理し、計画との違いを明らかにします。そのうえで、理論的枠組みや実践事例を通して、戦略的思考が博物館の持続可能性や社会的価値の創出にどのように寄与するのかを探っていきます。経営戦略を理解することは、単に管理技術を学ぶことではなく、文化を通じて社会の未来を構想する力を身につけることにつながるのです。
経営戦略の基本概念 ― 計画ではなく“変化を導く”思考
経営戦略とは何か ― “変化を導く”という考え方
経営戦略という言葉は、しばしば「長期計画」と同義に捉えられます。しかし、博物館のように社会的・文化的使命を担う組織において、戦略とは単なる計画ではなく、変化を導くための思考とプロセスを意味します。経営戦略は、組織の最適な未来を定め、その未来を実現するために必要な変化を導くプロセスとして定義され、すなわち“変化をデザインする”営みです(Lord & Markert, 2017)。
この「変化を導く」という視点は、戦略理解の核です。戦略は外部環境の変化に受け身で対応するものではなく、変化を先取りし、組織を自ら変えていく意志を伴います。例えば、来館者の減少に直面した博物館が、展示内容の見直しのみならず、教育普及の形態や地域連携の設計を刷新することは、「変化を導く戦略」の実践です。
計画(plan)と戦略(strategy)の違い ― 安定のマネジメントと変化のマネジメント
「計画」は既定の目標達成に向けて手順やスケジュールを整理するもので、比較的安定した環境で有効に機能します。これに対して「戦略」は、環境が常に変化する前提に立ち、何を変えるべきか、どの方向に進むべきかを判断するための意思決定の枠組みです。計画が「現在を管理するための道筋」であるのに対し、戦略は「未来をつくるための道筋」と言えます(Lord & Markert, 2017)。
| 観点 | 計画(Plan) | 戦略(Strategy) |
|---|---|---|
| 時間軸 | 短期・固定的 | 長期・柔軟的 |
| 対象 | 業務・タスクの遂行 | 組織全体の方向性 |
| 前提 | 環境が安定している | 環境が変化している |
| 成果 | 実施・達成 | 学び・変革 |
| 主体 | 管理者中心 | 組織全体・参加的 |
博物館の例で言えば、展示計画は「どの作品を、いつ展示するか」を定めますが、展示戦略は「その展示を通して、来館者の学びや社会の理解をどのように変化させたいか」を構想することです。
博物館における戦略の独自性 ― 公共性と社会的価値
博物館の経営戦略は、企業のような市場競争の優位獲得ではなく、社会的価値の創出を目的とします。目的は収益の極大化ではなく、社会における使命(ミッション)を持続的に果たすことにあります。そのため、戦略の形成には倫理性・公共性・透明性が不可欠であり、理事・職員・市民が協働して形成する参加型プロセスとして捉えられます(Lord & Markert, 2017)。
戦略的思考を育てる ― 学びとしての戦略プロセス
経営戦略は一度立てたら終わりではなく、実行→評価→再設計を繰り返す学習のプロセスです。戦略的思考とは、変化を前提に考える習慣であり、成果や課題から次の行動を修正する柔軟性を備えることです。組織全体でこの思考を共有できれば、博物館は単なる計画実行型から、学びながら進化する組織(learning organization)へと成長できます(Lord & Markert, 2017)。
経営戦略とは「未来を描くこと」ではなく「変化を導くこと」であり、計画との差異を理解することが博物館経営の第一歩です。戦略的思考を持つことで、博物館は社会の変化に流される主体ではなく、変化を生み出す主体となることができます。
博物館経営戦略の基本構造 ― 環境・組織・社会をつなぐ考え方
戦略を支える3つの視点 ― 環境・組織・社会
博物館における経営戦略は、単に事業を並べる計画ではなく、環境(外部)・組織(内部)・社会(公共)という三つの視点を往復しながら、変化に応答していくための思考の枠組みです。言い換えれば、戦略とはこの三角構造のバランスを設計し、使命を持続的に実現するための指針です(Lord & Markert, 2017)。
外部の視点 ― 環境を読む力
社会動向、来館者の関心、技術革新などの外部環境を的確に読み解くことが戦略の出発点です。例えば、観光客の減少や学校教育の変化が起きた地域で、博物館が学校連携の体験型プログラムへ軸足を移すのは、単なる事業の追加ではなく、環境の変化をどう読み、どう応えるかという戦略的判断に基づく行動です。研究でも、来館者や地域のニーズを理解する「市場志向」が組織の革新や成果につながることが示されています(Blasco López, Herrero-Prieto, & Rodríguez-Prado, 2018)。
内部の視点 ― 組織を動かす力
優れた戦略も実行できる組織がなければ機能しません。博物館の資源には、展示品や建築といった有形資産だけでなく、学芸員の専門性、職員のネットワーク、ボランティアの活動、地域との信頼関係などの無形資産が含まれます。経営戦略は、これらの資源をどう活かし、どう再構成していくかの選択です。人員が限られる中で外部の教育機関やNPOと協働し、新しい展示やプログラムを設計するのは、まさに資源をてこにした戦略的発想の実践です。
社会の視点 ― 公共的価値をつくる力
博物館の経営戦略の最終目的は、収益や来館者数の拡大ではなく、社会における文化的・教育的役割を果たすことにあります。多文化共生を促す展示、環境教育に取り組む特別展、高齢者や障害のある人の参加を促すプロジェクトなどは、いずれも社会的価値(social impact)を生み出す戦略的取組です。戦略とは「社会にどのような変化をもたらしたいのか」を問う営みであり、博物館が使命を再定義し、社会との関係を築き直すプロセスでもあります(Lord & Markert, 2017)。
以上のように、環境を読む/組織を動かす/社会を変えるの三視点を行き来しながら構築される戦略は、どれか一つが欠けても持続的に機能しません。外部の変化を捉え、内部資源を活かし、公共的価値を創出すること――これが現代の博物館に求められる戦略的思考の基本構造です(Blasco López et al., 2018; Lord & Markert, 2017)。
経営戦略の立案と実行 ― “考える戦略”から“動く戦略”へ
戦略立案の出発点 ― 現状を知ることから始める
経営戦略は「考えること」で終わらず、「現場で動かすこと」へとつながってはじめて意味を持ちます。出発点は、自館の現状を正確に把握することです。内部と外部の両面から状況を整理するために、SWOT分析(Strengths/Weaknesses/Opportunities/Threats)が有効です。ただし重要なのは、表を埋めること自体ではなく、職員間の対話を通じて「何を変えたいのか」を共有することです。戦略立案は、紙の上の作業ではなく、組織の学びを促すプロセスです(Lord & Markert, 2017)。
目標設定と優先順位 ― すべてを同時にはできない
限られた資源の中で成果を出すには、やるべきことの優先順位を明確にする必要があります。ここではSMARTの原則が役立ちます。
- S(Specific/具体的):何を、誰に、どこで、どのように。
- M(Measurable/測定可能):達成度を測る指標がある。
- A(Achievable/達成可能):現実的に実行できる。
- R(Relevant/妥当):館の使命・戦略と関連している。
- T(Time-bound/期限):いつまでに達成するかを定める。
例:「来年度中に、地域の小学校と協働した体験型教育プログラムを3回実施する」。このように目標を具体化することで、戦略は抽象的な理想ではなく、現場の行動計画として機能します。
実行プロセス ― 組織を巻き込む戦略
戦略を動かすのは人です。館長や理事だけでなく、学芸、教育、広報、運営、ボランティアなど、多様な担い手が参加して合意形成することで、戦略は「共有された約束」になります。Lord & Markert(2017)が強調する参加型の戦略策定(participatory process)は、現実性と実行力を高めます。
- 部門横断のワークショップで展示方針を議論・可視化
- 役割分担(RACIなど)と実行スケジュールの明確化
- ステークホルダー(学校・NPO・自治体・企業)との協働設計
これにより、戦略は計画書から「動く仕組み」へと変わります。
評価と改善 ― “つくる”だけで終わらせない
戦略は立てて終わりではありません。実行 → 評価 → 再設計の循環を回し続けることで、戦略は進化します。評価は数値だけでなく、組織の学びや社会的成果にも目を向けます。
- 定量:来館者数、参加率、寄附・会員数、プログラム満足度
- 定性:地域連携の深まり、学習効果の質、包括性・アクセシビリティの改善
気づいた課題を次の目標に反映させることで、博物館は変化に対応するだけでなく、自ら変化を創り出す主体へと成長します(Lord & Markert, 2017)。
以上のように、現状把握 → 目標設定 → 実行と巻き込み → 評価と改善のプロセスを意識的に設計することが、「考える戦略」を「動く戦略」へと転換する鍵です。
戦略を動かす組織の力 ― 実行・定着・成果をつなぐプロセス
経営戦略は、単に計画を立てることではなく、それをどのように組織の中で実行し、定着させ、成果へと結びつけていくかというプロセスの設計です。戦略は完成された文書ではなく、組織の中で常に書き換えられ、学びながら成熟していく“生きた仕組み”であるとされています(Lord & Markert, 2017)。博物館のような文化組織では、この循環が「実行」→「定着」→「成果」という三段階で進行します(Lord & Markert, 2017)。
実行の段階 ― 戦略を“動かす”仕組み
戦略を具体的な行動に移すには、館長や理事が方向性を示すだけでなく、学芸・教育・広報・運営などが目的を共有し、同じ方向へ動く体制づくりが不可欠です。文化組織では、戦略を参加型の意思決定(participatory process)として設計することが効果的だとされています(Lord & Markert, 2017)。展示企画の初期段階から複数部門が協働し、意思決定に関わる仕組みを持つことで、戦略は現場に根ざした実践へと変わります。こうした「共有 → 共感 → 行動」の連鎖が、実行力を生む基盤となります(Lord & Markert, 2017)。
- 全館キックオフで戦略目的・指標・役割を明確化
- 部門横断ミーティングで課題とリソースを可視化
- 短期スプリント(試行)で素早く仮説検証
定着の段階 ― 戦略を“文化”として根づかせる
実行が一過性で終わらないためには、戦略が日常の仕事に組み込まれる必要があります。鍵となるのは組織文化の働きで、何を重視し、どんな行動を「当たり前」とみなすかという無言のルールが定着を左右します。対話を奨励し、失敗を共有できる環境が整えば、職員は安心して新しい行動に挑戦できます。定期的な振り返り会議や成功・失敗事例の共有は、戦略を文化として定着させる実践的な方法とされています(Lord & Markert, 2017)。この段階で戦略は、単なる「行動」から「習慣」へと変化します。
- ポスト・プロジェクト・レビュー(定例の振り返り)
- ナレッジベース(学び・事例・指標)の共同編集
- 表彰・可視化による望ましい行動の強化
成果の段階 ― 戦略が“社会価値”を生み出す
博物館の経営戦略の目的は、来館者数や収益の拡大だけでなく、社会における文化的・教育的な変化を生み出すことにあります(Lord & Markert, 2017)。地域の学校との協働が進み学習拠点として機能する、地域住民や支援者との信頼が深まる、といった成果は、数値化が難しくとも重要です。これらは「信頼」「学び」「関係性」といった質的側面として現れ、次の戦略に反映されることで、循環はさらに強化されます(Lord & Markert, 2017)。
- 定量:参加率・継続率・会員/寄附・満足度
- 定性:学校・地域との協働の深まり、包摂性・アクセシビリティの向上、対話の質
- 再設計:学びを基に目標・施策・体制をアップデート
以上のように、経営戦略は静的な計画ではなく、実行→定着→成果→再設計の循環として組織の中で生き続けます。仕組みと文化が調和し、人々が共通の目的に向かって学び続けるとき、戦略は“現場で生きる知”として根づき、博物館は変化に対応するだけでなく、自ら変化を生み出す組織へと進化します(Lord & Markert, 2017)。
戦略の成果と社会的インパクト ― “数字”から“価値”を測る
経営戦略の目的は、計画を立てて実行するだけでなく、その成果をどのように評価し、次の学びへつなげるかにあります。とりわけ博物館では、成果を「どれだけの人が来たか」だけでなく、「社会にどのような変化をもたらしたか」という視点から捉えることが重要です。戦略は、実行と評価を繰り返すことで組織の成熟を促し、公共的価値の創出へと結びつきます(Lord & Markert, 2017)。
評価の二つの軸 ― 量的成果と質的成果
戦略の成果を理解するには、量的成果(quantitative outcomes)と質的成果(qualitative impacts)という二つの軸を意識します。前者は数値で把握できる指標、後者は社会・文化への「意味のある変化」を示します。KPIは活動の可視化に有効ですが、「指標のための活動」に陥らないよう、戦略目標との整合性を常に検証する必要があります(Lord & Markert, 2017)。
量的評価 ― 指標で見る経営成果(KPI)
代表的なKPIの例:
- 来館者数・再来館率
- プログラム参加率・回数・満足度スコア
- 収益・寄附額・会員数
- ウェブ/アプリ利用、SNSフォロワー・エンゲージメント
重要なのは、KPIを目的ではなく道具として用いることです。例えば、来館者数だけでなく「再来館率」や「教育プログラム参加率」のように、関係の深まりを測る指標を組み合わせると、戦略の方向性をより適切に確認できます(Lord & Markert, 2017)。
質的評価 ― 社会的価値と文化的影響
質的評価では、活動が社会にどのような変化を生み出したかを検討します。
- 地域教育との連携強化:学校との協働、学習拠点化
- 包摂・アクセシビリティ:高齢者・障害のある人・多文化市民の参加拡大
- 市民の学び・態度変容:地域文化理解の深化、環境・社会課題への関心促進
- コミュニティ関係:支援者・住民との信頼関係の構築
これらは数値化が難しい一方で、博物館が果たすべき公共的価値を示します。把握にはアンケート、インタビュー、観察、エスノグラフィなどの定性的手法を併用します。研究でも、文化組織の持続性はイノベーションと社会的価値の創出の両立に支えられると指摘されています(Blasco López, Herrero-Prieto, & Rodríguez-Prado, 2018)。
評価を“学び”に変える ― 循環する改善プロセス
評価の目的は、成績表づくりではなく学習にあります(Lord & Markert, 2017)。結果をチームで共有し、次の戦略に反映させる仕組みを設計します。
- 年度末レビュー:「うまくいった点」「課題」「次の仮説」を全館で共有
- 改善アクション:KPIと質的所見を踏まえ、目標・施策・体制を更新
- 公開性:評価結果の外部発信により、説明責任と信頼を強化
この循環により、戦略は静的な管理ツールではなく、組織が成長するためのプロセスへと転換します(Lord & Markert, 2017)。
“数字”と“価値”を往復する
量的指標が戦略の方向性を確認する羅針盤だとすれば、質的インパクトは社会との関わりを読み解く地図です。両者を往復しながら成果を分析することが、持続的な戦略を築く第一歩となります(Lord & Markert, 2017; Blasco López et al., 2018)。
持続可能な経営戦略 ― 変化する社会と未来への適応
経営戦略とは、ある時点での課題を解決するための計画ではなく、変化の中で使命を持続的に実現するための考え方です。特に博物館のような文化組織では、経済的な成果だけでなく、社会や人々の学びに寄与し続けることが求められます。つまり戦略の本質は「維持」ではなく「進化」にあります。文化機関の戦略は“固定的な計画書”ではなく、“学びながら成長するドキュメント”として扱うべきだとされており(Lord & Markert, 2017)、社会の変化に応じて内容を柔軟に書き換えられる状態が理想です。
戦略における持続可能性 ― 理念を変えずに手法を変える
戦略における持続可能性とは、理念を保ちながら手法を変化させる柔軟性を意味します。社会のニーズや技術の進展に合わせて展示方法や来館者との関わり方を更新していくことは、戦略の中核に位置づけられます。持続可能性とは、過去を守ることではなく、使命を未来へつなぐための更新の力です。
- 地域博物館がデジタル技術を活用してオンライン展示を実施する
- 常設展示を再構成し、現代的課題(環境・多文化共生)を取り入れる
- 教育プログラムを地域ニーズに合わせて刷新する
このように、形式を変えても使命を貫く柔軟性が、長期的に信頼される経営を支えます(Lord & Markert, 2017)。
変化する社会への適応 ― 外部環境を再定義の機会とする
戦略を持続させるためには、変化する社会への適応力が不可欠です。少子高齢化、多文化共生、デジタル化、環境問題など、現代社会の変化は博物館運営に直結します。重要なのは、こうした変化を脅威ではなく再定義の機会として活かすことです。
- 外国人来館者の増加を「異文化理解を促す教育的機会」と捉える
- 地域高齢化を「生涯学習プログラムの拡充」の契機とする
- 環境問題を「展示テーマと学びの連携」に取り込む
柔軟に社会と対話し、変化を成長資源に変えることが、持続可能な経営の基盤となります(Blasco López, Herrero-Prieto, & Rodríguez-Prado, 2018)。
イノベーションと学びの文化 ― 続くために変わる
持続可能な戦略のもう一つの柱は、組織内にイノベーションと学びの文化を根づかせることです。小さな試行(pilot project)や内部提案を繰り返すことで、戦略は常に新たな形へと進化します。
- 展示手法の改善や新規教育プログラムの試行
- 部門横断チームによる創発的プロジェクトの立案
- 失敗を共有し次に活かす「反省と学習のサイクル」
イノベーションは技術導入だけでなく、教育・展示・協働の新しい形を創出する営みでもあります。挑戦を許容し、学びを共有する環境が整うことで、戦略は一度きりの計画ではなく継続的に更新される学習のシステムとなります(Lord & Markert, 2017)。
更新の仕組みを設計する ― 持続性の制度化
持続的な戦略には、更新の仕組みを制度として組み込むことが求められます。以下のようなサイクルを明確化すると、戦略が組織の日常に根づきやすくなります。
- 3〜5年単位の中期計画を策定し、毎年のレビューで進捗と課題を確認
- 評価・改善プロセスに職員全員が参加し、戦略を「共有された実践」にする
- 外部評価・専門家助言を導入し、社会的視点から戦略を再点検する
このように、継続と刷新を両立する制度設計が、戦略の持続性を高める鍵となります(Lord & Markert, 2017)。
まとめ ― 変化を設計する戦略へ
持続可能な経営戦略とは、変化を恐れず、受け入れ、そして自ら設計していく力です。社会が変わっても、博物館の使命は変わりませんが、その実現方法は常に更新されるべきです。経営戦略を「完成品」ではなく「進化する思考」として捉えるとき、博物館は未来に向かって成長し続ける組織となります(Lord & Markert, 2017; Blasco López et al., 2018)。
経営戦略の本質 ― 学び続ける博物館へ
博物館経営の核心 ― 戦略は「文化を未来へつなぐ知恵」
経営戦略とは、単なる経営の技術や手法ではなく、文化を未来へとつなぐための知的営みです。博物館が果たすべき使命は、収蔵品の保護・展示にとどまらず、社会との関係を再構築しながら文化的・教育的価値を持続的に提供することにあります。すなわち戦略は「成果を上げるための計画」ではなく、「変化の中で文化を生かし続ける知恵」です。文化組織の戦略は生きた学習プロセスとして捉えられ、対話と更新によって成長する体系であるとされています(Lord & Markert, 2017)。
学習する組織としての博物館
博物館経営の中心にあるのは学びと信頼であり、この二つが組織の持続力を支えます。信頼は職員間の協働を生み、学びは新しいアイデアをもたらします。日々の業務や展示活動の中で、職員が観察・改善・提案を行うことで、戦略は現場に根づきます。こうした共有学習を通じて組織は柔軟性を高め、挑戦を受け入れる文化を築き、経営は管理行為から創造的な知的活動へと変化します(Lord & Markert, 2017)。
- 現場での観察→改善→提案の循環を常態化
- 成功と失敗の知見を全館で共有
- 学芸・教育・運営・広報の越境協働を促進
経営戦略の未来 ― 社会とともに進化する
教育格差、地域の分断、環境問題、デジタル化など、社会の変化は博物館経営に直接影響します。戦略の未来像は、社会とともに進化する柔軟なビジョンの中にあります。博物館が「知識の蓄積装置」ではなく社会の学習装置として機能するとき、経営戦略は内部方針を超えて社会的対話の枠組みになります。文化組織の持続性は、社会的価値の創出とイノベーションの継続によって支えられるとされています(Blasco López, Herrero-Prieto, & Rodríguez-Prado, 2018)。
- 量的成果(KPI)と質的成果(社会的インパクト)を往復しながら評価
- 地域・学校・NPO・企業との共創でテーマを共進化
- 小さな試行(パイロット)で学びを蓄積し戦略を更新
まとめ ― 戦略とは“未来をデザインする文化的実践”
最終的に、博物館の経営戦略とは未来をデザインする文化的実践です。戦略は過去を守るだけでなく、変化を設計し、学びを促し、社会との関係を再構築するための道筋です。経営とは、文化の継承と革新のあいだに橋をかける行為であり、学び続けることが戦略の原動力となります。社会とともに変化しながらも文化の本質を見失わない博物館こそが、これからの時代に持続可能な経営を実現する存在です(Lord & Markert, 2017; Blasco López et al., 2018)。
参考文献
- Blasco López, M. F., Herrero-Prieto, L. C., & Rodríguez-Prado, B. (2018). Museums, innovation and sustainability: A model of dynamic efficiency. Museum Management and Curatorship, 33(5), 442–459.
- Lord, G. D., & Markert, K. (2017). The manual of strategic planning for cultural organizations: A guide for museums, performing arts, science centers, public gardens, heritage sites, libraries, archives. Rowman & Littlefield.