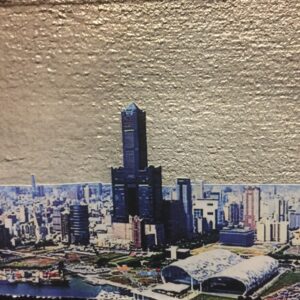はじめに:見えない原則としての価値観
近年、「価値観(バリュー)」という言葉が、企業経営だけでなく非営利組織や公共機関においても重視されるようになっています。特に文化施設や博物館においても、ミッションやヴィジョンと並んで「どのような価値を大切にしているのか」「どのような原則に基づいて行動するのか」といった姿勢が問われる場面が増えています。ただし、企業のように「私たちのバリュー」といった言葉を積極的に掲げる博物館はまだ多くはなく、むしろ明文化されていない形で“価値観”が日々の運営判断や職員の行動に反映されているのが実態といえるでしょう。
この「価値観(バリュー)」とは、組織が何を大切にし、どのような判断や行動を是とするのかという根本的な姿勢を示すものです。それは理念やミッションの背後にある“見えない原則”であり、日々の意思決定や対外的なふるまいの中に、しばしば無意識のうちに現れるものでもあります。たとえば、来館者からのクレームにどのように対応するのか、社会的にセンシティブな展示内容にどう向き合うのか、あるいは地域との連携にどこまで力を注ぐのかといった問いに対して、博物館がどのような選択をするかは、その組織が内面化している「価値観」によって左右されることが多くあります。
特に今日、博物館を取り巻く環境は大きく変化しています。来館者の多様化、社会的説明責任の高まり、包摂性や多様性への対応、持続可能性の追求など、さまざまな要請に応えることが求められるなかで、博物館が「何を大切にするのか」を組織として明示し、職員間で共有する必要性が増しています。ミッションやヴィジョンだけでは捉えきれない、日常的な判断や対話の基盤となる「価値観」のあり方が、これまで以上に注目されているのです。
本記事では、まず「価値観(バリュー)」という概念そのものについて整理し、ミッションやヴィジョンとどのように異なり、どのように関係するのかを考察します。そのうえで、博物館における価値観が、具体的にどのような場面で表れ、またどのように浸透していくのかを、国内外の先進事例とともに検討していきます。最後に、価値観の共有と実装が、博物館の持続可能な経営や信頼性の確保にどのように寄与するのかを展望し、公共文化施設としての博物館が今後進むべき方向性について考えていきます。
価値観とは何か ― 博物館組織における概念と理論の基礎
私たちは日々、何気ない判断や行動の背後に「何を大切にするか」という基準を持っています。それは個人であれば家庭や教育、人生観に基づくものかもしれませんし、組織であれば理念や目的に裏打ちされた集団的な価値判断である場合もあります。この「何を大切にするか」という基本的な信念や判断の軸を、一般に「価値観(バリュー)」と呼びます。
本節では、博物館組織における価値観とは何かを明らかにするために、まず言葉の意味と背景から確認し、次に経営学や組織論における理論的な位置づけを整理します。そして、非営利・公共性を有する博物館という組織特性の中で、価値観がどのような役割を果たしているのかを考えていきます。
組織における「価値観」とは何を意味するのか
「バリュー(value)」という言葉は、哲学や倫理学では「善悪の基準」、経済学では「交換価値や効用」、社会学では「文化や行動の規範」といった多様な文脈で使われてきました。組織論においては、特定の集団が共有する「望ましい行動のあり方」や「判断の優先順位」を示す用語として理解されています。
とくに非営利組織や文化機関における「価値観」は、売上や成果といった数値的評価だけでは測れない、“この組織がどんな信念に基づいて動いているのか”を内外に示すものです。それは単なる標語ではなく、個々の職員のふるまいや意思決定に深く関わるものでもあります。
組織文化の中核としてのバリュー
経営学や組織論の分野では、価値観はしばしば「組織文化」の中核的要素として捉えられてきました。組織文化は「アーティファクト(表層に見えるもの)」「信念と価値観」「基本的前提」という三層構造で説明され、このうち“価値観”は行動の背後にある意識的な判断基準として、組織内部に共有されているとされています(Scott, 2010)。
たとえば、「来館者中心の運営を重視する」「学術的中立性を守る」「地域と共にある博物館を目指す」といった価値観は、意思決定や職員教育、サービス設計などに深く影響を与えます。このような価値観が明示され、共有されていることは、組織としての一貫性と信頼性を支える基盤となります(Hooper-Greenhill, 2000)。
非営利組織にとっての価値観の役割
非営利組織は、営利企業のように「利益の最大化」を目的としていません。その代わりに、社会的使命の達成や公益の実現といった目的が優先されます。したがって、組織が“どのような価値を実現しようとしているのか”を明確にすることが重要になります。
博物館は利益ではなく価値によって駆動されるとされており(Fleming, 2015)、ここでいう「価値」とは、教育、文化、記憶、社会包摂といった、数値化しづらいが社会的に意味ある成果を指します。こうした価値を実現するために、博物館は何を重視し、どこに資源を投下し、誰と連携するのか。これらの選択にこそ、組織の価値観が反映されているのです。
「公共的価値」としてのバリュー
近年注目されているのが、「パブリック・バリュー(公共的価値)」の考え方です。これは、公共機関は単にサービスを提供するのではなく、「市民にとって意味ある価値」を創出すべきであるとする理論に基づいています。この視点では、公共的な価値観は行政の方針だけでなく、市民との対話や協働によって形づくられていくべきものとされます(Scott, 2010)。
博物館における価値観もまた、社会的要請や対話を通じて変化・更新されるべきものであり、一度定めれば終わりという性質のものではありません。価値観はあくまで、組織が変化する社会との関係の中で問い直され続ける「生きた指針」であるといえるでしょう。
価値観は組織を導く“見えない原則”である
このように、「価値観(バリュー)」は単なる理念や装飾的な言葉ではなく、博物館の運営や判断、組織文化に深く根ざした要素です。明文化されているかどうかにかかわらず、価値観は組織のふるまいに表れ、信頼の構築や内部の一体感の形成に寄与します。組織にとっての価値観は、外部に示す方針であると同時に、内部で共有される行動の軸でもあり、あらゆる局面において判断を支える“見えない原則”として機能しているのです。
次節では、この価値観がミッションやヴィジョンとどのように関係し、戦略的にどのように活用されているのかを、より具体的に見ていきます。
ミッション・ヴィジョン・バリューの三位一体 ― バリューが生きるための理念の整合性
組織における価値観(バリュー)は、それ自体が単独で完結するものではありません。バリューが実効性を持ち、日々の行動を導く“生きた原則”として機能するためには、その背後にあるミッション(存在意義)とヴィジョン(将来像)との間に明確な整合性が必要です。この三つの理念が互いに補完し合い、一貫性をもって共有されているとき、初めてバリューは「掲げられた言葉」から「実際に使える判断軸」へと転化します。
三者の関係性を理解する
まず、ミッション(mission)は、組織が「なぜ存在するのか」という問いに対する答えです。博物館であれば、「文化財の保存と公開を通じて、市民の教育と学びに貢献する」といった表現が該当します。これは一度定めたらそう簡単には変わらない、長期的かつ普遍的な存在意義を示すものです。ミッションは、すべての活動の土台であり、存在の正当性を社会に対して説明する根拠でもあります。
次に、ヴィジョン(vision)は、組織が中長期的に目指す理想像や将来の姿を描いたものです。ミッションが現在地における「なぜ」、すなわち出発点だとすれば、ヴィジョンは「どこへ向かうのか」という目的地にあたります。たとえば、「多様な市民がともに学び合う、包摂的な地域拠点となる」や「グローバルな文化交流を促進するリーディングミュージアムとなる」といった表現がヴィジョンとして使われます。ヴィジョンは職員にとってモチベーションとなり、社会にとっては連携や支援のきっかけにもなります。
そして、価値観(バリュー)は、ミッションとヴィジョンの“あいだ”に位置し、組織が「どのように行動するか」「何を優先するか」を規定する行動原理です。「来館者に対して常に誠実である」「多様性を尊重する」「対話を重んじる」「専門性と市民性のバランスを大切にする」など、具体的な判断やふるまいの指針がバリューとして明示されます。つまり、バリューは理念を実践に移す際の“翻訳装置”であり、戦略を文化として根づかせる鍵でもあるのです。
三者が連動してはじめて意味を持つ
問題なのは、これら三者がしばしば独立して語られ、互いに接続されていない場合があるということです。たとえば、ミッションに「地域とともに歩む」と書かれていても、ヴィジョンで「国際的研究機関としての地位確立」を掲げ、バリューに「参加と協働」を含めている場合、それぞれの方向性が噛み合っていないと、現場では何を重視すべきなのか迷いが生じます。こうした齟齬は、職員の判断にブレを生み、組織としての一貫性を損ないます。
逆に、ミッションが「地域文化の継承と対話を通じて、共生社会に寄与する」であり、ヴィジョンが「文化を共有し学び合う公共圏の創出」、バリューが「尊重」「共創」「持続可能性」で構成されている場合は、すべての理念が相互に支え合い、強い整合性と説得力を持ちます。このような整合性があると、現場での判断がしやすくなるだけでなく、ステークホルダーにも組織の姿勢が明確に伝わりやすくなります。
信頼と行動につながる理念設計
理念が整っている組織は、対外的な信頼を得やすいとされています。ミッションが明快で、ヴィジョンに共感でき、バリューが行動として感じられる博物館は、行政や助成団体、地域社会、来館者といった多様な関係者にとって、「信頼できる組織」「支援したくなる組織」と映るからです。これは単に広報戦略として有効であるだけでなく、ガバナンスや説明責任、持続可能性といった観点からも重要な意味を持ちます(Semmel & Bittner, 2009)。
また、整合された理念は、内部における職員の意思決定や行動規範にも良い影響を与えます。特にバリューが明確になっていると、現場で判断に迷ったときに立ち戻る拠り所となります。展示の構成、教育プログラムの方針、トラブルへの対応など、日々の細かな場面で「この博物館は、どのような価値観に基づいて行動すべきなのか」が共有されていれば、職員の間に一体感や信頼感が生まれます。
このように、ミッション・ヴィジョン・バリューという三つの理念は、それぞれの機能を担いながら、互いに支え合い、価値観を“使えるもの”にする枠組みとして働いています。とりわけバリューは、組織の日常に根を下ろすための“実践的な接点”であり、理念を文化として内在化させるための要であると言えるでしょう。
理念を“掲げる”から“活かす”へ ― バリューを実務に根づかせる視点
価値観(バリュー)を明示する博物館は、近年少しずつ増えてきています。ミッションやヴィジョンと並んで、行動原理を可視化する試みとして、ホームページや報告書の中に「私たちの価値観」という記述が見られるようになってきました。しかし、こうしたバリューが組織の中で本当に“活きている”かどうかについては、慎重に検討する必要があります。掲げられた言葉が、日々の業務や意思決定の中で使われていないとすれば、それは単なる「理念としての飾り」にすぎません。
理念疲労と“かざりのバリュー”
組織において理念が定期的に更新されず、現場の参加もなく、一方的にトップダウンで共有されるだけの場合、職員の間には「理念疲労」とでも言うべき感覚が生まれることがあります。これは、ミッションやヴィジョン、バリューといった理念が繰り返し語られるものの、実際の業務とは関係がなく、職員の判断や行動に結びついていないと感じられる状態です。
特にバリューについては、「ポスターには書いてあるけれど、現場では使われていない」といった指摘がしばしば見られます。こうした“かざりのバリュー”は、むしろ逆効果となり、職員の中に理念への懐疑や不信を生み出すことさえあります(Scott, 2010)。このような事態を避けるためには、価値観を単なる標語としてではなく、職員一人ひとりが「自分の言葉で語れる」「行動の理由として使える」レベルにまで浸透させることが必要です。
判断と行動を支える“使える価値観”
実際の博物館運営では、方針が明文化されていない場面での判断が求められることが少なくありません。たとえば、ある展示内容に対して抗議や意見が寄せられたとき、どのように対応すべきか。あるいは、特定の来館者からのクレームにどう向き合うべきか。こうした状況で職員が立ち戻るべき判断の軸となるのが、まさに価値観です。
このとき機能するバリューとは、「来館者の声を尊重する」「社会的包摂を重視する」「説明責任を果たす」といった、具体性と柔軟性を備えた原則です。これらはマニュアルでは規定しきれない状況のなかで、職員の行動を支え、組織としての一貫性を保つために不可欠な役割を果たします。特に現場での迷いや葛藤の多い実務においては、抽象的な理想よりも、「今この場で、何を大切にするのか」という問いに答えられる価値観こそが、もっとも必要とされています。
バリューを組織文化として育てるには
価値観を活かす組織になるためには、掲げるだけでなく、それを“育てる”視点が欠かせません。育つとはすなわち、時間をかけて職員間で共有され、実際の行動や言葉の中に自然と浸透していくプロセスを意味します。そのためには、まず職員自身が価値観の中身を理解し、自分の業務とどのように関係するのかを考える機会が必要です。研修やワークショップを通じて、理念を言葉のまま受け取るのではなく、自分たちの仕事に引き寄せて再解釈することが求められます(Hooper-Greenhill, 2000)。
また、価値観を制度的に支える仕組みも重要です。たとえば、評価制度において単なる成果だけでなく、「組織の価値観に沿った行動がとれているか」を評価項目に組み込むことで、職員の日常的な判断にも理念が反映されやすくなります。さらに、館内での会話や会議の場においても、「この選択は私たちのバリューに合っているか」といった問いかけがなされるようになると、価値観は静的なスローガンから、動的な“対話の土台”へと変わっていきます。
価値観を「共有された文化」として根づかせるためには、トップダウンとボトムアップの両方からのアプローチが必要です。経営層が価値観の重要性を繰り返し発信するとともに、現場の実感や経験に根ざした声が理念の見直しに反映されるような循環が求められます。こうした双方向的なプロセスによってこそ、価値観は“掲げられた理念”から“生きた文化”へと変わっていくのです(Semmel & Bittner, 2009)。
実例:価値観を明示した博物館の取り組み ― 行動に表れるバリューのかたち
これまでの節では、価値観(バリュー)が単なる理念上の言葉ではなく、組織の判断や文化に深く関わる「行動原則」であることを確認してきました。本節では、実際に価値観を明示し、それを展示・教育・運営の中で体現している海外の博物館の事例を紹介します。これらの博物館は、価値観を掲げるだけにとどまらず、それを現場で「生きた原則」として活用する努力を積み重ねており、バリューの実装に向けた先行例として重要な示唆を与えてくれます。
価値観を“示す”という選択
博物館が自らの価値観を明示的に発信することには、組織の透明性や信頼性を高める意義があります。ミッションやヴィジョンが「何のために」「どこを目指すか」を示すものであるのに対し、バリューは「どのように行動するか」を示す基準です。つまり、バリューは来館者対応や展示制作、教育プログラム、職員のふるまいなど、日常の実務ともっとも密接に関わる指針であり、組織の人格を形づくるものだと言えます。
とくに近年では、社会的多様性の尊重、公平性への関心、対話型学習の重視といったテーマが重視されるなかで、博物館が自らの価値観を「見える化」することが、来館者との関係性構築や社会的説明責任を果たす上でも求められるようになっています。こうした背景のもと、次に紹介する二つの博物館は、価値観の明示と実装の両立において先進的な取り組みを行っています(Scott, 2010;Fleming, 2015)。
NMAAHC(スミソニアン国立アフリカ系アメリカ人歴史文化博物館)
アメリカ・ワシントンD.C.にあるスミソニアン国立アフリカ系アメリカ人歴史文化博物館(NMAAHC)は、設立当初から「人種正義」「真実の語り」「尊厳」「包摂性」といった価値観を中核に据えた博物館運営を行っています。同館の公式サイトでは、”Our Values” として “inclusivity(包括性)”“integrity(誠実さ)”“respect(尊重)”などの信念が明示されており、これらは単なるスローガンではなく、展示構成、来館者対応、教育プログラムの設計にまで一貫して反映されています。
たとえば、奴隷制度や人種差別の歴史に関する展示では、過去の苦難を美化することなく、あえて厳しい現実を伝える構成がとられています。その一方で、アフリカ系アメリカ人の文化的達成や希望を描く展示も併置されており、尊厳や希望という価値観が空間全体に表れています。また、来館者の声を反映したプログラム開発や、教育現場との連携など、組織としての意思決定にも価値観が反映されている点が特徴です(Fleming, 2015)。
このように、NMAAHCでは、価値観が単なる理念にとどまらず、来館体験や組織運営の中に“にじみ出る”かたちで一貫して表現されており、社会的課題に応答する文化機関としてのあり方を体現しています。
テ・パパ・トンガレワ(ニュージーランド国立博物館)
ニュージーランドの首都ウェリントンにある国立博物館「テ・パパ・トンガレワ(Te Papa Tongarewa)」は、「Mana Taonga(宝の力/マオリの知識体系の尊重)」「共生(co-existence)」「多文化性」「地域との協働」などの価値観を明確に掲げ、それを組織文化として定着させていることで知られています。これらの価値観は、公式ウェブサイトや運営方針に明示されており、展示・教育・研究の各領域で具現化されています。
たとえば、展示空間の設計では、マオリの伝統的な知と科学的知を対等に扱うことを意識し、マオリの言語や文化的表現が自然に空間に取り入れられています。また、コミュニティと協働して企画展を構成するプロセスや、地域住民が専門家として参加する制度なども、組織の価値観を反映した運営の一例です(Scott, 2010;Hooper-Greenhill, 2000)。
テ・パパの特徴は、価値観がトップダウンで定められただけでなく、現場の実践やコミュニティとの対話の中で育てられ、更新され続けている点にあります。こうした「社会との共生を体現する博物館」の姿勢は、博物館が価値観を通じて社会とどのように関わるかを考える上で貴重な実践例となっています。
事例から見える共通点と学び
これらの事例から明らかになるのは、バリューは単に掲げるものではなく、組織のあらゆる活動に一貫して「にじみ出る」ように設計され、実装されるべきものであるという点です。NMAAHCとテ・パパに共通して見られるのは、明示された価値観が展示内容や空間構成、教育プログラム、来館者対応、そして組織内部の意思決定に至るまで、一貫して浸透しているという特徴です。
また、これらの博物館では、価値観が一方的に上から与えられるのではなく、対話と協働を通じて育てられています。つまり、バリューは静的なスローガンではなく、動的に更新され続ける「社会との関係性を映す鏡」として機能しているのです。
日本の博物館にとっても、こうした事例は多くの示唆を与えてくれます。価値観を言葉として明文化するだけでなく、それが行動や判断にまで一貫して表れる仕組みづくりが必要です。そしてそれは、経営者だけでなく、職員や地域社会とともに考え、育てていくものであるべきでしょう。
バリューの共有と更新 ― “掲げる”から“生きる”へ
これまでの節で見てきたように、価値観(バリュー)は博物館のミッションやヴィジョンと並ぶ中核的な理念でありながら、それ自体が組織の判断や行動の拠り所として日々活用されなければ、その意味を十分に果たすことはできません。ここでは、バリューを「掲げる」だけで終わらせず、組織文化として「生きる」ものにするための条件と、その継続的な更新のあり方について考察します。
理念は“配布”ではなく“浸透”されるもの
価値観を明文化し、ウェブサイトや報告書、職員マニュアルなどに掲載することは、バリュー共有の第一歩にすぎません。理念が単に「配布される」だけでは、組織の実態にはなり得ません。実際の業務や判断の中で繰り返し参照され、語られ、応用されることによってはじめて、価値観は組織の文化として根づいていきます。
たとえば、来館者対応や展示方針に迷いが生じたときに、「私たちの価値観に照らしてどうすべきか?」という問いを自然に投げかけられる状態が、本当の意味での「共有されたバリュー」だと言えるでしょう。価値観は一度読み上げられたからといって自動的に理解されるものではなく、対話を通じて意味を確認し、状況に応じて再解釈されながら浸透していくものです(Scott, 2010;Semmel & Bittner, 2009)。
価値観を“使う”ための仕組みを持つ
理念を実務に活かすためには、日々の業務の中に価値観を組み込む「仕組み」が必要です。たとえば、職員研修において価値観を扱う時間を設けたり、評価制度に「価値観に即した行動がとれているか」を加えたりすることで、バリューは抽象的な理念から実践的な指針へと変わります。
また、会議や意思決定の場で、「この選択は私たちのバリューと合っているか」という問いが共有されていることも重要です。こうした問いかけが日常的に行われることで、価値観は特別なときだけ参照されるものではなく、常に判断の背景として機能するようになります。
このように、価値観を「使える」ものとして根づかせるには、単なる理念教育ではなく、日常の言語や行動と接続された運用のデザインが不可欠です。職員一人ひとりが価値観を「自分の言葉で語れる」状態を目指すことが、組織としての成熟につながります(Hooper-Greenhill, 2000;Scott, 2006)。
価値観もまた変わり得る ― 更新される文化として
重要なのは、価値観そのものもまた固定されたものではなく、社会の変化や組織の経験に応じて見直されるべきものであるという視点です。価値観が「行動の指針」であるならば、社会の倫理観や多様性の捉え方が変化する中で、その指針も柔軟に更新される必要があります。
たとえば、かつて重視されていなかった「気候変動への対応」や「ジェンダー平等」が、近年多くの博物館で価値観として明示されるようになったのは、社会的要請に応答する文化機関の姿勢として自然な変化と言えるでしょう。
こうした更新は、経営層が一方的に行うのではなく、現場の職員や地域の声を取り入れながら、対話的に進められることが理想です。定期的な見直しの場や職員参加型のレビュー、来館者との意見交換などを通じて、価値観を“育てていく”という姿勢が求められます。理念の中核を保ちつつ、柔軟に再定義することこそが、「生きたバリュー」を持つ組織の特性です(Fleming, 2015;Scott, 2010)。
このように、価値観は掲げるだけでは機能しません。理解され、使われ、再び問い直されるという循環のなかでこそ、価値観は博物館という組織の文化として深まり、持続可能な経営の基盤となっていきます。価値観を“生きた理念”として育てる営みは、博物館を内側から変えていく静かな力なのです。
参考文献
- Fleming, D. (2015). Museums and the values we should champion. In R. Sandell & E. Nightingale (Eds.), Museums, equality and social justice (pp. 17–33). Routledge.
- Hooper-Greenhill, E. (2000). Museums and the interpretation of visual culture. Routledge.
- Scott, C. (2006). Museums, the public and public value. Cultural Trends, 15(1), 45–75.
- Scott, C. (2010). Museums and public value: Creating sustainable futures. Ashgate.
- Semmel, M., & Bittner, C. (2009). Measuring museum public value. Museum Management and Curatorship, 24(2), 117–132.