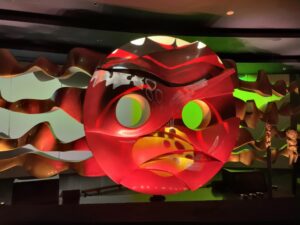博物館では近年、収蔵品の高精細画像、展示映像、音声資料、3Dスキャン、さらにはWeb展示やSNSを含むオンライン発信まで、デジタル化の対象が急速に広がっています。こうした流れの中で、「デジタル化したのだから保存できたはずだ」と考えてしまいがちですが、実際にはデジタル化とデジタル保存は同義ではありません。バックアップを取っていても、ソフトウェアやファイル形式の陳腐化、権利条件の不確実性、作成過程の記録不足によって、将来“読めない”“使えない”状態に陥ることがあります(Corrado & Moulaison Sandy, 2017)。
とりわけ博物館では、資料の一点性や、画像・映像・3Dといった非テキスト系データの比重が高いこと、権利関係が複雑で保存行為そのものが制約されうること、そして真正性やプロヴェナンスが学術的価値の中核になることが、課題をより難しくします。たとえば3Dモデルは客観的な再現物のように見えても、取得条件や後処理の選択が前提にあり、それが記録されていなければ真正性の評価が揺らぎます(Lang & Salcedo Paparoni, 2025)。また権利情報が曖昧なままだと、公開以前に、形式変換や再利用判断が止まって「触れないデータ」が生まれます(Dişli & Candela, 2025)。
本記事では、こうした状況を踏まえ、博物館に固有のデジタル保存課題とは何かを、整理して説明します。
デジタル保存はバックアップでも公開でもない
博物館におけるデジタル保存を考える際、最も多い誤解の一つが「バックアップを取っているから大丈夫」「公開サイトに載せているから残っているはずだ」という認識です。しかし、デジタル保存の定義はそれらよりもはるかに広く、また厳密なものです。デジタル保存とは、単にデータを失わないようにする行為ではなく、将来にわたってそのデータが理解され、利用可能な状態を維持するための継続的な管理行為を指します。博物館におけるデジタル保存とは何かを正しく理解するためには、まずバックアップや公開と保存との違いを整理する必要があります。
バックアップとデジタル保存の決定的な違い
バックアップの主な目的は、障害や事故が発生した際にデータを元の状態に復元することです。サーバ障害、誤削除、災害といった短期的なリスクへの備えとして、バックアップは不可欠な仕組みです。しかし、バックアップが保証するのはあくまでビット列としてのデータの存続であり、そのデータが将来も意味をもって解釈できるかどうかまでは担保しません。
デジタル保存では、「ビットが残っているか」ではなく、「意味が保存されているか」が問題になります。ソフトウェアやファイル形式が変化すれば、バックアップされたデータであっても開けなくなる可能性があります。また、作成時の目的や利用文脈、判断の背景といった情報が失われると、データは存在していても学術的・実務的に利用できない状態になります。バックアップは短期的な障害への対応としては有効であるが、ソフトウェアの陳腐化や文脈の喪失といった問題には対応できないとされている(Corrado & Moulaison Sandy, 2017)。この点において、バックアップはデジタル保存の一要素ではあっても、それ自体が保存を意味するわけではありません。
公開用データが保存データにならない理由
もう一つの誤解は、公開されているデジタルデータがそのまま保存データになるという考え方です。博物館のWebサイトやデジタルアーカイブで公開されている画像や映像は、多くの場合、表示速度や利用環境を考慮して解像度が制限され、色調補正やトリミングなどの加工が施されています。また、著作権や肖像権への配慮から、本来の情報の一部が意図的に省略されている場合もあります。
このような公開用データは、「見せるためのデータ」として最適化されたものであり、必ずしも「残すためのデータ」ではありません。保存の観点からは、元データや作成過程の記録、権利条件を含めた管理が必要になります。公開と保存を同一視してしまうと、公開可能な情報だけが残り、将来の研究や再解釈に必要な情報が失われる危険性があります。したがって、公開用データが保存データにならない理由は、目的と前提条件が根本的に異なる点にあります(Corrado & Moulaison Sandy, 2017)。
博物館に特有のデジタル保存課題
博物館におけるデジタル保存の難しさは、単に扱うデータ量が多いことや、技術の進化が速いことだけに起因するものではありません。博物館が扱うデジタル資料には、図書館や文書館とは異なる特性があり、それが保存上の固有の課題を生み出しています。ここでは、博物館デジタル資料の特性に注目しながら、なぜデジタル保存が特に困難になるのかを整理します。
一点性と不可逆性がもたらす保存上の困難
博物館資料の大きな特徴は、その多くが一点ものであり、失われれば再取得できないという点にあります。この一点性は、実物資料だけでなく、それに付随して作成されるデジタル記録にも引き継がれます。初期調査時に撮影された画像や、特定の展示条件下で作成された記録、旧来の技術によって生成されたデジタルデータは、後から同じ条件で再現することができません。
とりわけ、デジタル化の初期段階に作成されたデータは、現在の技術水準から見ると不十分に見えることがあります。しかし、それらは当時の観察方法や判断基準、技術的制約を反映した記録であり、後年の研究において重要な意味を持つ場合があります。博物館資料に付随するデジタル記録は、後から再作成できる代替物ではなく、その時点の観察と判断を示す一次資料として扱われるべきであるとされている(Corrado & Moulaison Sandy, 2017)。この点において、博物館のデジタル保存は「新しいデータに置き換える」発想では対応できない課題を抱えています。
非テキスト系データは「環境が失われると意味を失う」
博物館のデジタル資料は、テキスト情報よりも、画像・映像・音声・3Dデータといった非テキスト系データが中心になります。これらのデータはファイルとして保存できたとしても、表示や再現には特定のソフトウェアやハードウェア環境を必要とします。表示エンジンの違いやバージョンの更新によって、見え方や解釈が変わることも少なくありません。
特に3Dデータは、客観的な再現物として受け取られやすい一方で、実際には取得条件や後処理の段階で多くの選択が行われています。3Dモデルは客観的な再現物のように見えるが、実際には取得条件や後処理に基づく選択の結果であり、その前提が記録されていなければ真正性を評価できないと指摘されている(Lang & Salcedo Paparoni, 2025)。表示環境や制作過程の情報が失われると、データは存在していても意味を正しく読み取ることができなくなります。
権利関係が保存行為そのものを制約する
博物館のデジタル保存では、権利関係が公開段階だけでなく、保存行為そのものに影響を与えます。デジタル保存には、複製、形式変換、正規化、場合によっては改変が伴いますが、これらはいずれも著作権や契約条件の制約を受ける可能性があります。
権利情報が十分に整理されていないデータは、公開できないだけでなく、保存レベルを引き上げる判断や、将来的な形式変換ができなくなる恐れがあります。権利情報が不十分な文化遺産データは、公開だけでなく保存や形式変換の判断も困難にし、結果として「触れないデータ」を生み出すとされている(Dişli & Candela, 2025)。このように、権利情報の欠落は、時間の経過とともにデータの活用可能性を狭めていきます。
真正性は「不変性」ではなく「追跡可能性」によって担保される
デジタル資料の保存において、しばしば「改変しないこと」が真正性の条件であると誤解されます。しかし、長期的な保存を考えれば、ファイル形式の移行や表示環境の更新は避けられません。重要なのは、変更を行わないことではなく、どのような変更が、どのような判断のもとで行われたのかを追跡できる状態を保つことです。
デジタル資料の真正性は、改変を排除することではなく、生成・変更・管理の過程が説明可能であることによって支えられる(Corrado & Moulaison Sandy, 2017)。博物館におけるデジタル保存では、履歴や判断の記録そのものが、資料の一部として位置づけられる点に特徴があります。
なぜ保存方針・記録・文脈情報が不可欠なのか
博物館におけるデジタル保存を考える際、しばしば見落とされがちなのが、保存対象を「データそのもの」と捉えてしまう点です。しかし、博物館のデジタル資料は、ファイル単体で完結する情報ではありません。どのような目的で作成され、どのような条件で利用されてきたのかという文脈が失われると、データは存在していても意味を十分に読み取れなくなります。そのため、保存方針・記録・文脈情報を一体として管理することが不可欠になります。
データ単体では意味が保存されない
デジタル資料は、ハードディスクやクラウド上に保存されている限り「残っている」ように見えます。しかし、文脈や前提条件が欠落したデータは、時間の経過とともに解釈不能になる危険性を抱えています。たとえば、画像データであれば、撮影目的や照明条件、色補正の有無が分からなければ、研究資料としての価値は大きく損なわれます。3Dデータであれば、取得精度や後処理の内容、想定された利用方法が不明なままでは、その形状が何を示しているのか判断できません。
また、利用条件や制約に関する情報が欠けている場合、保存されているにもかかわらず、実務上「使えない」状態に陥ることがあります。文脈・目的・利用条件といった情報は、後から補完することが難しく、作成時点で記録されていなければ失われてしまうことが多いのが現実です。したがって、博物館のデジタル保存では、データ単体を守るだけでは不十分であり、その意味を支える情報を同時に残す必要があります。
「将来理解できる状態」を設計するという発想
デジタル保存を長期的に成立させるためには、技術が更新され続けることを前提に考える必要があります。ファイル形式やソフトウェア、表示環境は将来必ず変化し、現在の最適解がそのまま維持されることはありません。そのため、保存の目標は「現在の状態を固定すること」ではなく、「将来においても理解可能な状態を維持すること」に置かれます。
この視点に立つと、判断の記録そのものが重要な保存対象として浮かび上がります。なぜこの形式を選んだのか、なぜこの処理を行ったのか、どのような制約のもとで判断がなされたのかといった履歴は、後年に資料を再解釈する際の手がかりになります。博物館におけるデジタル保存では、データの変更や移行を避けることよりも、その過程が説明可能であることが重視されます。保存方針を明文化し、記録と文脈情報を体系的に管理することは、「将来理解できる状態」をあらかじめ設計する行為だといえます(Corrado & Moulaison Sandy, 2017; Lang & Salcedo Paparoni, 2025; Dişli & Candela, 2025)。
博物館におけるデジタル保存の本来の目的とは
ここまで見てきたように、博物館におけるデジタル保存の問題点は、単一の要因によって生じているわけではありません。博物館資料は一点性が高く、失われれば再取得できないという性質を持っています。そのため、付随するデジタル記録もまた、後から置き換え可能な補助資料ではなく、当時の観察や判断を示す一次資料として扱われます。この点で、更新や差し替えを前提とした一般的なデジタル管理の発想は、博物館資料には適合しにくい側面があります。
さらに、博物館のデジタル資料は、画像・映像・3Dといった非テキスト系データが中心であり、表示環境やソフトウェアに強く依存します。ファイルが存在していても、その生成条件や利用環境が失われれば、何を示しているのかを正しく理解することはできません。加えて、著作権や契約条件、寄贈時の取り決めなど、権利関係が複雑に絡み合うことで、保存や形式変換といった行為そのものが制約される場合もあります。権利情報が不十分なままでは、時間の経過とともにデータが「触れない存在」になってしまいます。
こうした状況の中で重要になるのが、博物館資料における真正性の考え方です。デジタル資料は、長期保存の過程で形式変換や更新を避けることができません。真正性は、不変であることによってではなく、どのような判断のもとで生成され、変更され、管理されてきたのかが追跡可能であることによって支えられます。履歴や文脈を含めて説明できる状態を保つことが、博物館資料の価値を将来に引き継ぐ前提になります。
以上を踏まえると、博物館におけるデジタル保存の本来の目的は明確になります。それは単にデータを残す行為ではありません。博物館におけるデジタル保存とは、資料に付随する意味が、将来においても読み取れる状態を維持し続ける行為であるといえます。
参考文献
Corrado, E. M., & Moulaison Sandy, H. (2017). Digital preservation for libraries, archives, and museums (2nd ed.). Rowman & Littlefield.
Lang, M., & Salcedo Paparoni, V. (2025). Scanning authenticity: On the limits of 3D representation in museums. ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences.
Dişli, M., & Candela, G. (2025). Copyright and licencing for cultural heritage collections as data. Journal of Open Humanities Data.